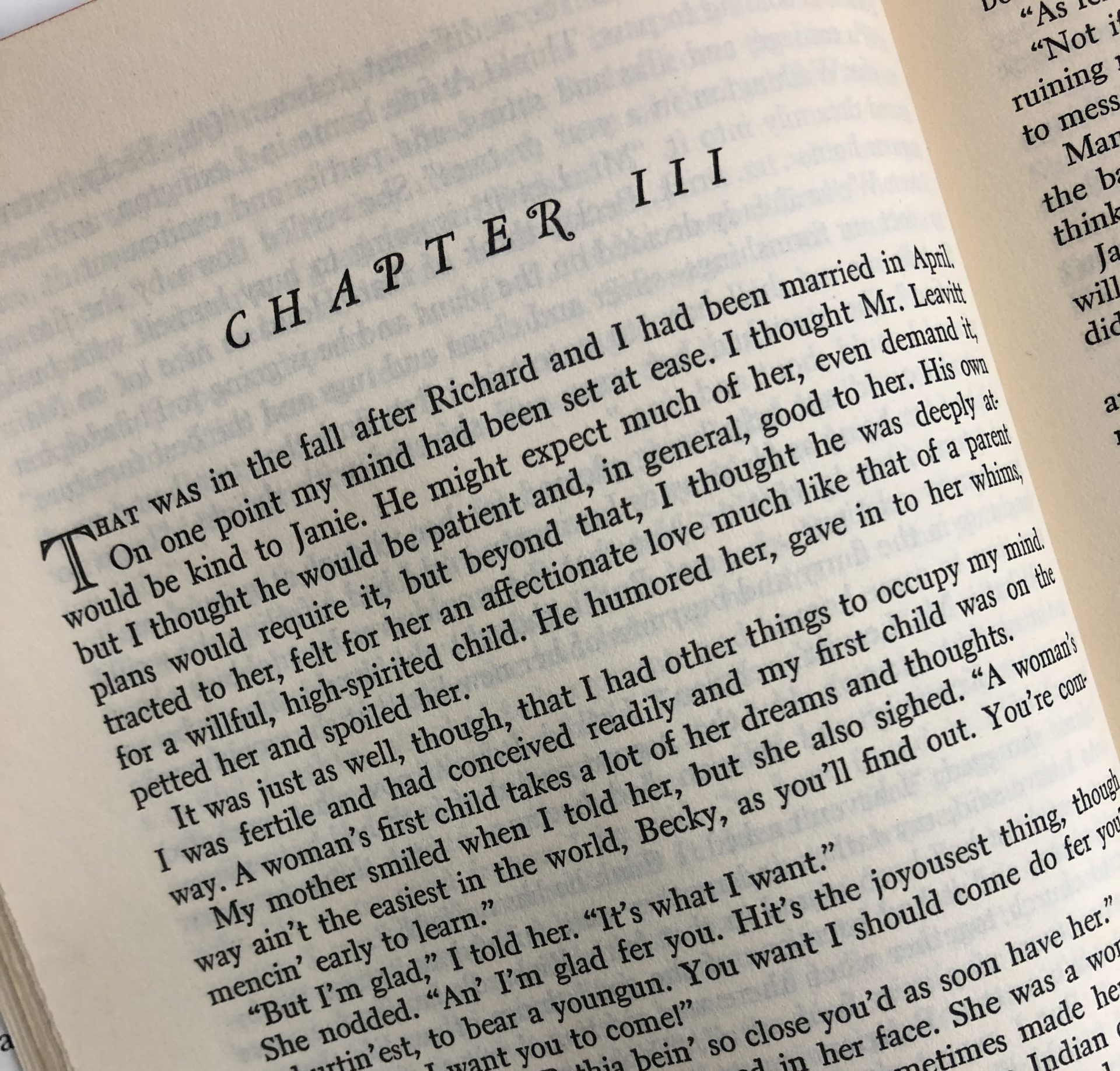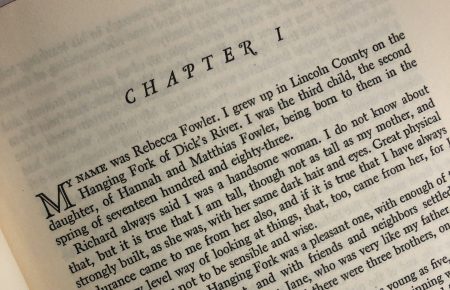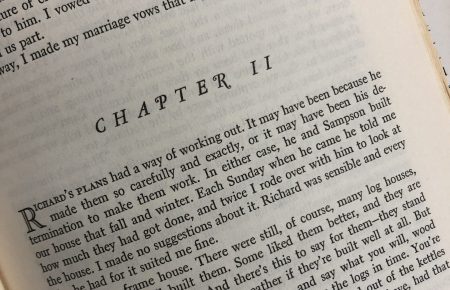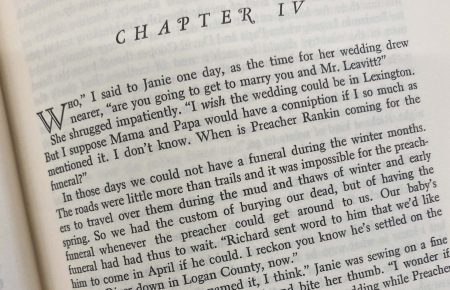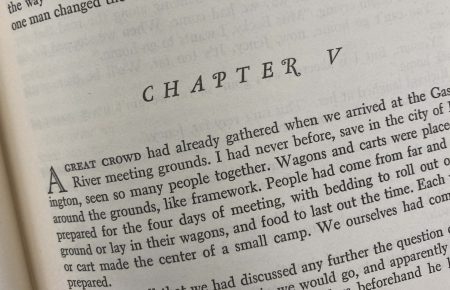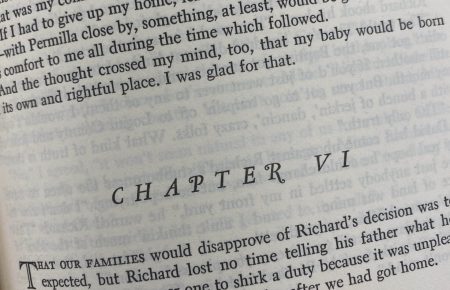私はリチャードと四月に式を挙げた。そして秋には、私の心も新しい生活に慣れ始めていた。私はレヴィット氏とジェイニーはうまくやっていけるだろうと思った。彼はジェイニーに多くを期待し、いろいろと注文をつけるかもしれない。しかし、辛抱強く、たいていは優しく接してくれるように思えた。レヴィット氏はジェイニーに強く惹かれていたので、まるで親が、わがままで威勢のいい子どもに対して持つような、温かい愛情を感じているだろうと思ったのだ。レヴィット氏は気まぐれなジェイニーに付き合い、機嫌をとって可愛がり、甘やかしていた。
といっても、私は他のことで頭がいっぱいだったので、そんなことにかかずらっていられなかった。私は一人目の子どもを身籠っていて、もうじきその子が生まれるところだったのだ。
初めての子には夢や思いを託したくなるもので、母は私の妊娠を喜んでくれたが、同時にため息ももらした。「ベッキー、まだ若すぎるからわからないと思うけど、女の人生はそう簡単ではないの」 「でも嬉しい、子どもを授かりたいとずっと思っていたから」と私は言った。 母はうなずいて「そうね、もちろん私も嬉しいわ。子どもを産むのは大変だけれど、すごく喜ばしいことだからね。何か手伝いに行ったほうがいい?」と言った。 「もちろん来て!」 「あなたベティアと仲良いでしょう。もしかしたら私ではなく、ベティアを呼ぶのかもしれないと思っていたわ」
母が喜んでいたことは、その顔を見ればわかった。母は血色が悪く浅黒い肌をしていて、その立派な眉のせいでたまに恐ろしく見えることもあった。実際、厳しい態度になることもあった。母はインディアンを殺したことがある。ためらいがあったとしても殺したのである。いつでも母はやるべきことをやる人だった。そのときはインディアンを殺さなければ、そこから逃げて父のもとへ帰ることができなかったのだ。
とはいえ、私が手伝いに来てほしいと言ったのは、本当にそう欲していたからで、単に母を喜ばせたかったからではなかった。母は強く、冷静で、何をすべきかいつも知っていて、そんな母がそばにいない出産なんてとても考えられなかった。私は母からの大きな愛情をもらって育った。そしてそれがどれほど懐深く、際限のないものだったかを理解している。
一、二日前から風邪を引いていたジェイニーは、母がいれたお茶を火のそばに座って飲んでいた。「よかった」と言って、ジェイニーはカップ越しに私を見て笑った。「私のはただの風邪だけど、ベッキーはお腹が大騒ぎね」 「それならずっと風邪を引いてなさい」と私はジェイニーをからかった。「私は楽しいから続けられる」 「二人とも、そんな会話はよしなさい。よくないわ」と母が言った。
ジェイニーは私のほうを見て顔をしかめたが、とりあえず私たちは黙ることにした。母は良し悪しについてはっきりとした意見を持っていて、大人になった私たちを叱ることも躊躇しなかった。 「それにお嬢さん。あなただっていずれそうなるのよ」と母は続けた。 「そうしたくなければ、そうならない」とジェイニーは言った。「見た目が変わっちゃうのは嫌だし、子どもなんて鼻水をたらして部屋を散らかすだけだし、時間も取られるだけ。私は育てたくない」
母がジェイニーのほうを向いて、一瞬、私は母が手をあげるのかと思った。「主の意志には逆らったりしないでしょうね」と母は言った。 「主の意志だってうまく避けるわ」ジェイニーはティーカップで口を塞いでいたが、そのつぶやきは私の耳に届いた。少し耳の悪い母には聞こえていなかったので、私はほっとした。もし聞こえていたら、母は愕然としたことだろう。
子どもが生まれるのを待つ時間は、長くもあり短くもあった。私はいたって健康で、気分が悪くなることもめったになかった。初めの頃は、私の頭の中で起こることを除いて、特に変わったこともなかった。それまでと同じように、自分の仕事をこなすこともできた。でも時が経つにつれて、私の身体は重く、思うように動かせなくなり、仕事は遅くなって、カッシーに私の分を回すことが多くなっていった。
とはいえ最後の数ヶ月は冬だったので、家の中で長時間を過ごすのには都合がよかった。
そして、ジェンシーが今まで以上に役に立ってくれることがわかってきた。誰も私の妊娠についてジェンシーに伝えてはいないはずだったが、私が妊娠していることは彼女をとても魅了したらしかった。ジェンシーはずっと私のそばにいてくれて、落とした毛糸の玉をとってくれたり、かがまなくてもいいように火の面倒を見てくれたり、水を持ってきてくれたりした。ジェンシーは子どもの世話には向いている、とベティアが言っていたのを思い出した。見ている限りではその通りで、時が来たらジェンシーはすごく役に立ってくれるはずだと思った。ある日、ジェンシーは少し恥ずかしそうにこっちに来て言った。「赤ちゃんはもう生まれるの?」 隠す理由もなかったので私は教えてあげた。「一月の中旬よ」
ジェンシーは私の足元に座って、毛糸を巻いていた私を手伝って、両手を上げていた。ジェンシーの肌は黒く、光っていて、顔の骨格にぴったりと張りついていた。目は驚くほど大きく、白目は青みがかって見え、目をむくと、しばしば黒目は完全に見えなくなった。髪は縮れてごわごわしていて、頭のあちこちで秩序なく突き出ていた。カッシーはときどきジェンシーの髪を三つ編みにして、まとめて一つに束ねてあげた。その時の三つ編みは、角のようにおかしな角度で突き出ていた。ジェンシーは細身でたおやかな子どもだった。私が教えてあげると、ジェンシーは唇を噛み、くすくすしながら頭を大きく動かした。「その子を抱かせてくれますか?」 「ちゃんと糸を持ってなさい。でないと絡まっちゃうでしょう」私は注意した。そして「抱いてみたい?」とジェンシーに聞いた。 「はい」
私は、ジェンシーと真剣に話そうと決めて、糸玉を巻く手を止めた。 「いい、ジェンシー。あなたもじきに一人で仕事をしなければいけなくなる。赤ちゃんのお世話をしてる時、蝶々やお花を追いかけていっちゃだめなんだから」 「そんなことしません!」 「今はしてるでしょう。水や薪を取ってくるようにいわれた時に。それに、掃き掃除やベッドメイキングもいい加減」 ジェンシーはうつむいた。「はい。そういうことはあんまり好きじゃないから。だけど、小さい子どもは好き」
今にもジェンシーを叱っている自分の声が聞こえるようだ。「そんなこと言っても、好きでも嫌いでもやらなきゃいけないの、ジェンシー。それがわからないような歳じゃないでしょう。仕事を与えられたら、できる限りちゃんとこなして、終わるまでやめちゃいけない。もしあなたが、赤ちゃんが生まれるまでにそれができるようになったら、あなたに赤ちゃんを任せられる。赤ちゃんはたくさんお世話が必要だから、たくさん手伝うことがある」 ジェンシーは喜んで、とても大きな笑顔を見せた。「仕事したら、赤ちゃんのお世話ができるってこと?」
私がうなずくと、ジェンシーは跳び上がって、片足でくるくる跳ね回った。 「今からやるような、掃いたり片付けたりはすごすぎて、きっと見たことないよ。ミス・ベッキー!」ジェンシーが火床のブラシをつかんで、灰をまき散らし始めたので部屋中に灰が舞い上がって、私は咳込みかけた。「ジェンシー! ブラシを置きなさい!」私は叫んだ。 「でも今から始めるつもりなのに、ミス・ベッキー」 「埃が舞わないように優しく掃くやり方を何回も見せたでしょう。ちゃんとやってみて」
驚いたことに、ジェンシーは丁寧に、簡単そうにやってのけた。そして赤ちゃんが生まれるまでのあいだ、彼女は私を驚かせ続けたのだった。ジェンシーはきちんと働き始めた。いい仕事と呼べるものはほとんどなかったとはいえ、努力し始めたというのはたしかだった。
ある日、カッシーが尋ねた。「あの子、何かあったんですか? あんなに一生懸命仕事をするなんて今までありませんでしたから」
カッシーは太った女性だったが、肉づきのよい引き締まった身体をしていて、ベティアのように軽い足取りをしていた。また、サンプソンと同じように、純血の黒人でとても黒い肌をしていた。私はジェンシーが赤ちゃんのお世話を任せてもらえるように頑張っていることを伝えた。 カッシーは笑った。「ミス・ベッキー、あの子は精一杯やっていると思います。とても助かっています。名案ですね」
この出産が大変なものになるかもしれないとは、私も母も思っていなかったのだった。「簡単なことではないけど、あなたは向いているから大丈夫」と母は言った。私にも不安はなかった。 母は予定日の一週間前には来てくれて、一緒に楽しい時間を過ごした。火のそばに座って、うとうとしながら一緒に過ごす時間は穏やかで本当に心地がよかったものだ。仕事のほとんどはカッシーがこなしてくれたので、母と私は座って編み物をしていろいろなことを話した。私たちのあいだで、しばしばジェイニーのことが話題にあがった。「あの子は服のことに時間をかけてばかりよ」母は言った。「パパにルイヴィルへ連れていってもらって、生地を見つけたらしいわ。かなりお金を使ったみたい。何でもないって言ってるけれどね。パパはもうすぐ離れ離れになってしまうから、人生で一度はあの子が欲しいものを買ってあげようと思っていたみたい」母はくしゃみをした。私ならジェイニーにやめさせようとしただろう。
母もジェイニーがルイヴィルに行けばどうなるかわかっていたが、それでもやめさせなかった。私が何も言わないと、母は続けた。「あの子は、私が見たこともないようないいものばかり買ってくるのよ。ちょっとしたジャケットやスカートのための毛織物とかカシミア、レース、高級な絹糸、それからムスリンとかなんとか、全部を縫うための金糸まで。全部結婚式のためだって言ってる。何着もボンネットや靴つきの新しいドレスを用意すると言っているから、お金がなくなっちゃうわ」 「そんな」と私。「でもパパにはいくらか貯金があるじゃない」 「それで血統書つきの馬を買うつもりだった」母は物憂げに言った。
ジェイニーの結婚式のドレスのために、馬を買う夢を諦めなければならない父のことを思うと胸が痛んだ。しかし、言ってもどうしようもないとも思った。「リネンはどうするの?」私は尋ねた。 「手作りはだめらしいわ」母は呆れて怒ったように続けた。「レヴィット氏がフィラデルフィアで買うから大丈夫だって言うの。花嫁がシーツも布団もキルトもテーブルクロスも持っていかないだなんて聞いたことない。私が用意してあげるっていってるのに、あの子ったらいいだって」 「でも、ママ」私はなだめようとした。「今はそういう時代なのかもしれないわ。ママが結婚した頃は……」
母が遮った。「私の頃はね、花嫁は持っているものは何でも持っていったわ。たしかに、私はいいリネンは持ってなかったけれど、やかんとか種とか、そういうものでも持っていった。身なりなんて気にしたこともなかった」 「でもママとパパは、私の時には家で必要なものをくれたじゃない」 「そうね、だってあなたは何が必要かちゃんとわかっていたでしょう」母はため息をついた。「あなたの言う通りかもしれない……時代は変わって、人も変わった。それでも、あの子も少しはこっちの考えをわかってくれたらいいんだけど」 「ジェイニーが他の人と違うのは仕方ない」 「仕方なくないわ。本当に、どうしてああなったのかしら。私はそんなしつけをした覚えはないし。何がいけなかったのかしらね」
母は、自分だって冒険をしながらケンタッキーにやってきたことを忘れているようだった。父と一緒ではあったけれど、彼女の人生は本当に冒険だった。私の父は(1)ホールストン郡からやってきた向こう見ずな若者だった。母は気づいていなかったけれど、ジェイニーが冒険好きになったのは自然なことだった。
いつの時代だって、若者は上の世代とは違うもので、そうやって新しい世代は自立してゆくのだと思う。私の父と母は手つかずの大地を切り拓いて、まずは差しかけ小屋を建てたのだ。そのあとに、自分たちの森から丸太を切り出して家を建てた。リチャードと私の土地は譲り受けたもので、リチャードとサンプソンが自分たちで建てたとはいえ、我が家はフレームハウスだった。加えて私には、カッシーとジェンシーというお手伝いもいた。リチャードの父親がすでに切り倒してくれていたので、私たちの土地には森もなかった。
そして今、ジェイニーは都会へ出ていこうとしている。彼女は召使いのたくさんいる良質な煉瓦造の家に住むのだ。物事は常に変化し続ける。手つかずの土地に住み続けることはできないし、人はそれぞれの生活を切り拓いてゆくのだ。
夜中に目が覚めた。どうして赤ん坊は、この世界への旅を夜中に始めるのか。何が、長いあいだ眠っていた赤ん坊を、人生のはじまりへ突き動かすのだろう。きっとお母さんが寝ている時のほうが静かで、邪魔されないからなのだろう。静けさに乗じて、「さて、この暗い場所から出る時間だ」とでも思っているのかもしれない。
最初の痛みで起こされたのは深夜のことだった。私はリチャードに母を呼んでもらった。母はすぐに来てくれた。母はリチャードを部屋の外へやった。私の様子が順調なのを見て、母は安心していた。「あなたは私のベッドで寝ていなさい。朝は普段の仕事をやっても大丈夫。たぶん、あなたに手伝ってもらうのはお昼頃になると思うわ」母はリチャードに言った。
男の人はこういうときに困ったり心配したりするものだから、リチャードも同じだったと思う。
陽が出て、時間が経っていくあいだに、痛みはどんどん強くなっていった。母は、(2)赤ちゃんが下りてくるまで寝ずに歩き続けてひざまずいて産むという昔のやり方で出産したけれど、今のやり方のほうがいいことは母もわかっていたから、私はずっとベッドの上にいた。
正午になっても赤ちゃんは生まれなかったけれど、私は心配していなかった。でも疲れはどんどんたまっていた。休みが欲しいと思っていた。母は言った。「休みが欲しければ、踏ん張り続けるしかないわ、ベッキー。今くじけちゃだめ」
午後が過ぎていった。私は自分がこんな痛みに耐えられるとは思っていなかった。でも痛みに耐えている時でも、母の顔に不安の色が浮かんでいるのがわかった。「何かがおかしいんでしょ? もう生まれてきてもいい頃なのに」 母は私の顔を冷やした布でぬぐった。「思っていた以上に時間がかかっているだけで、何かおかしければすぐわかるわ。そのまま踏ん張り続けて、ベッキー」母はその日、何回かベティアを呼んでくれて、二人はできる限りのことをやってくれた。私は母がベティアに囁くのを聞いた。 「ああ、ジェーン・マニフィーがいてくれたらね……」 「本当に」べティアは言った。
二人は、(3)痛みを断ち切るための斧をベッドの下に入れてくれた。また、温めたオイルで私の体をこすったり、温かいものを飲ませてくれたりした。そのあと羽毛で私の鼻をくすぐって、くしゃみをさせたけれど、何の役にも立たず、死にそうな痛みを感じただけだった。何をしても無駄だった。赤ちゃんは一向に出てこようとせず、どうしようもなかった。
そうしているうちに、二回目の夜が過ぎた。リチャードは応接室を歩き回っていて、ときどきドアから覗きこんだり、母と小声で話したりしていた。リチャードが見知らぬ人のように感じられた。とにかく、身体の痛みのことしか考えられなかった。ちらつくろうそくや獣脂を燃やしたような匂い、通り過ぎる人影を覚えている。それらに何の意味もなかった。変わらずに続く痛みと、その痛みから逃れるための奮闘、痛みをなくすためなら死なせてほしいという願い。それだけ考えていた。
二日目の午後、ようやく子どもは生まれた。というよりは、母の必死の努力で私から引き離された。赤ん坊は産声を上げなかった。私はそのことを一日か二日、知らなかった。痛みがなくなって幸い平穏を取り戻してから、私は眠り続けた。起きていたのは母やリチャード、ベティアに食事を食べさせてもらう時だけだった。ようやく目を覚まして、もう疲れも眠気もなくなっていることがわかった時、赤ん坊のことを知った。
母がそのことを私に教えてくれたのだ。「生きていなかったのよ、ベッキー。ずっと前に亡くなっていたから、どうしようもなかった。一カ月くらい前にはもう死んでいたみたい。だからなかなか出てこなかったのね。あなた一人で頑張っていたんだわ」 私は途方もない悲しみと孤独感に襲われ、手のひらに冷や汗があふれ出た。「リチャードは……リチャードはどこ」 「すぐに戻ってくる」と母は言った。「あなたの具合が悪いあいだは、遠くにはいかない。呼んでくるわ」
リチャードはすぐにやってきて、ベッドの上で私のそばに座って私を抱き寄せた。私は泣き崩れた。「そんなに悲しまないで」リチャードは私の髪を撫で、顔に頬をあてた。「悲しまないで」 私が泣き止むまでリチャードは抱きしめてくれた。「これでよかったんだ」 「どうよかったって言うの……あの子は生きていなかったというのに、どう良かったって言うの?」 「それはわからない」リチャードは静かに言った。「もしそれが主の望んだことなら、僕たちはそれに従うだけだから」
私はリチャードから離れて再び枕にもたれ、リチャードを見つめた。リチャードの強く、揺るぎない信仰心は慰めになってもよかったはずだった。しかし、なぜかそうはならなかった。私は血色のよい頬と四角い顎をした、たくましい顔をじっと見つめた。そうして私は頭を左右に振り、再び泣き始めた。「男の子だったの?」 「ああ、男の子だった……。ちゃんと身体はできていたよ」「でも生きていなかったのね」 「生きていなかった。小さな蝋人形のようだった」 「もう埋葬した?」 「生まれた日にね。それが一番だと思って」 「会いたかったわ」 「君がもっと悲しむと思ったんだ」
もちろん、そうだったと思う。私は泣き声を押し殺そうとした。「なんで……わからない。私たちはあの子を待っていたし、たくさんの準備もした、会えるのを心待ちにしていたのに……神はなぜこんなことをするの?」 リチャードは静かに言った。「そんなことわかるはずがない。きっと神は、僕たちを信頼できるかどうか試しているんだ」
そんなこと私には耐えられない! しかし、試練が教えてくれたこともある。主のお望みは人間には計り知れないということ、主は愛する者にでさえも受難を与えること、主の意志で人の運命が決まるということ。そう考えるしかなかったのだった。唯一、道理にかなっていて、悲しみを和らげてくれる考え方だった。しかし、私にはまったく理解できなかった。いえ、理解しようとしなかったのかもしれない。リチャードは私の手を取って言った。「次があるよ、大丈夫。きっと主は子どもを授けてくれる」
それが唯一の慰めだった。
私たちはまだ若かったし、きっと子どもを授かれるはずだった。私は一カ月のあいだ、回復できず、体調は戻らなかった。それでも徐々に身体を動かし始めて、身体に力が戻るようになっていった。身体の回復よりも、心の回復にはもっと時間がかかった。心の傷はなかなか癒えなかった。でも時間の経過が治せないものはないし、毎日の仕事や雑用がその助けになった。
幼子を失ったことは本当に悲しいことだった。しかし、食事の準備や服や家の世話の中で、悲しみは和らいでいった。あの頃は、子どもを失うのはありふれた話で、複数の子どもを亡くしたことのない女性のほうが珍しかったほどだ。この土地には、健康に育った子どもと同じ数の子どもが埋葬されているのではないかと思うこともある。それにもし無事に生まれたとしても、幼いうちには夏の暑さや冬の病気を乗り越えられない子どももたくさんいた。私の母は五人の子どもを育てたが三人を失っている。ベティアは七人を育て、三人を失っている。それが世の定めなのだ。ただ、少しだけでも生きてほしかったと願わずにはいられなかった。
その時、ジェンシーは妙な行動をとっていた。母が私に教えてくれたのだが、赤ん坊が亡くなっていたことを知った時、ジェンシーは森へ駆けだして、家にまで聞こえるほど声をあげて一日中泣いていたそうだ。そして戻ってきた時には、すっかり昔の通りになっていたという。
彼女は、今までよりももっと、それが可能だとしたらだが、不注意になり、仕事を任されないようにちょろちょろして、これまで以上にくすくすしたりふざけるようになった。お世話するはずだった赤ちゃんがいなくなってしまい、ジェンシーのもじゃもじゃ頭にはそうするほか考えが浮かばなかったのかもしれない。
ある日、ジェンシーに赤ん坊のための小さな服を片づけるのを手伝うよう頼むと、彼女は目をくりくりさせながら後ろに手を組んで、あとずさりした。「いやです。ミス・ベッキー、触りたくない。それ死んでいるから」
たしかに死んでしまっていた。それでも私は、それらがまた生を受けるように祈っていた。
第3章訳註
(1) ホールストン郡(the Holston country)
現在のテネシー州ノックスビル市の南に位置していた地名と思われる。現在は、地名は残っていないが、川やそこで取り決められた条約の名前の中にホールストンという語が用いられている。
(2) 赤ちゃんが下りてくるまで寝ずに歩き続けてひざまずいて産むという昔のやり方 (in the old-fashioned way)
古代文明の出産方法。古代では立ったまま、もしくはしゃがんだ状態で出産したとされる。19世紀では一般的ではなかったと推測される。
(3) 痛みを断ち切るための斧 (an axe to cut the pains)
安産に関する迷信。後陣痛を和らげる効果があるとされ、斧の刃を妊婦のベッドの下に置いた。