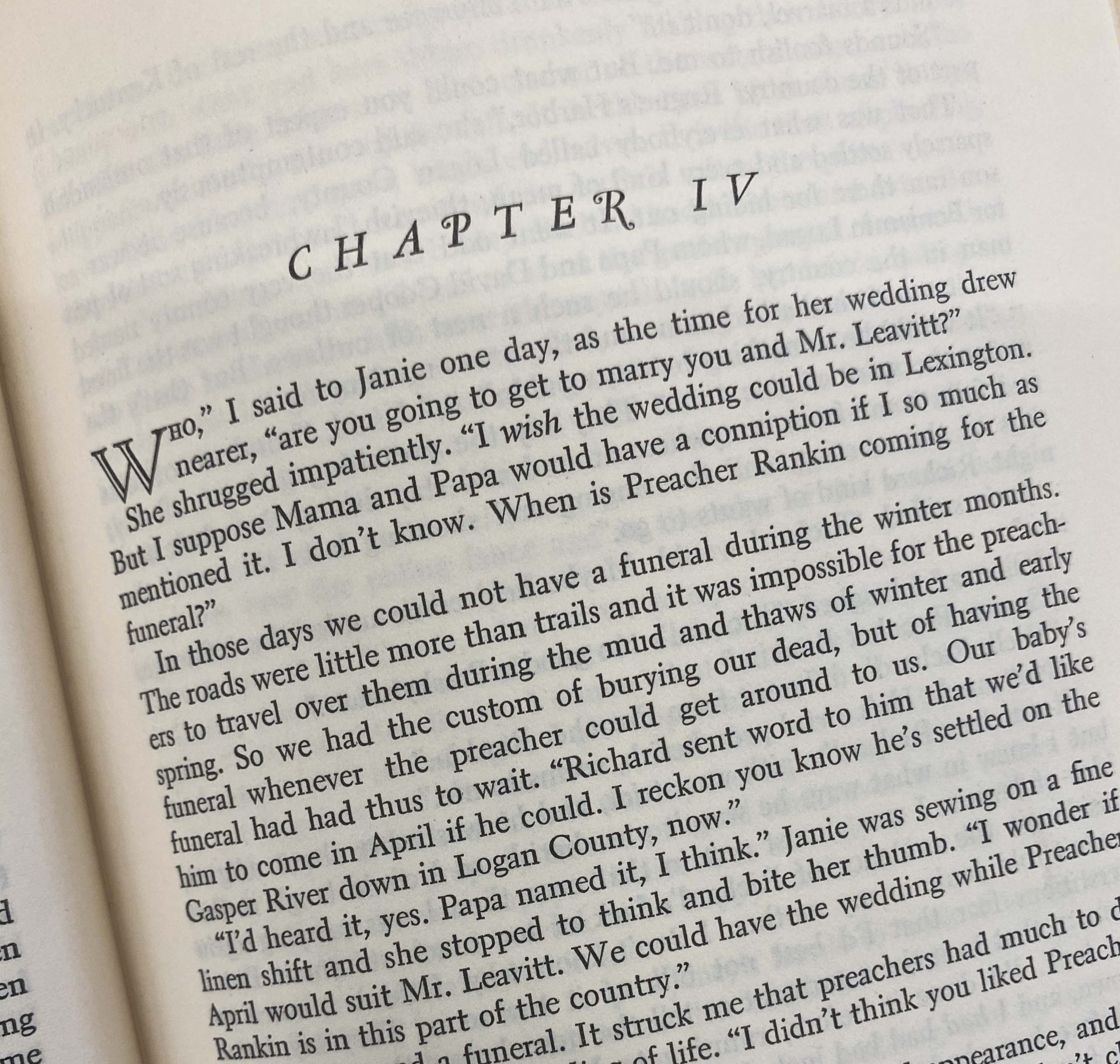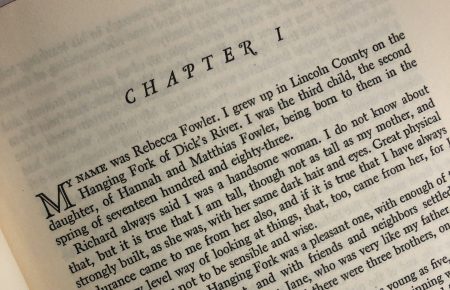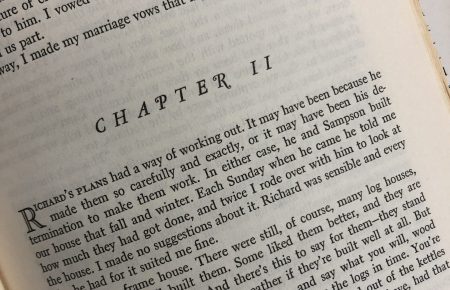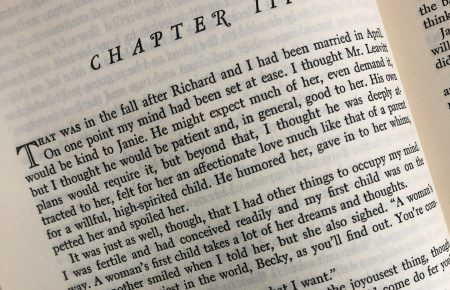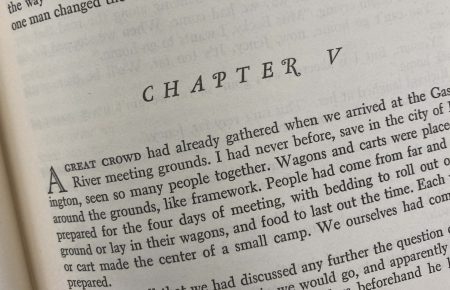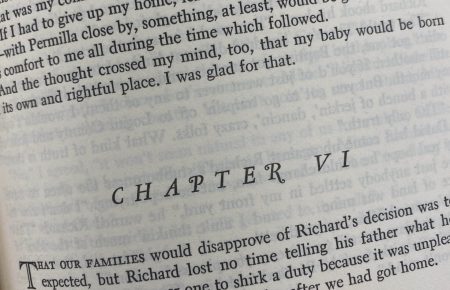「ねえ」ある日、私はジェイニーに尋ねた。結婚式がどんどん間近に近づいている時だった。「結婚式を誰に執り行ってもらうの?」
ジェイニーはいらいらした様子で肩をすくめた。「結婚式はレキシントンで挙げたかったの。でもパパとママはそのことを考えただけでかんかんに怒るでしょ。どうしようかな。ランキン牧師はいつお葬式に来るの?」
その頃、冬のあいだは葬式を挙げることができなかった。町からの狭い道は跡が少し見えるだけで、牧師がこの辺りまで来るのはほとんど不可能だった。それに冬から春先にかけては、雪解けのぬかるみがひどかった。遺体の埋葬は自分たちで行い、葬儀は牧師が来られる時に執り行うのが慣習だった。私たちの赤ちゃんの葬式も待たなければならなかった。「リチャードが、できれば四月に来てほしいとランキン氏に伝えたの。今(1)ローガン郡 の(2)ギャスパー・リバーにいるっていうのは知っているでしょ」 「うん、聞いた。パパがそう言ってた」ジェイニーは、リネンの細かい刺繍を縫っていたその手を止めて、親指を噛んで考えていた。「レヴィット氏は四月で大丈夫かな。それならこっちにランキン牧師がいるあいだに結婚式を挙げられるじゃない」
結婚式と葬式。私は、聖職者が人間の生を繋ぎ、終わらせる役目を負っていることに強く感じ入り、軽い衝撃を受けた。「ランキン牧師のことは好きじゃないのかと思っていたけど」と私は言った。 「まあ……牧師としてはね。でも見た目はいいでしょ、式も厳粛に取り仕切ってくれると思う。教養もあって、タバコも噛まないし、きちんとした服を着ているし」ジェイニーはうなずきながら続けた。「そうね、そうするわ。レヴィット氏にもできるだけ早く手紙を送ることにする」 「噂があるの」私は続けた。「ランキン牧師が長老派を抜けて、リバイバル派の影響を受けているって」 「知ってる。でも関係ないよ。ちゃんと結婚式を挙げられてまともな格好をしてくれるなら。そもそもローガン郡で何が起こってるの? パパが話してたのを少し聞いたけど」 「あっちのほうでは大きな(3)リバイバル運動が起きているみたい。週末に(4)野外聖餐礼拝(sacramental meeting) があったらしくて。このあいだ、うちの近くを通った男の人が教えてくれたけど、今年の夏にまた開こうとしているらしいわ。その人によると、そこで起きてることは、何かを信仰することを超えてしまってるらしいの。みんな聖霊の影響下に入って、痙攣して訳のわからないことを話して、踊って叫んで。宣教師たちによれば、知る限りではこの地域で起きたリバイバル運動の中で一番大規模で、テネシーとか、ケンタッキーの他の地域まで広まりつつあるらしいの。すごいと思わない?」 「馬鹿げた話だと思う。でもあの悪の巣窟(Rogue’s Harbor)のことだからね。訳のわからない場所だもの、仕方ないわ」ジェイニーは軽蔑するように言った。
皆がローガン郡のことをそう呼んでいた。住む人が少ないため、意地が悪く泥棒ぐせがあるような無法者が皆そこに逃げ込むような場所だった。ベンジャミン・ローガンにちなんで名づけられた場所が、そんな無法地帯になっているのは奇妙だった。ベンジャミン・ローガンは、父やデイヴィッドがこの地域一の偉人だと思っていたその人なのだ。しかし今、ローガン郡が悪い評判の場所なのは明らかだった。 「見てみる価値はあるんじゃない?」私は言った。「何百人もの人々が一度にそんなふうになってるのよ。説教は一日中続いて、いろいろなところから人が集まってきて、集会の四日間ずっといて、うたったり叫んだりするのは夜まで続くの。リチャードはちょっと行きたがってる」
ジェイニーは鼻で笑った。「リチャードだもん。もしかしたらリチャードも影響を受けちゃうかも」 「まさかね」私は笑った。「リチャードは模範的な長老派よ」 「ランキン牧師だってそうだったじゃない」 「でも、リチャードはランキン牧師とは違うもの」 「そうかな。私からしたらリチャードはかなり牧師っぽいけど」
たしかにリチャードは厳格な信仰を持っていて、宗教のことについてはまじめだった。けれども、私はリチャードの牧師らしくない一面も十分知っていたので、ジェイニーのコメントも笑い飛ばせた。その時、リチャードが極端に敬虔ではないのは私の中ではたしかなことだった。しかし、決してジェイニーや母にはそれを言わなかった。なぜだかはわからない。話すにはまだ早いだろう、という迷信めいた恐怖だったのだと思う。一部の女性のあいだでは、何かが起こる前に洋服を作ったり、ニュースを口にしたりするのは不吉なことだと言われていた。私は一度それをやってしまっていた。知ってすぐに母のところに走って……悪運が憑いてしまったのだ。もう二度とそんな危険を冒したくはなかった。
ジェイニーがレヴィット氏に連絡する前に、リンカーン郡に来るのは五月の中旬になるだろう、という知らせがランキン牧師を通して届いた。その知らせには、ギャスパー・リバー沿いに新しい教会を建てていて離れられないのだ、と書かれていた。話し合った結果、リチャードと私は赤ちゃんの葬儀をジェイニーの結婚式が終わるまで待つことにした。葬儀は悲しい時間になるだろうし、ジェイニーの幸せを私たちの悲しみで邪魔したくはなかった。ジェイニーは結婚式を五月十五日に決め、私たちは葬儀を十七日に行うことに決めた。葬儀の前にはジェイニーはここを去るから、私たちの悲しみが彼女の新しい人生を邪魔することはないだろう。
5月というのは、素敵でこの地域では一番穏やかな優しい時期だった。朝と夕に聞こえてくる、澄んだ、生き生きとしたツグミの歌声。牧草地のライ麦は高く、力強く、染められたベルベットよりも青々としていて、同じくらい柔らかい触り心地。空は濃い青に染まり、暗く大地を包みこみ、ときに漂っている羊毛のような白い雲。木々は花を咲かせ、イナゴと林檎とユリノキの季節で空気は心地よい香りであふれ、ふらふらと飛びまわっては蜜を作っている蜜蜂たち。水辺で騒ぎ始める小さなカエルたち、キョキョキョと鳴き声を響かせるヨタカ。新たに生まれる命、草木、新芽、花は咲き、生まれてくる仔羊や仔牛。作付けの時で、金色で暖かい太陽に柔らかくなった大地の様子。
ジェイニーの結婚式は金曜日にあった。リチャードはトウモロコシとオーツ麦を収穫し終わり、カッシーとジェンシーと私は庭の植付けをほとんど終えていた。ジェンシーが、名もない曲を鼻歌でうたいながらカボチャ畑で温かい土を盛っては、素手で畝を作っていたこと、黒と金の大きな蝶が飛んできた時に、捕まえようとしてきれいに作った畝を台無しにしてしまったことを、よく覚えている。カッシーは手を腰に添えて立ち、崩れた盛り土を見やった。「もう何してるの! ジェンシー、戻って来なさい! 聞こえたでしょ!」ジェンシーはもう柵を越えて森の端にいて、高い笑い声の返事のこだまだけがそっちから聞こえてきた。
私はいらいらしていた。「カッシー、あの子をどうすればいいの」
カッシーは頭を振り、几帳面に畝を作りなおし始めた。「わからないです、ミス・ベッキー。あの子がなんであんなになったのか。頭がまともに成長しなかったみたいです。どうしようもないんじゃないかと思う時もあります」
私も同感だった。それほどジェンシーの手伝いが必要なわけでもなかった。別にいなくても問題はなかったのだから。それよりも私の責任感が問題だったのだ。きちんと訓練をしなければこの先ジェンシーにいいことはないだろうし、幸せになれることもないだろうと思っていた。私は母と同じように、手は仕事をして喜びを得るためにあるのだと信じていて、今でもその信念は変わっていない。
それでもどうしたらジェンシーの手を仕事に向けさせられるのかわからなかった。新しい赤ちゃんがお腹にいると知ったら、また改心してくれるかもしれない。それでも、それはその時が来なければわからないことだった。
そして、ランキン牧師が結婚式の前日にやってきた。彼は直接父の家に行ったので、私たちはすぐには会えなかった。ジェイニーによれば、結婚式は正午に行うのが流行りらしく、彼女の結婚式ももちろん正午に予定されていた。
レヴィット氏は町に滞在していて、朝に馬でやってくることになっていた。二人の家はまだ完成していなかったので、レヴィット氏はレキシントンのホテルをとっていた。二人はまずそこに行って、ジェイニーは新しい家を実際に見て、そのあと二人はフィラデルフィアで家具を選ぶということだった。レヴィット氏はすでに一、二回行っていたけれど、ジェイニーはフィラデルフィアへの旅を楽しめるだろうし、自分でカーテンや絨毯を選ぶこともできることだろう。ジェイニーは喜んでいた。それは花嫁にとっては大変な旅行になるだろうけれど、ジェイニーはフィラデルフィアに行くのが待ちきれずとても興奮していた。「私のドレス、田舎っぽく見えないといいけど」とジェイニーは言った。 「そんなわけないでしょ」と私は返した。私はドレス選びを手伝っていた。どれもとても素敵だった。
結局、ジェイニーは腰まわりに金色の刺繍が入った美しい青いドレスを選んだ。「ルイヴィルで見た絵をもとに作ったから、最新のスタイルのはず。でも絵からドレープを完璧に再現するのは難しいでしょ。フィラデルフィアで他の人たちがどんな格好をしているか見られればいいんだけど。そしたら必要な手直しもできるのに」
私の結婚式の時のように家は汚れなく輝いていて、部屋中に花が飾られていた。近所の人たちの集まりがなかったのはさびしいものだった。それがジェイニー好みの結婚式だった。ジェイニーは地元の友人たちを呼ぼうとせず、母と父がいくらがっかりしていても、結局はジェイニーの言う通りになるのだった。「家族だけ」ジェイニーは言った。「あと、もちろんクーパー一家。あの人たちも今は家族だし」 「でもどうして、ジェイニー?」母が尋ねた。「みんな変だと思うわよ」 「人がどう思おうと勝手よ。これは私の結婚式だし、下品で無作法な人で家がいっぱいになるのなんて嫌。冗談を言って馬鹿笑いしたり、タバコを噛んで唾を吐いたり、ウイスキーをがぶ飲みする人たちよ。私は静かで、きちんとした式にしたいの」
ジェイニーは流行りの結婚式なんて経験したことはないはずだった。どこでそのようなものを知ったのかわからないけれど、たぶんレヴィット氏に教えてもらったのか、ルイヴィルで読んだ本に載った絵を見たのだろう。ジェイニーは完璧に、ドレスに合わせた小物を身につけ、小さな花の冠を頭に被せ、手にレースの長手袋をして、早春のバラの花束を持っていた。
レヴィット氏もとても格好よかった。真鍮のボタンのついたおろしたての青いコートを着て薄い黄褐色のズボンを履いていた。そして、ランキン牧師はいつも通り黒い服をきちんと清潔に保っているのだった。
式はとても静かで、まったく結婚式という感じがしなかった。私たちの他に、クーパー家しか来ていなかったし、そのクーパー家も全員ではなかった。ジョニーは来ようとしなかった。招待された時、ジョニーは笑っていた。「結婚式で俺に踊ってほしいのか、ジェイニー?」
ジェイニーは顔を真っ赤にして怒った。「違うわ」ジェイニーは短く言った。「来なくていい。どうせあんたは酔い潰れて私たちに恥をかかせるだけでしょう」ジョニーは大体の若い男たちと同じくらいは節度があったから、それはジェイニーの嘘だった。「心配ねぇよ」ジョニーは言った。「行くつもりないから」
ジェイニーは怒って飛び出していった。彼女は思っていた以上にジョニーのことを気にかけていた。決して認めようとはしないが、何時間もそのことで悩んでいたのだ。「ジョニー・クーパーがいなくても私の結婚式を挙げることはできる」と、ジェイニーは言った。
私たちは並んで座った。すべては最高の状態だった。男の子たちは体を洗われて、髪をきれいにとかしていた。そして、会場は静寂に包まれた。式は深呼吸の音が聞こえるほどに静かに行われた。
たいていの弁護士のように、レヴィット氏の声はしっかりしてよくとおるものだった。笑い出しそうになる瞬間もあった。その立ち居振る舞いが法廷での弁護士に見えてしまったのだ。いきなり振り返り、歩きまわって弁論を始めるのではないか、と私は半ば期待したりした。もちろんそんなことは起こらず、レヴィット氏はジェイニーの隣に堂々として立ち、しっかりとした受け答えをしていた。そして、式が終わった時に、レヴィット氏は私たちが今まで見たことのなかったことをした。ジェイニーのほうを向いて、私たちの目の前で、彼女を抱きしめ、キスをしたのだ。それは軽いキスでも、ぎこちないキスでもなかった。リチャードが足をもぞもぞ動かしているのが見えて、私は彼が恥ずかしがっているのがわかった。父が咳払いをした。そうして私たちは二人のまわりに集まって幸運を祈った。
テーブルを見ると、ジェイニーは食べ物についてもやはり注文をつけていたことがわかった。ハムにビスケット、チキンのテリーヌにソース、小さなケーキまであった。もちろん母がこんな料理を作るわけがない。父のおすすめの上等なウイスキーの代わりに、レヴィット氏が送ってくれたワインがあった。レヴィット氏はワインを飲む前にグラスを持ち上げて、ジェイニーに向かって頭を傾けた。 「我が妻に」とレヴィット氏は言った。私たちはみんなどうすればよいのかわからず、不格好に気まずさを感じていた。 それはまったくなじみのない行為だったからだ。
ジェイニーが着替えたあとに、二人はすぐ去っていった。母は玄関の前で腕を組んで立っていた。彼女がこうやって立っているのを私は何千回も見てきたものだ。母は、二人が道に向かって坂を下っていくのを眺めていた。「ああ」ついに少し辛そうに、母は言った。「私の一人目の子が行ってしまう。全然会えなくなってしまうのね」 「大丈夫、ママ」私は母を慰めようとした。「ジェイニーはレキシントンに行くだけ。ときどき帰ってくるよ」
母は頭を振った。「距離は問題じゃないの、ベッキー。ニューヨークに行ったとしても、その気になったら帰ってくるだろうし。そういう子なのよ。あの子は埃の被ったこの古い場所から出ていくのよ。もう帰ってこようとは思わないわ。だから悲しいの」
私も少しは理解できたけれど、ジェイニーが完全に浮ついて、お高くとまってしまうはずはないとも信じていた。頻繁に帰ってくるとは思わなかったけれど、完全に家族を見捨てるとも思えなかった。「帰ってくるよ、そのうち」と私は言った。
二人が去ったあとの家はがらんとしていた。それでも「切り替えましょう」とベティアが言い、私たちは片付けを始めた。 しかし、片付けを始めてすぐに、ジョニーが馬で現れた。これまでの人生でこの時ほど驚いたことはなかった。ジョニーは酔っ払っていて、父、デイヴィッド、リチャードが三人がかりでなだめなければならなかった。ジョニーは唸り、喚き散らして、母とベティアをとても怖がらせた。三人がジョニーをやっとのことで馬から降ろすと、リチャードは彼を殴って気絶させた。そうするしかなかった。ジョニーはジェイニーの部屋のベッドに寝かされた。
私たちはランキン牧師を伴って家に帰った。葬儀は日曜だった。それまでにやらなければいけない仕事がたくさん残っていた。ある意味で、葬儀も結婚式のようなものだ。様々な人々が遠くから集まってきて、仲のいい友人たちは家に泊まって食事をしていく。
葬儀は九時から始まる予定だと知らせていたので、日の出の時間には馬車や馬が集まり始めていた。すでに、かなりの人数が集まっていた。私の家族や私たちへの思いやりから来てくれた人もいたが、多くの人はただ集まることを楽しみにしている。
リチャードは赤ちゃんを、父親の家の裏にある草の茂った場所に埋めていた。そこはインディアン商人のジョニー・ヴァンやその息子、ベティアの死んでしまった子どもたちが埋葬されている場所だった。「他の場所がよかったかい?」あとでリチャードは私に聞いた。 「ううん、大丈夫。あそこは近いし、私たちの家族のお墓にもできるかもしれないわ」 「僕もそう思ったんだ」
参列者を見渡すと、三百人くらいが集まっているようだった。ランキン牧師はいつものように静かに、ゆっくりと、人生の儚さや、人が草のように瞬く間に枯れゆく様について話し始めた。旅立ってしまった純粋な魂について語った。その魂はこの世の罪や悲しみに触れることはないのだから、私たちは嘆くのではなく、喜ぶべきなのだと……。魂は天国で再び創造主のもとへと還り、今も永遠の平安と幸福の中で光の衣に身を包んでいるのだと。その話を理解してはいた。それでも私は考えてしまった。もし、あの子が生きていたのなら、今ごろにはまるまるとして、たぶん首もすわっていて、笑い始めているかもしれない。そして、一度も母乳をあげられなかった私の胸。乾いていることはほとんどなく、痛み、詰まってしまうこの胸のこと。光の衣に包まれず、授乳のために作った服に隠れている。それは悲しい時間だった。私の中に新たな生命が宿っているという確信がなければ、その悲しみはもっとひどかったことだろう。その身体の感覚はたしかだった。
ランキン氏の説教はさらに熱を帯びてきた。ランキン氏はいつも穏やかで、伝統を重んじ、説教壇では荘厳な雰囲気を作りだす人だったので、私には奇妙に思えた。ランキン氏は勉強熱心な人で、聖書の教えを一語一語説くことを喜びとしていたはずだった。 彼が大きな声をあげるところを見たのは初めてだった。その様子はまるで、内なる情熱に火がついたかのようだった。彼は非常に熱心に、体全体を大きく動かしながら熱烈に説教を続けた。私たちの目の前で大きく、力強くなっていくようで、その顔は紅潮し、汗がその顔を流れ落ちていた。ときにはその汗に涙までも加わり、顔の溝を川に変えた。
ランキン氏は人間の罪深さについて、そして悔い改め贖われる必要性を説いた。ランキン氏は言った。救済への唯一の道は、俗世での罪を告白し、それらを捨て去ること。そして受難に耐え、再来したキリストに続くことである。「主の再臨は近い」ランキン氏は叫び、その深い声はトランペットのように響いた。「地獄の番犬はすぐそこまで迫っている! 悔い改めよ……悔い改めよ……悔い改めよ!」
悔い改めること。この言葉は私たちに重くのしかかった。草地に座っていた人々は落ち着きなくもぞもぞと動いていた。罪のない者など一人もいない。耳を塞ぎたくなるような言葉だった。しかし、私たちは反応せず、聖霊の顕れは起きなかった。リバイバル運動はまだこの地域までは広がっていなかったので、私たちはなじみの教会の静かなやり方に縛られていたのだ。私たちの反応が芳しくないのを見て、ランキン牧師はその語気を強めた。お前たちの心は罪にまみれて麻痺している、お前たちは恩を忘れてしまった世代なのだ! と。そして、私たちを金の偶像に自らを犠牲に捧げた人々に例えた。「魂が危険にあるというのに!」ランキン氏は訴えた。「あなた方は家畜や土地や葡萄畑のことしか考えていない。さあ、手遅れになる前に、自分の魂のあり方について考えるのです!」
激しい説教は三時間にも及び、説教が終わった時には、ランキン氏のコートの背中は汗で濡れていた。
私たちはほとんど何もしゃべらずに丘を降りた。ランキン氏と一緒にデイヴィッドとベティアのところに戻った人も、私たちの家に立ち寄った人もいた。何を言っていいか誰にもわからなかった。しばらくして父が言った。「俺はおかしな言い分だと思うがね、ランキンさんの言っていることは。自分がそんなひどく罪深い人間だとも思わん。悔い改めていないと言われてもしっくりこない」 「私たち皆がそうかもしれない」リチャードは考え込みながらそう言った。「私たち皆がそうで、無知でいるだけなのかもしれない」
父はまだ納得がいっていないようだった。「俺が堕落しているかどうかはわからん。最善を尽くしているのはたしかだ。教会には行っている。隣人に親切にしている。俺もハンナも毎日祈りを捧げている」 「それが十分じゃないとしたら?」とリチャードは言った。「(5)パウロ も(6)『行いを伴わない信仰は死んだものです』 と言っている」 「だけど、どうやって行動を示すんだ? 叫んだり、震えたり、踊ったりする奴らだって話だが。俺はそんなことするつもりはない」 「でも、やってみるまではわからないだろう。聖霊に満たされる経験なんて」
私はリチャードを見て少し胸騒ぎを覚えた。ランキン牧師の話は、家に帰ってもリチャードの心に残り彼を悩ませていた。リバイバル派の奇妙な活動の肩を持つなんて、リチャードらしくないことだった。 「リチャード、そんなこと必要ないとわかってるだろ」父は言った。 「いや。わからないんだよ、何が必要で、何が必要でないのか。でもランキン牧師はわかっていると思うから、機会があれば聞いてみようと思う」
その機会が訪れた。その日の午後、ランキン氏が私たちの家を訪ねてきたのだ。ほとんどの人はもう帰っていたので、ランキン氏は説教しようとはせず、私たちに向かって静かに話を始めた。そしてギャスパー・リバーで起きている様々なことについて教えてくれた。「初めてだった。あんなことは今まで見たことがなかったんです。これまでにも語ってきたし、知っていると思いますが、私がギャスパー・リバーで説教を始めた頃は、あそこは驚くほど信仰に無関心な地域だったんです。あそこの人たちは罪にまみれていて、どんな説教に対しても頑なだった。宗教の本質に対する真剣さもまったく感じられなかった。それは変わりました。信仰の炎が彼らをとらえたのです。それはギャスパー・リバーの端々まで広がっています。人々はあらゆるところから集会に来て、そのほとんどが魂の確信に至っているのです」
ランキン氏は小柄で整った体型と顔をしている人だった。これまでに私たちの前で、今の話や今朝私たちが目の当たりにしたような情熱を見せたことはなかった。「どのように始まったんですか?」リチャードは尋ねた。 「ふた夏前、テネシー州から二人の牧師が来て、礼拝の集会で説教をしたんです。あんな説教は見たことも聞いたこともありませんでした。会衆の反応は驚くべきものでした。人々は奇妙な言葉や、動きへと駆りたてられていました。二人の説教はそれほどに説得力があって、終わる頃には疲れ切ってしまうほどに情熱的な説教でした」ランキン氏は続けた。「私自身にもその時、未体験のことが訪れました。いつものように私はきちんと説教の内容を決めていたのです。でも自分の番になった時、私の口からあふれだしたのは決めていた説教でも、私自身の言葉でさえもなかったのです。何を言ったのか覚えてもいません。それは明らかに天からのお言葉でした。私は主の言葉を伝えるただの道具となったのです。主は私を介して初めてお話をされたのです。私は泣き、叫び、熱く語っていました。そういう説教は威厳に欠けるといつも思っていたのにです。そして、喜びや言葉にできない感情に圧倒されていました」
リチャードは熱心に聞き、ランキン氏の話を吟味していた。「その感情はなんだと考えていますか?」 「主のお喜びです」とランキン氏は即答した。「ああ、その恍惚といったら!」 「他の説教者たちに影響を受けてだとは思いませんでしたか?」 「おそらく、ある程度受けていたのかもしれない。でもそうあるべきものなのです、リチャード。火は灯されるべきだったのです」
しばらく沈黙し、リチャードは少しためらいながら言った。「あなたは教会を離れた。そう聞きました」 「別の聖職を得たのです。これまでの信仰の明らかな誤りに気づかされたのです」 「それでは(7)予定説と神の無償の選びについてはどう考えますか?」 「誤りです」ランキン氏ははっきりと言った。「まったくの誤りです。悔いを改め、信仰告白し、そして受難に耐えることによってのみ、救済は保証されます。長いあいだ、誤りのもとではたらいてきたのです。そしてその誤りを教え説いてきました。しかしやっと真実を見ることができて、主に感謝しています」
リチャードは首を振った。彼は明らかに悩まされているようだった。そして、彼が悩んでいるということは、私にとっても悩ましいことだった。私は教会のやり方に満足していたからだ。疑問を持ったことはなかった。しかし、リチャードの中では引っかかることがあり、疑問を抱かせていた。リチャードは質問を続けた。私は落ち着かなかった。「こういう話を聞いたんです。あなたがたの集会では参加者が恍惚状態になって、身体を痙攣させたり、転げ回ったり、踊ったり、叫んだり、知らない言葉で話したりすることがある。幻覚や予言を得ることがあるのだと」 「本当です」 「どう説明されますか?」 「それは聖霊のはたらきによるものです。この時代において、主は人々に刺激を与え、人々を新たな情熱と喜びで満たすのです。主の再臨の前に、信仰を人々に取り戻そうという努力なのです」
リチャードも落ち着かない様子で身動きした。「信じない者は罰せられるのですか?」
ランキン氏はうなずいた。「罰せられるでしょう。もし話を聞き、自分の目で見てもいるのに、信じなかったとすれば、永遠の罰を受ける以外にはありえないのです」 「しかし聞いたことも見たこともなかったら?」 「聞き、目撃するための場所はあります。皆に開かれた、自由な場所です」ランキン氏は言った。「来てください。次は七月の第一週に開かれます。来て自分で見てください。きっと確信が得られると信じています」
リチャードは私を見た。私は行きたくなかった。以前は興味があり、変わった噂を聞いて、お祭り騒ぎを見てみたいと思っていたのは事実だ。しかし、リチャードの逡巡を見て、気が変わっていた。それはまるでおかしな沼地に足を踏み入れてしまい、次の足をどこに置けばいいのかわからないかのようだった。リチャードの悩みが本物なのか私にはわからず、こっちを見られて、私は何も言えなかった。ランキン氏の目の前では沈黙するほかなかった。私の考えや希望は関係ないのではないか、と思いもした。そして、リチャードは言った。「そうだな、行くかもしれない」
そこで私は、私も行くことになるのだと悟った。ランキン氏はいつもリチャードに対して強い影響力を持っていた。リチャードは昔からランキン氏のことを慕い、尊敬していた。何度もリチャードが「ジョン・ランキンはしっかりした男だ」と言っているのを聞いたことがある。その好意と敬意もあって、今のリチャードはランキン氏の導きにはどこまでも従いそうな勢いだった。 「よかった」ランキン氏は言った。「よかったです! 私が理解したように、あなたも理解するでしょう。私の信仰が開かれたように、あなたの信仰も開かれるでしょう」
そうして、私たちはビリーバーズに続くことになる道に一歩、足を踏み入れた。結婚式、葬式、そして一人の男に対するリチャードの信頼。私たちの生活は大きく変わることとなった。
第4章訳註
(1) ローガン郡(Logan County)
ケンタッキー州内に位置する郡。ベンジャミン・ローガンの名を取って命名された。「Rogues Harbour」の異名をもつローガン郡は、殺人犯、泥棒、盗賊などが多く逃げ込む、全国で最も危険な場所とされていた。幾度もの法律制定する試みも失敗したが、1800年Red River Meeting Houseで行われた最初のキャンプ・ミーティングを機にその治安が大きく変わり始めたとされている。
(2) ギャスパー・リバー(Gasper River)
ガスパー川。ケンタッキー州南西部にある全長62.1kmの川。ローガン郡の北東部から始まり、バレン川(Barren River)に流れ込む。
(3) リバイバル運動(Revivalists)
第2章 グレード・リバイバル運動を参照。第2章訳註リストへ
(4) 野外聖餐礼拝 やがいせいさんれいはい(sacramental meeting)
スコットランド長老派がアメリカへ持ち込んだ野外礼拝の形式で、数日間のキャンプ集会のクライマックスに聖餐式が行われる。聖餐式は、キリストの死と復活を記念するためにパンとブドウ酒をもって象徴的に食事をともにすることで、カトリック(ミサ)では礼拝の中心部分をなすが、プロテスタントの礼拝では年に数回特別な日に行われるのが通例。地方の小教会ではその機会が少なかったため、大規模な合同集会で実施され、信仰復興の強力な舞台設定となった。
(5) パウロ(Paul)
初期キリスト教の伝道者。当初はキリスト教を迫害する立場にあったが、幻の中で復活のイエスと出会ったことでキリスト教に回心する。エーゲ海沿岸地方を中心に異邦人に福音を伝えた。60年頃、ローマで殉教の死を遂げたと推測される。
(6) 行いを伴わない信仰は死んだものです
『新約聖書』中の一書、『ヤコブの手紙』の一節。(『ヤコブの手紙』2:26)「魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです」とある。
(7) 予定説と神の無償の選び (Predestination and the election of saints)
あらかじめ救われるものは神の意志によりとうの昔に予定されているという教理。それにもとづく神の選びは無償、つまり人間の信仰や善行は関係しない。この教理に対しては多数の論争が歴史的におこなわれたが、カルヴァンによる選ばれた民であるからこそそれに伴う人間的責任があるという見解はプロテスタントの労働倫理へと影響を与えた。