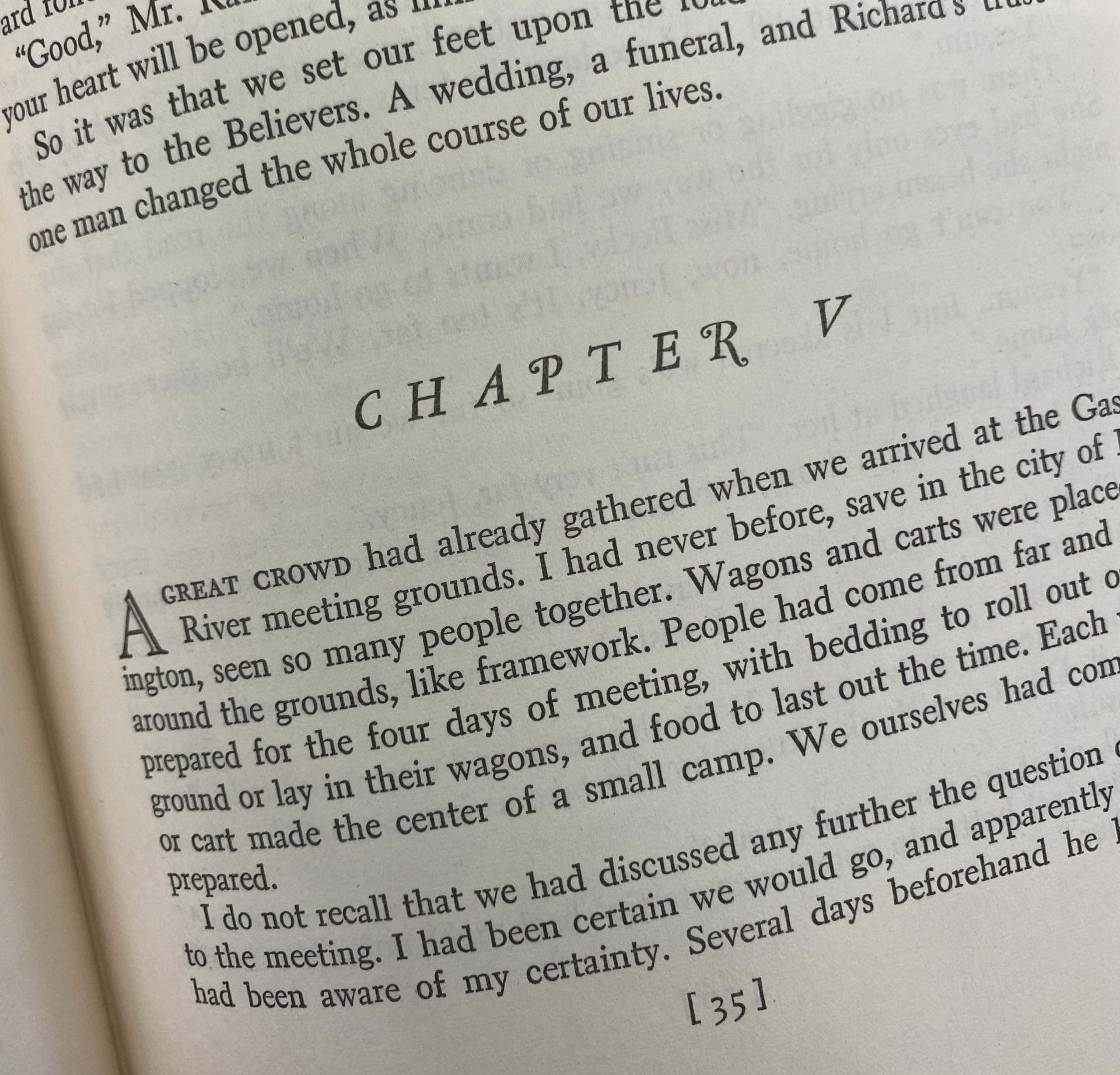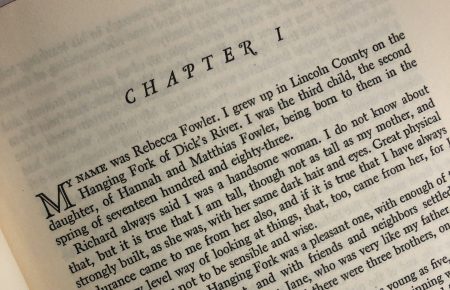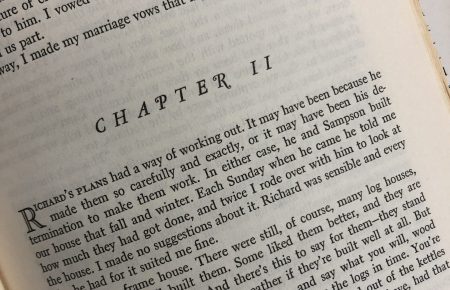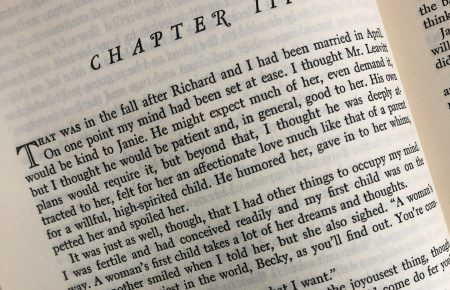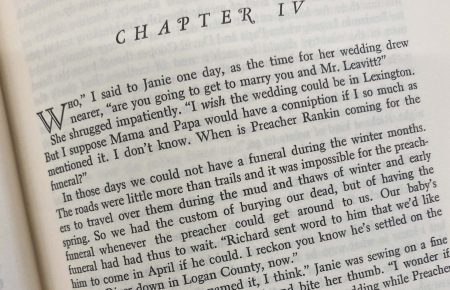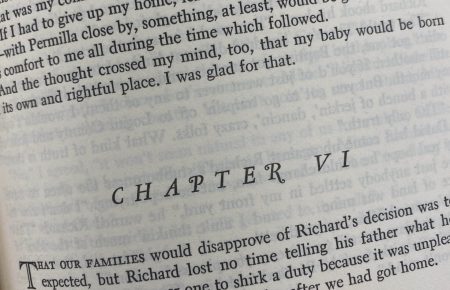私たちがギャスパー・リバーの集会場に着いた時には、すでにたくさんの人々が集まっていて、こんなに大きな群衆を見るのはレキシントンに行った時以来のことだった。たくさんの馬車が、隊列を組むようにいたるところに停められていた。人々は様々なところからやってきていたから、地面や馬車で寝るための寝具や、たくさんの食料を持って、四日間に渡る集会に備えていたのだ。ワゴンや荷馬車がそれぞれ小さなキャンプをつくっていた。私たちも同じようにキャンプの準備を整えていった。
そもそも、集会に行くかどうかをことさら話し合った記憶はなかった。私は絶対に行くことになるだろうと思っていたし、リチャードも私がそう思っていることを感じていたようだった。出発の数日前、リチャードが言っていた。 「ワゴンで行こうと思う。寝る時に便利だろうから」 「そうね」私は賛成した。「サンプソンに新しい藁を入れさせておく」
それから、私はカッシーと準備にかかった。食べ物を用意し、料理のためにやかんや鍋を箱に詰めた。カッシーとサンプソンは仕事があったので家に残ったけれど、何かの助けになればと思い、ジェンシーがついてくることになった。
四日間におよぶ移動の初めの頃、ジェンシーはずっと興奮していた。ワゴンの後ろで藁の上に座り、でこぼこした道を通る時に体が弾むと嬉しそうにしていた。また、新しいものを見るたびに目を丸くしてはくすくす笑っていた。他の時には、太陽と開けた道に喜んで、エンドボードの上を転げ回ったり、ワゴンから降りて花をつんだり、歌をうたったり、踊ったり、ワゴンと並んで走ったりしていた。
しかし、夕方になり見慣れない土地に入ってから数時間が経った頃、ジェンシーは静かに後ろのほうを振り返ってばかりいるようになった。一度、ジェンシーが下を向いて、今来た道を眺めているところを見かけた。ジェンシーが振り返った時、私と目が合った。「ミス・ベッキー、もうすぐ着きますか?」 「まだよ、ジェンシー」私は首を振った。「到着まであと三日はかかるわ」
それを聞いたジェンシーは目を大きく開けて息を大きく吸っただけで、何も言わなかった。
彼女は次の日も、とても静かにしていた。ホームシックなのだと思い、私は見知らぬ田舎の景色にジェンシーの興味を向けさせようとした。「ジェンシー、あの崖の岩を見て。シダがあんなふうに生えてるわよ」 「そうですね」
その日は、彼女からはくすくす笑いも歌も聞こえず、道に沿って踊ることもなかった。ジェンシーはただ、来た道を見つめるだけだった。野営のためにワゴンを停めると、ジェンシーは泣き始めた。「ミス・ベッキー、わたし帰りたいです」 「ジェンシー、今は帰れない。だいぶ遠くまで来てしまったから。すぐ目的地に着くことになるわ」 「はい。でもわたし、帰れなくなっちゃうくらい遠くまで行くのが怖いんです」 リチャードが笑った。「そこまで遠くはないよ、ジェンシー」 ジェンシーは彼女の指のあいだからリチャードのほうを覗いた。「わたしにはすごく遠く感じます」 「それは君が遠出したことがないからだよ」 ジェンシーは声をあげて泣きだしてしまった。「遠出なんてしたくないです! どうやったら帰れますか?」 「来た時と同じ道を戻ればいいんだ。このワゴンを馬たちに引いてもらって、轍に沿って進めばいい。僕が家への帰り方を知らないと思ったかい?」 「いいえ」 「よし、じゃあどうして泣いているんだい?」 「わたしはただ、これ以上離れてしまう前に引き返したいんです」 「それはできないよ」リチャードは素っ気なくそう言った。「だから、そのことは忘れてミス・ベッキーを手伝いなさい」
ジェンシーのさびしげな幼な顔は、私の心を締めつけた。元気づけてあげようと思って、リチャードが馬に水を飲ませにいっているあいだに、新しい赤ちゃんのことを話してあげた。「一月にね」と私はジェンシーに言った。「前の子と同じね」 ジェンシーはむすっとしてため息をついた。「それで、前の子と同じに死んじゃうんでしょう」 「そんなこと言わないで、ジェンシー!」 「はい。でも悪い運はそういうものでしょ。一度憑かれたら、もうなくならないんです」 ジェンシーが、ちょうど恐れていたことを言葉にしたので、私はつい厳しくあたってしまった。「薪を集めて。火を絶やさないようにしなさい」
しかし、四日目に(1)キャンプ場に着いた時に、ジェンシーは、私たちが向かっていたのは自分が考えていたようなこの世の終わりでなくて、実は他の人もいるような場所だったのだと気づいたようで、好奇心をそそられ、元気になり始めた。
新しく建てられた(2)集会所(meeting house)には入りきらないほどの人がいたので、説教は空き地で行われるということだった。二つの(3)講壇が建てられていて、そのうち一つは長い空き地の一端にあり、その四方から木々が迫っていた。子ども連れの家族には好都合の配置のようだった。そこを囲むように停められたワゴンの中に子どもたちを寝かせることができるから、そばの子どもたちの安全を確認しながら、母親たちは説教を聞き続けることができた。
多くの人が丸太やワゴンの(4)轅(ながえ)に座って、赤ん坊を胸に抱えたまま説教を聞いていた。それでも、説教をし、老人にトウモロコシパンを配ったりしている前方の牧師に目を向け集中して聞いていた。
私たちは混み合っていない場所を探してまわった。リチャードも他の人たちも、牧草地の近くで、日光と暑さからは逃れられる場所を探していた。しばらくして私たちはやっと場所を見つけた。子どものいる他の家族のワゴンがとても近くに停まっていて、リチャードは少し落ち着かないようだった。幼い子どもが三人、それで全員かはわからなかった。
私たちがワゴンを停めた時、その家族の女性が夕食を作っていた。その人は火から目を離してこちらを向き、子どもたちはそろってこちらをじろじろと見ていた。母親が手を振ると、子どもたちは四方に逃げ、ワゴンや木の幹の後ろから、またこちらの様子を窺っていた。ワゴンを停め、リチャードが馬を自由にしていた時、その女性はやかんを火から外してこちらに向かってきた。私は一日中座りっぱなしで体が凝っていたので、ぎこちなく車輪を乗り越えて荷台から下りようとした。ジェンシーはすでに荷台から飛び出ていて、講壇と大きく広がる牧草地を眺めながら片足ずつで飛び跳ねていた。 「どうぞ」その女性は微笑みながら言った。「手を貸すわよ」
それがパルミラだった。私のパルミラに関する最初の思い出は、差し出されたその手のことだ。そして、最後の思い出も同じようなものだった。
私はパルミラの手をとり、自分の身体のぎこちなさに苦笑しながら地面に飛び降りた。「ずっと乗ってると脚にくるでしょう。馬は馬で億劫なんだけど、ずっとワゴンに乗っているより馬に乗るほうがあたしは好き」パルミラは言った。
パルミラは私の母と同じくらい、つまり私より少し背が高く、これまで出会った女性の中で最も自然な美しさを備えた人だった。姿勢がよく、太ってもいなくて、やせこけているわけでもなかった。まるで、上品さと実用面を兼ね備えた完璧なプロポーションを、自然がパルミラに与えたかのようだと思った。私が昔読んだ美学の本には、女性の体の完璧な比率は三等分だ、と書いてあった。肩からウエスト、ウエストから膝、そして膝から足首までが同じ長さでなくてはならないのだ。パルミラの身体は、一目見ただけでそんなプロポーションに恵まれていることがわかった。胸もお尻も豊満で、エプロンが巻かれた腰は引き締まっていた。
パルミラの顔を見ると、肌は新鮮なクリームのようで、年齢を重ねたしわがなく、滑らかで彫りが深かった。どの部分も目立ちすぎず、ちょうどよい形をして互いに調和し合っていた。鼻や眉、顎、口すべて気品のある形をしていた。
彼女の眼は真夏の青空のように深い青色で、カールした長いまつ毛はふちどられていた。髪は前から後ろへきつく縛られ、首のところでお団子にされていた。髪は熟したトウモロコシのような金色をしていた。パルミラは帽子を被っていなかったが、それがまったく自然だった。「遠くから来たの?」 「リンカーン郡からよ」 「大変だったんじゃない?」 私はうなずいた。「四日かかったわ」 「私たちは近所から来たの。馬で来ようと思えば来られたんだけど、夫のトーマスが野宿をするにはワゴンが必要だって言ったからね」 「これまでに集会に参加したことある?」 パルミラは首を振った。「いいえ。でもいろいろ話を聞いていたから。実際に見たいと思ってね。だから子どもたちを詰めこんで来たってわけ」 「子どもは何人いるの?」 「この三人だけ。森の中に住んでいるもんだから、こいつらも自然の一部みたいなもの。マナーがなくて恥ずかしいわ」 「そんなこと。子どもって好奇心が強いものよ」
パルミラは少し笑って言った。「まあ、そんな機会がないから、賢くなるのを期待してもしょうがないね。あなたたち、今晩一緒にご飯を食べない? もうすぐ支度ができるし、疲れて料理する気にならないでしょう」 たしかに疲れてはいたが、リチャードは知らない人とご飯を食べるのは嫌がるだろうと思った。「夕飯は自分たちで食べるわ」私は言った。「でもありがとう」 「気にしないで」とパルミラは言った。
リチャードが馬に餌をあげ終わり、ワゴンのほうにやってきたが、私が知らない女の人と話しているのを見て躊躇していた。パルミラはリチャードに笑いかけた。「パルミラ・ベネットです」パルミラは言った。「すぐ隣でキャンプしてるの。夫はトーマス・ベネット。あなたたち遠くからやってきたみたいだから、奥さんを夕食に誘ったところ」 リチャードは自己紹介をし、私が思った通り、パルミラたちと夕食を共にすることに躊躇した。「面倒をかけたくありません」リチャードは言った。 「面倒だなんてとんでもない。トーマスが戻ってきたら、すぐに準備できるもの」パルミラは手で陽を遮り、草地を見渡してから、笑い始めた。「噂をすれば、やってきた」パルミラは少し待って、大きな声を出した。「トーマス! トーマス! こっちに来てクーパーさんたちに挨拶してちょうだい」
私はとてもびっくりした。私の父ほど高齢の男性がよろよろとこちらに歩いてきたのだ。げっそりとやせて、無精ひげを生やし、肩は曲がり、グレーの髪が帽子からこぼれ落ちていた。私の驚きが顔に出ていたのだろうか、パルミラは淡々と言った。「夫は少し年齢が上なの」
仲良くなったあとで、パルミラは過去のことを話してくれた。貧しい家族に生まれ、森で育てられたことや、何も持っていなかったことを。そして、トーマスがやってきた時、パルミラの人生をひどいものにした義母から逃れるために、年老いたトーマスについていったことを。貧しさはたいして変わっていないのだろうが、夫にひどい扱いを受けていないのなら、義母といるよりよっぽどましなのだろう、と私は思った。
トーマスはリチャードに感じよく挨拶をし、小さくおじぎをした。「夕食に誘ったところよ」パルミラはトーマスに言った。 「ただし」リチャードは付け加えた。「私たちも料理を持っていきます」 「それでいいな」トーマスは言った。 「あたしは食事の準備に戻らないと。食べるものがなくなるわ」パルミラは笑った。
トーマスは集会所を案内しようとリチャードに提案し、二人は出かけていった。パルミラは二人の背に向かって叫んだ。「あまり遅くならないでよ! すぐ食事の準備ができるから」 「すぐに戻るさ」トーマスは返事した。
パルミラと私は夕食の準備を始めた。集まってきた子どもたちはみんな同じくらいの年齢で、四、五歳に見えたけれど、本当のところはよくわからなかった。「この二人は双子?」私は聞いた。
パルミラは笑う時に頭を後ろに振るくせがあった。その様子はとても美しかった。「いいえ。でもそんなようなものね。全員十カ月も年齢が離れてなくて。その子は……」パルミラは女の子を指した。「ナンシーよ。六歳なの。マシューとアーロンはどちらも五歳。で、春にもう一人生まれるの」 「そんなに年が近いと大変でしょう」と私は言った。 「ときどき気が狂いそうになる。でもどうにかなるものよ。でもこの次の子が少し心配ね。もう体力が持たないかも。妊娠しないようにしたんだけど、いくら老人でもずっと拒否し続けるのはね」パルミラはため息をついてから笑った。「まあ、そんなにひどいわけじゃないわ」
私は、パルミラのオープンな話に少し決まり悪く感じ、かなりショックを受けた。とはいえ、女性同士のおしゃべりというだけで、特に深い意味はないのはわかっていた。それにトーマスのことを思い出すと、パルミラの言い分も理解できた。
その晩の夕食は、その後の四日間の集会の本当の始まりだった。私たちは一つの大きな家族のように食事を共にし、パルミラと私は、まるで互いのことをずっと知っていたかのように家事を分担した。パルミラは私と同じように家事をてきぱきとこなし、私たちは一緒に働くことにこれっぽちの違和感も感じなかった。私がパンを焼けばパルミラは肉を焼き、私が残り物を片付ければパルミラが食器洗いをした。二人で分担を話し合う必要さえなかった。私たちはまるで一つの体に腕が四本あって、お互いが何を必要としているのかを自然とわかっているかのようだった。
翌日の朝、最初の説教が始まった。四人の説教者が一日中交代で説教をした。正午に、食事をとるための休憩がしばらくあり、そのあと説教が再開された。陽が落ちる頃には、私はがっかりしていた。いつも行っている教会での集会が一日中続いているようだと思った。盛り上がりそうにはならなかったのだ。私が夕食の時、そのことを話すと、「本格的になるのは夜の説教らしいわよ。きっと本番は今夜からね」とパルミラが教えてくれた。
彼女の言うことは正しかったのだ。東の講壇付近に炬火が灯された。夜には説教者たちは一つの教壇で交代して説教をするのだった。暗闇が森と草地を覆い、炬火が煙と赤い輝きを人々の顔に落とした。それは説教者たちを鼓舞するようだった。
説教者たちは少しずつ説教をし、すぐに交代した。説教と同じくらい(5)歌がうたわれ、だんだんそれが増えていった。その歌はとても奇妙なものだった。普段教会でうたっている、落ち着いた賛美歌とは違い、速いテンポのものだった。しかし、中にはこの歌に慣れている人もいて、その歌をすんなり受け入れ、自分たちもうたい始めた。人々はうたいながら体を揺らし、手を叩き、時折「グローリー!」と叫ぶ人もいた。日中は姿を見せなかった、一人の説教者が前に進みでた。私は人々の顔に期待と興奮の表情が浮かぶのを見た。その説教者こそが、聴衆が集会に来た目的であり、待ち焦がれていた人だった。「あれは誰?」私はパルミラに小声で聞いた。私たちはその説教者がよく見えるように、聴衆の外側に残った。 「テネシーから来たブラザーの一人。誰だかは知らないわ」 聴衆たちが皆立っていたため、私たちも同じように立っていた。
背が高く、細身で、浅黒い肌に太い眉を持ったその男は、しばらく静かに聴衆をじっと見つめた。そして、まるで銃を突きつけるかのように、腕を伸ばし聴衆に向かって叫んだ。「お前たちは呪われている! そして地獄の炎がお前たちを待ち受けている!」うめき声が聴衆から湧き上がり、どこかで女性が悲鳴をあげるのが聞こえた。「お前たちは呪われている!」男は繰り返した。その男の声は低く、大きく、森の端まで届いた。
私はよく声の効果について考えることがある。最高の説教者は必ず、よい深い声を持っている。声に威厳が備わってさえいれば、説教の内容はあまり関係ない。説教者がたしかで威信に満ちた声を持っていれば、聴衆を導き、統治し、彼らを操縦することは簡単だ。同じように、弱々しい声では、何を言っても問題にならないのだ。その男は威厳を持って話した。その声は破滅の咆哮のようで、トランペットのように響き渡った。感動しまいと思っていた私でさえ、身震いするほどだったのだ。
その男がどれくらい説教をしたのか、覚えていない。時間の感覚はなくなっていた。男が話し始めて十五分で、私たちはランキン氏の話に聞いていたようなことが起こり始めるのを目撃した。聴衆は両腕を突き上げ、何度も回転し、死んでしまったかのように地面に倒れ込んだ。まるで死体のように硬直し、踏まれないところへ運ばれていった。
私たちから割と近いところにいた女性が、痙攣し始めた。女性の痙攣は頭から始まり、折れるのではないかと思うくらいに首を揺らし、腕、手、そして身体全体が震え始めた。それは身体がばらばらになったかのようになるまで続いた。女性の隣に立っていた夫と思しき男性は、まわりの人々から彼女を守ろうとしていた。最後には彼女を講壇の説教者のところへ導いていった。
ある人々は円になってゆっくり踊り、ときに激しく回転した。今度は、聴衆が奇妙で理解できない言葉を発し始めるのが聞こえてきた。どこを見たらいいのかわからず、未知の場所で私は呆然とし、困惑していた。
リチャードが私を肘でつついた。「ふちを回って前のほうに行ってみよう。まわりの音がうるさすぎて説教者の声が聞こえない」 私はパルミラにそのことを伝え、みんなで人をかきわけ先頭に進み始めた。「どう思う?」パルミラが後ろから聞いてきた。 「わからない」私は正直に答えた。「こんなもの今までに見たことないわ」 「もしこれが説教者の言うように、聖霊のはたらきだとしたら、妙なやり方よね」
私は聖霊のはたらきについて何も知らなかった。私自身は自分が(6)契約の子だと信じるように育てられてきた。両親は、物心つく前に私に洗礼を受けさせている。予定と(7)聖化 によって、自分は救済されるうちの一人だと信じて疑ったことはなかった。聖霊の力によって身体が動くというのは、私の考え方とはまったく違うものだった。しかし、もしかしたらランキン氏とこの説教者は正しいのかもしれない、とも私は考えた。今まで教わってきたことが間違いだったのだろうか? ランキン氏だって、自分の信仰の誤りに気づいたと言っていた。しかもランキン氏は牧師だった。私はとても心配になりつつあった。
私たちは講壇の近くに空いている場所を見つけた。倒れた人が多すぎて、その場所が空いたのだろう。講壇のすぐ前の踏みつけられた草にひざまずいているのは、涙を流し、叫び、踊り、祈りながら、祈りを捧げてもらうために前に進み出てきた人たちだった。説教者はそうした人々の上に立ち、熱心に賛美歌をうたい、力強く祈っていた。
私は、リチャードが深く心を動かされているのがわかった。前のめりになって熱心に今起きていることを感じ、その表情はまるで説教者の言葉がぶつかってきているかのようだった。「あの人には力があるんだ」リチャードがつぶやくのが聞こえた。「本当に力があるんだ」 私は立っているのにも疲れてきたが、まだ少しは興味が残っていた。その時、リチャードが突然前に進み出た。「僕は上に登って、祈りに行ってくる」 恐ろしくなって、私はパルミラとトーマスのほうを振り返った。「私も行くわ」私は二人に伝えた。 「あたしたちも行く」パルミラは言った。そして、四人で教壇の前でひざまずいている人々の中に加わった。
実を言うと、私はただ地面にひざまずき、まわりの音を聞き、輪になって踊る群衆を警戒しながら、やっと座れたことをありがたく思っていただけだった。ずっとリチャードの近くにくっついていた私は、リチャードがさらにのめりこんで祈りに没入した瞬間を感じた。汗がその頬を伝い、口が動いた。しかし、出た声はまわりの音にかき消された。パルミラは私のすぐそばに座り、そのそばにトーマスが座っていた。二人も私と同じで、感銘を受けるというよりはおもしろがっているように見えた。
いきなり肩を触られ、私は驚いた。「やあ、レベッカ。君もリチャードも来たんだね」それはランキン氏だった。私はリチャードの方を指すと、ランキン氏はリチャードの肩に手を置き、身をかがめた。「そのまま動き続けるんだ、リチャード」ランキン氏は諭した。「その調子だ。報われるだろう」
とうとう、リチャードの身体が痙攣し、身体が前にドサッと倒れた。私は怖くなりリチャードに手を伸ばそうとしたが、ランキン氏に咎められた。「最初の徴だよ。そっとしておいてあげなさい」ランキン氏はリチャードの隣にひざまずき、自分も声をあげて祈りを捧げ始めた。
その晩、リチャードにそれ以上の啓示が訪れることはなかった。ついに疲労が限界を越え、私たちはキャンプ場に戻り、無言でトーマスとパルミラと別れた。「赤ん坊になった気分だ、力が完全に抜けてしまった」リチャードは私の隣で言った。
ワゴンの下の藁のベッドに寝ていたジェンシーがすすり泣いた。「ミス・ベッキー、寝られないんです。うるさすぎて眠れません。いつまであれを続けるのですか?」 「わからないわ」私は答えた。「頭を藁に突っ込むしかなさそうね」 ジェンシーはそのあと静かにしていたので、その通りにしたのだろう。私自身はすぐに寝つくことができたが、集会は一晩中続いたらしかった。
二日目の晩も、三日目の晩も、リチャードに一日目以上の徴は訪れなかった。それでも、リチャードは毎日前に進み出て、真剣に祈っていた。パルミラとトーマスと私も毎日ついていった。
最後の晩の直前、夕食を食べている時にリチャードが話し始めた。「僕には確信がある。でも啓示を授かることができないんだ」 トーマスが彼を見た。「あいつらが真実を語ってると思うんだな?」 「語っているんだ。残っていた疑念はなくなった。でも、なぜか顕現が来ないんだよ」 「もしかしたら今夜来るかも」パルミラが言った。 「そうなるよう祈っている」リチャードは私のほうを向いた。「レベッカ、もう以前のような誤った信仰に戻ることはできない」 私は、ランキン氏がリチャードに話しかけた時からこのことを見越していたにもかかわらず、「私には何を言っているのかわからない」とだけ言った。 「誤りを説いている教会から離れなければいけない」 「それでどうするの?」私は、幼い頃から友人や家族と集まった、小さな丸太で建てた集会所のことを思い出して、懐かしくて仕方がなかった。ギャスパー・リバーになんて来なければよかったと思った。 「わからない。いずれわかると思う」
私はリチャードの心境がなんとなくわかった。まず疑念が起こり、次に恐怖、最後に確信。 これから何が起きるのかは理解できていなかったとしても、何かが起こるのだ、という確信はあった。リチャードの信仰はひっくり返ってしまった。その信仰がどこにあるのか、それがどこに繋がっているのか、私にはまだわからなかった。後戻りするという選択肢がないことだけは、たしからしかった。
最後の晩、ランキン氏が説教をした。他の日、ランキン氏は日中に説教をし、夜は二人のブラザーたちに説教を任せていた。しかし他の二人が疲れ果ててしまったので、ランキン氏が代わりに立つことになったのだ。そのことが、最終的にリチャードの殻を破るのにどれくらい影響したのかわからないが、何かしらの影響はあったに違いない。リチャードはランキン氏のことを敬愛し、信頼していたのだから。そのランキン氏が自分に向かって、お前は呪われている、と説き、告解と悔い改めによる救済を差し伸べた時、ついにリチャードは残っていた理性から解き放たれたようだった。私はそれを目撃してしまった。普段はおとなしくて穏健な夫が、くるくると踊り狂い、泣き、笑うところを。そして顔に喜びが広がり、私には理解できない言葉を叫ぶ奇人になるのを。リチャードが叫んでいた言葉を理解することはできなかった。
ランキン氏はリチャードが我を忘れる姿を見て、講壇から降りてきて賛美の言葉を叫び始めた。しかし、リチャードはランキン氏に気づきもしなかったろう。「どうすればいいのでしょうか?」私はランキン氏に聞いた。「リチャードが怪我しないか心配だわ」 「そっとしておいてあげなさい」ランキン氏は答えた。「落ち着いたらキャンプに連れて帰っても大丈夫です。神に感謝しなさい。リチャードの魂は神に届いたのです」
神に感謝する気にはあまりなれなかった。リチャードが正気を失う様を見て、当惑するばかりだった。そして、リチャードのものが移ったのか、自分自身から湧き起こったのかわからないが、リチャードのすぐあとに、トーマスも奇妙な言葉を発し始めた。パルミラは驚いて夫を一瞥し、ランキン氏に言われたようにそばを離れた。「驚いた。まさかトーマスに起こるとは思わなかった」パルミラは私に言った。 「静かに、私たちは自分たちのために祈ったほうがいいと思う」 「そうしたら。私はもう十分祈ったわ」
そう言っても、パルミラはリチャードとトーマスが落ち着いて、キャンプに連れて帰られるようになるまで隣にいてくれた。群衆は、畏れるように道をあけてくれた。神の力に屈したものは誰でも、まるで天使のお告げを受けた者のように扱われた。何人かは、自分たちも同じ啓示を受けられることを期待して、二人に触れようと手を伸ばしたりしていた。
リチャードはその晩、子どものように眠りに落ちた。リチャードは馬車まで運ばれたことや、私がそっと藁に寝かせてあげたことにさえ気づいていなかっただろう。まるで夢遊病者のように、おとなしく私についてきて、言われたことをやるだけだった。リチャードは一言も話さなかった。深い寝息が聞こえてきて、彼が眠りに落ちたことがわかって、私はやっと気を落ち着かせることができた。神経をすり減らされ、混乱させられる一日で、私はベッドの心地よさに慰められた。夫の中に知らない人間がいることを感じ、少し泣いてしまった。それでもこの人はリチャードで、私の夫であり、私の隣にいるのだ。
そして集会は終わりを告げた。
しかし私たちはすぐに家に帰り始めたわけではなかった。「ブラザー・ランキンと話をしてくる」次の朝、朝食さえ食べる前に、リチャードが私に言った。
リチャードがランキン氏のことをそんなふうに呼んだのは初めてだった。この新しい信仰において、男はみな兄弟で、お互いにそう呼び合うのだった。リチャードが行ってしまうのを見送りながら、私は次に何が起きるのかわからず、不安でいっぱいだった。ジェンシーが頭に藁をくっつけたまま、荷馬車の下から這い出てきた。「ミスター・リチャードはどこへ行ったの? 私たち今日帰るでしょ?」 「わからないの」私は言った。「ミスター・リチャードはランキンさんと話をしにいったわ」 「ミス・ベッキー。私たちをずっとここにいさせるのよ。二度と家に帰れない」ジェンシーは泣きだした。「私帰りたいんです。ママに会いたいです。こんな場所いや」
私は気の毒に思いつつも、いらいらしていた。「家には帰るわよ」私は保証してあげた。「たぶん今日ね。ミスター・リチャードは少しだけランキンさんとお話ししたいだけよ。もうすぐお母さんに会えるわ。さあ、お水を飲んできなさい、いい子だから」 ジェンシーはドレスの裾で涙を拭いた。表情は悲しみで沈んでいた。「ミスター・リチャードは違う人になっちゃったのでしょう?」
本当にリチャードは変わってしまっていたけれど、ジェンシーにそれを言うことはできなかった。「自分のことをしてきなさい、ジェンシー。私たちは帰れるわ、約束する」 「どうしてわかるのですか?」ジェンシーは疑い深そうに聞いた。 「もう、頭を使いなさい。私たちには畑と家があるのよ、そしてカッシーとサンプソンの監督もしないといけないのよ。ここにいられるわけがないじゃない」 ジェンシーの表情は明るくなった。「本当ですね、家に戻って片付けることがある」 私はジェンシーにやることがあるという考えが彼女の慰めになったことにほっとし微笑した。
私は朝食をパルミラと共に作っていた。「あなたとトーマスはいつ出発するの?」 パルミラは肩をすくめた。「聞いてない。トーマスはリチャードと一緒に、あの宣教師に話をしにいったよ。一日だけの旅路だからね、そんなすぐに出発しなくてもいいの。でもあなたは早く帰りたいでしょ」 「ええ」私は正直に認めた。
夫たちが朝食までに帰ってこなかったので、子どもたちに食事をさせ、しぶしぶ自分たちも食べ始めた。私たちは夫たちのぶんの朝食を残し、朝食の片付けをして、荷造りをした。そのあとは二人が帰ってくるのを待つだけだった。
朝も遅くなってからやっと二人は帰ってきて、真剣で重たい表情を浮かべていた。 パルミラも私も、何も聞かなかった。二人は朝食を食べたあと、それぞれ馬を馬車につないだ。「さあ、これでお別れね」私はパルミラに言った。 「そうね」パルミラは私の手を握りしめて言った。「でもきっと次の集会で会えるわ」 「だといいわね」
パルミラは突然、両腕で私を抱きしめた。「レベッカ、元気でね。あたしはあなたが大好き。こんなことはめったにないわ」
トーマスが先に馬車の準備を終え、四日間私たちの家となった場所を出ていった。パルミラは手を振り、子どもたちも手を振り、トーマスはお別れに頭をひょいと下げた。「いい人たちだ、親切で」リチャードが言った。「隣人としてあの家族がいるのはいいことだね」
リチャードの発言はこれから起こることの前触れで、道に出たあと、リチャードは自分の決意を話した。「グリーンの土地を売って、ここの土地を買おうと思う」
その話について私は理解しようとしたけれど、あまりに急すぎた。「私たちの土地を売るということ? 譲ってもらった土地を? 新しい生活を始めるのにあんなに頑張ったのに?」 リチャードはゆっくりとうなずいた。「ブラザー・ランキンにそのことを話したんだ。僕はあの人がいるところにいたいんだよ。今まわりにいるのは世俗の人間ばかりで、信念を理解してくれないだろう。この土地で、聖霊の力を受け入れた者たちで、力を合わせるべきなんだよ」
しかし、私は聖霊を受け入れてはいなかった。私のまわりにいるのは、理解のない世俗の人間ではなくて、私の家族だった。一体誰と力を合わせろというのだろう。私は異質な地でよそ者になってしまうことだろう。私は、自分の故郷と似てはいてもどこか違う、この土地を見渡した。なぜかはわからないけれど、私はリチャードに言われたにもかかわらず、この見慣れない土地で暮らすことなどまったく信じられなかった。理屈にも合わないことだと思った。そもそも、私たちはリンカーン郡で生まれ育った。子どもの時から、近所の人で知らない人などいなかったし、知らない人が地域に入ってくることもなかったのだ。ここでは私たちがよそ者なのだ。よりによって、ローガン郡、犯罪者と違法者の場所、にいなければいけないのだ。
私は母のことを強く想った。母の力強い、優しい両腕に泣きながら飛びこんで、リチャードの馬鹿らしい計画から守ってほしいと思った。しかし、この考えは、あふれだすと同時に消えていった。私は女だ。結婚もしていた。私の夫が考えたことなのだ。そのうえ、もうすぐ子どもが生まれる。既婚女性には義務や責任がある。既婚女性は安心を求めて、泣きながら母の腕に飛び込んだりはしない。それは、子どものやることだ。女性は強さや安心感を夫に求めなければいけない。
リチャードがまた話し始めた。「ブラザー・ランキンがいい畑を知っているんだ。そこを買えばいいと言っている。グリーン・リバーの畑ほど大きくなくて、僕たちがいいスタートを切るためにはちょうどいいだろう」 「もし」私は突然切り出した。「もしお父様のデイヴィッドが土地を売らせたがらなかったら?」 「父は権利証書と一緒にあの土地を譲ったんだ。土地を売るのに口出しはできないよ」 「でも気に入らないでしょうね」 「初めはそうかもしれない。もちろん売る相手は慎重に選ぶし、時間が経てば父もわかってくれるんじゃないかな」
その土地はもともとデイヴィッドのものだった。どれだけ気心が知れていても、自分たちの前庭によそ者が住むなんて、決してデイヴィッドは好まないと私はわかっていた。それでも、リチャードの考えを変えるのも無理だとわかっていた。リチャードの頑固さならこれまでずっと見てきたし、理解していた。義務を確信してしまえば、心を決めるのに躊躇しない人なのだ。他に何が期待できるというのだろうか。「どのくらい早く引っ越すつもりなの?」 「しばらくはしないよ。まずは収穫だろ。そのあとに土地を売って、新しい土地を買って、来年の春に向けて土地を耕し始められる」
リチャードを疎ましく感じたのは、結婚して以来初めてのことだった。リチャードは考えていることをほのめかしさえしなかった。彼はランキン氏のところへ一人で行って、勝手にことを決めてしまったのだった。
もちろん、我が家のことに関しても意見を求められたことはなかった。自分の父に与えられた土地に、自分の判断で家を建てたのだった。男性が先に立ち、進むべき方向を決めるのは当たり前のことで、女性はただついていくだけである。しかし、女性の人生が根本から変わってしまう場合には、せめて相談してくれてもいいのではないかと思った。しかし、私は何も言わなかった。言ったところでいいことは何もないし、もっと悪い方向に話が進んでしまったかもしれなかった。「カッシーとサンプソンとジェンシーはどうするの?」私は尋ねた。
リチャードは驚いたように私を見た。「一緒に来るに決まってるだろ。今まで以上にサンプソンが必要になる」
ジェンシーはおそらくすべてを聞いていたらしく、突然泣き崩れた。「言ったじゃない、ミス・ベッキー。言ったじゃない、家には帰れないんですね!」
リチャードが振り返った。「ジェンシー、静かにするんだ。でなきゃ馬車を止めて、鞭打ちだ。今、家に帰っているところだろう」 「でもずっとじゃないでしょ。そう言ったでしょ。この神に見捨てられたところに引っ越すんでしょ」
リチャードは怒りだした。「そんなことは二度と聞きたくない、ジェンシー。この土地で神に見捨てられたのではなく、祝福を受けたんだ。主の意思はこの地で啓示された。主のお望みは明らかだ。僕たちは約束の地に引っ越す」
ジェンシーはすぐリチャードのことを怖がった。リチャードの黒人に対する態度は公平だったが、ときにとても厳しくなることがあった。ジェンシーは鼻をすすり、もごもご言った。「約束の地になんて見えないです」 リチャードにもそれが聞こえていたかもしれないが、内容までは聞こえなかったのだろう。リチャードはただ「もういい、ジェンシー」とだけ言った。
私たちはしばらく何も言わずに進んだ。私が最初に口を開いた。「トーマスとパルミラもギャスパー・リバーに引っ越すの? 隣人になるって言ったでしょう」 「ああ、僕たちの隣の土地を買うことになった」
私は、パルミラが同じように、そのことを伝えられているのだろうかと思った。私とは違って、パルミラはトーマスに言い返していることだろうと想像して、私はすこし微笑んだ。しかし、パルミラから聞いた話から推測すると、ギャスパー・リバーは彼らの今住んでいるヒルファームと比べたら、かなりいい土地だろう。だから、パルミラは引っ越すことに喜んで同意するかもしれない。
パルミラが隣人になるということが、唯一の慰めになった。家を捨て、家族と離ればなれになり、知らない土地に行かなければいけないのだから、パルミラの近くに住めることだけがせめてもの救いだった。私はこの温かい気持ちに、今後ずっとしがみついていくことになった。
私の赤ちゃんもこの正当な土地で生まれることができるのだ、という考えが頭をよぎった。そして、とても嬉しい気持ちにもなった。
第5章訳註
(1)キャンプ場(camp)
キャンプ・ミーティングの会場。キャンプ・ミーティングはアメリカ合衆国の開拓期である19世紀に当時のフロンティア地域で行われた、野外での宗教復興集会の一種。キリスト教の長老派教会からはじまった集会様式。
(2) 集会所(meeting house)
ここでは、ギャスパー・リバー・ミーティングハウスのこと。第二次大覚醒期のキャンプ・ミーティングに際してギャスパー川のほとりに建設されたログ・ハウス。
(3) 講壇(platform)
キャンプ・ミーティングで説教者が立った説教用の台。キャンプ・ミーティングでは、講壇を異なる宗派の説教者が交代で用い、説教を行った。第二次大覚醒期の記録図には、木造の簡単な造りで、屋根付きの講壇が多数記録されている。
(4)轅(ながえ)
馬車・牛車(ぎっしゃ)などの前方に長く突き出ている2本の棒。先端に軛(くびき)をつけて牛や馬にひかせる。
(5) 歌がうたわれ
キャンプ・ミーティングでは、即興の旋律や既存の旋律に、聖書の言葉などを乗せて歌う讃美歌が謡われた。即興の讃美歌は、同じ歌詞を繰り返し、その都度少しずつ変化させながら、徐々に韻律の形を整えていき、誰でも簡単に覚えられるようにした。なお、シェーカーにも類似の讃美歌があり、シェーカー・ソング(shaker song)と呼ばれる。第7章にて後述。
(6) 契約の子(a child of covenant)
神との契約を交わした子。創世記17「契約と割礼」に、「わたしは、あなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そして、あなたとあなたの子孫の神となる。(中略)だからあなたも、わたしの契約を守りなさい、あなたも後に続く子孫も。あなたたち、およびあなたの後に続く子孫と、わたしとの間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて、割礼を受ける。」とある。よって、教徒の子は等しく生まれながらに神と契約を交わしているとする。(ただし、解釈は宗派による)
(7) 聖化(sanctification)
キリスト教で、聖霊の働きによって人間が罪から救われ、神の聖性にあずかり、聖なるものとされること。