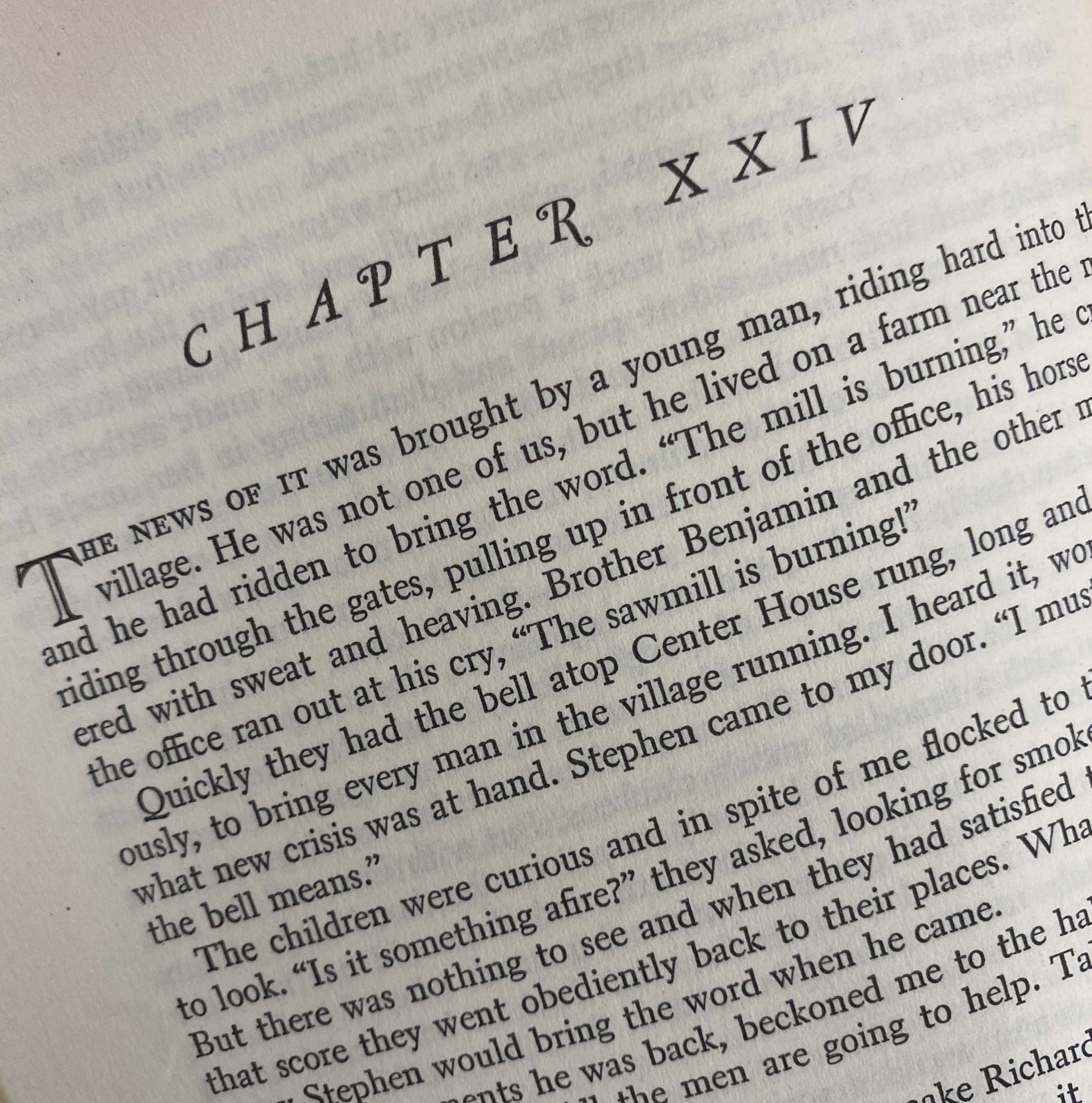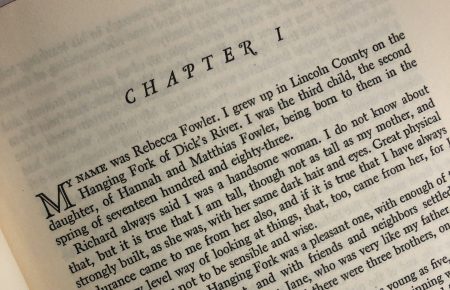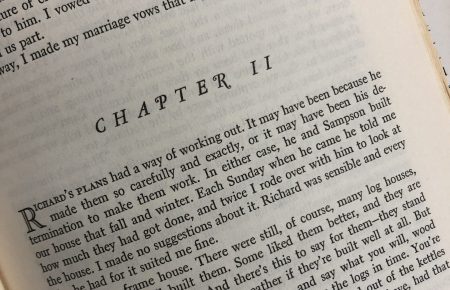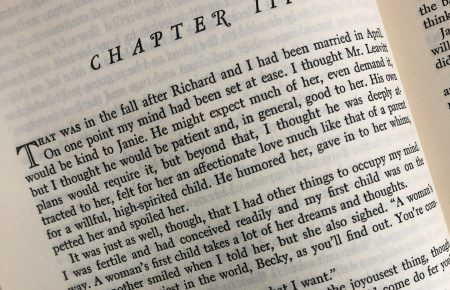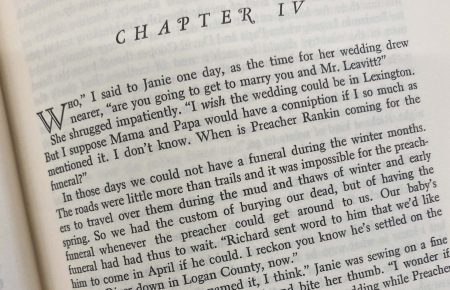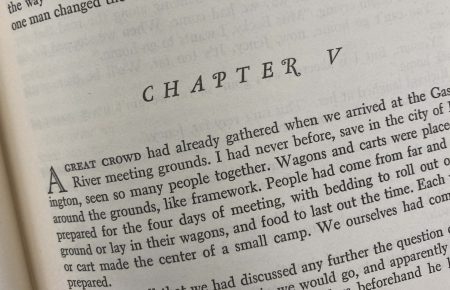その知らせは、ヴィレッジに駆けこんできた若者によって伝えられた。彼はシェーカー教徒ではなかったが、製材所の近くの農場に住んでいて、私たちに知らせるために馬を走らせたのだった。「製材所が燃えています」彼は叫んだ。門を通り抜け、事務所の前に到着した時、彼の馬は泡汗をかいていた。「製材所が燃えています!」ブラザー・ベンジャミンや他の男たちは、彼の叫びを聞いて事務所から走りでた。
彼らはヴィレッジのすべての男性を急いで向かわせるために、すぐにセンター・ハウスの頂上の鐘を長く、騒々しく鳴らした。私はそれを聞いて、どんな危機が間近に迫っているのだろうかと思った。ステファンが私の教室のドアまで来た。「なぜ鐘が鳴っているのか、確かめなければなりません」
子どもたちは何が起きているか知りたがって、私に構わず外を見るために窓際に群がった。「何か燃えてる?」煙と炎を探しながら彼らは尋ねた。しかし、他に見えるものが何もなく、見飽きて満足すると、彼らは素直に自分の場所に戻った。それが何であれ、私はステファンが戻ってきて事情を伝えてくれるとわかっていた。
すぐに彼は戻ってきて、私にホールに来るように合図した。「製材所が燃えています、レベッカ。すべての男性が消火を手伝っています。学校のことをお願いします」
私は、このことがリチャードにとってどれほどの心痛をもたらすかを考えた。製材所での仕事に誇りを持ち、利益が出るように懸命に働いてきた彼にとって、どれだけ衝撃的なことだろうか。私は彼らが製材所を守ってくれることを望んだ「どのように出火したんですか?」
「放火されたと言っていました。一報をくれたこの少年が……火を見て助けを求めてきて、ブラザー・ランキンによってそのことを伝えるようにここによこされました。私は行かなければなりません。すべての男性が必要とされていますから」
「もちろんです。あなたのクラスの男の子たちは、誰が面倒を見るのですか?」
「ジェームズ・ヘイウッドです。彼なら一人でもなんとか面倒を見られるだろうけれど、時折様子を見てやってください」
ジェームズ・ヘイウッドは年長の少年で、最近、両親と一緒にヴィレッジにやって来た子だ。ステファンは以前、彼のことについてどれほど信頼できて責任感があるか、そしてどれだけ聡明であるかを語っていた。「なんとかします」私は言った。
彼は踵を返した。私は背中に声をかけた。「ステファン、気をつけて」
彼は振り返ってにっこりとし、手を振った。「気をつけます」
私は教室に戻ってから、なんて残酷なことが起きてしまったのかと思った。……製材所に火がつけられるなんて。地域の人間から迫害を受ける時は、彼らはいつもどこか致命的な部分を攻撃した。製材所は盛んに動いていた。私たちは、製材所を頼りにして金銭のほとんどを得ていた。うらやましいと思われたのだと、私は思った。それにしても残酷で非情なことだ。
それは早朝のことだった。授業はほとんど始まったばかりだった。午前中は火事のことばかり考えながら授業をした。男性たちがどれほど必死に消火しようとしていたかと、機械のいくらかを救い出そうとしていたことはわかっていた。材木の山を退かし、小川から水を運ぶあいだじゅうずっと、炎は高く燃え上がり熱かったことだろう。とても長い午前だった。
正午過ぎに、黒ずんで煙で汚れ、疲弊した男性たちの行列が門を通り抜け始めた。校庭から、行列の前方の人たちが担架を運んでいるのを見つけた。誰かが怪我をしたようだった。ステファン! 私は一瞬よろめいた。そして、何をしようと考える暇もなくスカートを持ち上げて、センター・ハウスに向かって走り始めた。私がシスター・ドルシーに何も言わず、その横を走って通り過ぎた時、彼女は驚いて口をあんぐりと開けていた。それはステファンだとわかっていた。彼は自分の身の危険など顧みなかったのだろう。火のついた材木が彼をとらえたのだろうか。あるいはボイラーが爆発し、火傷したのだろうか。それとも、樹脂を含んでいるために燃える、新しい木材の山が彼を襲ったのだろうか。道をすごい勢いで駆ける時、いろいろな可能性が頭を去来した。目の前に恐ろしい光景が思い浮かぶたびに、さらに恐ろしい新しい光景がとって変わり、私は満足に速く走れなかった。足はぎこちなく動き、スカートが邪魔になっていた。ボンネットが落ち、髪の結び目がほどけたけれど、立ち止まらなかった。髪の毛が流れ、スカートが膝にあたり、急いで足がほとんどつまずきそうになりながらも、この大きな恐怖から、速く、速く走るように駆りたてられて、私は走り続けた。
ちょうど、担架がセンター・ハウスのドアに着いた時に、私も到着した。ブラザー・ベンジャミンが私を見て、私の腕に手をおいた。「彼は死んでしまった?」私は息を切らしあえぎながらも、ドア近くの男たちの横を通り抜けようとした。
ブラザー・ベンジャミンは頭を振って、私を制した。「いいえ、レベッカ、致命傷ではありません。顔と腕に火傷を負っていますが、ほとんどは、疲労とたくさん煙を吸い込んでしまったことが原因です」
私は頭が回っていなかったけれど、それを聞いてとても安心した。彼は死んでいなかったのだ。ぼんやりと辺りを見回してみると、ステファンが門から入ってくるのが見えた。私は彼に触れたいと思い、また私自身を安心させたいと思って、喜んで彼に向かって二歩踏み出した。その時、ブラザー・ベンジャミンの言葉を思い出した。「彼ほど強く戦った男を見たことはありません」と彼は言っていた。「彼は何度も建物に入っていきました。建物が本当に崩壊するまで、彼は諦めませんでした。そして、おかげで多くの設備が守られました」
その瞬間まで、ブラザー・ベンジャミンがリチャードのことを話していたと気づかなかった。火傷を負って担架に乗せられ、センター・ハウスに運ばれたのはリチャードだったのだ。
そしてその瞬間、私はステファンをどれだけ愛していたかを知った。この数カ月間、私はリチャードのことを一度も考えたことがなく、いつの間にかステファンを愛していた。私が考えることはすべてステファンについてであり、私が恐れるのはすべて彼のためであり、私の最も強い感情は、彼が無事であるかどうかという一点についてだった。私はステファンの顔を見た。彼の顔は煙で汚れていて、目の縁は赤らみ、髪は傷んでいた。彼のシャツは肩のところが破れ、長い傷口から血が出ていた。そういう彼の姿を見て、私の心は溶けだした。彼は顔をゆがめて微笑み、手を挙げてスクール・ハウスに向けて門を出ていった。
センター・ハウスの中まで私は担架についていった。
私はリチャードを看てあげたかったが、彼がそれを許さないだろうと思った。彼はチャーチ・ファミリーの男性に看護を頼んだ。私は彼がソファーに寝かされた時、彼を少しだけ見た。そして、彼に大きな憐憫を感じた。彼はとてつもない苦痛の中にいながら、少しも声を出さなかった。彼はうめき声を我慢して、唇を固く結んでいた。彼は目を開け、私がそこに立っているのを見たようだった。私は彼に近づいたけれど、彼は私を遠ざけた。ブラザー・ベンジャミンが私の腕に触れた。「レベッカ、私たちが看護します」
「はい」
「あなたには逐一連絡します」
「よろしければ、お願いします」
私はその場を立ち去ろうとした。ブラザー・ベンジャミンとシスター・モリーがドアのところまでついてきてくれた。彼らはリチャードについて、彼の信心、献身を挙げ、また彼らがいかに彼を頼っていたかについて話した。彼らがリチャードを拠りどころにすればするほど、私がリチャードから離れなければならなくなったのは皮肉だった。しかし、皮肉も今や私には役立たない。私は新たな事態に直面していたのだ。それで私は彼を置き去りにした。彼には、私よりも男性教徒たちとの生活が好ましかったのだ。
私はセンター・ハウスから一直線にスクール・ファミリー・ハウスへと向かった。ステファンはそこで、彼にこびりついたすすと血を洗い流していた。私が流し場のベンチに座っている彼のところに行くと、彼は哀し気ににっこりと私に笑いかけた。彼は上半身裸の状態で、片手で洗おうとしていた。見たところ、彼の肩の傷口は乾き始めているようだった。彼は取り繕おうとしてシャツを取ろうとしたが、私はそれを遮った。私は彼の手からその服を取り上げた。「そこに座ってください」私はベンチの端を指さして言った。「私に処置をやらせてください」
「今の私は見られたものではありません」と彼は言った。
「洗って軟膏を塗らなければなりません」と私は答え、できるだけ優しく傷口を洗い流した。水で傷口を洗っているあいだ、彼は時折痛みにひるんだが、私の処置に対しては大人しく従ったままだった。それはそこまで深い傷というわけではなかったが、長く、筋肉に沿っていた。「この傷はどうしたのですか?」私は尋ねた。
「木材の破片が落ちてきたのです」
それから私が傷の手当てをするあいだ、私たちは黙っていた。私の手がステファンの肩にかかった時、私はリチャードのこと、それから、昔どうやって彼の肩こりを揉みほぐしていたかを思い出した。私はリチャードのことを偽りなく心の底から愛していた。彼は私の生活のすべてだったし、私が愛するもの、気にかけるもの、考えるものすべての中心に彼がいた。私は彼が導かれるところへもついていったし、その場所は私にひどい不幸をもたらしたが、それでも彼を信じ続けた。それは何のためだったのだろうか、と思った。今、こうしてステファンの肩を優しく手当するためだったのだろうか。そして私を亡霊が襲った。それは二人以上の男を愛する女性ならば、誰もが必ず自分の中に呼び寄せてしまうものだ。そこには学ぶべき新しいものは何一つない。すべてはもう済んでしまっているのだ。
傷を包帯で巻き終わると、ステファンは立ち上がり、私を見つめた。言葉を交わすこともなく、私は彼の腕の中へと抱かれた。彼の両腕がしっかりと私を抱きしめるのが感じられた。私は唇を彼の唇へと重ねた。私は彼をしっかり抱きしめ、それから泣いた。「あなただと思ったのです……とても恐ろしくて、考えられませんでした……あの担架を見た時に、あなたに違いないと思ったのです」
ステファンの腕は力強かった。「私を心配してくれたのですね」彼は頬を私の頬に寄せた。「ああ、レベッカ、レベッカ……私はずっとこうなることを望んでいました。私はこうなることを待っていたけれど、決して叶わないだろうと思っていました」
私たちは、私が笑いながらふらふらと腕を解くまで、互いに強く抱き合っていた。それから私は大昔から女性が尋ねる質問を投げかけた。「いつ頃からあなたはそう思っていたんですか?」
彼もまた笑って言った。「初めからですよ。私は、あなたの心はたくましく、揺るがない信条を持っていると思っていました。それから、あなたはとても美しい女性です。レベッカ」
「私が?」私は乱れた髪を後ろに押しやった。「私はいつだって平凡でした。ジェイニーは美しい女の子でしたけど」
ステファンはもう一度私を抱き寄せた。「決して、決して自分が平凡だなんて言わないでください。あなたの美しさは百年たっても色褪せない美しさなのです。あなたが年老いても、あなたはきっと美しいままでしょう」
「まあ」私は笑った。「誰もそんなに長くは生きられませんよ」
「やってみて」彼は私に顔を近づけ、キスをして言った。「やってみてください、レベッカ。私は百年間あなたと一緒にいたい」
私は驚いて身を引いた。しかし、私が答える前に足音が聞こえた。ステファンは彼のシャツを引っ掴み、身につけた。しかし私はハウスの中へと逃げた。私はあまりにも混乱し、動揺していたので、誰とも顔を合わせられなかった。
自分の部屋で私は身体をベッドに投げ出し、身を震わせた。幸福、絶望、希望、悲観に混乱していた。彼は百年も私といたいのだ! そして私も百年彼と一緒にいたい。しかし、私はリチャードと結婚している。そして婚姻関係は死ぬまで続く。私たちの愛がどうにかできるのだろうか。彼の唇が私の唇に触れたのを思い出して、私は彼を諦めるくらいなら死んだほうがましだと思った。結婚の誓約を思い出して、私は先が真っ暗になった。
私はその夜、ベッドの上で眠れないまま何時間も考えていた。女性の生き方について。私はステファンと出会ってからの月日に、思いを巡らせた。あらゆる言葉を思い返し、今となっては私たちが会っていた時間のどれもが、とてもはっきりと一つの結末につながっているように思えた。同時に、それらのどんな言葉も、私たちを導いたあらゆる事柄も、どれもが愛おしかった。愛され——愛する、それが女の人生なのだ。それがなければ、女は彼女の一部において死に、しなびて、無味乾燥で、はかないものになってしまう。自分の血液の拍動が、自分の心臓の鼓動がすべて感じられた。それらは新しく、この数年で最も生き生きとしていた。私は再び、生きているのだと感じた。しかし、このような高揚が訪れるたびに、リチャードのことが頭に浮かんだ。私にはすでに夫がいるのだ。私の希望は一体どこにあるのだろうか。石壁のように固い障壁があるのに、どんな結末があるだろうか。結局眠れたものの、落ち着かず不規則な眠りだったので、朝にはすっきりとせず、疲れていた。私は教室へと戻った。
リチャードは数日間ずっと体調を崩していたが、身体の丈夫さと意志の強さゆえ、今は少しずつ快方に向かっていると聞いた。それでも、二週間、彼は床に伏せていた。
その二週間で、ゆっくりと、苦しみながら、一つの結論に至った。ステファンと私の二人きりで会う機会はあれ以来なかったし、私には作ることができなかった。彼も二人で話す機会を作らなかったので、彼は私には一人で考える時間が必要であることがわかっているように思えた。食事の時間に、彼は食堂で、私に笑顔を投げかけた。ある時は教室で、甘くてぼんやりするような香りを漂わせた、いっぱいに咲いたローカストの花束を見つけたりした。またある時は、机の上で新しい本を見つけたりした。しかし、話しかけることもなく、彼は私に何のプレッシャーも与えてはこなかった。それでもしかし、私は彼を見るたびに、彼の腕に抱かれてキスをし、彼と一緒にいたいという切望が押し寄せて、柔らかくとろけるような甘い心地になるのだった。スクールの庭を彼が歩いているのを見ると、私の鼓動は速くなった。私はそんな状態に懸命に耐えなくてはならなかった。
リチャードがベッドから出られるようになり、椅子での生活になったと聞いて、私は自分のすべきことがわかった。私はステファンと話すために教室に会いにいった。教室へ入ると、私は後ろ手でそっと扉を閉めた。ドアの閉まる音を聞いて彼は振り向き、私の顔を見て、立ち上がった。しかし、彼はその場から動かなかった。「心が決まったのですね」彼は言った。
「はい」それはとても難しいことだった。私はうつむきながら、決意が揺るがないことを祈った。
それから、私は何とか彼をまっすぐ見つめた。「私を信じてください、ステファン。これは私がしなくてはならないことなのです。もう一度、リチャードに私と共にヴィレッジを出ていくように頼むつもりです。私の夫ですし、もしコミュニティを去り、また私と共に生きるつもりがあるなら、それは私たちにとって正しいことだし、私がしなくてはならないことなのです」
ステファンの瞳の中の輝きは消えていた。しかし、眼差しは私に向いていた。そして少し微笑んですらいた。二人ともしばらく何も言わなかった。ステファンが口火を切った。「はい。わかりました。あなたがそう考えるのはわかります。あなたの決意を尊重します。大切な人、レベッカ」彼の顔は少し青ざめていたが、微笑みは絶えなかった。その様子に胸が張り裂けそうだった。エプロンのポケットから、ステファンのために作った贈り物を取りだした。決心するまでのあいだ、ジョン・ダンの詩がどういうわけか思いだされ、頭にあった。自分の髪の毛を切って、ステファンの手首につけるブレスレットを編んだ。彼の手を取って、それを手首につけた。彼はその意味をすぐに悟り、次の言葉を引用した。「(1)金髪で作られた腕輪……近頃の法律によって禁じられた封印の個所を自然が解放しても、二人の手は触れることはなかった……」
私は彼の手首のブレスレットを触りながら言った。「もし私たちが会うのがこれで最後なら、これを忘れ形見にしてください」
彼は私の手を取って持ち上げ、手の平に顔を寄せ、両手に口づけ、頬を寄せた。彼と別れたあと、私は彼の口の感触と頬のぬくもりを手の奥に刻み込んだ。
その夜、私はリチャードに会うことが許された。二人きりで会うことは許されなかったため、ブラザー・ベンジャミンも立ち会った。リチャードは元気そうに見えた。以前より肉づきがよくなっていた。十分な休息や食事が、彼の回復を大いに助けたのだろうと思った。顔にはまだ包帯が巻かれていたが、隙間から私を見ていた。「よくなったの?」私は聞いた。
彼はうなずいた。「ブラザー・ベンジャミンの看病のおかげでね。何一つ不自由はなかったよ」
「何より」
「一、二週間のうちに製材所に戻れるようになるはずだ」
ブラザー・ベンジャミンは穏やかに微笑んだ。「すぐですよ、リチャード。もうすぐです」
二人はしばらく話し続けていた。リチャードが救いだすことができた機材や、東の共同体から取り寄せなくてはいけないものについて、また、どのくらい早く製材所を再建できるかについて話していた。彼らが話し終わった時、私は、前置きなしに突然決心したことについて切り出した。私は彼に言った。「リチャード、もう一度あなたに頼みたかったの。私と一緒にサウス・ユニオンを出て、もとの家に戻りましょう」
彼は、まるで聞いたことが信じられないかのように、私を凝視した。「私はここでは幸せではないわ、リチャード。だから出ていきたいの。真のシェーカーになることはできない。ビリーバーになることは。一緒についてきてほしいの、また私とやり直しましょう。もう一度……」口ごもってしまったけれど、「もう一度私の夫として」と言おうとしていた。
それから、リチャードはやっと口を開いた。「それは、ありえない! 君は自分が何を言っているのか、何を頼んでいるのかわかっていない! サウス・ユニオン以外に帰るところはないんだ。外の世界に僕の人生はない。ここが僕の居場所だから、ここに留まるつもりだ。君はできることを最大限やる必要がある」
私は立ち上がった。「それならば」と、私はリチャードとブラザー・ベンジャミンの二人が聞き間違えないように、とてもゆっくりと言った。「独りで、出ていきます」
二人は呆然として私を見つめた。そしてブラザー・ベンジャミンが言った。「レベッカ、あなたの人生はここにあるのです。リチャードがいるここに」
「私の人生は、自分が望む場所にあって、それはここではありません。リチャードはもはや人間ではありません。しかし、私はそうです。リチャードは人として死んだも同然です。私は違います。私は、このような生き方から自由になれるし、なりたいと思っています」
「しかし、君は僕の妻だ!」リチャードは私に叫んだ。
「リチャード、私はもう長いあいだ、あなたの妻ではなかった。法律上はそうだったけれど。今度は法律がこの関係を終わらせる手段になる」
「どういう意味だい?」
「リチャード、今年、(2)離婚法が制定されたのよ。忘れていた? ビリーバーズの教徒であるということは、夫婦が離婚して離れる理由になる」
リチャードの目がカッと燃え上がった。「まさか、そんなことしないだろう!」
「するかもしれない……するつもりよ」
「レベッカ、しかし離婚は」とブラザー・ベンジャミンは言い立てた。「離婚は恥ずべきことです。リチャードとこのコミュニティに傷をつけるでしょう!」
「リチャードとこの共同体に私は傷つけられてきました。離婚については……私たちはすでに離婚しています。お互いが離れて暮らし、結婚の絆はありません。法が簡単にそれを正当化してくれます」
リチャードはブラザー・ベンジャミンに向き直った。「そんなことが可能なのですか?」
ブラザー・ベンジャミンは手を広げた。「残念ながら可能なのです、リチャード」彼は私に訴えかけた。「レベッカ、じっくり考えたのかい? それがたしかに君のやりたいことなのかい?」
「本当によく考えてきた。もし、リチャードがヴィレッジを去るつもりがないならば、これが私のやらなければならないことだと完全に確信しているわ」
リチャードが身を切るような目で見ていた。
「君がこんなことをしようと思うなんて夢にも思わなかった……まったく夢にも……」
「あなたは私が考えることを気にかけなかった」私は熱くなって彼の言葉を遮った。「私が感じることにも、何を欲しているかにも……本当に長いあいだ、気にかけなかった。私はあなたが何を考え、何を感じ、何を欲しているかに沿ってきた! このヴィレッジでの生活を愛しているのよね、リチャード……それならば、ここに留まってちょうだい。私は決してここには留まらないし、あなたにも強要されない!」私はブラザー・ベンジャミンのほうを向いた。「あなたがこの場にいてよかった。早速手続きに取りかかれます」
やるべきことはほとんどないに等しかった。私には農場はもう必要なかった。しばらくは母のところに行こうと思った。しかし、私は自分たちのものだったお金の権利を半分持っていた。そして、カッシーとサンプソンはまだ私に属していた。私は彼らの書類を頼んで持ってきてもらった。リチャードは、私とのお金の配分の書類にサインをした。百ドルだった。そして、私は農場の権利を彼に渡す書類にサインをした。
私が名前を書いた時、彼は紙を見て、それから私のほうをぼんやりと見た。彼はまた怒りを燃やしているように見えた。「レベッカ、君はまっすぐ地獄に落ちようとしている」
「でもあなたは安全よ。あなたにとってはそれだけが大事なことでしょう」
「リチャード……レベッカ……」ブラザー・ベンジャミンは声を漏らした。「レベッカ、出発はいつがいいですか?」
「学校の学期が来週終わるので」私は彼に伝えた。「それから、すぐに出ていきます」
「我々が手配しましょう」彼は約束した。
ドアのところで私は振り返った。「さようなら、リチャード」
彼は別のところを向いていて、話そうとしなかった。最後に彼を見た時、彼は固まった姿で、椅子にまっすぐ腰かけ、私を避けるように顔を背けていた。
私たちが話しているうちに、辺りは暗くなっていた。穏やかな暖かさの中、スクール・ハウスに向かって歩いて戻った。星が頭上のとても近いところで、明るく輝いていた。その途中で、ステファンに会った。私は彼の腕の中に飛びこみ、すすり泣いた。今の今まで、怒りが私を支えていた。しかし、私は深く揺さぶられた。「彼はここを出ていかない」私は言った。
暗闇の中で、ステファンが吐息をつくのが聞こえた。「彼が出ていくとは正直考えていませんでしたが、可能性がなかったわけではない。もう部屋で独りで待っていられなかった。できる限り早く、どうなったかを知らなければならなかった」彼は私を支えキスをした。「ベッキー、これから、どうするのですか?」
「学期を終わらせて、母のもとに戻りたい」
「そこでどうするのですか?」
私は彼の肩にもたせかけていた頭を上げた。答えるのはとても辛かった。私は数回唾を飲みこんだ。「自由になるために、新しい離婚法を使うつもりです。恥辱を受けるだろうことはわかっています。でも、生きながら死んだままでいるよりは、恥を忍ぶ方がましです。ああ、ステファン、私の目の前には私の人生すべてがあるのです……私たちのすべてが……! リチャードと一緒に自分の人生を犠牲にするつもりはありません」
彼は私をきつく抱きしめた。「愛しい人、あなたが恥辱を受けることはありません。あなたはすぐにでも、私の妻になるのだから」彼は大喜びで笑いながら私の肩を掴んで離した。「いつあなたのもとへ行けばよいですか?」
私はそのことについて思いを巡らせた。「夏の終わりがいいと思います」
「それより前でなくてよいですか? 離婚の手続きが大変な時に、私にそばにいてほしくはないですか?」
「大丈夫です。自分でやらなければいけません。夏の終わりがいいです、ステファン。あなたはどうしますか? それまでここに留まりますか?」
「いいえ、そのつもりはありません。町へ出ようと思います。——そこで部屋を借りようかと。もう長いこと、長編の叙事詩を書いてみようと思っているのです。題材は何年も前から浮かんでいます。あなたを待っているあいだ、それに取りかかってみようと思います」
「どうやって生活するのですか? 私を待つあいだ、どうやって稼ぐつもりですか?」
「あなたには話していませんでしたが……それは心配ありません。自分で稼ぐ必要はないのです。私は裕福な身ではありませんが、ほとんど手をつけていない遺産があります。それを使おうと思います」
「ステファン」私は尋ねた。——彼は英国人だと言っていた。「あなたは貴族か伯爵か何かなのですか?」
「いいえ」彼が首を振るのを感じた。「いいえ。ですが、私の父が交易で成功して、子どもたちにかなりの額を遺してくれたのです」
「それはよかった」
「ええ、私たちにはお金の心配は要りません」
「いいえ、私はあなたが貴族の肩書のある人でなくてよかったと思っているのです」
私たちは、お互いに心地よく笑い合った。「お金のことも少しは喜んでください、ベッキー。どこでも望むところへ行けるのですよ」
私はからかうように言った。「ミズーリにも?」
彼もまたからかうように返した。「私もそれは少し考えていました」
「きっとそうだろうと思いました」
そして、私たちはそれぞれ考えながら黙った。来年の今頃には、私たちはきっとミズーリにいるだろう。そして私たちの人生がどうなるか、素晴らしい光景が浮かび、私の目を涙が曇らせた。自由……ステファンがそばにいて、かつてのように本を愛して、二人一緒に本を書いたり、旅をしたり、冒険をしたりするのだ……それはまるで楽園が天から落ちてきて、私の手の上に、完璧な贈り物として収まったようだった。それを傷つけるのは、離婚の必要があるということだけだ。私は、婚姻関係は一生続くものだと心の底から信じていた。だが、リチャードの生き方のせいで、夫婦関係は死んでしまった。それは法廷の裁きによって埋葬され、葬送の説教を受けるのを待つのみだった。
その翌週、私はカッシーとサンプソンと話す機会を設けた。私は、彼らに自分がどうするつもりかを伝えた。「自由になりたい? それとも私と一緒に来たい?」
カッシーは即答した。「私たちはあなたが行くところなら、どこへでもついていきます、ミス・ベッキー。これ以上、ここにいようとは思っていません。それから、私たちはあなたと一緒にいれば十分自由なのです」パルミラには、事のすべてを伝えた。ステファンとのことを打ち明けたのは、彼女が最初だった。彼女は喜んで、私を抱きしめた。「嬉しい。あなたもわかるだろうけど、こうなるだろうと思ってた。でもあなたはリチャードのことになると本当に頑固だったから、心配でね。いつ結婚するつもりなの?」
「夏の終わりに」
「待ちきれないよ」彼女は笑った。そしてこっそりと言った。「きっと子どもができるよ」
私は首を振った。「それは望まないようにしてる」しかし、それは嘘だった。私はそう望んだし、切望し、祈りさえした。
私たちは庭にいて、私がその場を去る時、パルミラのほうを見ると、彼女の目は涙でいっぱいだった。「私たち、長いこと仲良くやったよね、ベッキー?」
私の目にも涙がこみ上げた。「ずいぶんね。あなた以上にいい友人はいなかったよ、パルミラ。あなたのことは絶対に忘れないし、あなたをずっと愛してる。あなたと離れたくない」
「駄目」彼女は感情的に言った。「できるうちにここから出なきゃ。いくらお金をもらっても、あなたをここに引き留めるわけにはいかない。私が望むのはあなたの幸せだから」
「あなたも出ていけたらいいのに」私は思い沈んで言った。
「ああ、私には悩まされるようなこともないから。私たちはここでうまくやっていくし、ここよりいいところがあるかもわからない。でもあなたは、ここを出て、ステファンと幸せに暮らす。あなたにとっては、素晴らしいことでしょ、ベッキー?」
「世界で一番素晴らしいことね」と私は言った。
ステファンは、私が出発する前の晩に別れの挨拶を言った。私を抱きしめて、囁いた。「もし私が必要なら、一言連絡をください。」
「そうします」私は誓った。
「長い夏になりそうだ」
「あっという間ですよ。詩に取り組んでください。それから私に手紙をください。そして、九月の頭に来てください」
「あなたをさらってしまうために、白馬で乗りつけましょう」と彼は誓った。
「私たちをミズーリへ運んでくれるくらい、強い馬でね」私は笑った。
私はシェーカー所有の、良い馬を一頭譲り受けた。そして、あと二頭をカッシーとサンプソンのために購入した。最後に、私が馬に跨ってしまってから、パルミラが小包を持ってやってきた。「お腹がすくだろうから」彼女はそれを私によこして言った。「ケーキを作ったよ」
感情がこみ上げて、彼女にお礼を言うこともままならなかった。見送りは他に誰もいなかった。ブラザー・ベンジャミンとシスター・モリーはその週のあいだじゅう私に冷たく、シスター・ドルシーも彼らからそうするように言われていた。しかし、私のサウス・ユニオンでの最後の記憶は、パルミラが門のそばに立って、見送りのために手を挙げているところとなった。彼女と二度と会うことはないのだ。
ヴィレッジを出てから、アマンダとウィリアムのところに一晩滞在した。カッシーが、ジェンシーと離れることを悲しむだろうと思い、クレイトンとジェンシーが私たちと一緒に来られるよう、クレイトンを買うつもりだった。
アマンダは、今やそれほど唇が薄く、ほっそりした顔つきではなかった。彼らは農業で成功していた。最初、ウィリアムはクレイトンを売ることに乗り気ではなかった。「彼なしでどうやったらいいか、わからないな」と彼は言った。「彼は本当によい働き手なんだ」
だが、わたしはクレイトンを買うのにかなりよい値を提案した。ステファンがそうするように言ったのだ。「このお金で屈強な黒人を二人買えるわ」と私はウィリアムに持ちかけた。最終的に彼は承知し、奴隷を売り渡す書類を作ってくれた。
私はジェンシーが私たちと一緒に行くことになったと伝えるために、彼女を探した……彼女と、クレイトンと、その子どもを。その子は丸くぽっちゃりとした、チョコレートの雫のような男の子で、肌の色はジェンシーよりも明るく、しかしクレイトンほどは白くなかった。ジェンシーは喜びのあまり大はしゃぎでぐるぐると走りまわり、カッシーが彼女を落ち着けるまで次々に物を掴んでまわった。「落ち着きなさい。ミス・ベッキーは忙しいんだから。私たちは、ここを出る準備をしなきゃ。ポットや仔猫を持っていっても仕方ないから、服をまとめなさい」
クレイトンも嬉しそうだった。「ミス・アマンダとミスター・ウィリアムのところは、食べ物に恵まれているし、彼らは誰も虐待しない。でも、余分にものを分け与えてくれることもない」と彼は言った。
ジェンシー、カッシーと私は、町で安く買ったワゴンに乗って、かなり長い道のりを進んだ。クレイトンとサンプソンは馬に乗った。それは私が今まで見た中で、最も幸福な一団に見えた。「なんて幸せな日!」ローガン郡を出た時、カッシーは歌った。「あの場所の最後を見ることができて、本当に嬉しい!」「あの場所を出ることができて、本当に嬉しい!」
私は、母に嘘をつこうとはしなかった。どうするつもりか、すぐ母に伝えた。当初、母は衝撃を受けたようだった。離婚だなんて! 離婚するのは恥知らずだけだ。自分の娘がそんなことを考えるなど、思いもよらなかったのだ。「神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない」母は私に、聖書の一節を引用して言った。
「でも、リチャードの神が私たちを引き裂いたのよ、ママ」私は言った。「一八〇七年にシェーカーがやってきてから、リチャードはもう私の夫ではなかったわ」
この一言が、彼女にさらなる衝撃を与えたのだと思う。「その時からずっと、彼はあなたと一緒に生きるつもりはなかったということなの?」
「まったくね。彼は私のことをほったらかしにして、私を遠ざけて、一年以上も私に話しかけてもこなかった」
母が、シェーカーが教徒に要求していることを完全に理解したことはなかったと思う。母は首を振った。
「そんなに不自然なこと、今まで聞いたことがないわ」母はしばらく考えこんだが、最後には「あなたをまったく非難しないとは言えないけれど、そうするよりほかなかったの?」と言った。「そう」
離婚の手続き自体は、驚くほど簡単だった。私はただ嘆願書を提出しさえすればよかった。離婚の理由は、私の夫がシェーカーになり、シェーカー・ヴィレッジに住みついたことだ。嘆願書はすぐに承認された。デイヴィッドとベティアは、まるで私の実の両親のように誠実だった。「君は正しいことをしたんだ」とデイヴィッドは言った。「リチャードは、生ける死者の中にいるんだ」
そうして、私は新しいケンタッキー州の離婚法を利用した最初の女性になったのだ……私、レベッカ・クーパーは、嘆願が受理された時、誰にも負けず劣らず驚いていた。自分が初めてそれを利用することになるとは、思ってもみなかった。
その夏は長く、暑い日が続いた。私の兄弟の妻は妊娠していて、彼女のほとんどの世話をすることができて、嬉しく思った。母は以前ほど元気ではなかったので、彼女の仕事の大部分を私に任せるよう説得した。私を待つ、新しい人生の中で唯一悲しかったのは、母と別れることだった。そのことは母を悲しませ、私は母から離れて遠くへ行くことをひどく恐れた。だが、どんな子どもにも、無神経なところや、熱中すること、家から遠ざかる原因があるものだ。そして、実際に病気でなくとも、母と再び別れることはわかっていた。
シェーカーのドレスを脱げて嬉しかった。何年も前に手織りで作られたのに丈夫で頑丈な私の服は、私が他の服を着たことがなかったかのように、ぴったりと合った。ママは私の赤い毛糸のドレスと、二枚の白いリネンを見た。「これがあなたの服の全部なの?」と彼女は尋ねた。
「そう。私達は各季節に二着しか持つことを許されなかったの。焼いて、縁を切ってしまおうと思って」
母は呆れた様子だった。「その必要はないわ。しっかりと、よく織られているから。一度縫い糸をほどいてから縫い合わせて、新しい服にしましょう。」
私が気に留めずうなずくと、母はすぐに取りかかった。
ジェイニーから手紙が届いた。私がシェーカー・ヴィレッジを離れたことを喜ぶ文面と、不思議なことに、ジョニー・クーパーのことでいっぱいの手紙が。「結婚式はいつ?」と彼女は書いていた。「ジョニーと私で参加するわ」
ママは、私が手紙を読みあげると、うなずいた。彼女は「彼女たちが、次ね」と言った。
私は嬉しかった。「嬉しい。ジョニーはずっと彼女のことが好きだったから。でも、ジェイニーが彼を愛する日が来るなんて思わなかった」
「そうね。彼女はもう彼のことしか書かないわ。彼は至るところで運送と売買をしているんだって」
私は八月の最終週に来るよう、ジェイニーに返信した。
ちょうど九月一日に、ステファンがやってきた。夏の日差しで茶色く焼け、私が出発した時よりも少し体重が増えたようで、全速力で小川のほとりの斜面を駆けあがってきた。「あの若者は、注意していなかったら、馬を吹き飛ばしそうね」ママはそっけなく言った。
だが、私には彼女の声はほとんど聞こえていなかった。私は彼に会いに丘を駆けおりた。彼が馬から飛び降りて私を抱きしめた時、私の胸の肋骨を一本一本折るのではないかと思った。誰が見ていようが気にせず、彼は私に何度もキスをし、私を離して見ると、再びしっかり抱きしめ、そのあいだずっと笑いながら「レベッカ!」と言った。そして私は……何も言うことができなかった。私にできたのは、彼にしがみつきながら、泣き、笑うことだけだった。彼とまた会えて本当によかった。
母とジョニーとジェイニーは、彼のことが気に入った。ステファンとジョニーはすぐに意気投合して、ミズーリについて延々と語っていた。ジョニーは以前セント・ルイスで商売をしていて、そこで有名な(3)シャトー兄弟と知り合っていた。「あそこは未来の国さ」と彼は何度も言った。
私は「西へ行こう!」とか「ミズーリへ!」というスローガンが派手に書かれたワゴンを思い浮かべた。シェーカーのブラザーたちは、その運動に反対して否定的だったので、「彼らは焦燥感に駆られた愚かな人々です。どんな苦労があるかを知ると、喜んで帰ってくるでしょう」と不機嫌に言っていた。
だが、私はそのワゴンを羨ましく思っていた。彼らは私にとって焦燥感を駆り立てる以上の存在だった。彼らは、私たちの祖先、新しい土地を目指して海を渡った祖父母、新しい国で命を懸けた私たちの両親の永遠の道のために立っていた。危険も、窮乏も、敵対的な先住民も、彼らを止められなかった。洪水で波が押し寄せるように、彼らは土地に流れこみ、山を押し戻し、森林を拓き、背の高い牧草地に自分たちの種を植え、家を建て、作物を育てた。それが我々民族のやり方で、それがすべてであり、私はそれを見て理解し、羨んでいた。しかし、今や私はその一部になろうとしていた。私はやっぱり、タイス・ファウラーとハンナ・ファウラーの娘なだけあった。
「ジョージが言うには」とジョニーは私の考えを遮るように言った。「一緒に商売をしないか、って。僕とジェイニーがセント・ルイスに行って、商品を仕入れてそこから運送して、シャトー家と取引する。君とベッキーが(4)スリー・フォークスで交易所を運営することだってできる!」
「スリー・フォークスってどこ?」私は尋ねた。
ジョニーは戸口の段の近くの土の上に地図を描いて、アーカンソー川、ヴェルディグリス川、グランド川の三つの川がどのように合流するかを示した。「ここさ。(5)オセージ族の領地で、シャトー家もそこで商売をしているんだ」と彼は言った。
ステファンは目を輝かせて、私を見た。私はオセージ族の先住民と交渉したことはなかったが、でも彼が行きたいなら私も行こうと思った。私はうなずいた。「決まりだ」彼はジョニーに言った。「どうだろう」とジェイニーは元気よく言った。「セント・ルイスの生活は私に合うと思う?」
「セント・ルイスは奥地じゃないよ」とジョニーは彼女に言った。「シャトー家の暮らし方を見てみたらいいよ! 今持っているものはもちろん全部、それ以上のものだって手に入るよ」
「そんな」彼女は笑った。「私だって綿菓子でできてるわけじゃないだから」彼女は輝いた目で私を見た。「二組同時に結婚式をしてみない、ベッキー?」
「一緒に?」私は聞いた。彼女の言葉はとても信じられないくらい嬉しかった。
「ジョニーと私でずっと計画していたんだ」彼女は手をするりと伸ばし、ジョニーがその手を取った。「あなたの知らせを聞いてから、私たちずっと待ってたんだよ」
私はステファンを見た。彼は私に微笑んで、頷いた。私の心をいっぱいにするはそれだけで十分だった。
(6)牧師の前で私たち四人が一緒に並んだ時、私は母が作り直した真っ赤な羊毛のドレスを着ていたが、これは大分異色だった。しかし普通とは違う格好を、私はとても気に入っていた。ステファンも気に入っていた。そして私たちは二人とも感傷的になっていた。シェーカーは私たちにまさしくお互いを与えてくれたのだ。そして私たちはそれを忘れることができなかった。
それらすべては二十年前のことだった。今、ドレスの残りはさまざまな方法で使っている……長男と続く他の三人の息子のベッドカバーとして。いまだ暖炉の前に敷いてある編んで作ったラグの一部として。それからステファンが机で使う椅子のクッションカバーとして。
ミズーリ準州は、私たちが最初に来てから大きく変化した。分割が重ねられ、(7)私たちがかつて定住した部分は、現在はインディアンの居住区となった。長年に渡り、スリー・フォークスには軍の宿営地があった……(8)カントンメント・ギブソンと呼ばれていた。
結婚後、すぐにケンタッキー州を出発し、道中は順調に進んだ。ステファンは、旅を快適なものにするための費用を惜しまなかったからだ。私たちはワゴンと荷馬車で旅した。ジェイニーとジョニーはオハイオ州を下り、ミシシッピ州からセント・ルイスまでもっと速く進んだ。
私たちの旅を、私は決して忘れることはないだろう。苦労する覚悟はできていたものの、何も起きなかった。私はずっと快適に馬車に乗っていて、夜のキャンプもカッシーとジェンシー、クレイトンとサンプソンのおかげで楽に過ごせた。そして、その旅の途中で、ステファンの愛の豊かさ、親切さ、優しさ、そして素晴らしさを知り、私の心は居場所を見つけたのだとわかった。さらに旅の途中で、喜ばしいことに、子どもを身ごもったことに私は気づいた。このことに最初気づいてからも、私はまったく恐れを抱かなかった。それどころか、その子は健康で無事に生まれ、そして私たち二人に喜びをもたらすだろうという確信は、揺らぐことはなかった。
ジョニーとステファンが選んだスリー・フォークスは荒野だったが、私は荒野を冒険する準備ができていたので、嬉しく思い、ワクワクした。私たちは家を建てる場所を選んだ。この土地はすべて、ミシシッピ州の西に移動させられていた東部のインディアンのために確保されていたので、私たちはそれを買うことはできなかった。しかし、その土地に家を建て、インディアンとの交渉を続けることはできた。
私たちの家は丸太の木材でできていて、メインルームのあいだには「(9)ドッグ・トロット」と呼ばれる風変わりな廊下があった。しかし、家については粗雑なものや美しくない部分はなかった。丸太で造られていることを除けば、家として素晴らしかったし、セント・ルイスから持ってきた家具は、豪華で上品で見事だった。
子どもは、連続して四人の男の子が生まれた。パルミラの子どもたちと同じく元気で、体格がよく、健康で、ふくよかで、幸福な子どもたちだった。子どもたちは、私たち全員、特にカッシーとジェンシーの喜びだった。ジェイニーも彼らを心から愛していた。彼女には子どもはいなかったのだ。彼女とジョニーのもとに二人の子どもが生まれたが、私の最初の二人の子どもたちがそうであったように、どちらも死産だった。ステファンは、リチャードとジョニーの両方が受け継いだクーパーの家系にはいくつかの弱点があると考えていて、私もそう思っている。
私の男の子たちは、もうすっかり大きくなっている。彼らは若いクマの子どものように、床の上で格闘し、たくさん食べ、風のように速い馬に乗り、私の父がそうしたように銃を操るのだ。ステファンによく似ていて、彼の名を取って名づけられた長男は、ジョニーの部下と一緒に、プラット川とミズーリ川の上流まですでに二回も旅をした。彼はいつの日か私たちのもとを去り、さらに西へ移動するのだろう。
ステファンは私たちのまわりのインディアンたち、最初にオセージ、次にチェロキーに魅了され、アーカンソーから西に移動した。彼はインディアンの中に自由に入っていき、彼らの言語を学び、彼らの歌や話し方、伝統や儀式を書き留めた。彼の最もよい本は、インディアンについて書いたものであり、大部分が彼らの言葉を翻訳したものである。
彼は執筆を続けている。彼は、毎日数時間必ず机で過ごしている。そして、彼がペンを動かすその手首には、何年も前に私が巻いた髪のブレスレットが今もある。こんなに素晴らしい夫を持つ女性はいないだろう。私たちは幸せだったし……今も幸せだ。
ジェイニーとジョニーはセント・ルイスに住んでいるが、頻繁に訪ねてくる。私たちは皆、予想を超えて成功してきた。この土地に来て以来、私たちが経験した唯一の悲しみは、母の死だった。彼女が衰弱しているという知らせが届き、私たちはケンタッキーに戻る旅に出た。彼女は八十歳まで生きたので、私たちの知る限りでは、単に高齢が原因だったと言える。もちろん悲しみも感じたが、彼女は望んでいた方法で人生を全うできたのだとも感じた。彼女は家の後ろの丘の私の父のそばに埋葬されている。父を埋葬した日、彼女が言ったことを思いだした。「彼はここで安らかに眠れるだろうね。愛した土地を見渡しながら」私は、母も安らかに眠れると思う。
シェーカー・ヴィレッジは、サウス・ユニオンとプレザント・ヒルにまだあり、一つはギャスパー・リバーに、もう一つは(10)ショーニー・ランにある。しかしステファンは、彼らは破滅の運命にあると言っている。すぐにではないが、おそらく、しかしやがて、彼らは絶えるだろうと言うのだ。なぜなら、人は病気になったり、衰えたりせずに人生から抜けだすことができないからだ。生殖を拒否することは自然に逆らうことだ。また、初期の白熱したリヴァイヴァル期の頃の熱狂は、維持できないだろう。年長の指導者の何人かはすでに亡くなったし、それは今後ますます続くだろう。後継の若い指導者たちは、ヴィジョンにより人々を駆り立てる力や冒険への推進力を欠いているだろう。この国は、自由を愛する人によって打ち立てられたのだ。安全のために、喜んで自由を犠牲にしてまで耐えられる熱意と精神を持つ人は、ほとんどいない。それゆえシェーカーは死ぬだろう。自身の健全さを失うことで、内側から弱体化されるだろう。
しかし、私はどうか彼らに害が及ばないでほしいと思う。彼らのうち、最も献身的なのは善良な人々だったし、彼らのよい行いを見てきた。私と彼らとのいさかいは、彼らの善の概念が他の人にとっての善を容認しないことから起こり、私はそれを暴政だと感じていた。それは悪意のない暴政であったが、私はそこからまさに邪悪さが生まれるのを見たのだ。邪悪さはどんな暴政からも生まれるのであり、悪意がないことは善の保証とはならない。
ステファンは、シェーカーでの経験について黙っている私の努力を笑い飛ばす。しかし、それは穏やかで優しい笑いだ。今、ここに最後の言葉を書き終え、私はこの日記を焼こうと思う。自由で軽やかな聖霊の風は、私の人生に優しく吹きこみ、シェーカーでの年月がその風をさらに愛おしいものにした。私はビリーバーズと決別した。
第24章訳註
(1)金髪で作られた腕輪……近頃の法律によって禁じられた封印の個所を自然が解放しても、二人の手は触れることはなかった……
対訳出典:高木登「ジョン・ダン全詩集訳」
(2)離婚法
アメリカで初めての離婚裁判は1682年に行われ、1776年以降、離婚法の規制は緩和された。離婚裁判を行うことは、立法府にとってより重要な仕事であるため、司法に委ねられ、現在に至っている。ケンタッキー州での離婚法適用の歴史は確認できなかった。
(3)シャトー兄弟
シャトー兄弟とは、オーギュスト・シャトー(René AugusteChouteau, 1749? -1825)とピエール・シャトー(Jean PierreChouteau, 1758 -1849)兄弟を指す。ピエールはオーギュストの実母と、その再婚相手でオーギュストの養父、フランス出身のピエール・ラクレド(Pierre Laclède Liguest, 1729-1778)との子で、オーギュストと異父兄弟にあたる。シャトーとは、ピエール・ラクレドの子どもたちが共通して受けた洗礼名である。2人の養父ラクレドは旧フランス領ルイジアナの一部、現ミズーリ州東部に1764年にセント・ルイスを建設した。その前年1763年より貿易会社を設立、貿易権を独占したが、その後フレンチ・インディアン戦争(1754-1763)の終結後の調停によりフランスのルイジアナからの撤退が決まった際、貿易独占権を失い一度は倒産する。シャトー兄弟はその後、原住民(主にオセージ族)から高品質の毛皮を仕入れて販売する毛皮商として成功し、一財を築いた。シャトー兄弟は原住民の文化を尊重し、公正な取引を行い、また高品質な商品を原住民へ提供することによって、原住民からの信頼を得たとされる。
(4)スリー・フォークス
スリー・フォークスはオクラホマ州のワゴナー郡、マスコギー郡、チェロキー郡を流れる、アーカンソー川、ネオショ川(グランド川) 、ヴェルディグリス川の3河川の合流地点である。旧くからカドー族、オセージ族、ウィチタ族など多数の原住民部族が生活していた地域で、1700年代以降にヨーロッパ系アメリカ人が入植した。同地域の発展にはシュトー家の事業が大きく関わっており、1796年には、ピエール・ラクレドはネオショ川流域に交易所を開設し、交易を促進するためにオセージ族に近くへ移住するよう奨励していた。後に息子のオーギュストとピエールがこの交易所を管理、貿易業を拡大し、ヴェルディグリス川に新しい施設を建設した。他のヨーロッパ系アメリカ人のトレーダーは近くに拠点を設け、この地域は毛皮(ビーバー、バイソン、シカ等)とヨーロッパの貿易商品の交換のための重要な経済拠点となった。また、アーカンソー川を伝って東部の市場へ容易にアクセスできるルートも開拓された。
(5)オセージ族
オセージ族はアメリカ・インディアンの部族で、その祖先はオクラホマ州の広域を領地としていた。1200年頃にオセージ族およびその敵対部族のイロコイ族はケンタッキー地域を出発し、ミシシッピ以西へ向かい、以降はフランス領ルイジアナ地域の多くを侵攻、領有した。
(6)牧師
第1章でもあるように主人公(レベッカ)の家族はプロテスタントの長老派であるため、ここでは牧師と訳出する。
(7)私たちがかつて定住した部分は、現在はインディアンの地域となった。
1824年ごろ、トーマス・ジェファーソン大統領をはじめとする政府は、ミシシッピ川東部のインディアンを川の西部に定住させることを支持し、奨励していた。1830年5月28日のインディアン排除法の成立後、政府は彼らを強制的に排除し、編入領地である川の西側の土地に再定住させた。最も影響を受けた部族は、オーセージ族、チェロキー族、クリーク族、セミノール族で、これらの部族は現在のオクラホマ州東部にあるフォート・ギブソン付近の土地に移された。
(8)カントンメント・ギブソン
カントンメントン・ギブソンは軍の宿営地であり、この地域ではフォート・ギブソンが、1824年4月にアメリカ政府の西方拡大政策とインディアン排除のためにカントンメント・ギブソンとして設立された。1824年5月26日に制定された法律により、アーカンソー州の西の境界線が約40マイル延長された。この法律を見越して、陸軍は当時最西端の軍事基地であったフォート・スミスに駐屯地を設置する必要があると考えたためである。
(9)ドッグ・トロット
19世紀中ごろから20世紀初頭にかけてアメリカ南東部で建てられた住宅の形態の一つ。左右の同じボリュームの室内空間を中央で幅の広い廊下が分断している平面計画が特徴である。廊下はドッグトロット(dog-trot)又はドッグラン(dog-run)と呼ばれ、3メートルから4.5メートル程と幅が広く、両端は外へと開かれている。これは風を通して室内を涼しく保つための工夫であった。
(10)ショーニー・ラン
ケンタッキー州の地域であり、ここでプレザント・ヒルが設立した。