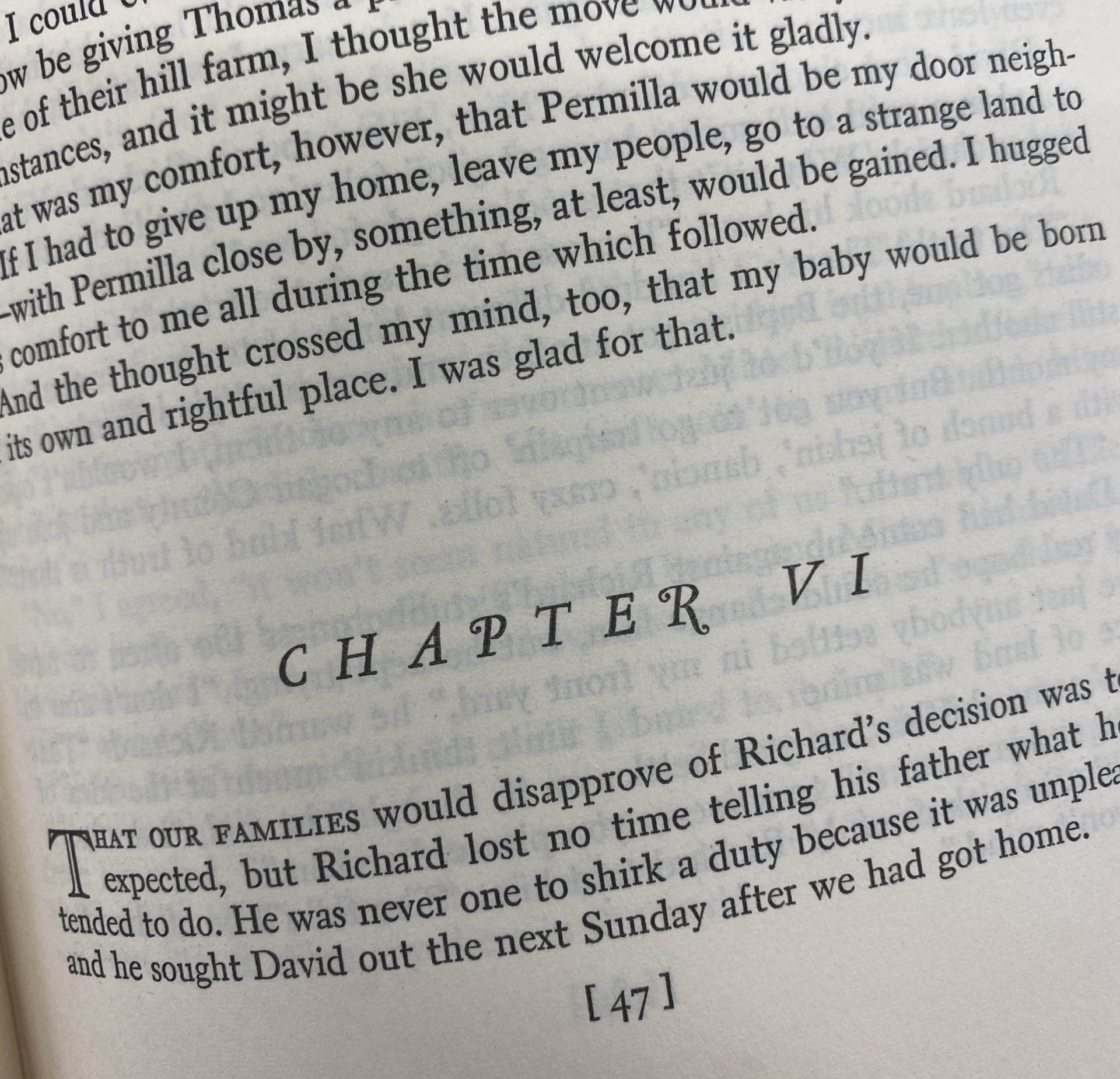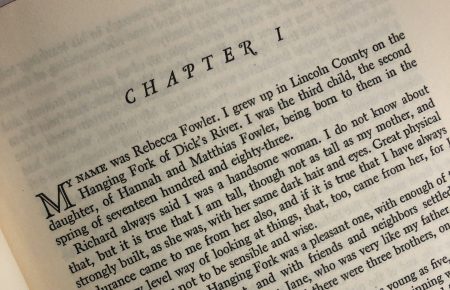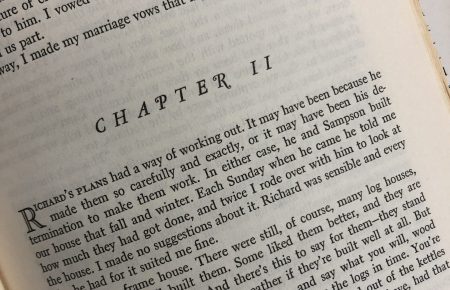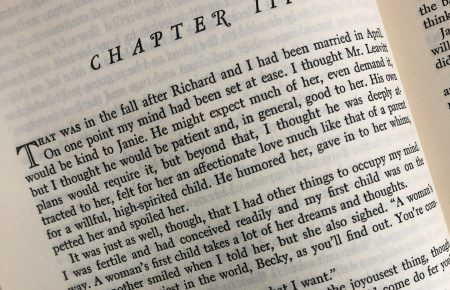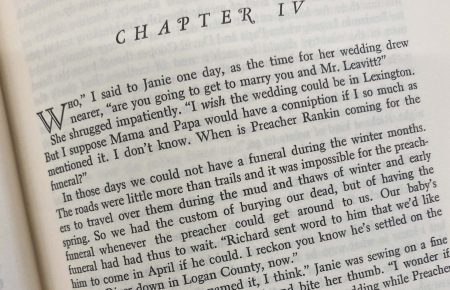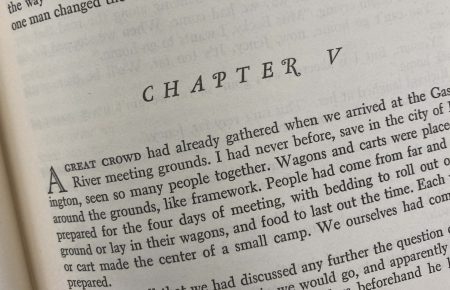リチャードの決断に、私たちの家族が反対するだろうことはわかっていた。案の定、リチャードは帰ってすぐに自分のしようとしていることを父親に説明することにした。リチャードは自らの義務と思ったことを怠るような人では決してなかったので、私たちが家に戻った次の日曜日にはデイヴィッドに会いにいった。
その場面を私が忘れることは絶対にないだろう。デイヴィッドとベティアはショックを受け、初めは信じようとはしなかった。ようやく、デイヴィッドが状況を飲みこみ、リチャードの言ったことを理解した時、デイヴィッドはリチャードに怒鳴り散らし、口のまわりが白くなり体が震えるほど怒り狂った。デイヴィッドは声が枯れるまで叫び、論じ、懇願した。しかしリチャードは少しも動じなかった。
「なんてこった」デイヴィッドはリチャードに向かって、拳を振り回しながら語りかけた。
「お前がこんな馬鹿げた無茶なことを言いだすなんてわかってたら、そもそもお前に土地を与えようとは思わなかったからな。俺はお前がしっかりしてて信頼できると思っていたんだ。土地を与えるのはお前にふさわしいし、お前も喜ぶだろうと思っていた。俺はお前が新しいスタートを切る手助けをしてやろうと思ったんだよ」
「手助けになってるよ」リチャードが言い返す。「それに僕が恩知らずだなんて思わないでほしい。そうじゃないんだから。本当に助かったんだよ。でも男なら自分が正しいと思うことをやらなきゃいけない」
「正しいだって!」デイヴィッドは大声で怒鳴った。「土地を売って、それもギャスパー・リバーのほうをほっつき歩くのがどうしてお前にとって正しいんだ。それのどこが正しいんだ!」「僕は正しいと信じてる。父さんに反対して申し訳ないけど、僕は僕の信念に従わなきゃいけない」
「何が信念だ、クソ!」デイヴィッドが叫んだ。「そんなことはただの愚行だ。その牧師の野郎を、鞭でしばき倒してやる」
リチャードは何も言わなかった。二人の口論を前に、ベティアは何を言っていいのか、そもそも何か言ったほうがいいのかもわからず、口を震えさせながら窓の横に座っていた。私は二人の言い争いを聞きながら、真っ二つに切り裂かれるような思いだった。私自身はギャスパー・リバーには行きたくはなかった。そしてグリーン・リバーの自分たちの土地を手放したくもなかった。今になって、この時のことをじっくりと思い返すと、この新しい奇妙な信仰は、どの部分をとっても私の欲するものではなかったのだ。しかし私は、リチャードが自分の決断を覆すことは絶対にないだろうとわかっていた。そうしなければいけないとしたら、自分の父親と母親と別れ、二度と会わないのも厭わないだろう。私が怖かったのは、そうしなければいけないとしたら、彼は私のもとすらも離れてしまうかもしれないことだった。
デイヴィッドは少し落ち着いて続けた。「いいかリチャード。お前は本当にいい場所で育った。いい人たちに囲まれて、ちゃんとした教会だってある。どうしてここじゃだめなんだ」
リチャードは首を振った。「真実を見てしまったからだよ」
「真実! 真実なんて何百個もあるんだよ。(1)メソジストが一つ、(2)バプテストがもう一つ、それからどの宗教もそれぞれが新しいものをもう一つ見つけたと思っているんだ。そのどれにお前がはまろうと俺は口出ししない。でもな、わざわざローガン郡のほうへ行って、体を痙攣させて踊ってる頭のおかしい奴らの集団に加わるとは、それはどういう種類の真実なんだ」
「たった一つの真実だよ」
デイヴィッドはリチャードの頑なさをよく知っていて、リチャードの決断を変えることなんて無理だと知っていたに違いないのに、説得を続けた。「俺の前庭に住みつく奴が誰でもいいとは思ってないからな」デイヴィッドはリチャードに警告した。「あの土地は俺のものだった。俺はその土地をお前にやったのだし、お前はお前の好きな奴にそれを売ってもいい。それでも、怠け者のだめな奴には入ってきてほしくないと思っている」
「慎重に選ぶつもりだよ」リチャードは言った。「きっと父さんも気に入る人たちに売るから」
「ふん」とデイヴィッドは言った。
ベティアはもう泣いていた。「リチャード、私はあんたがわからないよ。どうしたらいいのかわからないよ」
「大丈夫だよ、母さん」大声を出して言い争うことに、もはや疲れきったリチャードが母に答えた。「ただ僕に任せてくれればいい。僕は僕が信じることに従う。それでもし僕がここを離れることになるなら、ただそうするしかない」
「遠くに行くって言うんでしょ!」
「そんなに遠くじゃないよ。ここから行き来できる距離だって」
「なら行き来するのはお前だな」デイヴィッドが不機嫌に言った。
「俺はそんな無法地帯には足を踏み入れないからな」それ以降、リチャードの両親が私たちのところへ来ることは実際になかったし、両親とリチャードのあいだの緊張関係がなくなることもなかった。
私の両親に伝える仕事を私に押しつけなかったのも、リチャードらしいことだった。そのすぐあとの日曜日、リチャードは私の両親に説明をした。もしこれから海外で暮らすのだ、と言ったとしても、私の母はこれほど驚かなかっただろう。母の顔は疑心暗鬼から恐怖へ、そして私には言葉では表現できないほどの早さで悲しみの表情へと変わっていった。「嘘なんでしょ!」ついに母は言った。
「いえ、本当です」
母は悲しそうに私を見た。「あなた、私に残されたたった一人の娘をとりあげようっていうの?」
リチャードは落ち着いていようとしていた。「それがあるべき道なんです、ハンナ。もっと近くだとよかったんですが、ギャスパー・リバーにしかないんです。川もそこの人たちも僕たちには動かせません。僕たちが行くことしかできないんです」
デイヴィッドと同じように母は悲しみ、なぜなのかと聞き続け、リチャードはもう一度説明しようと試みた。しかしそれも無駄なことだった。あの光景は実際に自分で見た人でなければ、決して理解はできないようなものだ。私たちの家族は誰も理解できないだろう。それは神を説明しようとするようなものなのだ。あるいは人が春に抱く感情か、心が愛で満ちあふれる喜びを説明しようとするようなものだ。言葉では説明できないのだ。言葉はただ告げるだけなのだ。言葉は、人間の持つ唯一の、ものごとを伝えるための道具だが、役に立たない時もあるのだ。心が語ることができればいいのだろう。しかし心はただ、脈打ち、痛み、傷つくだけだ。
カッシーとサンプソンは静かに受け止めた。それでもカッシーはあとで悲しかったことを打ち明けてくれた。「残りの人生をずっとここで過ごすのだと思ってました」とカッシーは言った。「ミスター・リチャードはどうしたんですか。あんな変わった場所に連れていこうなんて。正しくない感じがします、ミス・ベッキー」
「そうね。しばらくは理解できないでしょうね。でもあなたの仕事は今まで通りです。そして今まで通り、ミスター・リチャードと私があなたたちの面倒を見る。心配することはなにもないから」
「はい。心配はしていません。ただいきなりのことだから」
ジェンシーは何も言わなかった。わざと頭の外に追いやっているようにも見えた。いつものようにうたって踊り、蝶を追いかけて、ふらふらしていた。ジェンシーが一番気にしていないようにも見えた。蝶々は世界のどこにでもいるのだから。
私たちはいつものように仕事を続けた。サンプソンとリチャードは畑で働き、カッシーと私は家事を続けた。でも私の頭の片隅には、常に引っ越しのことがあった。何を持っていくか、何を売って、何を手放すべきか、荷造りのことを常に考えていたのだ。目の前に待ち受ける新たな試練のことを考えすぎて、どの仕事にも楽しく没頭することができなかった。何をしても悲しさが込み上げてきた。気になることがあると仕事には集中できないものだ。ここでの生活はもう終わりなのだと思うと、もう家で誇りや喜びを感じることはできなかった。その代わりに家や農園、川や丘に毎日さようならを告げていた。感傷に浸って馬鹿だったとは思う。でもどうしようもなかったのだ。二十四時間ずっと悲しみは私につきまとい、重たい雲のようにまとわりついて、まるで幽霊のように出没した。
そして、母が訪ねてくる時が一番辛かったものだ。母の面長で色黒の顔を見ると、もう気軽に遊びには来られなくなる日々がすぐに来るのだと思い起こされ、私の心は刺されたように痛んだ。また会えるまで、何か月、あるいは何年もかかってしまうかもしれないのだ。
母はずっと悲しんでいたが、女は自分の夫の行くところへと行かなければならない、そのことだけはわかってくれた。そこに疑問を持つことは決してなかった。ただ、リチャードの信仰の変化を、そしてここを去らなければいけないことを悲しんでいるのだった。
私の毎日が少し明るくなる瞬間もあった。パルミラのことを思いだしている時、赤ちゃんのことを考えている時、そしてジェイニーの手紙を読んでいる時だ。
ジェイニーは結婚以来、一度も戻ってきていなかったが、頻繁に手紙を送ってくれた。
それは長い手紙で、ジェイニーの毎日の話題でいっぱいだった。ときどきは母宛てで、ときどきは私宛てだったが、全部二人に向けて書かれていた。手紙は配達人によって郡都まで送られ、それを誰かがいつも私たちのところへと届けてくれていた。家が完成してそこに落ち着いた話、フィラデルフィアで買った本格的なレースのカーテンと赤いベルベット生地が届いて家を飾っている話、レヴィット氏が若いアジア人の女の子をメイドとして買ってくれた話、それに優秀なコックともう一人黒人のコック助手までいる話、ジェイニーを連れだす専用の馭者(ぎょしゃ)がいて、新しい馬車がある話、舞踏会で新しいイブニングドレスを着て靴が擦りきれるまで踊った話。私は無我夢中でそれを読んだ。
ジェイニーの心の中についての話題はなかった。内容はいつも、やったこと、行ったところ、着ているものについてだった。それでもジェイニーは、快活で、わくわくするような楽しい生活を送っているようだった。ある時、母が言った。「子どもができたかどうかまだ言ってこないわね」
「手紙では書かないでしょ、ママ」
「そうね。そもそも私には言ってこないんじゃないかしら。あの子、この家のことを恥じてるのよ」
「やめてよ、ママ」
母はまっすぐに私を見た。その暗い目は鋭く辛辣だった。「そうなのよ、わかるでしょ」そう言って母は首を振った。「金持ちみたいに都会に住んで、私からしたら本当に変よ。私の子とは思えない」
口には出さなかったけれど、私も同感だった。けれども、ケンタッキー州はもともと向上心の高い人々によって造られた場所で、ジェイニーは自分の道を進んでいたのだ。母は絶対に理解しないだろうから、それを口に出すのは無駄だった。
母は私が思ったよりも早く、私にもう一人の子どもができたことを見抜いていた。今回は一人目の時ほど感じたわけではなかったが、引っ越しの不安によるものだったのかもしれない。母の目は、私のお腹が大きくなるずっと前にまず胸が膨らんでくるのを見逃さなかった。「また子どもができたんだね」とある日母は言った。
「そう」
「行ってしまう前に生まれてくれたらいいんだけど。前の時だって大変だったんだから、私が面倒を見られないところにあんたが行ってしまってたら嫌よ」
「その予定よ。前と同じ一月」
母の顔が明るくなった。「よかった。今回は大丈夫そうね。初めの子を失くして、それ以降うまくいくのはよくあることだから」そのことはよく知っていた。多くの女性が初めの子を失くし、その後うまくいっている。しかしジェンシーの予言が私の頭から離れなかったのだ。私は、ジェンシーに言われたことをまさに恐れていた。私は悩み続け、二人目の妊娠を心から喜ぶことができなかった。
不安は的中した。赤ちゃんは出産の予定日すら迎えることができなかった。十月のこと、予定日のまる三カ月前に、生き残る望みすら持たずにその子は生まれてきた。また男の子だった。今度は流す涙すらなかった。私には、その結末がずっと前からわかっていたかのようだった。唯一感じたのは、深い失意と絶望であった。私は自分を励ます強さすら起きず、ひどい倦怠感の中でベッドに横たわっていた。
リチャードは、気味の悪い言葉を発した。「これは罰なんだよ。ベッキー」ある日、私に夕食を運んだ時に横に座って言った。「僕たちの今までの生き方に対する罰なんだ。神に認められるまで、僕たちは子どもを授かることはできない」
希望とは奇妙なもので、まったくそぐわない感情から生まれてくるのだ。私の場合、それは絶望からだった。リチャードが部屋から出ていったあと、私は横になって、言われたことを考えていた。何かがおかしかったが、リチャードの言ったことは正しかったのかもしれない。あの夏、あの集会の時に感じた、奇妙な感情のことを思い出した。私はその感情を押し隠し、嫌悪し、決して信じようとはしなかった。きっと、罰を受けたのはその私なのだ。
リチャードは真実を目撃し、真の言葉で語り、神の恩寵を受けていた。でも私は疑い、困惑し、リチャードの真実の隣に身を投げ出そうとしなかった。私たちに向けられた神の怒りは私のせいなのだ。ベッドに横たわって回復を待つ日々、私は考え続けた。母は静かに出入りし、私や家の世話をして、私のことも赤ちゃんのことも母なりに深く悲しんでいた。
そして突然私は確信したのだ。リチャードが正しいこと、早くギャスパー・リバーへと移らなければいけないことに。無駄にする時間は一刻もない。疑いは捨てて、リチャードとランキン氏が信じたように、私も信じるのだ。私は祈り、つつましく生きる。そしてきっと主の罰は避けられるだろう。私は、すぐに出かけたい衝動に駆られていた。またすぐに子を授かるだろう。神によって救われた信徒たちのもとに加わり、私自身が真実を授かってからでなければならない。急がなければ、次の赤ちゃんも呪われてしまうだろう。
私はリチャードを呼んだ。私の調子が悪くなったのではないかと心配し、リチャードはすぐに来てくれた。
「具合が悪いのか?」リチャードはすぐに尋ねた。
「いいえ、ただ話したいことがあるの。時間はある?」
「どのくらいかかる? トウモロコシを収穫してるところなんだ。夕食まで待てるかい?」「いえ、今すぐに話したいの。気持ちがはっきりしているうちに。リチャード、私たち予定より早く出発できない?」
リチャードがベッドの横に椅子をひいたので、私は枕の上で体を起こした。「どうだろう。やらなきゃいけないことがたくさんある。君を急いで行かせることはできないし。本当のところ、君はあまりよく思ってないのかと思ってたよ。怖がってるんだと」
「そう思ってた。行きたくないと思ってた。馬鹿げてるし、どうかしてるとも思ってた」そして私は、どうやって今の思いに至ったかを説明し、今や早く行きたくて仕方がないことを説明した。「やっとわかったの」と私は言った。「あなたは導かれたの。そういう運命だったのよ。今の状態になったのは私のせい。急ぎたい。また子どもがだめになってしまう前に、急がないと」
リチャードの顔が喜びに輝いた。口は震え、目は突然の涙に瞬いていた。腕を上げ、大喜びで拳をぎゅっと握りしめた。「君が確信を得られるようにずっと祈ってたんだ。ギャスパー・リバーから戻ってきてから、ずっと昼も夜も祈ってたおかげだ。君が完全には信じてないってわかっててもどうしようもなくて、すごく悲しかった。でもやっと祈りが報われたんだ」リチャードは立ち上がって椅子を後ろに押しのけた。「行こう。準備ができたらすぐに行こう。サンプソンが収穫を終わらせて、僕が土地を売りにいく」
「どのくらいでできそう?」
リチャードは、やらなければいけないことを一つひとつ数えあげながら考えた。「クリスマス前だ」ついにリチャードは言った。
私は彼の前で、がっかりした顔をしてしまったのだろう。
「心配しなくていいよ」私の気持ちを読み取ってリチャードは言った。「僕は決して……」いくら結婚しているとはいえ、男女があけすけに語るようなことではないと気づき、リチャードは言葉を切った。けれども私には、何を言うつもりだったかわかった。ギャスパー・リバーに辿り着くまで、新たな子どもができる機会はないだろう。私はわかった、とうなずいた。リチャードは体を曲げて私にキスをして、私の髪を後ろにはらい、笑いかけた。
あの集会から家に帰ってきて以来、一番リチャードを近くに感じた瞬間だった。もう一度夫の手をとり、旅に出て、どこへでも行けるのだと感じた。もう一度、私は夫に寄り添うことができたのだと思った。信念の上でも、私への愛情の上でも、他人と感じることはなくなった。それは最高に心地よかった。今や私は、強さと心と意志とを取り戻し、熱意と喜びさえも感じながら、これからの日々を楽しみにすることができていた。
辛いこともあったが、やるべきことは終わった。デイヴィッドはリチャードの土地が家族以外にとられることを嫌がり、自分で土地を買い取ろうとした。でもリチャードは売らなかった。「もともと父さんがくれたもので、父さんからお金をもらうなんてできないよ」とリチャードは父親に言った。「でもギャスパー・リバーで土地を買うのに、お金が必要なんだ」
「俺が払うと言うのだから関係ないだろ」とデイヴィッドは言った。
「大いに関係あるよ」リチャードは短く答え、デイヴィッドは怒って家から出ていってしまった。
結局土地を買ったのはワージントン家の人たちのうちの一人だった。彼らはもともと隣人だったので、デイヴィッドもいやいやながら、他の誰かが買うくらいだったらワージントン家の人たちが買ったほうがいいことを認めた。
リチャードはランキン氏にギャスパー・リバーの農場を買うことを伝え、ものを仕分けし、荷造りし、出発の準備を整えた。荷物は馬車まる二台分になり、一方をリチャードが、もう一方をサンプソンが操った。家畜は雌牛と仔牛を一頭ずつだけ連れていき、残りはデイヴィッドと父に買い取ってもらった。
新しい農場には小さなログハウスしかなく、すぐに荷物でいっぱいになってしまうことはわかっていた。けれど、リチャードができるだけ早く新しい家を作ると約束してくれたので、私は家のものを全部持ってきていた。
出発は水曜日の朝だった。母と父が手伝いにきて、私たちの出発まで残っていてくれた。ベティアも旅のための食糧を持ってきてくれたが、デイヴィッドは顔を出さなかった。これから約束の地へ赴くのだ、という思いでいっぱいでなければ、私はきっと重く悲しい気持ちで旅立たなければならなかっただろう。それでも、振り返って後ろを見ると、涙が流れた。玄関に立っている背の高い母が、どんなに悲しく思っているか。父は老いて背が少し曲がっているように見えた。次にいつ会えるのかもわからない。ベティアはエプロンを目に当てて泣いていた。リチャードは聖書を引用し、私を慰めようとした。「(3)神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子、畑を捨てた者はだれでも、今この世で、迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も百倍受け、後の世では永遠の命を受ける」
「ええ」涙をふいて私は言った。「わかってるの。それでも辛いの」
サンプソンは不機嫌で、カッシーは頭にショールを被せて馬車に座っていた。がっしりした肩を落とし、うなだれて、ぶつぶつ文句を言っていた。デイヴィッドの所有だった他の黒人たちからは引き離されたものの、二人が別々になったわけではない。それでも川下に売り飛ばされたような気分だったのだろう。「こんなことして何もいいことなんてないのに」カッシーはずっとぼそぼそとつぶやいていた。「覚えておきなさい。本当にいいことなんて何もないの」
リチャードが彼女を黙らせた。
雌牛と仔牛を連れていたジェンシーが一番元気だった。道すがらずっと声をあげて泣くのではないかと心配していたが、実際にはいつものように馬車の横で踊り、うたい、くすくすと笑っていた。ジェンシーはお馬鹿さんなので、ギャスパー・リバーに一度行ったことさえ忘れていたに違いない。
ジェンシーは牛を連れるのがうまいとは言えない。道のあちらこちらへ常にせわしなく動き、石を拾い、しばらく握ってからそれを捨て、乾いた草を拾っては、振って芽を払い落としたりするので、牛はほとんどジェンシーが行きたい方向についていくだけだった。リチャードは頻繁に操縦を私と交代し、馬車を降りて、ジェンシーを急きたてた。「ジェンシーはまた」リチャードがぼやいた。「どうしてあんなしっかりしたカッシーから、あんな間抜けな子が生まれるのか」
私は笑った。「カッシーに似てるところはほとんどないもの。サンプソンのほうよ」
「サンプソンはのろまだけど」リチャードが同意した。「でも馬鹿ってわけじゃない。ジェンシーはただおっちょこちょいなんだよ」
今は冬だ。この辺りは風が強かったけれど、寒すぎることはなかった。木や丘は冬までに骨組みだけにはぎとられ、どこよりも荒涼としていた。夏は緑に満ちる牧草地も、草が寒さでやられてしまえば、茶色く死に絶えている。
とても重い荷物を運んでいるうえに、歩くのがゆっくりな雌牛と仔牛まで連れている私たちは、目的地へと辿り着くのに一週間かかったのだった。住むことになるログハウスを見たことはなかったが、どれだけ窮屈で劣悪な環境かはよく知っていた。地元にはログハウスがたくさんあり、一つか二つの部屋に家族全員が住んでいた。つまりカッシーとサンプソン、ジェンシーのための居場所を作るまでは、私たちは一つの部屋で暮らし、裏の部屋に彼らを住まわせなければいけないということだ。ゆっくりするのも、料理も、食事も、寝るのさえすべて一つの部屋でやるということだ。気が進まなかった。
リチャードが七日目にようやく言った。「ここからが僕たちの土地だ」私は今までより興味を持って辺りを見渡した。
地面には起伏があり、茂っていて、雑草も生えていたけれど、悪くはないように見えた。「いい土地なの?」と私は聞いた。
「ブラザー・ランキンはこの辺の他のどことも引けをとらないって言うよ」
「この辺の土地はそもそも上等なの?」
リチャードはうなずいた。「前と同じか、それ以上にいいところだよ。ちょうど小川が流れてくるところに家が立ってる」
ともかく、水が近くにあるのはいいことだ。水に関しては、もとから心配してはいなかった。ケンタッキー人はいつだって水に近いところに家を建てるものだ。水は、家の場所を選ぶのに一番最初に考えることなのだ。「家はどれくらい遠いの?」と私は聞いた。
「あの曲がり道のところから半マイルくらい離れたところだよ」
私たちはその曲がり道まで来て、右に続く脇道に入った。「見えない」私は言った。
「あそこのちょっと上がったところの先だよ」
煙が見えた。「リチャード」私は言って、その腕をつかんだ。「煙突から煙が出てる」
「本当かい! きっとブラザー・ランキンが家を温めておいてくれているんだ」
「今日来るって知っているの?」
「手紙を送っておいたからね」
しかし気の利く人物はランキン氏ではなかった。私たちがドアのところまでやってきた時、ドアが開いて中からパルミラが飛びだしてきた。美しい顔に笑みが広がる。「ようこそ」パルミラは叫んだ。「レベッカ、よく来たね!」
私は母親に会えて喜ぶ子どものように、喜びのまま真っ先に馬車から飛び降り、そのままパルミラの腕に飛びこんだ。「ああ、会えて本当に嬉しい」私は言った。「パルミラ、あなたがいて本当によかった」
第6章訳註
(1)メソジスト(Methodist)
メソジズム(Methodism)を信仰する人々のこと。メソジズムは、18世紀にジョン・ウェズリー(John Wesley)によって起こされた、英国の教会を内部から改革しようとする運動である。
(2)バプテスト(Baptist)
キリスト教プロテスタントの宗派の一つ。他の多くのプロテスタントと同じ信条を持ちながら、信者のみが洗礼を受けるべきであり、またそれは水をかけるものではなく全身を浸すことで行うべきであると主張する。
(3) 「神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子、畑を捨てた者はだれでも、今この世で、迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も百倍受け、後の世では永遠の命を受ける(“There is no man that hath left house, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel’s, but he shall receive an hundred fold … and in the world to come eternal life.”)日本聖書協会「マルコによる福音書」10:29『聖書 新共同訳』に即して訳した。”イエスは言われた。「はっきり言っておく。わたしのためまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を捨てた者はだれでも、今この世で、迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も百倍受け、後の世では永遠の命を受ける。」”