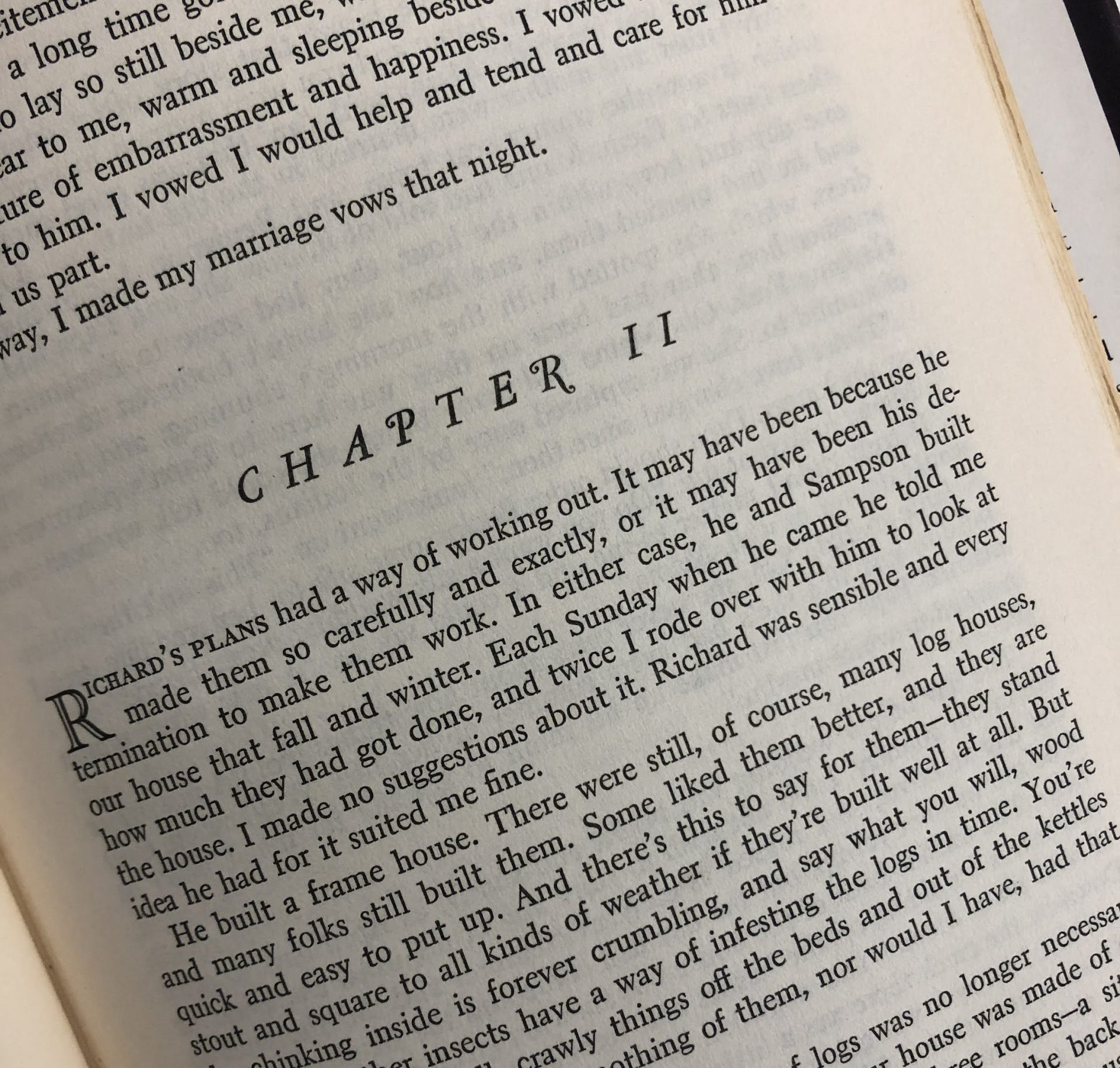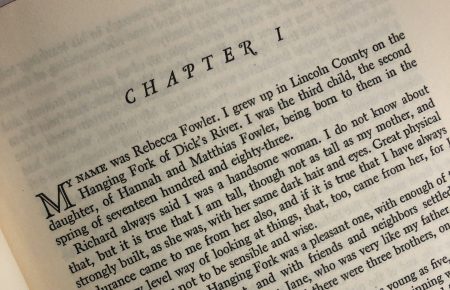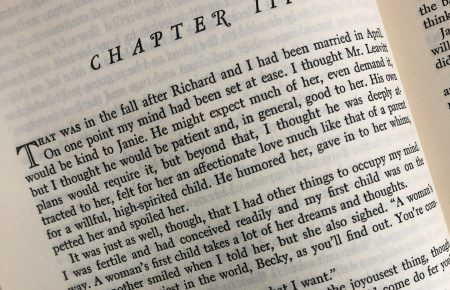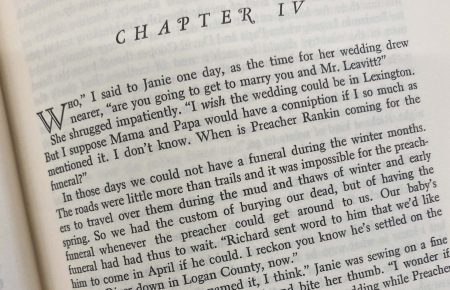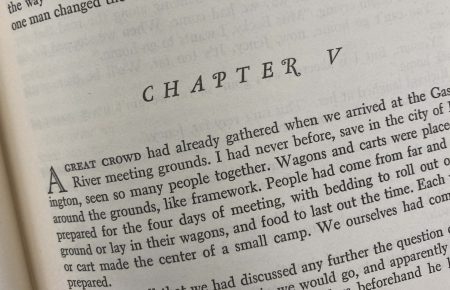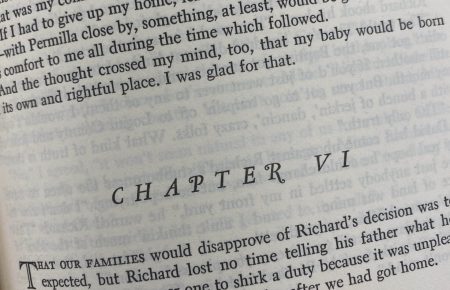リチャードは首尾よく計画を進めた。彼は計画を細心の注意を払いながら意欲的に進めていた。
リチャードとサンプソンは、その年の秋と冬のあいだに家を建て終わった。リチャードは毎週日曜日に私を訪ねては、進み具合を教えてくれた。それで、私も連れられて二回ほど現場を見にいったことがある。家のことについて、リチャードはしっかりと自分のやることをわかっていたので、私がそれについて口出しすることはなかった。
リチャードは(1)フレームハウスを建てた。速く簡単に作られることから、いまだに好んでログハウスを建てる人たちは多かった。もちろんログハウスも捨てがたい。しっかり建てられてさえいれば、どんな天気にもびくともしないからだ。しかし、すきま風の入るログハウスの中では、丸太のくずがなくなることはない。何といっても、建てられてから時間が経つと、キクイムシのような虫たちが家をくい荒らしてしまうのだ。だから、ベッドの上や食器の中には、常にもぞもぞと動く虫がいて、それを払いのけ続けるというのが、ログハウスの日常だった。私の母は、それをまったく苦にしていなかった。それと同じように、もしリチャードがログハウスを望んだとしたら、私も気にしなかったと思う。
とはいえ、この地域には材木工場があったので、ログハウスの家をあえて建てる必要はなかった。家はオーク材を枠に使い、光沢のある金色のポプラ材で壁を張っていた。家に入ると、手前に応接室と寝室があり、奥に台所があった。それぞれの部屋が大きくて風通しがよく、まるでクーパー家のようだった。私はベティアを見倣って、明るくきれいな色のラグを作ることをひそかに決めていた。
手先が器用な私の父が、ベッドを作ってくれた。そして冬のあいだ、母と私はシーツと枕カバーを織った。ベティアはキルトの掛け布団と羽毛のマットレスを作ることを約束してくれた。ジェイニーはもっぱら私が何を着るかについて心配していた。ジェイニーは「最低でも一着はシルクのドレスを持ってなきゃだめ」と母に文句を言っては、この近所でシルクとサテンを手に入れるのが難しいことに苛立っていた。「女の子は誰でも結婚式にはシルクを着なきゃいけないのよ」 「私は違ったわ」と、母は短く答えた。 「知ってる」とジェイニーは言い返した。「その話は何度も聞いたもの。その頃お母さんは二着しかドレスを持っていなくて、二番目にいいドレスを着て結婚したんでしょう」 「結婚できたのだから、それで十分」と母は言った。
父と母は、現在の郡庁所在地となっている(2)古い砦で結婚式を行った。その砦は(3)ベンジャミン・ローガンのもので、ベンジャミン・ローガンその人が、二人の式を執り行った。それは母が持っていた逸話の一つだった。ある日、二人は結婚することを決めた。それから一時間のうちに、二人はベンジャミン・ローガンのところへ行き、式を挙げてもらった。その時、母は朝の乳しぼりで汚れていたドレスを着替えようとさえ思わなかったのだ! 二人は、結婚することを決めた二時間後には、夫婦としてハンギング・フォークの我が家へ向かったのだ。母は、その気になれば語るに足るたくさんの経験を持っていた。彼女はインディアンに捕まったことさえあるのだ。 「もう昔とは違うんだから」とジェイニーは続けた。 「この辺りだってもう荒地じゃないわ。ベッキーのためにシルクの生地を注文するべきよ」 母は私を見た。 「ベッキー、あなたはシルクのウェディングドレスが欲しい?」 本当にどうでもいいことだった。 「新しい白の(4)ムスリンで十分だと思う」と私は言った。 「本当にベッキーは見た目に気を使わないんだから! 白のムスリンなんて毎年夏に作っているのと同じじゃない! 私が結婚する時には、絶対にパパにシルクを買ってもらうから。私は白のムスリンを着て結婚したりしない」ジェイニーは鼻を鳴らして言った。
結婚式の当日は、明るく天気のよい日だった。四月のこの時期で天気が悪くなることはあまりなかった。私はいつもの時間に起きて乳しぼりに向かった。我が家での最後の一日をいつものように始めたかった。朝日はまだ出ていなかったけれど、すでに一日は始まっていた。空気は澄み、新鮮だった。裏の丘では、新芽をつけ始めた茂みや木々が新緑の色合いを見せていた。野生のプラムが白い霧のように花を咲かせ、ハナミズキの花が丘全体に広がっていた。小川を下ったところに立ちこめていた霧は、ちょうど消え始めていた。今日は素晴らしい一日になる、と私は思った。
しかし奇妙なことに、私は少しの興奮も感じていなかった。冬が始まるずっと前から今日のことを考えていたのだから、それも当たり前なのかもしれなかった。その日は長く待ちわびた日で、素晴らしい日になる予感がしていた。私は安堵感と満足感に満たされていた。リチャードの隣に立って、誓いの言葉を述べる瞬間のことを落ち着いて考えられたし、そのあとのことに考えが及ばないように、自分をコントロールすることもできていた。
式についていえば、私もリチャードも、緊張してはいなかったはずだ。我が家の一番大きな部屋は掃除され、隅々まで磨かれて輝いていた。ジェイニーは兄弟に頼んで、腕いっぱいの白い花を裏の丘から摘んできてもらっていた。私たちは暖炉の前に立って誓いの言葉を述べることになっていたので、ジェイニーはその花々を暖炉のまわりじゅうに飾りつけたりした。それは、私が今まで目にした中で一番きれいな光景だった。それは、まるで森の春が家の中に入ってきたようだった。さらにジェイニーはプラムの花でブーケを作って渡してくれた。のちに、私は長らく聖書に挟んだそのプラムの花々を、乾いてぼろぼろになってしまうまで大切にした。そのブーケを作っている時のジェイニーの手つきや、渡してくれた時のその感覚は、私にとって大切な思い出だからだ。
結局、私はシルクのドレスに身を包んで結婚した。父がジェイニーの思い通りに、わざわざ(5)ルイヴィルまで生地を買いにいってくれたのだ。それは深い茶色の光沢のあるリブつきのドレスで、小さなベルベットのリボンがスカートに縫いつけられていた。ジェイニーは、白か薄い青色のドレスにしたがったけれど、薄い色のドレスでは繕うのが大変だと知っていた。私にも母親と同じく実用的な面があって、そのドレスが教会に行く時や特別な時のために長く使えるものであってほしいと思っていた。
結婚式はしばしば、この地域を訪れていた若い長老派の牧師によって行われた。リチャードはまじめで熱意のあるこの牧師を気に入ったようだった。テネシーから来たその牧師は、名前を(6)ジョン・ランキンといった。彼の声は深く、厳粛で、その声によって式は厳粛さに包まれて行われた。
家は友達や隣人たちで混み合っていた。式が終わると、家の中は騒がしく明るい雰囲気で満たされた。母は、隣人の助けも借りて何日も前からごちそうの準備をしてくれた。食卓として使っていた長い車輪つきのテーブルが木陰に運びだされて、テーブルはその上に置かれた素晴らしいごちそうの重みできしんでいた。父が、自分で作った上質のウイスキーをたくさん用意していて、笑い声や冗談がたくさん交わされた。リチャードの顔が真っ赤になるのを見た。実をいうと、自分の顔も熱くほてっているのを感じた。結婚式の宴の場で交わされる冗談というのは、新婚のカップルには刺激的なものだった。
やっと私たちは退席を許され、近所の若者をみんな従えて席を立った。景品である(7)ブラック・ベティーのボトルを競い合って、若い男たちはわれ先にと馬に乗っていくのが習慣だった。私たちを追い越し、周囲を走り回って、興奮して叫び、冷やかしてきた。私たちは、その夜も二人きりになることはなかった。若者たちは、夜になってからフライパンややかん、鉄の棒を叩いて、リチャードが私を家に招き入れるまで口笛を吹き、歌をうたうのだった。私たちはベッドには行かなかった。というのも、何が起きるのかを知っていたので、ベッドに入る必要はなかったし、寝室着を他の人に見せるつもりもなかった。若者たちは家の明かりがついていて、私たちがきちんと服を着ているのを見て、少しがっかりしたようだった。若者たちにとっては、夫婦を暖かいベッドから出させることが最も楽しみなことなのだ。
私たちは食事を振る舞い、持ってきたバイオリンを奏で、若者たちは朝まで踊り通した。私とリチャードは踊らなかった。ときどきお互いのことを見つめては、これが早く終わるのを願っていた。そうはいっても、この地域のしきたりには従わなければならない。朝方になって初めて、私たちは二人きりになった。すべての法に許され結婚した自由な夫婦として、私たちは見つめ合った。
私は、結婚してからのこの最初の数カ月間を、どのような言葉で表現できるのかをずっと考えていた。完璧な言葉を探したのだが、自分が思いつくあらゆる言葉を思い浮かべても、どれもぴったりこなかったのだ。
それは「火」だった。私たちのあいだで清く美しい炎がうたい、踊っていた。あるいは、それは喜びだった。笑いがあふれ、心臓が高鳴り、全存在を通して高らかに美しい歌をうたっていた。それは誇りだった。お互いのものとなるあいだに、私の頭を雲の上まで持ち上げた。それは善だった。健康な身体と活力から来る堅固な善良さだった。それは優しさだった。優しさは溶けて、柔らかく、流れていた。それは平和だった。魂の祈りのように静かにそこにあった。それは、これまで人間に与えられた中で最も完璧な時間だった。
そして、日々の仕事が大変だったのはたしかだった。デイヴィッドは土地をすべて牧草地にしていたから、刈るべき草はごくわずかだった。しかし地中深く絡みあった草の根を抜く作業は大変な仕事だった。
リチャードは夜に家に帰ってきて、ベッドにも辿り着けないほど疲れていることがよくあった。 「肩をもませて」と、私はある日頼んだ。 「それでよくなるとは思えないな、肩にこぶができたみたいだ」とリチャードは疲れてそう言った。
それでもリチャードはシャツを腰まで下ろしてくれたので、私はオイルを手に取って、凝った背中と首と肩を揉み始めた。私の手の下で身体がほぐれ始めるのが感じられた。 「すごい、楽になったよ」リチャードは驚いて言った。
それから、毎晩リチャードの肩を揉むのは私の日課になった。リチャードの鍛えられた肩は滑らかで、広く、シャツを着ていても毎日の仕事で日焼けしていた。私は自分の手でその生命と力強さを感じることができた。私にとって、肩は男性の姿形の中で一番素晴らしい部分だ。夫の肩に触れながら、夫に対する誇りが湧き上がってくるのを感じることもよくあった。その肩はきつい仕事に耐え、一方で優しさに満ちた抱擁も与えてくれた。男性の腕に抱かれること、彼の力強い欲求に満ちた力を間近で感じることは、女性にとっての一番の特権だ。リチャードの腕に抱かれる時には、いつも純粋な喜びが体全体に行き渡るのが感じられた。リチャードはよく私を抱きしめてくれた。
私にも自分の仕事があった。家事やカッシーとジェンシーの監督、牛や鶏の世話、庭の整備、洋服を縫ったり、繕ったり、洗濯とアイロンがけを管理したり、全員分の料理を作り、掃除をしたりした。有能な黒人がいたとしても、家事の義務と責任は夫人にあるのだ。家のことはしっかり滞りなく行おうと心に決めていた。
グリーン・リバーの丘を背後に、谷を目の前に臨むその場所に、私たちは少しずつ家を作っていった。エメラルド色の清流の音がいつも一緒だった。
その土地は、子どもの頃から訪れていたなじみのある場所だった。いま私がリチャードのあとについて川や草原を歩いていくのは、魚釣りや罠を仕掛けたりしにいった子どもの頃から何も変わっていない。私は、ハンギング・フォークの土手と同じくらいのなじみをそこに感じていた。ホームシックになることは決してなかった。新しい人生はとても幸せだった。私は妻としての義務をとてもまじめに捉えていた。カッシーに指示を与えたり、ジェンシーを追い払ったりするのをどれだけ重要に考えていたかを今になって思い出すと微笑ましい。
黒人を監督するのに学ばなければいけないことはたくさんあった。ハンギング・フォークに黒人はいなかった。それは私の父や母が黒人の所有に反対だったからではなく、所有する余裕がなかったからだった。カッシーとジェンシーを監督しなければならない日々の中で、ベティアが近くにいることは私にとっては安心だった。
リチャードの母であるベティアは小柄な女性だったが、恰幅のよい女性でもあった。七人の息子を生んだが、彼女の足取りはとても軽く、どんな動きも優雅に見えた。ベティアはよく笑い、スカートに飾りをつけていた。私が知る限り、ベティアは自分の髪を特別誇りにしていた。その髪は美しく豊かに輝いていて、白髪はほとんどなく、きれいな赤褐色をしていた。その髪をきちんと結び上げて、普通よりも小さな帽子をいつも被っていた。ベティアはそのきれいな髪を覆ってしまいたくなかったのだと思う。
カッシーとジェンシーについて、ベティアはこのように言っていた。「カッシーはよく訓練されているわ、ベッキー。でも自ら何かやることはないわね。何をしてほしいか指示をして、最初はどうやってほしいか見本を見せなくちゃだめ。そうすれば、いつもそのように仕事をやってくれる。あなたがやっていることを見るだけでは、やるべき仕事を判断することはできないから、ちゃんと日課を与えて。そうすれば、あなたの望む通りに仕事をやってくれると思う。カッシーは不平を言うことはないし、おおかた健康で有能よ。ジェンシー……あの子に関してはどうすればいいのかわからない。もう仕事を覚えさせてもいい年齢だけど、彼女は軽はずみで、まだ始められていなかったの。すぐ嘘をつくし、自立して何かさせることはもちろんできない。唯一できることは、考えたり技を使ったりする必要のない雑用だけね。彼女は水を汲みにやれば、バケツ半分以上の水を持って帰ってくることはできる。薪を取りにいかせることもできる。その気になれば、子どもの面倒を見ることもできる。庭を掃除することも、洗濯物を持ってくることもできる。でも、集中力がいる仕事は何一つ信用して任せることはできなかった。例えばアイロンがけをやらせたら、全部に焦げ目を入れてしまうか、冷やしすぎでしわ一つとれないかのどちらか。台所を掃除させたら、シンクの石鹸水をシャボン玉にして一日中遊ぶのが目に見えてる。わからないけれど、彼女は軽はずみに生まれついて、何かを教えるには単純すぎるのかもしれない。あなたなら教えられるかもしれないけれど、私にはそんな時間はなかった」
私にとっても、ジェンシーは重荷に違いなかった。しかしジェンシーはカッシーの娘で、父親と同じくリチャードの方針は決まっていた。リチャードは家族を離ればなれにすることなど夢にも思わないだろう。サンプソンとカッシーとジェンシーは一緒に来るのだ。その時でジェンシーは十歳になっていたと思う。どんな質問にも、高いくすくす笑いで答えて、「わかんないです」と言って、笑って目をむくのだ。どこに(8)暖炉掃除用のターキーウィングをしまったのか、石鹸のボウルをどこに置いたのか、私のアイロン仕立ての帽子をどこに置いてきたのか、ジェンシーが教えてくれることはなかった。ジェンシーが落ち着かないせいで、一日に何度も私は邪魔をされたりした。たいてい、ふらふらして人の邪魔をしては、馬鹿げた歌をうたったり、くすくす笑ったりしているのだ。
ジェンシーはきれいなものが大好きで、リボンの結び目やきれいな鳥の羽根で何時間も遊んでいた。自分の縮れ髪に結びつけたり、ボタンの穴に通したりしていることもあった。いつも幸せそうに見えて、不幸せさを感じるほどの頭もないのではないかと思うこともあった。私もカッシーとベティアのやり方に倣って、ジェンシーには簡単な外での雑用をやらせていた。
初めからジェンシーのお気に入りはジェイニーで、もしジェイニーの役に立つのなら、私は喜んでジェンシーを彼女に譲ったことだろう。しかし、それはもちろん無理な話だった。カッシーはジェンシーが十マイル離れただけで嘆き悲しむと思われたのだ。
ジェイニーは、その頃よく私の家を訪ねてきた。ほとんど毎週日曜日に馬に乗ってくるのだった。私が家を出てからは、ずっと落ち着かなかったのではないかと思う。ジェイニーと母はいつも何かしらで争っていた。もちろん、母はジェイニーのことを愛していた。一人目の子どもなのだから当然だ。でも、ジェイニーは意志が強くて、自分のやりたいようにいつもやっていた。母はよく、こんなに手のかかって言うことを聞かない子どもは初めてだと言ってていた。自分の言うことを聞かない子どもをそのままにしておくのは、もちろん母のやり方ではなかったのだ。
そのせいで、子どもの頃、ジェイニーは罰を受けることがよくあり、ふてくされていることが多かった。一方で、私は考えが母に似ているところがあったので、理屈を自然に理解することができて、何ごとかに従うのは難しいことではなかった。ジェイニーは母が私のことをひいきしているといつも思っていたが、実は反対だった。本当はジェイニーが母の一番のお気に入りだった。 私は従順で目立った問題を起こさないというだけだったのだ。
とはいえ、ジェイニーが家で落ち着けることはほとんどなかったから、もしジェイニーが男の子だったとしたら、外の世界に向けてとっくに家を出ていただろうと思う。でもジェイニーは女性として生まれ、退屈さで擦り切れるかのような女の人生に縛りつけられていた。
ジェンシーは、ジェイニーが日曜日に訪ねてくるのを楽しみにしていて、姿が見えると駆け寄って、まるで小さな黒い犬のように馬のまわりを駆け回ったりした。ジェイニーは、いつもジェンシーにきれいな石や小さなケーキ、新しいリボンの切れ端、途中で摘んだ花の一束といった小さなお土産を持ってきてくれた。それらは全部ジェンシーの宝物になった。ジェンシーは私に追い払われるまで、私とジェイニーのあとを追いかけ回すのだった。しかし、追い払うとジェンシーはむっつりして不幸な顔をするので、私もいささか申し訳ない気持ちになるのだった。
ジェイニーが何か仕事を与えると、ジェンシーは喜んでやることが判明した。ジェイニーは回りくどい方法で彼女に仕事を教えなければならなかったが、辛抱強くやってくれた。「こういうふうに帽子を広げるのよ、ジェンシー。一度に少しずつ。そうしたら気をつけてアイロンを試しにあててみる。きれいにアイロンがかけられるでしょ? さあ、やってみて。一つのしわなしにアイロンをかけられる?」そうするとジェンシーは台に身を乗りだして、舌を噛みながらジェイニーの言った通りにやろうと頑張るのだ。
もし指示したのが私だったら、ただくすくす笑って「わかりました」と言って雑に仕事をし、シンプルな帽子にたくさんのしわをつけたことだろう。「どうしてかわからないけど、あなたの仕事はちゃんとできるみたい」と私はジェイニーに言った。 「ジェンシーは私のほうが好きなの」とジェイニー。「ちょっとしたプレゼントを持ってきたり、かまってあげる時間があるからね。あなたは他にやることがたくさんあるでしょう」
子どもや犬、黒人のような単純な人たちは、彼らが愛されている時、それを本能的に知っているという物言いは、真実とは思えない。ただ表面的なことしか見ないだけのことなのだ。彼らにとっては、撫でてくれる人間はみな親切な人間なのだ。ジェイニーはジェンシーのことを愛してはいない。彼女はジェンシーのことを、ただおもしろがっているだけだった。たしかに、ジェイニーのほうがジェンシーをもっとうまく訓練できたのかもしれないけれど、ジェイニーは実に気分屋だった。私はジェンシーのことを鞭で打ったことはないけれど、ジェイニーは悩みもせず打ったかもしれない。
実家での彼女の苛立ちはさておき、ジェイニーは地元の二人の男性のあいだで心を決めかねていた。リチャードの兄ジョニーと一緒になってくれればいい、と私はいつも思っていたのだが、所詮むなしい望みにすぎなかった。二人は一緒にいて五分も経つと、口論せずにはいられなかったのだ。ジェイニーはジョニーが無責任で落ち着かないと言い、逆にジョニーはジェイニーが見栄っ張りで頭が悪いと言った。
ジェイニーに言い寄っている男性は、二人とも人里離れた場所に住んでいたのが問題だった。二人とも見た目はまあまあよく、生活は安定していて、信頼できるのはたしかだった。しかし、どちらに嫁いだとしても、ジェイニーは幸せになれないだろうと思った。ジェイニーは人と関わるのが好きだったので、奥地の農家に住むのを楽しむことはできなかっただろう。人口の多い地域の真ん中にある、ハンギング・フォークさえジェイニーにとっては田舎すぎた。
ある日曜日、ジェイニーが私のもとにやってきた時、何かいいことがあって、興奮しているようだった。彼女は私に報告したくて、夕食のあいだじゅうずっとそわそわしていた。やっとリチャードが父親を訪ねるためにいなくなった時、ジェイニーはしゃべり始めた。「レキシントンのレヴィット氏が、ここ三日間うちに泊まっていたの!」 「誰?」と私は聞き返した。 「ジョン・レヴィットよ!」
それで私は思い出した。その人は街の弁護士で、(9)フェイエット郡の議会員をしている人だった。
彼はとても影響力のある人だった。ケンタッキーで起こった問題で、ジョン・レヴィットと何らかの関係を持っていないものはほとんどなかったほどだ。「どうしてレヴィット氏がこの地域に来ているの?」 「ずっと続いている土地を巡る裁判のごたごたを解決しようとしているんだって。顧客が家の裏の土地を所有していると主張していて、その場所を見にきたみたい。パパと話したがっていたから、パパが仕事が終わるまで泊っていくことをすすめたの。レヴィット氏は独身よ!」 「もちろんあなたに目をつけたんでしょう?」私は笑った。 ジェイニーも笑って「そうかもしれない」と言った。 「まだ家にいる?」 「昨日街に帰った。そうでなきゃ今日ここに来てないわ」 「そうね。その人は何歳なの?」 「男の子とは呼べないかな。どういう質問なの?」 「男の子じゃないことはわかってる。あの人が男の子であるはずがないもの。何歳なの?」 ジェイニーは頭を傾けて、考えていた。 「あなたの基準では年寄りといえるかもね。正確にはわからないけれど、四十歳くらいじゃない?」 「それは年寄りね」と私はすぐに言った。「ジェイニー、おじいさんと結婚したくはないでしょ? どうしたらその人を愛せるっていうの?」 「愛ね」ジェイニーはいらいらしているようだった。「それがどう関係あるの」 「愛してない人と結婚してみればすぐにわかるよ」 「試してみる。レヴィット氏はもう議会員なの。国会議員に立候補するつもりだと教えてくれたわ。そしたらワシントンで仕事することになる。ワシントンで暮らすことを考えてみてよ! もしワシントンに行かなかったとしても、レキシントンに住めるの、都会に! いい家に住んで、召使いやきれいなドレスを持てるの。お金持ちとお出かけして、私もお金持ちになれる」 「今より大して幸せにはなれないかもしれない」 「なれるわ。私とあなたとでは幸せの意味が違うから、ベッキー。あなたはこの川の近くにリチャードと住んで、これまでとまったく同じことをやっていても幸せでしょう。私はこんなところじゃ死んでしまう。私は旅をして、お金を持って、いい暮らしをしたい」
私は少し動揺したけれど、ジェイニーの言っている私の境遇は真実だった。私たちはまったく違う種類の人間なのだ。私は単純なものを求めていた。リチャードとこの家、川、そして子どもを持つこと、いま持っているものに満足していた。しかし、ジェイニーはいつも夢を見ていて、しゃれたものを愛し、狭苦しい田舎にはうんざりしていた。私が恐れていたのは、ジェイニーのやろうとしていることが、若さや好奇心、冒険心によるものであることだった。若馬が威勢がよいのは当たり前だ。人生と時間が、いつかジェイニーを引きずり下ろすのではないか、と心配だった。「その人がもう結婚を申し込んできたみたいに話すけど、どうなの?」と私は尋ねた。 「まだだけど、また家に来てもいいかパパに聞いていたから」 「結婚したがると思う? 街にはレヴィット氏に目をつけているご婦人たちがたくさんいるんじゃないかな?」 「それは心配してない。私が結婚したいと決めたら、絶対彼は申し込むもの」
その通りなんだろう、と私は思った。ジェイニーは自分の欲しいものを手に入れる手段を知っていたから、レヴィット氏を欲しいと思ったら、手に入れることはたしかに思われた。でも私には、レヴィット氏が田舎の少女を気に入ることがあるだろうかと思った。ジェイニーはきれいで明るく、聡明だったが、田舎の人間が地味であることには変わりない。もちろんケンタッキーに上流階級はいなかった。開拓時代に名を上げた人たちがいくらかはいたが、傑出した人のほとんどは、あとからレキシントンやルイヴィルに来た人たちで、その地域に古くから住む人間を差し置いてリーダーになったのだ。レヴィット氏もその一人だ。「まあ、決断する前にちゃんと考えてね。ママはその人のことどう思っている?」 「ママは街の人間を誰も信用していないわ。もちろんレヴィット氏は歳をとりすぎているとも思ってる。自分だって、パパが四十歳くらいのときに結婚したくせに。私がどこかの荒野の小屋に住んだほうがましだと思ってるのよ。レヴィット氏がまた家に来ることで、ママとパパは喧嘩してた。意味はないけどね、二人が何と言おうと、レヴィット氏に会いたければ会うだけだわ」 「家から抜けだして会ったりしないでしょうね?」 「そうしないといけなければ、もちろんそうする」 私はいまだにそれほど大胆になったことはなかった。「もし見つかったら?」 「何もできないでしょ。私はもう大人だから、ベッキー。ママはもう私を鞭で打つことも部屋の端に縛りつけることもできない。ママにできるのは文句を言うことだけ。それは気にしない。でも私を止めようとはしないと思う。ママは文句を言うけど、パパはレヴィット氏が家に来ることを許すもの。見てて」
そして、事はその通りになった。母はことさら本人の前では文句を言うことはなかった。また、父はレヴィット氏が訪ねてくるのを止めはしなかった。
ある土曜日に、リチャードと私もレヴィット氏に会うことになった。
レヴィット氏は背が低くやせていて、ジェイニーと同じくらいの背丈で、髪は薄くなりかけていた。思ったよりも感じのいい人だった。教養のある人間らしいマナーを持っていて虚勢を張ることもなく、上等の服を着ていた。よくしゃべり、自慢げになることはなかった。いい馬に乗って、手は白く、手入れが行き届いていた。手を使った労働をしたことはなさそうだった。もしあったとしても、それはとても昔のことなのだろうと思われた。
レヴィット氏がジェイニーのことを慕っているのはよくわかった。話している時でさえ、目は部屋の中のジェイニーを追っていたし、ジェイニーが座って、話を聞いているだけの時も、その顔を見つめて微笑んでいることがあった。ジェイニーは、まるで二人のあいだに秘密の取り決めがあるかのように、微笑み返した。求婚の決まりごとは形式にすぎないかのようだった。
それが真実だったのだろう。
レヴィット氏はその月、毎日曜日に両親の家を訪れた。その月にジェイニーが一度も私の家に来ることはなかった。結婚が決まったあとに、やっとジェイニーはレヴィット氏を家に連れてくることになった。レヴィット氏が高級な食事に慣れていることを考えると、夕食の準備には緊張した。しかし、レヴィット氏は雰囲気よく食事ができるように心くばりしてくれたようだった。食事のあと、レヴィット氏は土地の価値に詳しいというので、リチャードは農地を案内した。二人が戻ってきてから、レヴィット氏は言った。「ここはよいところですね。この辺りを見た中では一番いい。リチャード、君はよい仕事をしている」
レヴィット氏が結婚の意思を私たちに伝えた時、ジェイニーは下を向き行儀よくしていた。「家を離れるようにミス・ジェーンを説得するのは大変だった。家やこの土地に愛着を持っていらっしゃるから。でも、私は彼女に都会の魅力をわかってもらうことができた。そして、私の妻になるということを承諾してもらえました」
ジェイニーはまつ毛の下からこちらを見た。おもしろがっているような目の輝きを私は見逃さなかった。笑いだしそうだった。ジェイニーが家と土地に愛着を持っているですって? でたらめに違いなかった。ジェイニーはそのどちらも喜んで、潔く捨てるだろう。ジェイニーが謙虚さと貞節を、両親と家に忠実な娘のイメージを、レヴィット氏のためにつくろっていることがわかっていた。
レヴィット氏は続けた。「お父さんに許可を求めました。考慮されたあと、許しをいただくこともできました」レヴィット氏は正直に、政治家としてぴったりの妻が必要だったことを認めた。 「ミス・ジェーンのような女性と出会えたことは幸運でした。私の愛する女性で、私の家を美しく飾ってくれる人です」
私には少しもったいぶりすぎているように聞こえたけれど、その言葉は、レヴィット氏とジェイニーがお互いの意図と要求を理解し合っていることの証拠でもあった。レヴィット氏は自身の政界でのキャリアを進めるために、家のホステスとなる美しく優雅な妻が必要だった。そしてジェイニーはきれいで優雅で、呑み込みが早いぴったりの候補だった。ジェイニーの望みは、まさに彼が与えてくれる生活であり、新しいことを学ぶ意欲も持ちあわせていた。ただ、二人とも清廉潔白でないことはたしかだった。「日にちは決めたのですか?」と私が尋ねた。 「それはですね」レヴィット氏はよく裁判所にいるかのように話すことがあり、その調子で重々しく話し始めた。「ミス・ジェーンに決めてもらうのがいいでしょう。私にとっては早すぎるということはないので」ジェイニーを好ましげに見ながらレヴィット氏は言った。
ジェイニーは同じようにレヴィット氏を見つめ返して言った。「十分な時間はあるでしょう」
二人ともお互いに愛以上のものを求めていたとしても、うまく隠していた。二人のあいだでは間違いなく取り決めは交わされていたのだと思う。しかし、私たちや他の人には、愛し合う男女のように見せていた。
ジェイニーは別の時に私に向かって言った。「急いで格好の悪い式を挙げるつもりなんてないわ。服を選んで作るのに一年はいるでしょう。この秋にパパにルイヴィルに連れていってもらって、ドレスとかを選ぶつもり。冬を使ってドレスを縫って、次の五月がちょうどいいと思ってる」
ジェイニーは爪先立ってくるくると回った。まったく違う理由で、私もリチャードがプロポーズしてくれた時に同じようにしたことを思い出した。「ベッキー、欲しかったものが全部手に入るの、考えてみて! レキシントンのちゃんとした家、召使いに馬車、シルクにサテン、パーティーに遊び! もしかしたら一、二年のうちにはワシントンに住めるかも!」ジェイニーは暖炉の脇に座って、夢見心地に炎を覗きこんだ。「レヴィット氏は私たちの家を建てるのに忙しくなる。煉瓦造の家! 想像できる? メインストリートにいい土地を持ってるのよ。計画はもう決めたから、(10)フィラデルフィアまで行って調度品を買ってきてくれる。銀食器に陶器、敷物、最高級の家具をね。お客様を迎えることが多いから、家をきちんとしなければいけないのだって」ジェイニーは伸びをすると、喜びに震えた。「嬉しすぎて、叫んだりうたったりしたい気分だわ」
もちろん私も喜んでいた。しかし、ジェイニーがレキシントンのような遠くに行ってしまうことを考えると悲しかった。めったに家に帰ってこなくなってしまうだろう。もちろんジェイニーが田舎の家族を下に見るようになるわけではなく、新しい生活でやることが多すぎて、家に帰ってくる時間などなくなってしまうと思った。 「レヴィット氏の宗派は?」と私は尋ねた。なぜこんな質問をしたのかわからない。その頃、(11)グレート・リバイバル運動がケンタッキー全体を駆け抜けていて、信仰はどの家でも重要なことだったからかもしれない。
ジェイニーは鼻で笑った。「聞いてないけれど、特に信仰心はないんだろうと思う」
前にもいったように、私たちの両親は信仰深い、厳粛な長老派信者で、子どもたちも同じ信仰のもと育てられた。リチャードの家族も同じく長老派で、一緒に教会での集会に出かけられるのはいいことだった。ジェイニーがもう一歩、私たち家族から離れていってしまうのを感じた。「自分の教会はどうするの?」 「なんでもいいじゃない? 宗教は私にとってつまらないものだから。なくても生きていける。たぶん一番流行している教会に行くんじゃないかな。重要な人にそこで会えるし、一番いい服を着ていけるとしたらそれでいい」
私は首を振って言った。「教会に関しては厳しくしつけられたのに」
「それでうんざりしてたのよ。田舎の教会、地味な服を着た女の人、格好悪いドレスと頭に被るボンネット、ジョン・ランキンみたいな田舎の牧師。旧約聖書の預言者並みに陰気臭くて、灰みたいに乾ききってるじゃない。せいせいする」
たしかにジェイニーのこれまでの人生が、彼女にまったく合っていなかったのは間違いない。ジェイニーが集会をくだらないと思っているのは知っていたし、儀式のあいだじゅう静かに座っていることもなかったけれど、教会に行かないでせいせいする、なんてことをこれまで口にしたことはなかった。「そんなことを言わないで」私は震えながら言った。「何か悪いことが起こるかもしれない」 ジェイニーは笑った。「どうかな」
それは私には絶対にできないことだった。神に罰を与えられると考えると、とても恐ろしかった。
第2章訳註
(1) フレームハウス(frame house)
木造軸組の家屋。木材で柱や梁といった主要構造部を組み、壁を鎧板などで張る構造。アメリカでは開拓時代より、ログハウスと並んで主流な家屋の建築方法。
(2) 古い砦(Logan’s Fort)
1775年にベンジャミン・ローガンとジョン・フロイド(John Floyd, 1750–1783)によって造られた砦。要塞は150フィート×90フィートの柵のようなつくりで、先住民の攻撃に対して造られた。のちのリンカーン郡の都市であるスタンフォードの起源。
(3) ベンジャミン・ローガン(Benjamin Logan、1742-1802)
アメリカの開拓者、軍人、政治家。アメリカ独立戦争ではケンタッキーの市民軍で指揮をとり、イギリスと手を組んだ原住民の軍を撃退した。
(4) ムスリン(muslin)
欧米において、白く柔らかい平織の綿織物のこと。もともとは西洋では木綿や羊毛を平織にした織物のことを指し、織物が盛んであったメソポタミアのモスールに由来するとされる。アメリカでは、18世紀末から19世紀初頭にかけて田園風のスタイルとしてムスリン製のドレスが流行した。
(5) ルイヴィル(Louisville)
アメリカ合衆国のケンタッキー州の都市。同州最大の都市であり、また同州内ジェファーソン郡の中心地でもある。
(6) ジョン・ランキン(John Rankin、1793-1886)
アメリカ長老派の牧師、教育者、廃止論者。テネシー州に生まれるが、同地では奴隷制への反対意見が受容されなかったために北方のリプリーへと移動、奴隷制度に反対し続けた。
(7) ブラック・ベティー (Black Betty)
ウィスキー酒のことで、結婚式での景品になることは習慣であった。
(8) 暖炉掃除用のターキーウィング(turkey wing)
鳥(七面鳥)の羽のような形をしたほうき。暖炉の煤を効率よく掃き出すためという他に、デコレーションとしての意匠性を持たせ、米国国会のシンボルとして七面鳥を推進するためにこの形になった。
(9) フェイエット郡 (Fayette County)
ケンタッキー州の中央に位置する郡。1780年に設立された際にはヴァージニア州の一部であり、ケンタッキー郡を三つに分けたうちの一つである。1792年にはケンタッキーが15番目の州として分離し、その際よりケンタッキー州にフェイエット郡は位置する。
(10) フィラデルフィア(Philadelphia)
アメリカ合衆国、ペンシルベニア州の最大都市。大西洋に開くデラウェア湾口から約150キロメートル上流の、デラウェア川とシュイルキル川の合流点に発達し、ニューヨーク、ボストンなどとともに合衆国の発展を担った歴史の古い港湾・工業都市である。
(11) グレート・リバイバル運動 (a great revival)
18世紀のアメリカやイギリスに始まった強い信仰覚醒を目的としたキリスト教の宗教活動のこと。教会生活と信仰が形式化してしまったときや、信徒たちが信仰から離れ世俗化して生きているようなときに、その不信仰と罪を糾弾し、信仰に再び立ちかえらせる伝道を指す。信仰の活性化がみられると、神がリバイバル (信仰復興) を行ったとみなされ、キリスト再臨が近いことのしるしとして信じられている。 アメリカのニューイングランドで1740年代にリバイバルが行われると、その後意識的に各地にて集会が開かれ、大覚醒 (The Great Awakening) とも呼ばれるようになった。