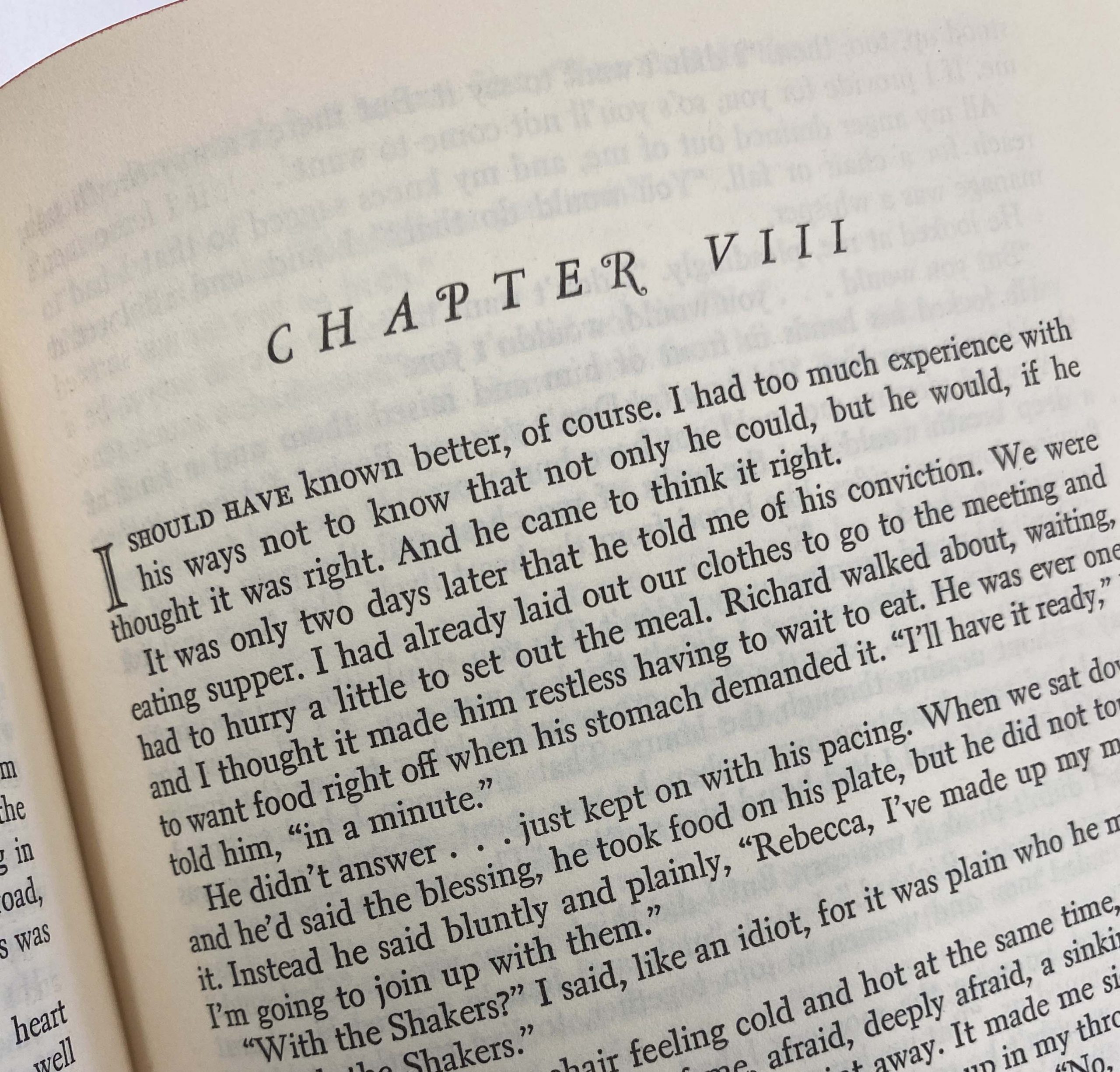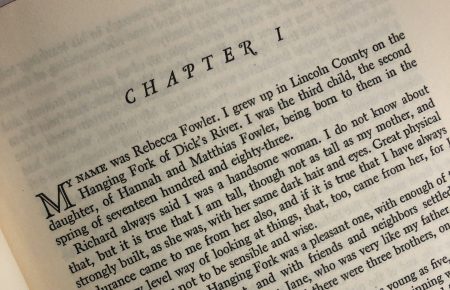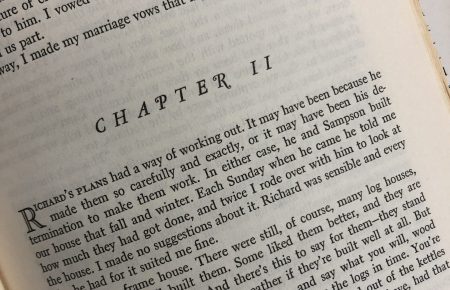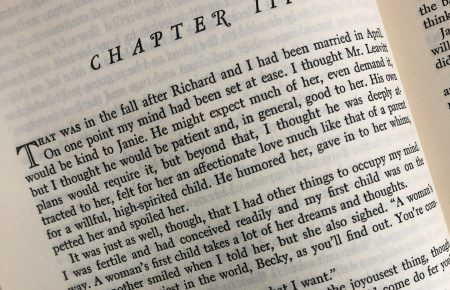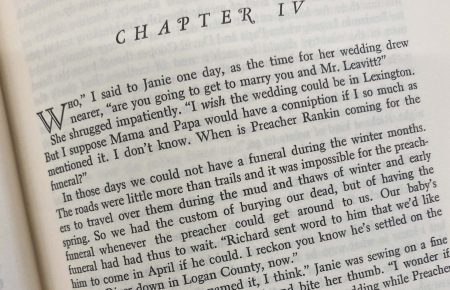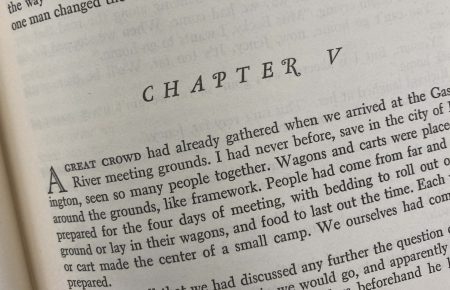もちろん、それは間違っていた。リチャードには、正しいと思うことを行動に移す意志だけでなく、絶対にやり遂げる力がある、そのことを私はよく知っていたはずだった。リチャードは、それを正しいことだと考えるようになった。
リチャードが自分が確信したことを伝えてきたのは、その二日後のことだった。私たちは夕食をとっていた。私は集会に行くための服を準備していて、夕食の準備は遅れていた。リチャードは食事を待ちながら、うろうろと歩き回り、いらいらしているようだった。彼はお腹がすいた時にすぐに食べたい人だった。「もうすぐできる」私は言った。
リチャードは返事をせず、まだうろうろしていた。席について、お祈りを口にしたあと、彼は自分の皿に食事をとりわけたが、手をつけようとしなかった。代わりに、単刀直入にこう言った。「レベッカ、僕は心を決めた。彼らに加わるつもりだ」
「シェーカーに?」誰のことを言っているのかは明らかだったが、私は知らないふりをしてそう言った。
「シェーカーに」
私は寒さと暑さが一緒に来たように感じがして、椅子にもたれかかった。奇妙な震えが身体の中で湧き起こり、とても恐ろしさを感じた。気を失いそうなほど気持ちが沈んでいった。
さっき口にした食べ物が、のどをせり上がってくるような感覚がした。「だめ」口の乾きと吐き気を抑え、私はなんとかそう口にした。「だめよ、リチャード」
「決めたんだ」リチャードはコーンブレッドを一かけちぎってバターをつけると、それをじっと見つめ、指でこなごなにした。
リチャードの指のあいだで崩れていくパンを眺めながら、それが私たちへの仕打ちかのように感じた。私たち家族をこなごなにくだいてしまうつもりなのだろうか。突然、私は怒りにとらわれた。机のふちをつかみ、悪寒が走ったように身体を震わせながら立ち上がった。「だめよ!」私は叫んだ。それは声というより引き裂かれた叫びのようだった。私は、今までこんなふうにリチャードに向かって声をあげたことはなかった。しかし、今は彼のやっていることに我慢できなかった。「そんなこと絶対にだめ!」テーブルを拳で叩き、皿をガチャガチャいわせながら、私は叫んだ。「あの人たちは、私なしであなただけを迎えることはしないわ。夫だけを連れていったり、妻だけを連れていくなんてことはしないの。私はそう言っているのを聞いたのよ! 私は絶対一緒に行ったりしない! 聞いてるリチャード? 私は絶対にしない!」
リチャードは両手で顔をおおった。顔が青ざめているのが見えた。彼の手も震えていた。リチャードの口が動いたけれど、言葉は何も出てこなかった。憎しみに近い気持ちを持って、私は立ち尽くしたまま彼を見つめていた。ついに、リチャードが手をおろした。
「こんなことを言いたくない」そう言って、立ち上がった。
「こんなことは言いたくなかったんだ。だけど、受け入れてもらう方法はあるんだ。もし、僕が君を養えば、君がお金に困ることはないだろ……もし、別れたとしても」
怒りさえ空っぽになり、膝ががくりと折れ、椅子につかまらなければ床に崩れ落ちてしまいそうになった。
「そうするつもりなの?」私は囁くような声をなんとか絞り出した。
リチャードはすがるような目で私を見た。「そうしたくない」
「だけど……そうするつもりなのね?」
手を組んで少し持ち上げ、リチャードは身体を震わせた。 「そうしなきゃならないんだ! わからないのかい、ベッキー? しなきゃならない!」
剣で刺し貫かれるよりも強く胸が痛んだ。息を深く吸うと胸が引き裂かれ、まるで心臓そのものから血が吹き出すように、痛みが体を流れ落ちていった。熱い涙が流れた。 「リチャード……?」
「やめてくれ」リチャードはそう言って背を向けた。「やめてくれよ。僕にとって簡単なことだと思ってるのかい?」
そんなことはない。実際、簡単なことだとは思っていなかった。私はリチャードがベッドから起きて、歩き回り、真実を知った苦しみにうめき、何時間も休みなく祈りを捧げるのを見てきた。私が誘惑したあの午後、リチャードが顔をそむけながら、ひどく疲弊した真っ青な顔で、私と、そして自分自身に腹をたてていたのを知っていた。こうつぶやくのが聞こえた。「(1)あなたが私に与えたあの女が……」
簡単なことだとは思っていなかった。しかし、間違ったことだとは、はっきりとわかっていた。「神があるべき姿を創られたのよ、リチャード」私は訴えた。「男と女を創られた。神は男女が一緒になり、共に住み、子どもをもうけるように……」
そう言って私は黙った。今の言葉が、他ならぬ私自身が、自分たちを糾弾してしまったのだと気づいた。 「僕らには子どもがいない」リチャードは言った。「まさにそこなんだ。子どもがいたら、あるいはもつことがあったら……行為を正しいと考えるのは難しくないだろう。だけれど、明らかじゃないか。聖書は『季節に子どもを繁殖するために』と言っている。僕たちには季節はないだろ、ベッキー。僕たちにとってそれは色欲で、罪なんだ」
私はそこで、もうリチャードを揺るがすものは何もないと知ったのだった。
そして、ジェイニーが手紙を送ってきた。「どうしてそんなことしたの? どうしてリチャードに反対しなかったの?」
私の両親も送ってきた。「なぜ?」
リチャードの家族も送ってきた。「なぜ? どんな理屈なの?」
ただ一つの理屈、それはリチャードの行くところに私も行かなければいけないということだ。他に何ができただろうか? ビリーバーズが唯一の究極の真実を知っている、それがリチャードの確信していることだった。それを確信し、私を捨てることも厭わないようになった。二人のあいだを、何ものにも引き裂かせてはいけない、それが私の確信していることだった。離れて住むことになるかもしれない、それでも同じ場所にいることはできる。リチャードに会い、見守ることのできる場所に。
ある晩、集会が始まる前に、私たちはブラザー・ランキンと他の二人と共に、リチャード・マクネマーに罪の告白をした。他の人は喜びながら罪の告白をしたようだった。
一方、私は悲しみと痛みに沈んでいた。告白すべき罪は少なくても、ブラザー・マクネマーは私が悲しむ様子を見て、その悲痛を感じとっていた。優しくとも、厳格にこう言った。「あなたは進んで告白をしなければなりません、シスター・レベッカ」
「進んでやっています」
「誰のためにですか? リチャード? それともあなた自身?」
「私たち二人のためです」
「でも、信じてはいないのですね?」
これは告白だから、嘘はつけない。「はい」
短い沈黙のあと、ブラザー・マクネマーの声がはっきりと聞こえた。
「準会員(パーシャルメンバーシップ)に入ることを認めましょう、シスター・レベッカ。信じる努力をするのなら、ですが。どうですか?」
私はリチャードが行くところに行くのだ。
「やってみます」と答えた。選択肢はないに等しい。
ブラザー・マクネマーが微笑んだ。
「十分です。我々はあなたたちを(2)チャーチ・オーダーに迎えることはできません。しかし、(3)ノヴィシエイトになることができます。あなたの努力が実を結んだ時、チャーチ・ファミリーに入ることができます。信じています」
どういう意味なのか、使われた用語の意味がわからなかった。リチャードは、この制限に不満を抱くかもしれないと思った。しかし、違っていた。むしろ、リチャードは私に満足しているらしかった。「その時は来るよ。僕たちもすぐに信者になれる」
私たちはその晩、初めて儀式に参加した。私たちが信仰告白をし、受け入れられたことは周知のこととなった。私は、人目が気になって落ち着かなかった。しかし、リチャードとブラザー・ランキンは、まるでそれが以前からの習慣のように、ゆっくりとしたすり足のステップと(4)シェーキングに参加していた。大きな喜びと涙と歌があった。ブラザー・ランキンは異言の(5)ギフトを受け、それをうたい、語りかけた。
私には何の喜びも訪れなかったが、少なくとも多少の平穏は得られた。私と同じ決断をした妻たちや夫たちはたくさんいた。平穏や、最終的に喜びさえ得られた人もいたが、何も得られなかった人もいた。パルミラはそのうちの一人だった。とはいえ、パルミラにとっては、平穏もシェーカーたちにとっての喜びも、求めているものではなかった。入信しなければ、トーマスに捨てられたから、パルミラはそうしたのだった。トーマスにはパルミラに与えるほどの財産はなく、五人もの子どもを抱える彼女に選択肢はなかった。パルミラはうんざりして言った。
「子どもたちのためじゃなかったら、あの老いぼれの馬鹿を勝手にさせたのに。でもトーマスが財産をくれたとしても、母親だけだったらきっと子どもたちは苦労するでしょう。この方法なら飢えないし、安心だから」パルミラは笑った。
「彼に煩わされるよりはまし、ってことだけは言える。せいせいした。あの人たちとくっついて暮らすのは嫌ね。どういうふうにやっていくつもりなのかしら、ベッキー?」
三人の宣教者はひと月滞在し、全部で二十三人が改宗した。宣教師たちが出立する前の最後の晩、私たちは呼び集められて指示が与えられた。私は、明らかに聴く意志のなかったパルミラに内容をできる限り説明した。「私たちは、今と同じようにそれぞれの家で、家族一緒に住み続けることになる。だけど男性は共同体のために働かなくてはいけなくて、収穫を売った利益や、作ったものはすべて共有の財産になる。ブラザー・ランキンが当面私たちのリーダーとなって、ユニオン・ビレッジからは説教と管理のためにときどき誰かが来るらしい。準備が整えば、私たち、それぞれの家族は配属される」
「それが一番わからないのよね」パルミラは言った。
私は彼女の言っていることを嫌というほど理解していた。それが起きること、そして私たちが配属されるということは、私たち家族の崩壊を意味していた。私たちは家を捨て、コミュニティを作り、そしてシェーカーファミリーとして共にそこで暮らすようになるのだ。
コミュニティは、ここギャスパー・リバーのほとりに作られるだろう。ブラザー・ランキンはすでに農場を譲渡していて、おそらく彼の家がコミュニティの一部として使われることになる。夫と妻と子どもは家族ではなくなるのだった。シェーカー教は、信者を三つのファミリーに分類していた。リチャード、私、パルミラ、トーマスが入ったノヴィシエイトには、結婚していて、まだ財産も身も捧げていない夫婦たちが所属することになっている。
(6)ジュニア・オーダーには、未婚で、各々の事情によって完全なメンバーになれない人たちが所属する。そしてチャーチ・ファミリーには、自分たちもその所有物も完全に教会に属し、再びコミュニティの外に戻るつもりのない人々が所属する。ブラザー・ランキンはすぐに正会員になった。私たちの中にも、すぐに正会員になれたはずの人もいて、それを望んだ人もいた。リチャードを引き留めたのは私だった。リチャードは準備ができていた。しかし私は、できていなかった。
「黒人たちはどうなるの?」パルミラが尋ねてきた。
「私たちと一緒よ。配属の時までは、一緒に住むの。それまでは大した変化はないわ。そのあと、リチャードは黒人たちを解放するつもりみたい。出ていきたければそうできるように。もし残るとすれば、コミュニティに(7)ブラック・ファミリーを作るのに十分な数の黒人がいると、ブラザー・ランキンが言っていたわ」
「それって規則なの? 解放するっていうのは」
「いいえ。所有しておきたければそれもいい。もちろん、自分に仕えさせるのはだめで、コミュニティのために働かせることになる。配属のあとには、ビリーバーズが責任者になる」
「ふーん」パルミラが言った。
「たくさん財産を手に入れるために、いい計画を立てたもんね。土地をくれてやる必要はないけど、そうしなきゃ教会の中枢には入っていけない。財産を寄付しない人がうまくやっていけるとは思えないし。黒人を手放す必要はないけど、どっちにしろ同じこと。黒人を使うことはできない。奴ら頭が切れるのね」
多くの人はパルミラの意見に同意するだろう。しかし初めから私は違っていた。シェーカーたちが土地や財産をためこむことに関心があったとは思えなかった。自分たちが生活するのに必要なだけの土地と財産を手に入れようとしたのはたしかだ。それに、ショーニー・ランやギャスパー・リバー、オハイオ・ユニオンなどの村が、改宗者の土地提供によって始まったのも事実だ。けれども私は、シェーカーは信念を実践したいと望んでいるだけなのだということは信用していた。彼らは団結することによってのみ、世界から離れ、自分たちが最善と信じる、純粋で平和に満ちた生活ができると信じていたのだ。
富や権力を得ようという意図など、シェーカーたちにはみじんもなかった。土地を多く所有して経営をしようという意図も、決してなかった。私は当時も、そして今でもそう信じている。シェーカーたちは、コミュニティが必要とするものだけを手に入れることを望んでいた。たいていの場合、コミュニティの利益のためだけに、よい取引をしようとしていた。
それに、最終的に一体誰が土地や蓄えや建物を所有できたというのだろうか? シェーカーの中では、誰にも個人の所有は許されていなかった。コミュニティがすべてを所有するのだ。理事たちがコミュニティの代理だった。私は理事のつけていた厳格な出納帳を見たことがある。
シェーカーが欲深くて意地の汚い、血を吸うヒルのような集団だと思っていたのは、彼らに嫉妬した人間だ。シェーカーには、素晴らしい農場や家畜、丈夫な仕事場や家や工場があって、腕利きの取引人がいた。とはいえ、シェーカーには私もひどい思いをさせられていたのだから、パルミラに対してシェーカーの肩を持つのもおかしな話だ。それでも、自分の信じることを言わずにはいられない。パルミラは不思議そうに私のほうを見た。
「あんた、本当に影響されちゃったの?」
私は首を振った。
「だと思ったわ。でもリチャードのこととなるとおかしくなっちゃうから。私だったら、同じことをしたかはわからない」
そして、私はいつものセリフを言った。「他に何ができたかしら?」パルミラは肩をすくめ、笑いながら言った。
「何もできなかった。でもまだ若いんだから、別れたかもね。それで、新しい男を捕まえたかも」
「そうすればいいのに」私も笑いながら言った。
「五人のおちびちゃんたちと? 考えなかったわけじゃないけど」パルミラはいつもあけすけにしゃべっていたが、私は何とも思っていなかった。
「配属されたら、子どもはどうするつもりなのかしら」
私は、それをパルミラに伝えるのを恐れていた。私だったら、胸が張り裂けてしまっただろう。私がずっと沈黙したままだったので、パルミラは耐えきれずにもう一度尋ねた。仕方なく私は答えた。 「小さい子たちは(8)ナースリーに入って、他の子どもたちは(9)スクール・ファミリーに入るの。教師が世話をするのよ」
「自分の家族とは暮らさないの?」
「そうよ」
パルミラはしばらく考えていた。「でも会おうと思えば会えるはずよ」
「そうね」私は本当は知らなかった。誰もそのことを尋ねる人はいなかった。教団内の秩序づけに関しては、ブラザー・ランキンが話してくれたことしか知らなかった。
パルミラは最後にこう言った。
「まあ、子どもたちが私の目の届くところにいる限りは、あたしの手を離れるなら気が楽になるでしょうね。あの年頃の子どもたちはトラブルのかたまりだもの」
私はそんなふうに悩まされたいものだった。しかし、小さな子どもが一日中足元にまとわりついている母親たちは、愚痴を言うのだろう。
「子どもたちをきっちり教育して、シェーカーの道に導くためらしいわ」私は言った。
パルミラは両手を腰にあて、そり返って笑った。
「もし、あたしの子どもからシェーカーを育てることができるんなら歓迎するわ。成功するのか疑わしいけど。元気がよすぎるからね。あいつらをてこずらせることになるわ、見てなさい」
パルミラは薄情な人だったわけではない。貧困の中で厳しく育てられ、父親より年上の男と早くに結婚させられていた。トーマスは彼女を虐げたことこそないけれど、家族を養うのに役に立っていなかった。彼女にとっては今まで住んだどこよりも、ここが快適だったのかもしれない。ブラザー・ランキンは信者を生活に困らせなかったし、みんなが手を貸してくれた。トーマスがシェーカーに入信したのは、一番楽な道だと思ったからなのだろう。
彼は、コミュニティに自分の家族を養ってもらうつもりだったのだ。
それに、仕事をしなければいけないにしても、そんなに厳しいとは思っていなかったのかもしれない。ともかく、パルミラはそう言っていた 。「あいつは、怠けて他人に働いてもらった上で、当然のように取り分をもらおうとしてるのよね」。パルミラは、もうトーマスに何も期待していなかった。
見た目には同じでも、私たちの生活は大きく変わっていった。改宗者のほとんどはブラザー・ランキンの信者たちだったので、仕事、農作物の集積、各家庭への分け前の分配、集会の開催や私たちの監督はスムーズに進んだ。
私は、新しいやり方のもとで、分け前が増える人と、減る人がそれぞれいることを考えずにはいられなかった。例えば、トーマスとパルミラは家族が多いので、その分以前の収入より多くもらっていた。当然の分け前だったので、そのことでパルミラを妬んだことはない。
若い夫婦にロバート・ジュエットとその妻アニーがいた。ロバートは賢く有能な男で、二人はとても幸先のよい暮らしを始めたところだった。ロバートの作物はよく育っていた。
それはすべて共用の納屋に入れられ、二人の分け前は以前の収入よりも少なくなったようだった。アニーは長々と不満を言っていた。アニーはきれいな服が好きで、ロバートの収入で何を買うか、ひとり計画を立てていたらしかった。しかし、アニーのそんな計画は取り上げられてしまったのだ。
ヘンリー・エイキンズという人物は、トーマス・ベネットと同じくらい怠け者で役立たずだったが、若く、子どもをたくさん連れていた。ヘンリーと妻のレイシーはいい思いをしていた。子どもたちはこれまでになくたらふく食べていた。
ウィリアム・スティールは素敵な人で、立派な財産を持つ経営者だった。妻のアマンダは入信することにずっと抵抗していたが、結局は私と同じように降参したのだった。そのことを苦々しく思っていて、いまだに配属の時までにはウィリアムを説き伏せられると思っているのだった。それは、リチャードを説得するのと同じくらい無理な話だと思っていた。
彼ら二人は、生まれた子ども五人のうち四人を失っていた。それで、残された男の子を目に入れても痛くないほど可愛がっていた。その子を溺愛し、甘やかしていた。私でも同じことをしたと思う。
デイヴィッドとナンシー・ブラウンは善良で素敵な人だった。二人とも敬虔で、正会員になる準備もできていた。ためらいなく、彼らは自分たちのすべての所有物を教会に譲渡した。
十五歳ほどになる二人の息子ルシアンは、財産を失ったことをどう思っていたのだろうか。
ルシアンはハンサムで背が高く、まっすぐで、愛嬌のいい男の子だった。両親の財産を受け取るのにふさわしかったことだろう。私は、両親がしたことはひどいことだと思った。けれども、私には関係のないことだ。
ブラザー・ランキンは、コミュニティを運営するのにデイヴィッドやナンシー、リチャードやウィリアム・スティールに頼っていた。みな十分な財産を持っていて、利益をあげる方法を知っていたからだ。ブラザー・ランキンは頻繁に助言を求め、長い時間を共に過ごした。指導権の一部も譲られたようだった。
私たちが集会を開くと、噂を聞きつけて外の人々が見に訪れたりした。追い払われる人はいなかったが、私たちのほうを指差し笑っていた。儀式を邪魔しようとしたり、真似をしたりしてからかっていた。ブラザー・ランキンは、いつも信者に向けて、そして外部に向けて、二回の説教を行った。何人かの改宗者が出てきたが、決して多くはなかった。そして我が家は、私にとって落ち着かない場所になってしまった。リチャードは予備の寝室に移った。
私が二度と誘惑したりしないと決意していたとはいえ、最善の策をとったのだった。私もそれは理解していた。誘惑していると思われるのが怖くて、リチャードに触れることさえないように気をつけた。とはいえ、いつもの癖でリチャードのほうに手を伸ばし、その顔や肩の感触を思い出し、辛くなることがあった。リチャードの服に触れ、洗い、アイロンをかけることさえ、私にとっては拷問のようなものだった。たびたび、一人の時にはリチャードのシャツに顔をうずめては、彼に触れ、隣に寄り添っているかのような感覚に浸っていた。
宣教師たちによると、完全な禁欲が実行されるのは配属のあとだそうだ。しかし、リチャードにとっては関係なかった。リチャードには確信があって、それを達成するのだと決めていた。
それは辛いことだった。リチャードにとってさえ大変なことのようだった。自然とやってきた長年の癖をなくすのだから。何度も、彼の手が私のほうに伸ばされるのを見た。何度も、こちらに向けられた、焦がれるような視線に気づいた。けれども、リチャードはいつもなんとか自分を抑えて、ぶっきらぼうに顔をそむけると、大股に家から、私の視界から出ていくのだった。私はほとんど毎晩、広くさびしいベッドで憂鬱でみじめな気持ちになり、枕を濡らすまで泣いた。
リチャードはほとんど毎晩、夕食のあとブラザー・ランキンのもとへ出かけていっては、私が寝てしまうことを期待して遅くに帰ってきた。私が先に寝たことは一度もなかった。
いつもリチャードが帰ってくる音を聞いては、決意が鈍って、また私のベッドに戻ってきてくれることを願っていた。しかしそれは、木にすがって魚を求めるようなものだった。リチャードは禁欲を続け、続けるほど禁欲は容易になっていくのだった。
他の夫婦は関係を変えずにいたことは、すぐにわかった。例えばパルミラは、初めの年に妊娠した。「さっさと配属してくれないかしら! 配属されたら禁欲しなくちゃいけないことが、余計にトーマスを駆り立てるんだね!」パルミラは言った。
私は笑わずにはいられなかった。トーマスの思いそうなことだと思った。
「まあいいわ」パルミラも笑いながら続けた。「配属が済んだ時、奴らが世話しなくちゃいけないのが一人増えただけだしね。あたしが心配することじゃないわ」
パルミラにとって、妊娠は簡単なことだった。子どもたちはいつもふくよかで健康的で、エネルギーに満ちあふれていた。私は羨ましかった。いまや、私は二人の子どもを失ったことより、もう二度と子どもを授かれないことを悲しんでいた。これまでは、完全に希望を捨てたわけではなかった。しかし今は諦めなければならない。私は、二度と自分の子どもが持てないことを受け入れなくてはいけないのだ。
ブラザー・ベンジャミンが指導者として送り込まれてきたのは、それから一年半後のことだった。ブラザー・ランキンはうまくやっていたけれど、すべてのシェーカー・ヴィレッジは、東部から送られてくる管理者が統制することになっている。オハイオのユニオン・ビレッジにいる(10)デイヴィッド・ダロウという人が西部の長だった。デイヴィッド・ダロウは、マザー・コロニーであるニューヨーク州のニューレバノンから来た人だった。彼と一緒に何人かがサポートのために派遣され、ブラザー・ベンジャミンはそのうちの一人だった。
ブラザー・ベンジャミンは小柄な人で、私たちのところにやってきた時はまだ若く、三十歳をやっと過ぎたばかりだった。フルネームをベンジャミン・セス・ヤングスといい、小柄でも、それを補ってあまりある気迫や意志の強さ、利口さを持っていた。ブラザー・ベンジャミンは、竜巻のような勢いで物事を成し遂げていった。彼が来たのは一八〇九年の五月のことだった。配属の時が来ていないにもかかわらず、私たちは彼のもとで驚くほど団結していた。
ブラザー・ベンジャミンはブラザー・ランキンの家に住んでいたが、最初の年は布教のためにインディアナやオハイオ、その他にも様々な場所へ出かけていった。常にどこかに向かっていて、いつでも説教や勧誘をする準備ができていた。誰よりシェーカーについて知っていたと確信を持って言える。私たちが、マザー・アンの証言と呼んでいる(11)『キリスト第二の降臨の証言』を書いたのは、他ならぬブラザー・ベンジャミンなのだ。その本から引用してくることがよくあった。
私たちの集会は、活発で喜びに満ち、はつらつとしていて、改宗者は増えていった。
ブラザー・ベンジャミンは実用的な面でも有能で、配属の時に備え、建物の建設を始めた。
男たちはとても熱心に働き、春、夏のあいだじゅう、建設に取り組んでいた。ミーティングハウスは木造で、白く塗装された。次に、たくさんいた子どもたちのために、スクールハウスが建てられた。より大きい納屋が最初に建てられたのは、ミーティングハウスだった。より便利な場所に造られ、さらに土地が買い上げられていった。「自立できるまでは、配属を迎えることはできないのです」ブラザー・ベンジャミンは言った。「少なくとも千エーカーの土地と、それぞれのファミリーのために家が必要です」
ブラザー・ランキンの家も、そのために使われた。隣にあったマコーム家の建物も同じだった。黒人たちのための小屋が建てられ、スクール・ファミリーの家に転用できそうな大きい納屋もあった。しかし、チャーチ・ファミリーのためには、新しい家を建てなければならなかった。
壁が立ち上がり、間取りがわかった時、どんなに奇妙に見えたか、私はよく覚えている。その家にはドアが二つあった。一つは男性用、もう一つは女性用だった。大きな中央ホールがあり、そこには階段が二つあった。一つは男性用、もう一つは女性用として。上の階には廊下の両側に私室が並んでいた。一方は男性用、もう一方は女性用として。
三階には、ファミリーが儀式や礼拝を行うための大きな集会室があった。シェーカーは、日曜日と特別な日にミーティングハウスに集まって、全員で礼拝をした。その他に、毎日の礼拝は各ファミリーがそれぞれの建物の中で行っていた。
「他の家もこんなふうに区切られるの?」私はリチャードに尋ねた。
「シェーカーの家は全部こうなんだ」リチャードは教えてくれた。
「もちろん新しい家が建つまでは、うまくやりくりしなくちゃならない。だけど、そのうち全部のファミリーが同じような家を持つことになる」
ミーティングハウスを使うことは、私の心の準備になった。ドアの他に杭の囲いの門さえ二つあった。一つは男性用、一つは女性用だった。中では、男女は部屋の両側に分かれて座った。シェーカーは、人間の本性をまったく信用していないとしか考えられなかった。
男女を分けておくために、ありとあらゆることに注意を巡らせていた。シェーカーを非難するつもりはないし、正会員になる準備ができるまでは分離が大切なのはわかっていた。それでも、チャーチ・ファミリーのことはもう少し信用してもいいのではないだろうかと思った。私はリチャードにそのことを話した。リチャードは首を振った。
「信用していなのとは違う。ただ、分離を信じているんだ」
それはとても馬鹿馬鹿しく聞こえた。そして、私は思ったより辛辣な言葉を吐いてしまった。 「それなら、どうして単純にそれぞれ別の村を作らないの? どうして男女を一緒にしておくの? どうして男の村と女の村とじゃなくて、二つのドア、二つの階段、二つの入り口を作るの? もっとうまくやればよくないかしら!」
リチャードは驚いて私を見た。「なぜって、女の仕事と男の仕事があるからだ! 男が料理や掃除や子どもの面倒を見たり、家事をしたりできるかい?」
「そう」私は短く答えた。「何かしらの役に立てているって知られてよかった」 怒りが落ち着いて、私は続けた。「トラブルを望んでいるようなものよ、リチャード。別々のドア、別々の階段、別々の門では、自然な行動を妨げることなんてできないわ。ブラザー・ランキンやブラザー・ベンジャミン、それにあなたみたいな人なら、必要ですらないかもしれないけど。
それでも誘惑と闘っているような人からしたら、何もないのと一緒でしょう。誘惑を強めるだけよ。そういう人なら男用の階段を上っている時に、もう一つの階段のことを連想しない人はいないし、こっそりそっちを上ろうと考える人もいるかもしれない。それに、女性は分けられたドアを使う時はいつも、男性も同じようにもう片方のドアを通っていることを、全身で意識してしまうのよ。ちょうどタイミングが合うように見計らう人も出てくるかもしれない。リチャード、やり方はいくらでもある。見つける人もいるわ。分離なんてその人たちをそそのかすだけ」
リチャードは悲しげに私を見た。 「ああ、信仰の薄い者よ」聖句を引用してこう言った。
「たしかに、そうかもしれない。だけど当たり前の感覚だわ」
「いいかい、このシステムは東で何年も機能してきた」
「どう機能したっていうの? どれだけのルール違反があったのかしら?」
リチャードも知らなかった。もちろん、私の言葉が彼に勝っているわけでもなかった。
私は試みたこともなかったけれども、リチャードは自分の信じることを貫き、何ものもその意志を曲げることはできないのだ。しかし、この分離せずに分離するやり方は、とても非実用的に感じられた。パンさえないのにケーキをくれと頼むようなものだと思った。
そう思うのは、私の中の母に似た部分だったのだと思う。母はいつも物事の核心をついて欠点を指摘し、その不完全さを認めさせることのできる人だった。私も母のようにせずにはいられないたちで、私の常識はシェーカーのやり方はおかしいと言っていた。
私は、ずっと考えていた別のことを思い出し、今度はそのことを話し始めた。
「もし、結婚も出産も認めないっていうなら、どうやって続けるつもりなの? そのうち共同体は自壊する」
リチャードは答えを準備していた。「子どもを連れた改宗者はいるだろう」
私は思わず笑い出した。「子どもを持つには純粋すぎるシェーカーたちは、罪深き俗世に依存するっていうのね!」
リチャードは、厳しい目で私を見た。「レベッカ」リチャードはずいぶん前から、私をベッキーと呼ばなくなっていた。「まるで君は自分がシェーカーじゃないような口をきくじゃないか」
私はシェーカーではなかった。いくら信仰告白をしようと、信じる努力を約束しようと、私は決してシェーカーではなかった。私には無理だった。とことん考え抜くのが私のやり方で、疑問が湧いたら放っておくことはできなかった。シェーカーは、考えずにただ信じることを求めているように感じた。私は信じられず、考えずにはいられなかった。
一日の仕事が終わり、私たちは火のそばに座っていた。リチャードは疲れ果て、ブーツを脱いでいた。収穫期はほとんど終わっていたけれど、男性は一日中働き詰めだった。
その代わり、納屋はいっぱいになり、豊作なのには満足しているようだった。その時、私は編み物をしていた。穏やかな夜に、小さな炎が揺らいでいた。その炎で部屋は薄暗く照らされ、一本のろうそくの明かりだけがそこにあった。二人ともほとんど同時に、室内がとても明るくなったのに気づいた。リチャードはさっとあたりを見渡した。「どうしてこんなに明るくなったんだ?」
すぐに、外から光が差し込んでいるのがわかった。私は窓に駆け寄った。「あれは大納屋よ、リチャード! 燃えてるわ!」
リチャードはコートをひっつかみ、ブーツを履くのも忘れて靴下のまま外へ飛び出した。私はさっとショールを身につけると、そのあとを追いかけた。外に出ると、空に向かって火柱があがり、私たちのいる場所からでも火がパチパチと音をたてているのが聞こえた。燃えていたのは、ブラザー・ランキンのところにあった一番大きく新しい納屋だった。私たちは道を駆け下りて、他の人と合流した。先に火のもとに辿り着いた男性たちの怒鳴り声が聞こえてきた。
リチャードは真っ先に走っていった。彼は野うさぎのように駆けていった。私はパルミラとトーマスと合流した。トーマスはぜいぜいと息をきらしていた。「あれは消しようがないな」トーマスはあえぎながら言った。「もう手遅れだろう」
私とパルミラはトーマスの先を駆けていき、人混みの最前列まで辿り着いた。炎を消そうとして駆けずり回っていた男たちは、黒く焼け焦げたように見えた。煙に咳込み、こぼれる涙で目を瞬かせていた。私たちが立っている場所でさえ、火柱の熱が届き、顔を焼くように感じられた。ブラザー・ランキンは近くに立ち尽くし、涙を流しながら手を固く握りしめていた。ブラザー・ベンジャミンもそばに立ち、興奮しつつも人々の混乱を落ち着かせようと努めていた。ついに、ブラザー・ベンジャミンは両手を上げ、大声を出した。「これは無駄です。手遅れです。諦めましょう。焼けるままにしましょう。怪我をしてほしくはありません」
たしかに、諦めるしかなさそうだった。小川には火を消すほどの水はなかったし、あったとしても水を汲んで運ぶのには人が足りていなかった。その言葉を聞いた男たちは、熱と煙からあとずさって人混みに加わった。ブラザー・ベンジャミンはがっくりと肩を落とし、ブラザー・ランキンに言った。「悪魔の仕業だ、ジョン。外の人が火をつけたんだ。一番大きくて、一番作物の入った納屋を選んだんだ。失えば最も痛手になるからね」
炎の下で、ブラザー・ベンジャミンが顔を上げ、腕を掲げ、高らかに祈るのが聞こえた。「ああ、主よ、あなたがマザー・アンの姿になってもなお、あなたのしもべは迫害を受けています。どうぞ彼らをお許しください。何も知らない人々です。そしてあなたのしもべたる我々に、迫害に耐える母なる強さをお与えください」
私たちにとって、初めての迫害されるという経験だった。
第8章訳註
(1)あなたが私に与えたあの女
創世記3:12で、知恵の実を食べたことについて神に責められた際のアダムの弁明。「アダムは答えた。『あなたがわたしと共にいるようにしてくださった女が、木から取って与えたので、食べました。』」(新共同訳)
(2)チャーチ・オーダー(Church Order)
シェーカー教の教義に完全に従うことを誓った信者たちのこと。チャーチ・オーダーの全員がチャーチ・ファミリーに所属していたわけではなく、ノヴィシエイト以外の各ファミリーで暮らしていた。チャーチ・オーダーに属するには、完全に俗世から身を切り離す契約を交わす必要があった。
(3)ノヴィシエイト(Novitiate)
シェーカー教徒としての生活を試す為に仮入信した成人のこと。仮入信の契約を交わすことで衣食住や医療など、シェーカー教徒としての特権を与えられた。しかし、「ブラザー」や「シスター」の称号を受け入れることや、全ての集会に出席すること、割り当てられた労働を行うことが義務付けられた。
(4)シェーキング(the shaking)
シェーカー教は礼拝の際に、身を震わせて信仰を示した。
原著で”the shaking”と表される、礼拝の際に身を震わせる様子を本ページでは「シェーキング」と訳出する。
(5)ギフト(Gift)
ここでは、特にシェーカー教において用いられる”Gift”に関して。礼拝などの際に授かる神からの啓示のこと。これらは礼拝の中で、ギフトを授かった信者によって、歌やダンスのかたちでもたらされた。シェーカー教はこれらのギフトを記録に残し、礼拝における歌やダンスとして実践していった。
(6)ジュニア・オーダー(Junior Order)
何らかの理由でチャーチ・オーダーの契約を結んでいない人々。共同体ごとに意味が微妙に異なる曖昧な単語。19世紀中頃まではチャーチ・オーダーをシニア・オーダーと呼んだこ
とから、シニア・オーダーに属さない人々をジュニア・オーダーと呼んだ。小説内で説明されているような、完全に入信する準備ができていない未婚の信者を指す場合もある。
(7)ブラック・ファミリー(Black Family)
黒人の信者がいた記録はあるが、彼らのためだけのファミリーが形成されることは希であった。チャーチ・オーダーに属す黒人はごくわずかであったようで、ほとんどはノヴィシエイトの一部であった「バック・オーダー(Back Order)」に属していた。サウス・ユニオンでは、1815年には「ブラック・ファミリー」と呼ばれる黒人のためのファミリーが存在したが、住民を徐々に他のファミリーに移動させ、1822年の記録ではすでにこのファミリーの存在はなくなっている。
(8)ナースリー(Nursery)
『Historical Dictionary of the Shakers』に記載なし。「Nurse Shop」や「Infirmary」が同等の機能を担っていたと思われる。
(9)スクール・ファミリー(School Family)
「School Family」の存在が確認できる記録は見つからない。ジョセフ・ミーチャムが最初に設立した「チルドレンズ・オーダー(Children’s Order)」という組織が設けられていた場所はあり、子供用のチャーチ・オーダーとして扱われた。
(10)デイヴィッド・ダロウ(David Darrow)
デイヴィッド・ダロウ(David Darrow, 1750-1825)は1787年にニューレバノンの共同体が集結された際に、妻と4人の子供と入信し、後に初めての長老として任命された。また、中西部でシェーカー教徒たちをまとめる使命も与えられ、ケンタッキー州のプレザント・ヒルやサウス・ユニオンの形成にも貢献した。初期のシェーカー教は有力な家族の協力によって維持されており、ダロウ家もその一つ。
(11)『キリスト第二の降臨の証言』(The Testimony Christ’s Second Appearing)
シェーカー教の教義を記した書物。ベンジャミン・ヤングスを中心に、カルヴィン・グリーン、ジョン・ミーチャム、デイヴィッド・ダロウが共著した。