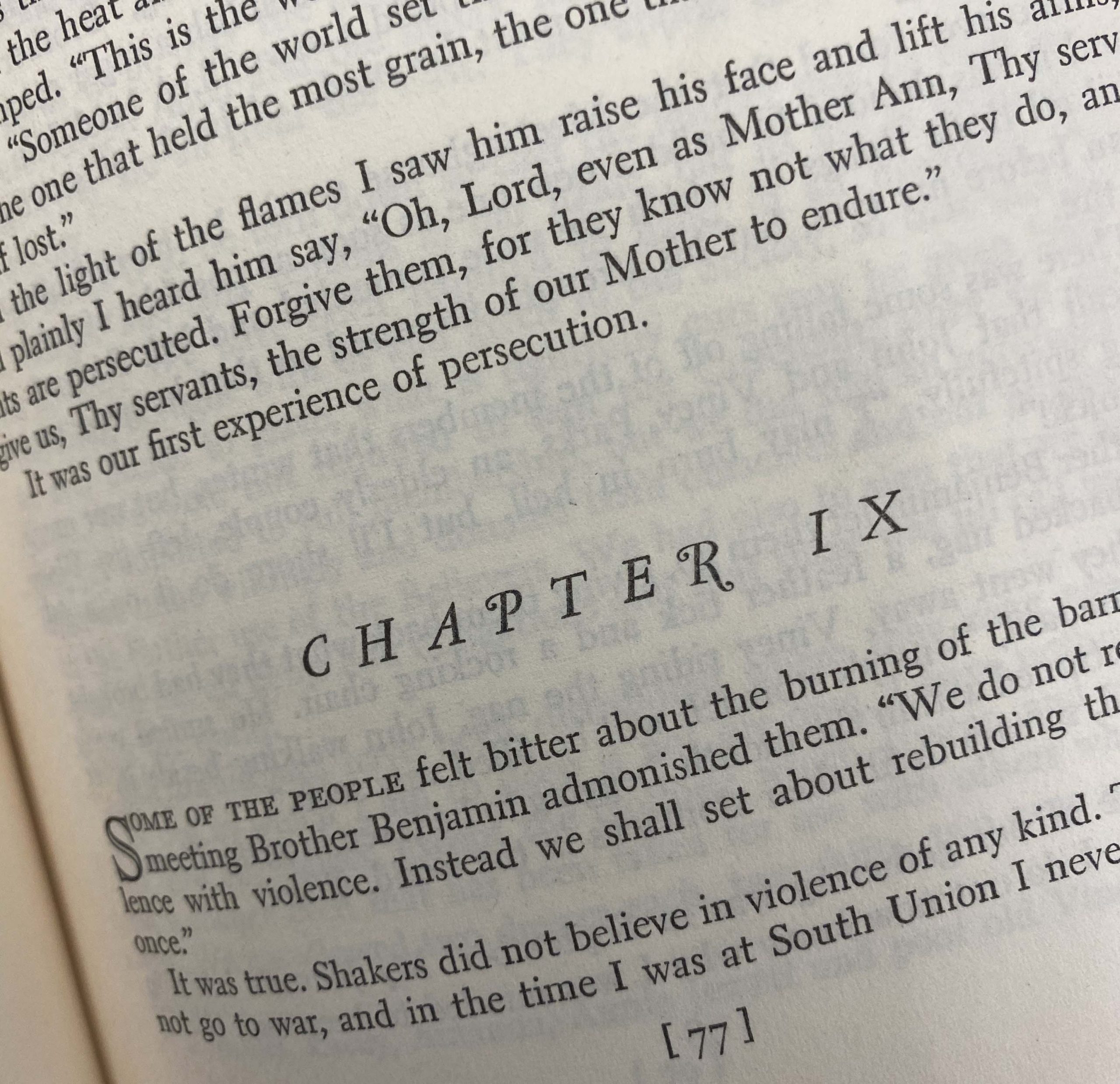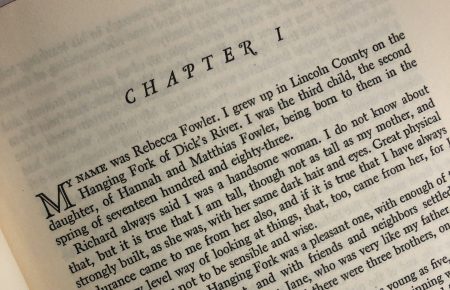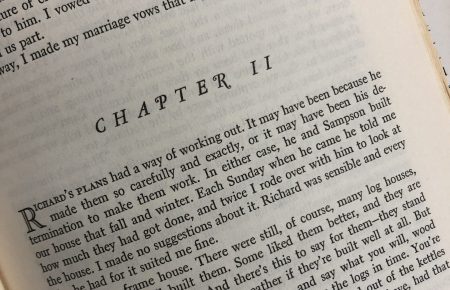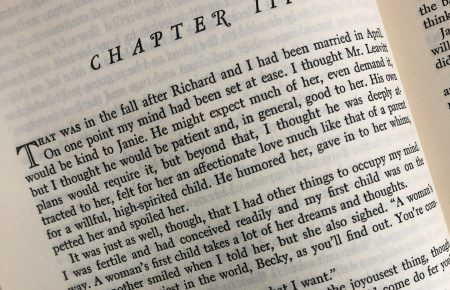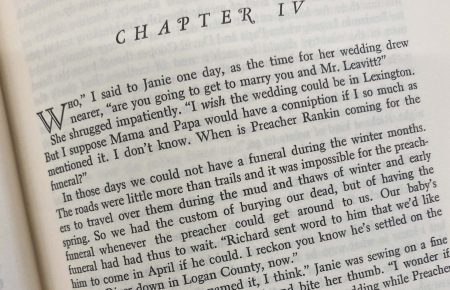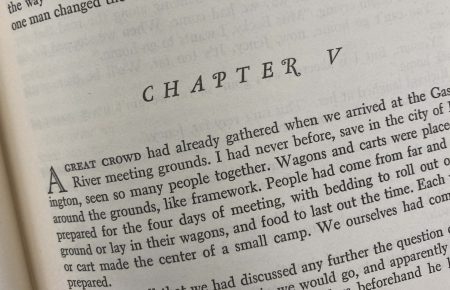畜舎が燃えたことを苦々しく思う人もいたが、ブラザー・ベンジャミンは、集会で彼らを穏やかに諭した。「私たちは、暴力に対して暴力では返さない。その代わりに、私たちはもう一度畜舎を建て直すだろう」。
それは事実だった。シェーカーはいかなる暴力も信じていなかった。彼らは戦争に行かなかったし、私が(1)サウス・ユニオンにいた時、私は教師が一番の問題児でさえ打ったことなど一度も聞いたことがなかった。リチャード・マクネマーは聞かせてくれた。(2)ハーバードから追い立てられた時、道を歩く彼らを打つ者がいたこと、そして仲間たちが肩を鞭打たれたことを。戦わないことは、シェーカーの穏やかで、優しく、愛すべき側面だった。
ともかく、私たちは疑いはしたが、納屋が故意に燃やされたとしても、それを証明する術はなかった。しかし、それは私たちをひどく傷つけた。彼らは最も被害の大きい選択をした。納屋はトウモロコシと小麦とオート麦でいっぱいだった。多大な穀物の損失によって、私たちはとても厳しい冬を過ごすこととなった。食べつなぐには、売るための家畜を殺さねばならなかった。それでもなお、とても貧しい時があった。ブラザー・ベンジャミンが徹底して子どもが飢えることがないように決めたため、子どものある人々はましに暮らせた。
やせて小柄なブラザー・ベンジャミンは、あまりに熱心に自制していたおかげで、風の中の一枚の羽のように見えた。けれども、その羽はしきりに私たちを励ますものだった。
「私たちは決して琴を柳の木に掛けてはいけないよ(悲運を嘆いてはいけないよ)」
たとえ世界がいくら私たちの生活を非難したとしても、その冬を耐えた私たちの勇気は称賛されるだろう。納屋は建て直された。チャーチ・ファミリーのための家を建てる仕事を始めることが決まった。そして私たちの小さな貯蓄にまわす代わりに、土地を買うことが決まった。肉が切れた時は、私たちはマッシュと牛乳を食べた。そして、それすらも十分ではない時でも、仕事は決しておろそかにせず、計画は変更されなかった。ブラザー・ベンジャミンは言った。「私たちが新しく買った土地の一部には、サトウカエデがある。一月にはサトウカエデの林を作れるだろう。そして小川に接して製材所を建てよう。次の建物は、頑丈で耐久力がある煉瓦造で建てなければならない。そのために、煉瓦窯は必ず建てなければならない」
私たちは火事のあと、集会所が燃えてしまうのを常に恐れていた。そしてなるべく早く新しい集会所を煉瓦で建てることが決まった。私たちはそれらすべてを専門家の助言と指導のもと行った。リチャードは私の目の前でやせていったが、いっさい疲れたように見えないほど、彼の体力は増していた。
その冬に、一員から離れるものもいたが、そう多くはなかった。シェーカーズを去ったジョンとヴィニー・パークスという年長の夫婦のことを、私は思い出す。ヴィニーは悪意に満ちて言った「地獄で焼かれても、お腹がいっぱいでいたほうがましだね!」
ブラザー・ベンジャミンは、彼らのもともとの持ち物を返し、背中を痛めた仔馬と、羽毛の布団とロッキングチェアを持たせ、彼らが去ることを許した。彼らが去る時、ブラザー・ベンジャミンは悲しそうに微笑んだ。ヴィニーは仔馬に乗り、ジョンはその隣を歩いていった。彼は言った。「ヴィニーのお腹がすぐにいっぱいになるかは疑問だよ」
彼らはひと月も経たないうちに帰ってきて、もう一度仲間になることを懇願した。彼らも、世の中でお腹を満たすことはそう簡単ではないと知ったのだった。
私たちが一つの家に集まるのは九月に決まっていた。私の日記もその月から始まっていた。どうして日記をつけようと思ったのか、今はよくわからない。それは悩む私の心を慰めるためのものだったかもしれない。あるいは、私が影響を受けたシェーカー教徒のあいだでは、日記をつけることが一般的だったからかもしれない。その理由は忘れてしまったが、今や大した問題ではなくなった。しかし、ここにその古びて茶色くなった日記はある。一八一一年九月十日から始まっている。そこにはこう書かれている。
「この日から、ついに私たちは配属されたのだ。リチャードと私は、ブラザー・ランキンの古い家に他の修練者と一緒に配属された。その家はチャーチ・ファミリー住居の東にあったので、私たちはもうイースト・ファミリーと呼ばれていた。
私たちの他に、この家にはパルミラとトーマス、ヘンリーとレイシー・エイキンズ、ロバートとアニー・ジュエット、ウィリアムとアマンダ・スティール、ジョンとヴィニー・パークスなどがいた。精神的な指導者は、ブラザー・サミュエル・イデスとシスター・スーザン・ロビンソンだった。一時的な指導者としてサミュエル・シャノンとプリシラ・スチュワートがいた。リチャードは男性の仕事を担当する補佐役に任命された。女性でその立場の人は誰もいなかった。シスター・プリシラその人が、女性の仕事を請け負うのだ。私たちにはまだその資格がないと、彼らは思っていたのだろう。私は最初の仕事として、洗濯担当に任命された。これはここでの務めの中で最も辛いものだった。私の不信仰の精神を鍛え直すものだったと思う。それは問題ではなかった。私は働くことができ、丈夫だった。そして、シスター・プリシラは、洗濯が私にとっていつも楽しみであることを知らなかった。
ジョセフ・アレンとそのシスターたち、モリー・グッドリッチとメルシー・ピケットが、ブラザー・ベンジャミンと一緒に村を管理するために送り出されてきた。彼らはみな、東部出身だった。彼らは敬虔で信頼できるように思えた。
私たちの家は、その挽材が村づくりで使えるかもしれないということで、取り壊されることになっていた。土地の名義は私たちに残ったが、使う権利はコミュニティに与えられた。自分たちが持ってきて、教会に寄付したものの目録を提出することを要求された。私たちがコミュニティを去ることを決めた時に、自分たちの所有物を返してもらえるようにである。私たちはまだ正会員になることを許されてはなかったので、契約書に署名することは要求されなかった。だが、自分の意思で来たこと、自分自身と所有物をビリーバーズのために寄付することに関する合意書に署名はした。私たちは同様に、借金と負債をすべて支払ったこと、世間からのなんの要求もされないことを約束し、署名しなければならなかった。
私たちの家具は必要なところに配られた。私の寝るベッドは私のものではなかった。
私が着ている衣服以外は、私はもはや何も所有していなかった。着替えでさえ服を十分に持っていない人に渡すために取り上げられた。私たちはそれぞれ、二着のドレス、二着のシャツ、二つの帽子、二つのボンネットを与えられた。
パルミラ、レイシー、アマンダ、アニー・ジュエットそして年寄りのヴィニー・パークスが、私と同じ部屋だった。二つの部屋のあいだの壁は、私たちが共有できるだけの広い寝室を作るために取り払われた。他にももう一つ、八人の女性のための広い寝室があった。ホールの向こう側には、同じような構成で男性の寝室があった。パルミラは自らの所有物を私の隣に置いた。私にとっては全部がすごく変わっているように感じられた。
私たちが自分たちの家を立ち去った日の感情を、どんな表現でも書くことはできない。
簡単に諦めることはできなかったが、できる限りの努力はした。けれど、新しい生活について何も知らないか、何も予想できない時、身近なものすべてから引き離されたらどんな気持ちになるか、その時が来るまで誰にもわからない。それは見捨てられた気分だった。夫と手を取り合っていても孤独であることさえあるのだ。その場合、少なくとも彼が隣に立っている快適さを感じることはできた。その快適さは失われ、リチャードが私のそばにいてくれることは二度とないことはたしかだった。私たちがどれほど長く生きようと、彼はもはや私の夫ではなかった。彼は、シェーカーの男性であった。私は彼のことを考えるべきではなかったし、私の道が彼の道と交わることもないのだ。
カッシー、サンプソン、ジェンシーは私たちと一緒に行った。リチャードは引っ越しの前夜に家に彼らを呼んだ。彼は彼らに渡すために奴隷解放の書類を作成していた。彼は私たちがこれからどうするかを説明した。
「僕たちと一緒に行く必要はないんだよ」と彼は伝えた。
「僕が渡した書類は君たちを解放する。君たちは望む場所に行けるし、もし一緒に来たければ来ることもできるよ」
頭の悪いサンプソンは、まるでその紙が向かってきて噛みつくかのように、その書類をにらんだ。
「リチャード様、我々はどこへ行きますか。我々だけでどこへ去りますか」
「行きたいところに行けばいいよ」
カッシーは彼女の書類を折りたたんだ。「私はどこに行くつもりもありません。ベッキー様に伴います。私は彼女のものであって、彼女の世話をするのです。それが私の望みなのです。サンプソン、あなたも同じ思いです」
リチャードはもはや私たちのために働くことはなく、彼らの仕事は村で割り当てられることになると説明した。「私にとっては違いはありません」カッシーは引きしまった表情で言った。「私はベッキー様の行く場所についていきます」
私が読み書きを教えようとして失敗したジェンシーは、彼女の奴隷解放書をじっくりと確かめ、知っている文字を見つけたら笑いだした。「これはびっくり」彼女はくすくす笑いながら言った。彼女はゆらゆらと暖炉明かりに向かい、最後には奴隷解放書は細く丸められ、彼女の編んだ髪に結びつけられた。「ジェンシー! すぐに髪につけた書類をとりなさい! そしてカッシーに渡しなさい」私は彼女に言った。
「これは私たちが持っていなければいけないのでしょうか」カッシーはまごつきながら尋ねた。「どこにとっておけばよいでしょうか」
リチャードは諦めた。「君たちのためにとっておこう。けれど、覚えておいてくれ。もし、君たちが去りたくなったら、書類のことを尋ねてくれればいいよ」
カッシーとサンプソンは安堵して、それを手放せたことにため息をつきながら書類を返した。ジェンシーはまだ持ったままだったけれど。「これは私のよ!」彼女は言った。
「それは君のだよ」リチャードは彼女に伝えた。「これは公式な書類だよ。将来これが本当に必要になる日が来るかもしれないよ」
「でも今欲しいの!」彼女はむっつりしながら言った。
「どうして?」
「だって可愛いんだもん……真っ白でパリっとしてて。好きなの」
「こちらに渡して」リチャードは言ったが、彼女は急に頭から書類をもぎ取ると、手の中にくしゃくしゃにしてくすくす笑いながら部屋から走って出ていった。カッシーは彼女のあとを追った。「一人にしてあげよう」リチャードは言った。「もし彼女がなくしたり、破ってしまったりしたら、もう一枚作れるから。
何日か彼女は頭から書類を生やし、いまや彼女の硬くて短い髪の中で粉々にちぎれていた。彼女はよく髪に手をやって書類をいじって、音がなるのを聞き、くすくすと笑っていた。
彼女はいまや、大きな胸に細いウエスト、細いお尻の大人の女性の身体になっていた。彼女がゆらゆらとしなやかに歩く姿は、私に風で曲がる花を連想させた。彼女は数年前からもう大人といってもよかった。彼女の成長はとても早かった。しかし精神的には幼少期を超えたことはなかった。しかもかなり早い時期の幼少期なのではないかと思うこともときどきあった。私は、彼女にはパルミラの六歳の子ども以上の知性は持ち併せていないのではと思った。これまで、彼女はカッシーのしっかりした手と私の用心深い目の下で育てられてきた。私はシスター・プリシラが彼女をカッシーの側においてくれるだけの気遣いがあればと願った。
その夜、ベッドへ向かった時、パルミラと私の気分はまったく違っていた。彼女は陽気だった。ついにトーマスと縁が切れて嬉しくて、彼女の手から子どもたちが離れることも嬉しかった。彼女は伸びをして、あくびをして、猫のように丸くなった。彼女は心地よく心安らかだった。「そんなに悪くはならないわよ。ベッキー」
私にはほとんど聞こえなかった。そこは変わった部屋だった。女性だけの存在、細長く硬いベッド、私とパルミラ、アニー・ジュエットが共有する簡素でまっすぐな箪笥に、私たちは自分の持ち物用の引き出しをそれぞれ持っていた。何といっても、ホールを挟んで男性部屋にリチャードがいるという事実は、私を悲しみで満たし、私は泣きたい思いだった。
私は必死で涙をこらえた。私がどんな気持ちでいるのかを他の人に悟られるなんて、私の自尊心が許さなかった。パルミラはろうそくが吹き消されたあと、穏やかに囁いた。「大丈夫? ベッキー」
「大丈夫よ」
「悲しいんじゃない?」
「少しはね」私は認めた。「でも大丈夫よ」
彼女は、温かく親切で愛らしい手を、私の手に重ねた。「ベッキー、私はリチャードではないわ。それでもあなたのすぐ近くにいられるわ」
私は彼女の手を握り、握りしめ続ける以外に返事をすることができなかった。パルミラは、赤ちゃんがいかに夜中にトラブルを起こすかについて囁き続けた。幼い子どもは、ナンシー・ブラウンが監督している黒人女性たちに面倒を見てもらうことになっていた。
ジェンシーもその黒人女性のところにいた。私はジェンシーがカッシーの側にいられるよう望んだが、シスター・プリシラはそうしなかった。ジェンシーは育児係になったのだ。カッシーは炊事場係だった。けれど、ジェンシーは子どもの世話は好きだったし、幸運にもカッシーと同じ場所で眠ることができた。
「カッシーとジェンシーが赤ちゃんの世話をするわ」私はパルミラに言った。「ジェンシーは赤ちゃんが大好きなの」
「あら、心配してないわ。たいてい彼女はよく眠るの。けれど夜に目が覚めて、また眠れるまでそっと揺すってあげるしかない時も何度かあるわ」
「ジェンシーが彼女を揺すってあげるわ」
「そうね」
パルミラは、一日に何回か子どもたちの面倒を見ることを許されていたが、他の時は別の人の世話に任せていた。パルミラの仕事は搾乳場だった。パルミラは一度に一頭以上の牛を所有したことはなかったから、そこでの仕事について何も知らなかった。もちろん、どうやって乳を搾ってチーズを作るのかは知っていたが、たくさんの量を扱ったことはなかった。容器やかめ、大桶の使い方も知らなかった。彼女は一度もチーズを作ったことがなかった。「よかったわ」パルミラは笑いながら静かに言った。私は暗闇でもパルミラの目が笑いで輝くのが見えた。「私を監督してくれる人がいてよかった。チーズは牛のお腹の中でできるものだとずっと思っていたんだもの」
「これから学べるわよ」私は彼女に言った。
「そうね」
その夜のファミリーの集会で、私たちに仕事が割り振られたのだった。それぞれの仕事は毎月変わること、そして、病気にならない限り、すべての種類の仕事をやることが求められていると告げられた。ベッドメーキングと部屋の掃除の仕事があった。炊事の仕事があったが、何人かの黒人が炊事場の整理を担当した。洗濯とアイロンがけの仕事もあった。女性はファミリーの男性の洗濯とアイロンがけも担当した。糸紡ぎと織物の仕事もあった。
当面、私たちは自分で持ってきた服を着なければならなかった。けれど、新しいものが作られたあとには、みんな同じような格好をすることになるはずだった。なぜならば、誰かが他の人より良いもの、高いものを持つことは許されなかったし、違った服装をしていることも許されなかったからだ。アニー・ジュエットという女性は可愛いものが好きで、集会で「色はみんな同じにするのでしょうか?」と聞いた。
シスター・プリシラは答えた。「いいえ。私たちの手で染められる色であれば、あなた自身で選んでいいわよ」
色の幅は想像以上に広かった。私たちは、どうやって染めるのか、明るく可愛らしい青色が作れるか、暗く深い赤色が作れるか、素敵な茶色、紫色、黄色、緑色が作れるか、すべて知っていた。私たちは何も買わなかった。けれど、私たちは自らの手で作ることができた。
店で売っている絹や綿、柄物の生地はなかった。それはつまり、アニーが心から好むような安っぽい派手さや、可愛さはないということだ。彼女はすねて、眉をひそめ、つぶやいた。「罪と同じくらい醜い服になるんでしょうね」
パルミラは彼女を小突いて囁いた。「アニー、赤色を選びなさいよ。それでシャツを脱げばいいわ。そしたら、あなたのお尻はよく見えるわ」
アニーはくすくす笑った。そして、シスター・プリシラは彼女を厳しい目つきで見つめた。
そのことを考えて私は微笑んだ。私たちが部屋に案内された時には、アニーはとても静かだった。彼女は素直に晩祷のためにベッドのそばにひざまずいた。けれど、彼女はすぐ誰にも言葉をかけず、ベッドカバーにもぐり込み、明かりに背を向けた。私たちのベッドは、壁の下部に長い列に並べてあり、ベッドの間にはわずかなすきましかなかった。私のベッドはその一番端にあり、パルミラのものが隣にあり、その次にアニー、アマンダ、レイシー、ヴィニーのベッドとなっていた。
誰かが囁いていた。私とパルミラも囁き合っていたが、私たちがやめたら、部屋はとても静かになった。私たちは晩祷のあとは話してはいけないことになっていた。けれど、最初の夜もシスター・プリシラがその場にいなければ誰も守ることのない規則だった。それは私たちにとってはまったく奇妙だった。普通の人間には、誰とも一言もしゃべらないなど無理なことだった。
静けさの中で、私は、すすり泣きを聞いた。鼻をすすり上げ詰まらせていた。アニーが、ずっとこらえていた悲しみに負けて泣きだしたのだ。パルミラはすぐに彼女のベッドのそばに行った。私もそれに続いた。彼女は、泣いているアニーの冷めきった手を握っていた。「家に帰れたら」彼女は声を詰まらせながら言った。「あぁ。家に帰れたなら。こんなシェーカーの家にいるくらいだったなら、地獄に落ちたほうがまし!」
「しーっ」パルミラは彼女を注意した。彼女の腕を持って前後に揺らして言った。「しーっ、静かに、アニー。シスター・プリシラがこの家にいるんだよ」
アニーはよりいっそう嘆き悲しむだけだった。「構わない。誰がいたって構わないわ。私はただ家に帰りたいだけなの。ロバートと私の赤ちゃんが恋しいの。一度だって私の赤ちゃんと離れて寝たことがないのよ。どうして子どもたちと一緒にいられないの?」
パルミラは軽く叩いて、彼女を揺すった。そして彼女の髪を撫でると、優しく話しかけた。「私にはわからない。もしかするとベッキーが話してくれるかもしれないけれど、それでもあなたにも私にも理解できないと思う。彼らはただ彼らの秩序を作ったの。そして私たちはそれに耐えるしかないと思う。私の子どもと同じであなたの子どもたちもきっと大丈夫よ。だからもう悲しまないで」
アニーは誰よりもホームシックになっていたのだろう。私たちの今の状況は、子どもが家ではないところで夜を過ごすようなものだった。彼女が子どもを愛しているのはたしかだった。けれど、私は、彼女が子どものことで不満を言っていること、子どもがとても煩わしい時には無視していたこと、泣きやんで静かにならない時はぶってさえいたことを知っていた。しかし、女性は自分の愛情を少しも損ねずに、同時に子どもからの煩わしさや苛立ちを感じてしまうのだと思う。今、私はアニーを哀れに思った。
それから、私のアニーへの哀れみは子どもや夫と離ればなれになった他の女性たちにも広がっていた。私は暗闇の中で、一体いく人もの人が泣いているのかと訝しんだ。私は、結婚したことのない人か、未亡人か、失うものが何もない人くらいしか、この配属を素晴らしいものとは感じないだろうと思った。というのも、これまでの世界での彼らの孤独は終わったのだから。そういった人たちの暮らしはたしかに豊かになるだろう。けれども、私たちは違った。大切なものが奪われたように感じられて、いくら永遠性を得られると言われ、それを信じようと努力しても、私たちの暮らしは貧しくなったように感じられた。
母親のようなパルミラの手によって、アニーは次第に落ち着いていった。
足音がホールに響き、私たちは罪を犯した子どもみたいにベッドへと急いだ。扉が開いた。そこにはシスター・プリシラが立っていた。彼女はろうそくを掲げつつ、厳しい眼差しで私たちを見ていた。「話し声がこちらから聞こえたように思いますが」
彼女は背が高くやせこけて、細い唇に灰色の目、灰色の髪、そして灰色の顔をしていた。
彼女は着ている服さえ灰色だった。彼女は、誰かをじっくりと見る時にかける、金属のふちの眼鏡を着けていた。その眼鏡は鼻の先っぽにいつも引っかかっていて、いつも指で位置を直しているのだった。
「はい。シスター」パルミラは答えた。
「アニーが腹痛を訴えていて。誰かを呼ぶべきかどうかをみんなで話し合っていました」彼女は明るく嘘をついた。
シスター・プリシラはアニーのベッドへ行くと、彼女の額に手をあてた。
「熱はありませんね」彼女は言った。
「はい。シスター。今は良くなりました」アニーは答えた。
「もしかすると薬を与えたほうがいいかもしれませんね」
「いいえ。おそらく私が食べたものが原因です。今は大丈夫ですから」
「他に具合の悪い者はいませんか?」シスター・プリシラは厳格な眼差しで私たちを見た。
アマンダがすぐに口を開いた。
「私もです。けれど、シスター・アニーほどひどい痛みではありませんでした」
「シスター・レベッカは?」
「はい、少しだけ」私も嘘をつけた。
「シスター・レイシー?」レイシーは怖がっているように見えたがうなずいた。
「はい」
「シスター・ヴィニー?」
「ええ。少しだけ」
シスター・プリシラは私たちみんなを見渡した。彼女が私たちを信じたのかはわからなかったが、パルミラの目には勝利が見てとれた。私たちは結束していた。これは最初の試練で、誰も負けはしなかった。私たちはみな共に闘っているのだった。「ふぅ」シスター・プリシラは彼女の眼鏡を直しながら言った。「もう誰も苦しんではいませんね?」
私たちは声を揃えて、いません、と答えた。
「それならよかった。でも、もう一度一緒に祈りを捧げたほうがよいでしょう」
パルミラは呆れた表情をしていたが、シスター・プリシラが祈りを捧げるあいだ、私たちは従順にベッドから出てひざまずいた。私はシスター・プリシラの祈りを重要だと思ったことはなかった。彼女は、私たちが何をすべきかをいつも主に伝えた。そして彼女が神に私たちの罪の許しと救いを願った時、私は、みんなが彼女に嘘をついたことを彼女は知っていたのではないかと思った。だが、それを証明する手段はなかった。
彼女は十五分ほど私たちをひざまずかせ、言葉なく去っていった。彼女の足音がホールから遠ざかり、他のドアが閉まる音を聞いた途端、パルミラは鼻をならし言った。「うるさがりやプリシラ!」
みんな笑った。その時から、内輪で彼女は「プリシー(うるさがりや)」と呼ばれるようになった。それは正しい行いではなかったけれど、今でも私はそのことを恥じていない。パルミラは、どこか人情味のある温かな拠り所を私たちに与えてくれた。シスター・プリシラが叱ったり、講義をしたり、厳しく私たちに話した時、私たちはいつもこっそり彼女の名前を口の中で呼んで笑い、お互いの絆を確かめていた。私たちが笑いによって絆を感じることが必要なことは、幾度かあった。
第9章訳註
(1)サウス・ユニオン(South Union)
ケンタッキー州の西部で活動したシェーカー教の共同体のひとつ。1807年に行われた宣教ツアーで、改宗者の人数が十分に集まったことから結集し、その後1922年まで存続した。1827年には最盛期を迎え、教徒は350人程度所属していた。
(2)ハーバードから追い立てられた時、道を歩く彼らを打つ者がいたこと、そして仲間たちが肩を鞭打たれたことを
これは1783年にアメリカで活動を開始したばかりのAnne Leeたちが、迫害され、ハーバードの居住地を追われたことを指すと思われる。その道中、道の脇にあった低木の枝でシェーカー教徒が殴られる様子がのちの教徒の日記に書かれている。
Once the group entered Harvard, the mob continued its brutal treatment of the Shakers. They then seized Elder James, tied him to the limb of a tree, near the road, cut some sticks, from the bushes, and Isaac Whitney, being chosen for one of the whippers, began the cruel work, and continued beating and scourging till his back was all in a gore of blood, and the flesh bruised to a jelly. They then untied him, and seized Father William Lee; but he chose to kneel down and be whipped, therefore they did not tie him; but began to whip him as he stood on his knees.
一行が一度ハーバードに足を踏み入れると、暴徒たちはシェーカーに対して残酷な仕打ちを続けたのだった。それから彼らはジェームズ長老を捕まえ、道路の近くの木の手足に縛り付け、茂みから棒を持ち出した。そして、鞭打ちの作業に選ばれたアイザック・ホイットニーは残酷な仕打ちを始め、長老の背中が血まみれになり、流れた血が固まるまで、殴打を続けた。それから彼らは彼を解放し、ウィリアム・リー神父を捕らえた。しかし、彼はひざまずいて鞭打たれることを選んだので、縛られることはなかった。彼がひざまずいて立っていると、暴徒たちは彼をむち打ち始めた。