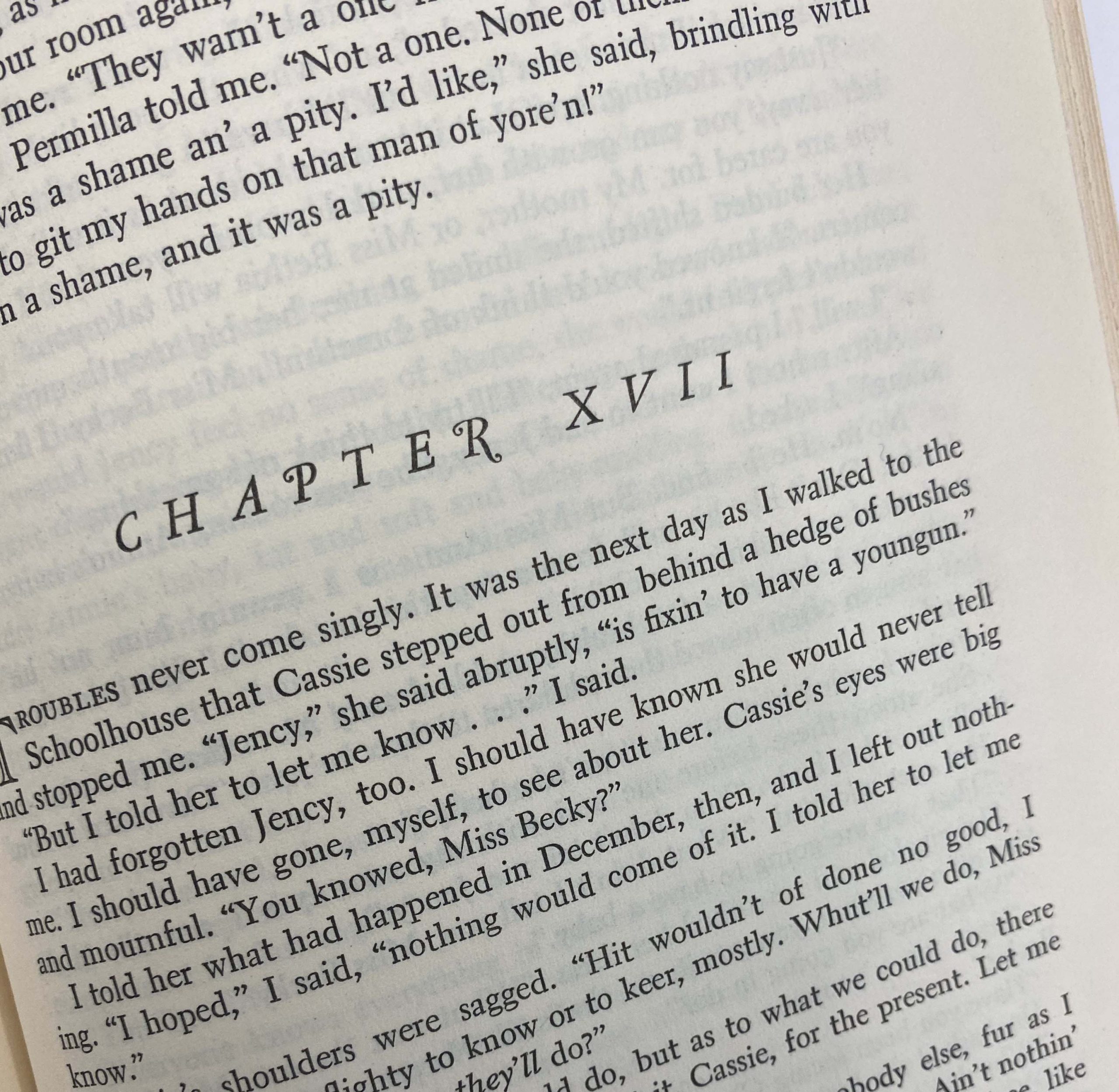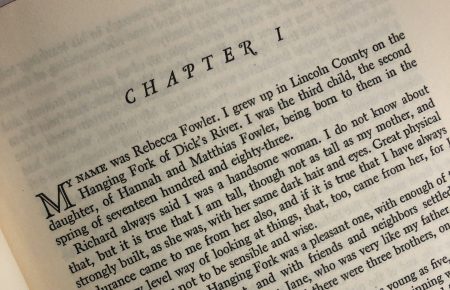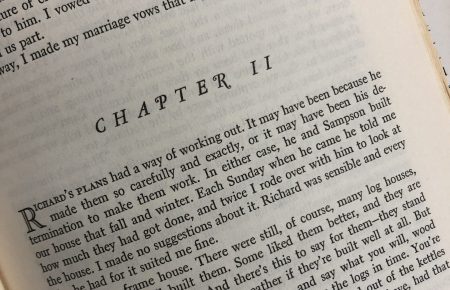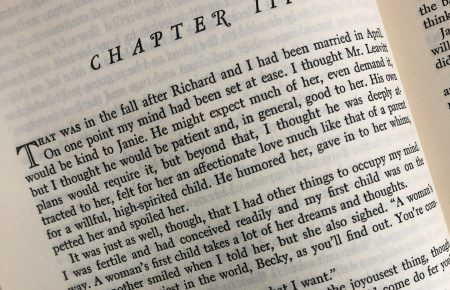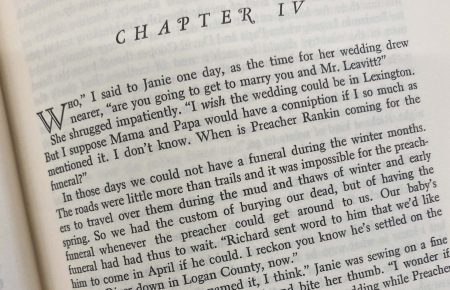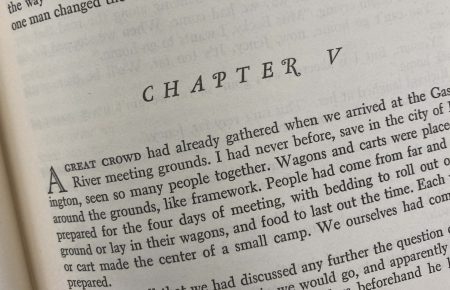面倒は必ず重なるものだ。翌日、スクール・ハウスへ行く途中、カッシーが茂みの陰から飛びだして私を引き止めた。「ジェンシーが身ごもっています」彼女は唐突に言った。「まず私に報告するように伝えたのに」私は言った。
私はジェンシーのことをすっかり忘れていた。彼女が私に報告しないことはわかっていたはずだ。私が気にかけておくべきだった。カッシーの目は見開かれ、悲しみにあふれていた。「知っていたのですか、ベッキーさん?」
私は十二月に起きたことについて、すべてを話した。「何も起こらないことを願っていたのに。何かあれば私に伝えるように言っておいたのよ」私は言った。
カッシーは肩を落とした。「あの子はそんな約束を守るには気まぐれすぎます。どうしたらいいでしょう、ベッキーさん? 彼らはあの子をどうするのでしょう?」
私は彼らが何をするかはわからなかったが、少なくとも私たちができることはほとんどないということはわかっていた。「今のところは黙っておきなさい、カッシー。もう少し考える時間をちょうだい。もうお腹は出始めているの?」
「私が気づくほどには出ています。でも他は誰も気づいていないと思うのです。シェーカーと一緒になんか来なければよかったわ、ベッキーさん。私が言ったように、悪いことばかりじゃないですか。昔のように元の場所に戻りたいです。あの頃は幸せでしたよ」
ビリーバーズが来るまでの私たちの家、そしてそこに満ちあふれていた平和で素晴らしい生活が、走馬灯のように思い出された。それは幸せな日々だった。私もカッシーと同じ願いをひしひしと感じた。でも、もう後戻りすることはできない。その願いを感じたと同時に、それは消えていた。今、この現実こそが、私たちの立ち向かう相手なのだ。私はカッシーの肩に手を置いて言った。「もうどうにもできないわ、カッシー。ミーティングで恥をかかされる以外には何もされないと思う。それすらもされるか定かではないわ。彼らはこのような罪を明るみに出すことは嫌がるだろうし。ジェンシーとクレイトンが結婚したり、あからさまに一緒に暮らさない限り、何もしないと思うわ」
カッシーは目元を拭った。「どこかへ連れていかれないかしら? それが一番の心配です。どこへ追いやられてしまうのやら。あの子のために私が何をしたらいいのかもわからないですし」
「今は何もしないで。自然と明るみに出させればいいわ。もしどこかへ追いやられるようなら、あなたも一緒に行けるように私がなんとかするわ。私のお母さんかべティアさんが世話をしてくれる」
彼女は重荷が少し下りたようで、口元は震えていたが笑顔を見せた。「どうにかしてくれると信じていました、ベッキーさん。あなたは私たちのことを忘れないって」
「ええ、なんとかするわ」私はもう一度約束した。
放課後に私はジェンシーのところへ行った。彼女はアニーの子をあやしていた。「その子、機嫌が悪いのかしら?」私は尋ねた。
「ううん、大丈夫です。でもアニーさんが手を焼いているんです。コップからだとミルクを飲まないんです」彼女はにこりと笑い、またあやし始めた。
アニーの子はふくよかで健康的だった。もう二歳にもなるが、三歳かそれ以上になる子どもでも保育されるのが普通なのだ。「貸してごらん」私は言った。
ジェンシーが私に手渡して言った。「重いでしょう?」
彼女が私の目の前に立ったので、お腹のわずかな膨らみが見てとれた。「教えてくれなかったわね、ジェンシー」
彼女は目を見開いた。「何をですか、ベッキーさん?」
「赤ちゃんを身ごもったこと」
彼女はくすくす笑って服のしわを伸ばした。
「なんの意味があるんですか、ベッキーさん? 赤ちゃんを産んで終わり。ただそれだけのこと。言っても意味ないもの」
「どうするつもりなの?」
「赤ちゃんを産みます。私の赤ちゃんを。私、赤ちゃんが好きなんです、ベッキーさん」
「ずっとクレイトンと会っていたの?」
彼女は平然と私を見た。「はい。クレイトンも好きです」
「それなら、結婚して二人でここから出ていったらどう?」
「ここから出ていくなんて考えていません、ベッキーさん。私たち、ここが好きだもの」
「でもクレイトンと結婚して、自分たちの家を持ちたくないの? 赤ちゃんも好きなだけ産めるのよ」
彼女は三つ編みをいじり、くすくす笑った「ここを出なくても好きなだけ赤ちゃんを産めると思います」
私はアニーの子を手渡した。笑いが込み上げてきた。彼女にとって倫理などどうでもいいことだった。私は、毎年黒人の赤ちゃんが生まれることも、どうにかジェンシーに罪について教えようと手を焼くシェーカーたちの顔も、生まれた赤ちゃんの扱いに頭を抱える彼らの姿も想像できた。それでも私は、彼女とクレイトンは結婚して村を出ていくべきたと思い、繰り返した。「やっぱり出ていくべきだわ、ジェンシー」
「もし出ていきたくても、出ていけません、ベッキーさん。クレイトンは自由じゃないんです」
「スティールさんは自分の奴隷をみんな解放したと思っていたわ!」
「いいえ、アマンダさんがそうさせないんです。クレイトンはスティールさんがいいって言わないとここを出ていけないし、スティールさんはアマンダさんがいいって言わないと出ていかせてくれません」
それでは話がまったく違ってくる。それでも来た時よりかは心が軽くなっていた。ジェンシーは子どもを産むことに恥じらいを覚えるどころか、自分の子どもを持てることに喜びを感じることくらいわかっていたはずだった。「赤ちゃんが好き」と彼女が何度も繰り返すのを聞いていたではないか。ああ、私も、私も赤ちゃんが好きだった。アニーのふくよかで柔らかい赤ちゃんの感触や匂いが腕の中に残っていた。そして私の人生が崩れ落ちていくようだった。私は自分の子どもを教育することがないことを確信しながら、他人の子どもたちを教えている。
それでもイースト・ハウスの味気なさとは比べものにならないほどましなのだと自分に言い聞かせた。少なくとも、私は毎日、心を満たしてくれることをやっているのだ。私はステファンがその日貸してくれた本を見た。
「ほら、このギリシャの歴史を読むといいでしょう」彼は本を私に突きだして言うのだった。「テルモピュライの古代スパルタ人について読むといい。昨夜のことを忘れられるかもしれません」
「知っているのですか?」
「こんな小さな場所ではすぐ皆に知れ渡りますよ、レベッカ。お気の毒でしたね」
私は顔を少ししかめて微笑んだ。「快くはないけど、もう終わったことです」
「そうですね。これを読めば心が安らぎますよ」
「悲しい話ですか?」
「いえ、壮麗な話です。ギリシャ人は素晴らしい死を遂げている」
「どのようにして死んでいったのですか?」
「泣き言を言うこともなく」
「それは私への教訓になるのですか?」
「あなたに教訓などは必要ありません。ただ、人は皆同じ運命を辿るということをお伝えしたいだけです」彼は首を振った。
菜園を横切った時、パルミラに呼び止められた。「タマネギやトウモロコシの新緑を見ていきなさいよ」
カラシナの硬い葉はすでに丸まり始め、タマネギの深緑の葉やトウモロコシは誇らしげにぴんとそそり立っていた。菜園全体が青々しく芽吹いている光景に、私はすっかり感心してしまった。そして私は少しのあいだ、ぼろぼろとした肥沃な土を鍬で耕し、萌芽し始めた豆が並ぶ畝の表面をほぐした。パルミラも鍬を手に、あとに続いた。
私は畝を一列耕し終わると、パルミラに鍬を渡した。「そろそろ行かなきゃ。勉強しなきゃいけないの。それから、ジェンシーが妊娠したわ」私は付け足した。
パルミラは目を丸くしたが、笑い出した。「あらまあ、あのやんちゃな子よね?」
私はパルミラに、十二月に起きたことをついに話した。彼女はくすくす笑いながら聞いていた。「逃げだしてあの古い掘っ建て小屋に二人で行くなんて! 怯えてなんかいなかったでしょうね」
「間違いないわ」私も笑って同意した。
「どうするつもりなの?」
「まだわからないわ」
「リチャードには言うつもり?」
「いいえ」
「リチャードのことから立ち直れそうね、ベッキー」
「今の彼を見ていると、立ち直ることなんて何もないわ、パルミラ。まったく知らない人のようだわ。もう思い出しか残ってない」
彼女は頷いた。「そうね、そして思い出だけでは生きていけないわ」
「そうね」
私は畝の端の草の上に置いていた本を拾い上げて、表紙にかかっていた土を払った。「立ち直ろうとしようとも思っていないわ。勉強に励んでいるの」
パルミラは本を指差した。「でも本は男の代わりにはならないわ」
突然、リチャードが私の腰に腕を回した時の感覚を思い出して、嫌な気持ちになった。記憶において最も辛いのは、感触、感覚、匂い、手触りが急に押し寄せて、記憶を鮮明に思い出させるのに、その思い出だけに依存して生きていくことはできないということだ。
パルミラが言った通りだとわかっていた。「ある意味ではひどいその場しのぎよね、でもそれはそれでいいことがあるのよ」私は言った。
「でもやっぱり男の代わりにはならないわ」パルミラの声は冷たかった。
私は笑った。「そうね。耕す作業を進めて、パルミラ。本を退かすわね」
彼女の脇を通る時、パルミラに優しくお尻を叩かれた。「勉強しすぎないでね」
「そうするわ」
夕食のあと、アマンダを見かけた。「あなたとウィリアムは奴隷を解放してないって本当なの?」私は聞いた。
「本当よ。ウィリアムはそうしたがってたけど、私は嫌だったの」彼女は言った。
「どうして?」
彼女はやせた肩をすくめた。「彼らには利用価値があるかもしれないじゃない」
「まだここから出ていくことを願ってるの?」
彼女はきっぱりと言った。「今は願っているだけじゃないわ」
私は彼女が言っていることがわからなかったし、知ったことではなかった。クレイトンが自由かどうかを知りたかっただけなので、それ以上質問しなかった。
数週間のあいだ、新しいミーティングが試されるらしいという噂が囁かれていた。それは対話形式のミーティングで、三、四人のシスターが選ばれて、同じ人数のブラザーたちとブラザーの部屋で、もちろん指導者も一緒に、うたったり祈ったり話したいことをなんでも話したりするようだった。ブラザー・ベンジャミンはそのミーティングが夫と妻が隠れて密会している問題を解決するだろうと考えていると噂されていた。
夕食後、私たちの部屋の中はとても盛り上がった。新しいミーティングはその夜に試されることになり、アニーはその参加者に選ばれた。それまで、アニーとロバートが抜けだしていたことに、指導者は薄々感づいていると思った。
アニーはきれいなハンカチを持たなければならないと神経質になっていた。パルミラは彼女に言った。「あなたのハンカチは十分きれいよ。今朝つけたばかりじゃない」
「膝の上に一枚置かないといけないの」アニーは言った。
私たちはみな、目を見開いて彼女を見つめた。その後でパルミラがようやく言った。「膝の上に? 一体何のために膝の上にハンカチなんか置かせるのかしら」
「知らないわ」アニーは短い毛に手間取りながら髪の毛を結った。「教えてくれないの。膝の上のハンカチの上に手を乗せるから、きれいなハンカチを持っていないといけないって言われたの。全部何のためなのかわからないわ」
「彼らは男性と女性を触れ合わせようとしているの?」ヴィニーが聞いた。
アニーは答えた。「違うわ、そんなわけないでしょ。シスター・スーザンは、男性と向かい合って五フィートの距離で椅子に座ることになると言っていたわ。私たちはみんな、男性も女性も膝の上のきれいなハンカチの上に手を乗せておかなければならないの」
パルミラは首を反らして笑いながら大声で言った。「五フィート離れているのに、手で何ができると思っているのか知りたいわ!」
「しーっ!」アニーはパルミラに頼んだ。「静かにして、パルミラ。もしプリシーが今ここに来て私を説教し始めたら、正気を失ってしまうわ」彼女は髪の毛をまとめて、それから帽子を被った。「ハンカチを持っていかなきゃ」
私は彼女に言った。「私のきれいなハンカチを持っていっていいわよ。別のハンカチを今夜洗うから」
「まあ、ベッキー、優しいのね。でもきっと明日また使えると思うわ。汚れるかすらわからないし」
パルミラは聞いた。「そうね、あなたの予備のハンカチはどこ? あなたのことだから洗ってないに違いないと思うけど」
アニーはしかめっ面をした。彼女はしょっちゅう同じハンカチを二日連続で身につけていたし、自分の持ち物にだらしなかったし、何回も大ざっぱにお風呂に入ったりしていた。彼女はきれいなものが大好きだったが、首元が汚れていても自分の体が清潔でなくても、あまり気にすることはなかった。秩序と清潔の規律は、彼女には厳しいものだった。
私はハンカチを探して彼女に渡した。彼女は四つ折りにした。「こうして持たなくちゃいけないの。どうかな、ちゃんとしているかしら」
私たちは彼女を一通り確認した。私はほつれた髪の毛をピンで留め、パルミラはスカーフの折り目を整えた。ヴィニーはスカートを整え、アマンダさえも手伝ってエプロンの紐を結び直した。それからアニーは椅子の端に座った。「シスター・スーザンが私を呼びにくるわ」
私は笑った。「私たちが彼女にパーティーにでも行く準備をさせているみたいね」
パルミラは鼻であしらった。「私が知っているパーティーとは程遠いわ」
アニーは言った。「私が知っているのとも違うわ。でもいつもとやり方が違うミーティングだし、私はこの機会を逃したくないわ」
アニーは突然青ざめて、椅子の上で揺れだして、口に手を当てた。「どうしたの?」私は聞いた。彼女はすごく具合が悪そうに見えた。
彼女は息を飲んだ。「吐きそう」
みんなが周りを囲んだ。パルミラが彼女に言った。「横になって。濡れた布を喉にのせるわ」
アニーは頭を振った。「時間がないわ。対話形式のミーティングに行けないのはいやよ。とにかく、おさまるはずよ」
しかし彼女は横になって、嘔き、空気を求めるように首をそらした。私は彼女の額を触って調べたが、冷たかった。それなのに玉の汗がどっと噴き出ていた。「熱はないわね」私は言った。私たちはコレラを恐れていた。
「そうね。胃が吐き気を催しているだけよ。きっとおさまるわ」
パルミラは彼女を鋭く観察して、それから笑い始めた。「あなたの胃は吐き気を催していて当然よね。妊娠しているんでしょう?」
アニーは頭を上げてパルミラを見た。「あら、そそのかしたのはあなたでしょ。そうよ、私は妊娠しているわ。ロバート坊やが乳離れして、新しい赤ちゃんを迎える用意ができたし、もしこれでも旦那がここから離れないのなら、シェーカーたちはもう一人赤ちゃんの世話をすることになるわ!」
「しーっ! 誰か来るわ」ヴィニーが言った。
私たちは小走りで椅子に向かい、アニーはまだ青ざめていて吐き気があったが誰よりも素早く動いた。シスター・スーザンが扉を開けた。「アニー、準備はいい?」
アニーは猫をかぶった。「はい、できました」
「じゃあ、ついてきて」
初めての恋人に会いにいく少女のようにかしこまって、アニーはシスター・スーザンについてホールに入った。彼女の後ろで扉がそっと閉まり、すぐにみんな椅子から離れて、くすくす笑って囁きながら私のベッドのまわりに集まった。「まあ、驚いたわね!」パルミラはそう言って含み笑いをした。「彼女は抜け目がないわ。ロバートはどうするかしら?」
「彼女と出ていかないなら、彼は愚か者よ」アマンダはきつく言った。
ほとんどの人も彼が出ていくと思っていたし、私としては心からアニーにやりたいようにしてほしいと思っていた。彼らが共に暮らせる幸せな人生を、こんなところで閉ざされるにはまだ若すぎた。
「今夜は何人参加するのかしら」パルミラは聞いた。
「三人よ。プリシーが言っているのを聞いたの」アマンダは答えた。
「プリシーはどう思っているのかしら」
「想像できるわ」パルミラは言った。
アマンダは笑って、
「彼女は認めていないでしょうね」と言った。
「私の順番が来た時に、彼女が担当じゃないといいけど」パルミラが言った。
「まあ、きっとシスター・スーザンかブラザー・サミュエルのどちらかが担当するわよ」アマンダは彼女に言った。
「プリシーは関わらないわ。精神的な類のものだから」と続けた。「私にはちょっと精神的すぎるわね」パルミラが言うと、みんな笑った。想像しているようには行われないだろうと、みんなわかっていた。指導者に見守られていて、どうしてそんなふうにできるだろう。一語一句聞かれている中で、一体誰が自然に話せるだろうか。
「私たちも交代で参加するのかしら?」私は尋ねた。私は、ファミリーの中でその当時起こっていたいろいろなことを把握しておらず、噂で聞く程度だった。
アマンダは頭を振った。「いいえ。強制されるわけじゃないの。でも望む人は参加できるわ」
私は突然決心して言った。「それなら、私は参加しないわ」
「どうして参加しないの?」ヴィニーが聞いた。しかしパルミラは理解したように私に眼差しを向けた。
「本を読むほうがいいわ」私は言った。
「私も参加したくないわ」アマンダは言った。
「あなたは本を読もうとしているわけじゃないでしょう?」ヴィニーは聞いた。
「そうよ。でも男の人たちのところに行きたくないわ。言うことがないもの、少なくともここにいる人たちには」
パルミラは服を脱ぎ始めた。「まあ、私は参加するわ。ミーティングがどう変わったのか興味があるからね。でも、とりあえず今は寝るわ。庭の仕事は疲れるの」
みんなもベッドに向かった。私は(1)キャンドルスタンド・テーブルを引き寄せた。九時半までは明かりをつけていてよい決まりだった。初めのうちは、明かりをつけていたら他の人に迷惑をかけるのではないかとよく気を遣っていたが、皆は迷惑ではないと言ってくれた。今では九時半まで読み物をする私の習慣に、みんな慣れていた。しばらくのあいだ、みんなそれぞれひざまずいて祈りを捧げ、ベッドに入った。
それは、私が毎日楽しみにしていた時間だった。邪魔の入らない、静かな時間だった。手の中にある本だけが現実のものに感じられ、少なくとも私の中では、それはシェーカー・ハウスを離れた他の土地や時代への探検と冒険の時間だった。一時間、幸運な時はそれより少し長く、私はサウス・ユニオンを抜け出し、一日のうちの最も素晴らしい時間を過ごすようになっていった。
私はステファンの本を開いた。もっと言えば、彼の所有する多くの本のように、彼が何度も読み返したせいでページに癖がついており、本がひとりでに開いた。彼の本を読むたびに、彼が私に語り掛け、彼の心が私を導いているような気がした。
私の手元には、テルモピュライのスパルタ人たちの碑文があった。
(2)『異国の人よ、スパルタに行きて伝えよ、我ら、汝らが命を果たし、ここに眠れりと』
これが私の心を高鳴らせるだろうと、ステファンが言った言葉なのだろうか? 私にはこの言葉の良さがわからなかった。この時、私はまだこの言葉の裏に何があるのかを知らなかったのだ。私は物語の冒頭へとページを戻した。
ペルシア戦争において、ペルシアの司令官であったクセルクセスは、巨大な軍隊を率いハルキディキ半島への唯一の道である狭い小路を進攻した、と本には書いてあった。ペルシア戦争やクセルクセスの存在は、私の中で少しずつ実体を持った。この物語は私の想像を掻き立てた。たった八千人の軍隊しか持たないレオニダスと彼の三百人のスパルタ人はひどく脅かされた。それから裏切りが起こった。私は同胞を裏切ったギリシア人を恥ずかしく思った。レオニダスの決断は、罠にかけられることやすべての兵士が殺されることを知ってのものだった。私には、彼の決断が言葉を超えて尊いものに思えた。彼は自らの小軍隊に、望む者は自由に去ることができると言い、残ったのはたった二千人の兵士だった。そしてそのうちの三百人のスパルタ人は、すべて残った。そして彼らは死んだ。まるで死地だと知っていたかのように、テルモピュライの峠で。私は再び碑文を読んだ。『異国の人よ、スパルタに行きて伝えよ、我ら、汝らが命を果たし、ここに眠れりと』それだけだった。私は、彼らがそれほど敬意を払われていなかったことに抵抗感を覚えた。
そしてそのことを、次の日ステファンに伝えた。
「彼らは死にました」彼は言った。「スパルタが望んだように。従順に。これこそが彼らの本当の碑文でした」
しかし女である私は同意しなかった。「彼らは墓に彼らの勇気や勇敢さを刻んだかもしれません。敬意の証として」
「敬意は示されていますよ。碑文は語っています。わからないのですか、レベッカ?
そこには何と書かれていましたか?」
「『異国の人よ、スパルタに行きて伝えよ、我ら、汝らが命を果たし、ここに眠れりと』」
私はゆっくりその言葉を読み返し、彼が言わんとしていることを悟った。彼らは死んだ。すべての三百人ものスパルタ人は、死ぬとわかっていながら命じられたままに死んだのだ。勇気と勇敢さは偉業で暗に示されていた。彼らの碑文こそ、その証書だったのだ。「一言でも付け加えれば、それは泣き言になってしまいます」ステファンは柔らかく言った。彼ら、ギリシア人たちは、自分が死ぬ運命を知っていた。泣き言は言わなかった。だから、私も泣き言は言わず生きていこうと思い始めた。また、ここ数年、リチャードと結婚してからというもの、自分がかなりの数の泣き言を言ってきたことに思い至った。私は人生における不幸に嘆き、自分自身を惜しみ哀れんできた。なぜ、なぜこのようなことが私に起こらなければならないのかと何度も何度も言い続けてきたのだ。私はもう二度と、苦しんでいる子どもの、胸を引き裂くような泣き声に屈することがないようにしよう、と強く心に決めた。私はスパルタ人ではない。死の脅威に晒されているわけでもない。それでも私は生きねばならなかった。そして今は泣き言は言わずに、勇気を持って生きたいと思った。
だから、子どもたちが自由に運動したり遊んだりしている昼前にアマンダがスクール・ハウスに来た時、そのことを指摘しなかった。彼女はとても率直な女性で、乾いた唇とすっとした鼻筋と顎をしていて、常に不機嫌さを表情に滲ませていた。正直、私は一度も彼女に好意を持ったことはなかった。しかし、彼女が子どもと引き離されたことに関しては同情を覚えた。「私はサイラスと少し話がしたいの。ベッキー、あなたさえよければ」彼女は言った。
彼は一週間ほど前から悪寒と発熱に苦しんでいた。風邪をひいている数日間、彼は学校に来ることができなかった。そのことをアマンダに伝えるのは、私の役目だった。彼女は面食らって、突然座り込んでしまった。「状態はひどいの?」
「いいえ。熱が出て、寒気がしているだけよ。シスター・ドルシーが彼の看病をしているけれど、彼女によれば、一、二日もすればよくなるそうよ」私は言った。
「シスター・ドルシーですって!」彼女は小馬鹿にしたように言った。「彼は私の子で、彼の看病は私の役目なのに」彼女は痛ましいほどに手を固く握りしめた。「シスター・ドルシーに任せていいか不安だわ、ベッキー。あの子は私たちに遺された最後の子だから、もし何かあったら……」
私は自分の手を彼女の肩に置いた。「シスター・ドルシーは良い看護師よ」
「でも彼女は母親ではないわ! 風邪を引いた時に小さいあの子が何を思うか、母親である女性がどう感じるか、少しもわかっていないのよ」
彼女とウィリアムは息子に対して過保護だったが、それがなぜなのか、理解することは簡単だった。もし私が彼らと同じ立場だったら、同じようにしただろう。日が経つにつれて、私は彼女に対してひどく申し訳なさを感じた。彼女は絶えず不安で、心が安らがなかった。彼女は息子の看病をする許しを請いたが、シェーカーは彼の病気を軽視して、彼女とウィリアムに日々の労働を課した。
三日おきに彼女はスクール・ハウスに会いにきて、息子に会いたいと頼んでいたが、そのあいだもずっと、彼の寒気は続いていた。「もちろん」私はためらいなく言った。「サイラスをあなたのもとに送るように、私からブラザー・ステファンに頼んでみましょう」
「本当にありがとう」彼女は言った。
ステファンはサイラスを連れてよこした。彼女は少し離れたところへ息子を連れていき、立ったまま話をしたあと、遠くへ行ってやがて見えなくなった。私が校庭の番だったので、シスター・ドルシーは中にいた。ステファンは男の子たちを置いてこちら側に来た。「彼女はどうしたかったのですか?」
「わかりません。でも、彼は今もまだ病気です。私の力が及ぶ範囲では、彼女は自分の好きなように彼と会うことができるでしょう」
「早くも反抗的になってきましたね、レベッカ」彼はそう言って、私に笑いかけた。
彼の髪は子どものような明るく淡い黄色で、こめかみあたりだけ少し白髪が混じり、耳にかかる巻き毛だった。彼はその巻き毛をねじる癖があった。彼が勉強をしているとき、私はしばしば彼のことを見ていた。長い時間、彼はぼんやりと巻き毛を引張り、指のあいだに挟んでねじりながら、先が小さな羽のように立つよう、斜めに押しつけていた。彼は今も巻き毛をねじり、彼の髪はまるで風に吹かれたかのように乱れていた。「かわいそうな巻き毛をいじめているようですね?」私は言った。
彼は髪を撫でつけながら歯を見せて笑った。「そうですか?」
「いじるのをやめないと、髪がすべて抜けてしまいますよ」
「やめられないんです」彼は言った。「やってはみました。夜に読書をする時、髪を引っ張らないように帽子を被っています。それでも結局、帽子は片方の耳に傾いてしまうだけです」
帽子が片方の耳の上に乗り、白髪の巻き毛があらゆる方向に跳ねている彼の姿を思い浮かべ私は笑った。その時、道を通るワゴンのキーキーという音がして、私たちは振り返った。砂埃が舞い上がった。その中で、私たちはワゴンを認識した。牛の群れがワゴンを引き、その隣で男が口笛を吹きながら牛たちを追い立てていた。ワゴンにはキャンバスの上に太字で言葉が印刷されていた。『ミズーリか、破滅か!』
私は言った。「あれは今月ここを通ってミズーリに向かった四番目のワゴンです。それはどこにあるのですか、ステファン? なぜ人々は大勢そこに行くのですか?」
ステファンはワゴンをちらっと見て、男の口笛に微笑んだ。「ミズーリは何年か前に、ジェファーソン大統領がナポレオンから買った広大な領土の一部です。(3)ルイジアナ買収と呼ばれています。ミズーリはミシシッピの西にあります。なぜ大勢の人がそこに行くのか、その答えは単純です。西だからです……。そこは新しく、開けていて、自由で、そして未開拓なのです。いつか」彼は手を髪に伸ばし、思慮深い目で続けた。「この国の歴史が書きつけられる時、最大のロマンは、西漸運動、つまり未開の地の果てに、大陸の端に向かって進もうとする衝動にあるでしょう……ヴァージニアから峡谷を経てケンタッキーまで、ケンタッキーからミシシッピを越えてミズーリ、そしてミズーリから、神のみぞ知る大陸の最果てへ」
私の想像は彼が話す西漸運動に揺さぶられ、心の中でカンバーランド峡谷に押し寄せる開拓者たちの姿を見た。
私は自分の父と母からそれについて聞いたことを思い出した。
私が、私自身が、ミズーリへの歴史の生き証人であることに気づいた。
男と女、転がるワゴン、整備された自然、交差した川、立ち上がった家々、未来に遺すために生まれた子どもたち、それらがまるで劇のように私の目には映った。
私は歴史の誕生を目にしているということに感服した。そしてさらに驚いた。そのことに対して今まで気づかなかったからだ。
突然、私はその一部になりたいと強く思った。ワゴンの一つに座って、リチャードや、馬や牛の群れと共にミズーリに向かいたいと強く思った。私は考えず、激しく言った。「ああ、行けることなら行きたい、新しい土地を見たいです!」
ステファンはまだワゴンを見ていた。砂埃を残して、ワゴンは過ぎ去っていった。「私は行きますよ、いつか」彼は柔らかく言った。
私はむきになって言った。「男性はいつでも好きなように振る舞うことができます! なのに女性は、男性が望むものに手足を縛りつけられ自由を奪われています」
ステファンは私を見て、それから笑った。「ならば男性になりたいと思いますか、レベッカ?」
「ええ、今は!」私は笑った。「でもたいていの場合はそうは思いません。女性にも女性だけの利点がありますから。私は本当に男性になりたいわけではないのです。私はただ、ミズーリに行きたいのです」
「あなたは行くでしょうね」
私は校庭へと向き直った。「いいえ。私はミズーリを見ることはないし、もう考えないほうがいいでしょう」
ステファンの視線が校庭の辺りをさまよった。それから彼が言った。「あの子たちがまたいなくなりましたね」
「誰ですか?」私は尋ねた。
「サブリナとルシアンです。知らなかったのですか? 彼らは愛し合っていますよ」
「そんなまさか!」
「なぜそんなに驚くのですか。とても美しいことではないですか」
「でもサブリナには何も起こってはいけません!」私は感じたままに熱く言った。「彼女は不幸になるべき子ではありません」
「サブリナがルシアンと結婚することで不幸になると考えているのですか?」
ルシアン・ブラウンは、とても公平で素直な男の子で、男らしく、とてもハンサムだ。サブリナは愛くるしく、聡明で、血色が良く、ぽっちゃりとしている。私は頭を振った。「彼らは結婚を許されないでしょう。彼らはまだ若すぎます」
「ではおそらく彼らは待つでしょう」
「もし待てなければ?」
「それならば、彼らが私を信頼してくれることを願っています。そして彼らがここから出る手伝いをします。ほら、今彼らが戻ってきました。ルシアンは男の子たちと今合流した。サブリナはあの離れ……」彼女は離れ家から戻ってきた。しかし、私たちはその多目的に使用される離れ家の良い呼び名を持っていなかった。「彼らはとても慎重です」ステファンは言った。「彼らは絶対に同時に出て行ったり、一緒に戻ってきたりはしません。二人のうちの片方がふらりと歩きだし、そしてしばらくしてもう一方が違う方向に進みます。私は、この状態がそう長くは続かないであろうことを危惧しています。彼らは今、愛し合い始めたばかりです。すぐに彼らはいっそう長くいたいと思うようになるでしょう。そして彼らの不注意で問題になるか、誰かが彼らが逃げる手助けをしなければならない時が来るでしょう。できることなら、私が彼らを助けたいと思っています」
私は、彼がサブリナたちを助けたいと思っているということが嬉しかった。しかし、彼自身のことが少し心配になった。「注意を欠けば、あなたが問題に巻き込まれます」
「そうかもしれませんね」彼は落ち着いて言った。「でもそのことで何か私に害があるでしょうか。ここを去るようを命じられるだけです」
「それこそ一番起こってはならないことです」私は言った。「あなたはここに必要な人です!」
彼は肩をすくめた。「求められない限り、私は出ていくつもりはありません。しかし助けを求めている人を見捨てるつもりもありません」
「テルモピュライで死なないでくださいね、ステファン」私は笑いながら言った。
「ええ」彼は笑いながら言った。「トロイアの木馬のほうが、私には似合っています。そろそろ読書の時間です」彼は言った。
「アマンダがまだ戻ってきません」私は彼に思い出させた。
ステファンは道の方を見た。
「大丈夫。シスター・ドルシーは気づかないでしょう」
私たちは子どもたちを集め、スクール・ハウスへ向かわせた。アマンダが息子のサイラスを連れてシェーカー・ヴィレッジから去ったことを、私たちは夕食の時間になるまで知らなかった。
第17章訳註
(1) キャンドルスタンド・テーブル
シェーカーオリジナルの家具の1つ。胴体から板までに細長いくびれがあり、そのためワインボトルとこの支柱は呼ばれる。シェーカー・ヴィレッジと年代により素材や形も多少変わるようだが、サウスユニオン・ヴィレッジでは足の部分の丸みが上向きなのが特徴である。
(2) 『異国の人よ、スパルタに行きて伝えよ、我ら、汝らが命を果たし、ここに眠れりと』 (The Believers ゼミ訳)
古代ギリシャ人のシモーニデース (Simonides of Ceos)の詩である。
(3) ルイジアナ買収 “ルイジアナ州は1762年以降スペイン領であったが,1800年の秘密条約により他国に譲渡しないという約束のもとでフランスに所属していたミシシッピ川以西ロッキー山脈にいたる領土。1803年、アメリカ合衆国の第三代ジェファソン大統領がフランスの当時の大統領であるナポレオンから、ミシシッピー川以西からロッキー山脈に及ぶ広大なルイジアナを買収した。