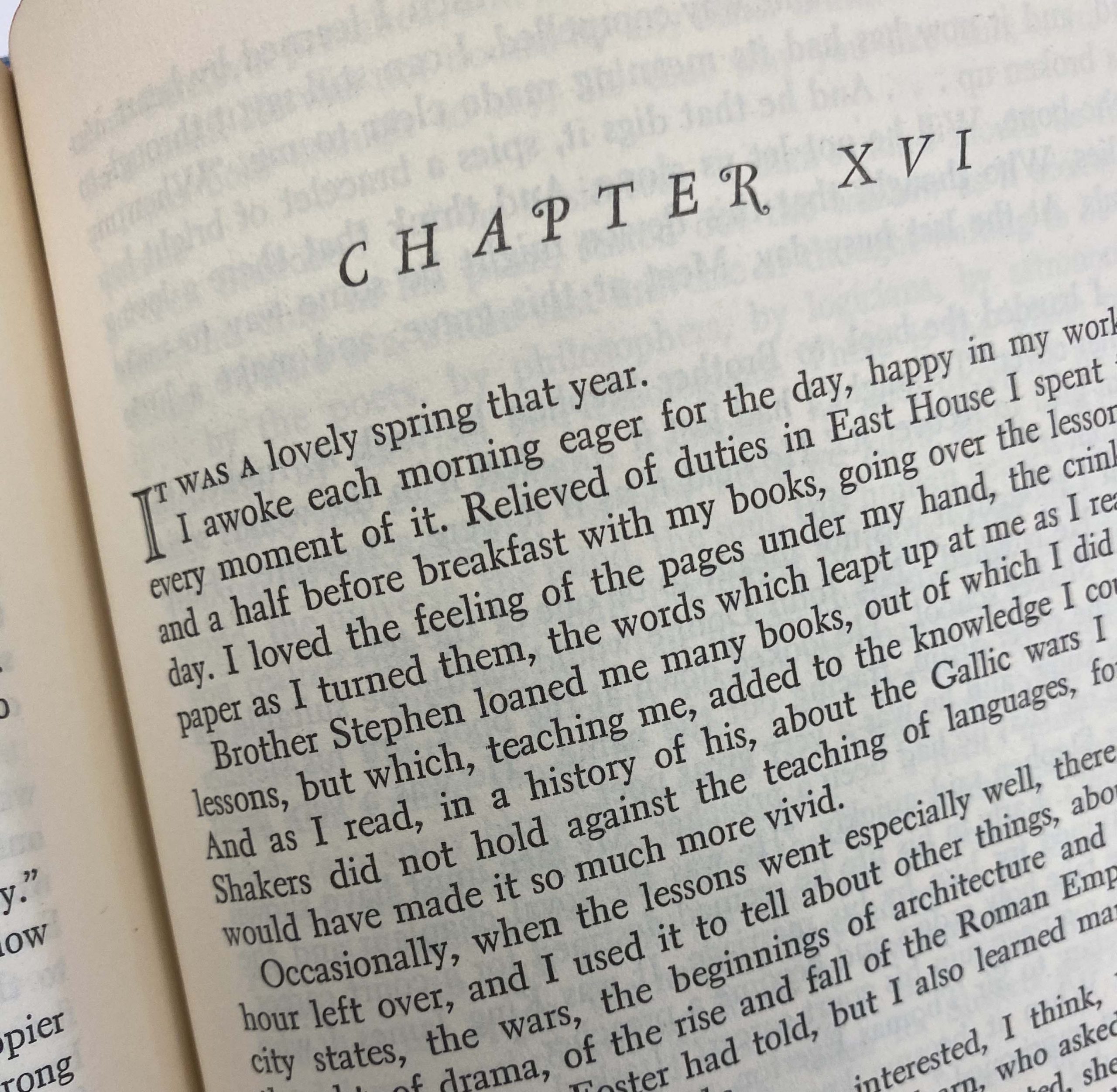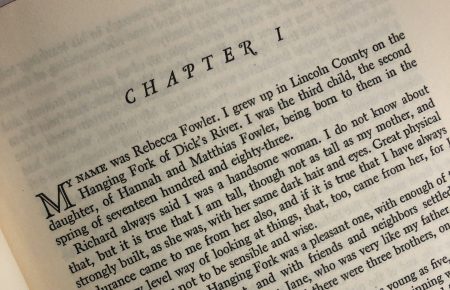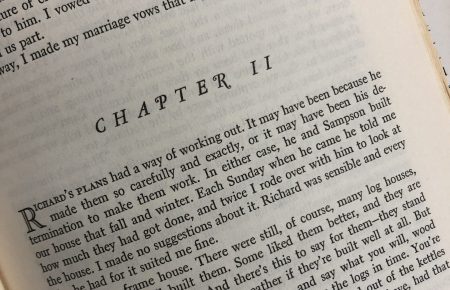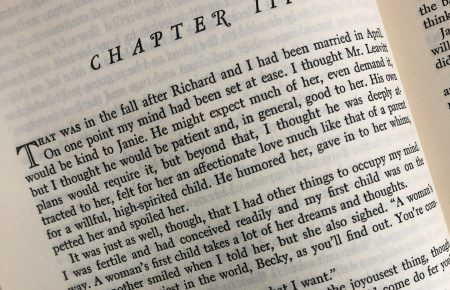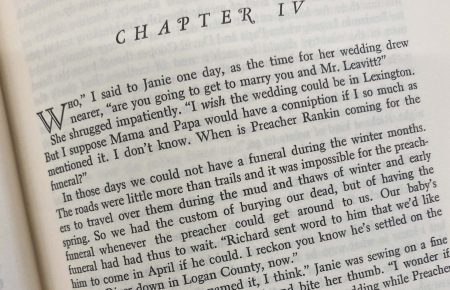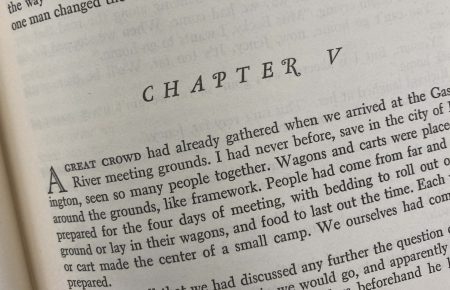その年の春は素晴らしかった。
私は毎朝新しい一日に待ち焦がれて起き、仕事に満足して、一瞬一瞬を愛おしみながら生活した。私はイースト・ハウスでの業務から解放されたあと、朝食前の一時間半を、その日の授業の準備と読書に充てた。私は手に触れるページの感触が大好きだった。紙をめくる時にカサカサ鳴る音や、私に向かって飛び出してくるような言葉たちが愛おしかった。
ブラザー・ステファンはたくさん本を貸してくれた。私はそれらを授業では使わなかったが、本は新たな知識を与えてくれた。そうして本を読んでいくうちに、私はガリア戦争の記述に行き着いた。原語のラテン語で書かれているもののほうが、場面をより鮮明に映しただろう。そのため、シェーカーにはもっといろいろな言葉を教えるべきだと思った。
時折、授業が順調にいった日には、時間が三十分以上余ることがある。そのような時、私はよく他のことを話した。例えば、ギリシャの都市国家から、戦争、建築と彫刻の始まりや、思想、演劇、ローマ帝国の栄華と没落についてまで、様々だった。私はフォスター氏の教えをしばしば思い出したが、ブラザー・ステファンの本からもまたたくさんの新しいことを教わっていた。
女の子たちは礼儀正しく熱心に聞いてくれた。その中でも一番学び、覚える意志があり、質問をしてきたのは、サブリナだった。私が本を読んだり話をしたりすると、彼女は大きく開いた目をらんらんと輝かせ、私を見つめ、すべてを吸収していった。私は、彼女が美しいフレーズに出合って息を飲むのをよく見た。そうして彼女はまるで脳にそれがまとわりついているかのように、目を夢見がちにとろんとさせていた。彼女はしばしば私を探し、さらに質問をしたり、本を借りたりした。彼女はやるべきことが終わったあと、自由な時間がある時に借りた本を読んでいた。
私は、おそらく初めから、自分がサブリナに特に積極的に教えていることに気づいていた。他の子たちはもっと学びたいという熱意がほとんどなく、割り振られた授業を機械的に受けているだけなのだ。サブリナはくすんだ茶色の鳥の群れの中にいる一羽の色鮮やかな鳥だった。彼女以外の女の子たちは、怠惰で魂がなく、さえずる歌も持たず、伸ばす翼も持っていなかった。私は彼女を心から愛するようになった。
一冊、ジョン・ダンの詩集だけは、彼女に貸さずにブラザー・ステファンに返した。しかし、私は返す前にその本にあるすべての詩を読み終えた。おおかたの詩が恋心を詠んだものだった。その大部分はインクで幾度も印がつけられていて、ブラザー・ステファンがそれらを読んで何かを見出したことを示していた。それが一体何なのか、私は気になった。彼が勉強して読み返すために印をつけた言葉たちを読み、その意味を知るにつれて私の顔は熱くなった。そしてその言葉たちは奇妙な感覚で私にまとわりついた。「初め、私たちは、誠実にたくさんの愛情を注いだ。愛するそれが何なのか、またなぜ愛するかは知らないままに……」
そしてその本の中には一つ、「聖遺物」という題名の詩があった。私はそれを暗記した。習いたくはなかったが、半ば強要されたのだ。私はいまだにそれを最後まで暗唱できる。そして今はその意味がはっきりとわかる。
(1)『僕の墓が暴かれ 次なる客が招かれる時、
墓を掘る人足が、
僕の骨のまわりに金髪で作られた腕輪を見つけても、
そのままそっとしておいて、
愛し合った二人が眠っているのだと思い、
最後の審判の日に、二人の魂がこの墓で
再会し、しばしの逢瀬を過ごすために
このような工夫を考えついたのだと思って欲しい』
私が本をブラザー・ステファンに返却した時、彼はそれをとって、くたびれた革のカバーを撫でた。「失くしてしまったかと思っていました……森かどこかに置いてきたものとばかり。戻ってきて嬉しいです」彼はまるで宝物かのようにそれを受け取った。「これを読みましたか?」
「はい。けれど、これは教科書として使うべきものではないと思いました」
もちろん違います、と彼は笑った。ジョン・ダンの本はシェーカーのスクールで教えるのにはあまりに向いていなかった。彼は本を見下ろし、細長い指を表紙の上に滑らせて名前をなぞった。「彼は素晴らしい司祭でした。そして、見事な詩人でした」
彼が司祭だったことに私はとても驚いた。私の表情にそれが表れていたのだろう。ブラザー・ステファンがすかさず言った。「彼は宮廷お抱えの司祭であり、またセント・ポール大聖堂の主席司祭でした。早い段階で彼は法廷で職務を執ることが決まっていましたが、結婚によってその道は閉ざされました。彼に聖職者として司祭になることを強く勧めたのは王であるジェームズ一世です」
「彼の結婚は宮廷での仕事にどのような影響を及ぼしたのですか?」と私は尋ねた。
「彼は(2)トーマス・エガートン卿の秘書でしたが、秘密裏に卿の姪と結婚しました。それが公になった時、彼は役職から降ろされたうえに収監されてしまったのです」
「彼は何をしたのですか?」
「彼はそのとき……」この時、私たちは教室に立っていた。この日、生徒はすでに帰っていた。下の階でシスター・ドルシーが部屋を片付ける静かな音が聞こえた。ブラザー・ステファンがゆっくりと机のほうに歩み寄った。「座りませんか。ジョン・ダンのことを知りたいですか、シスター・レベッカ?」
「ええ……ぜひ。お願いします」 そうして私たちは席についた。私たちは、自分たちがどちらもシェーカー教徒であることを忘れ、またこのような会話が禁止されていることも忘れていた。
「彼はローマ・カトリックとして生まれ、オックスフォードで教育を受けました。しかし若くしてカトリックの信仰を捨て、英国国教会に改宗したのです。彼はリンカーン法曹院で法を学び、第二代エセックス伯と共に海を越え、スペインへと向かいました。帰って来た時、彼は(3)ブラックリー子爵のお抱えの秘書としての地位を用意されていました。けれども、先に述べたように、子爵の姪であるマリーへの愛と秘密の結婚は、結果として解雇へと繋がりました。彼は幾年にも渡って法に従事しましたが、哲学の思想を掘り下げ始め、カトリック教会に異論を唱えたことで国王の目に留まりました。王に説得され、彼は英国国教会の司祭となりました。彼以上に感動的な説教をする者はおらず、また彼以上に精緻な詩を書く者もいませんでした。彼は彼自身で思考していました。彼は自分以外の何物にも縛られなかったのです」
「それが、あなたが彼を好み、特定の詩に印をつける理由なのですか」と私は意を決して問いかけた。
「そうですね」 彼は躊躇してから言った。「人間の精神は自由であるべきだからです」
彼は手のひらに顎を乗せて、遠くのものを見るかのように窓の外を眺めた。「世界には、詩人や、哲学者や、倫理学者や、天文学者、はたまた科学者や、随筆家、神学者によって、探求されるのを待つ思考の宇宙が広がっています。そこにはこの世のすべての秘密があるのです。レベッカ、考えたことがありますか」彼は顎から手をおろし、熱心な様子で前のめりになりながら言った。「すべての事物に対し、我々が知るのはごくわずかなのですよ。世界も、宇宙も、精神も、魂も、私たちが人間と呼ぶ人類ですらそうです。私たちはこれらを知るにあたり、まだ一歩を踏み出したばかりです。そのことにあなたは気づいているでしょうか。ギリシャ人は……彼らは考え始めていました。けれど果てしない時間の中で考えれば、それはたった昨日のことなのです。いまだそこには多くの解き明かされない謎があるのです」
人間の精神は自由であるべき……私は胸中で繰り返した。その言葉は私の顔に降りかかった真新しい雨のようだった。その雨は透き通って、心地よく、爽快なものだった。その言葉は幾度も私の心に響いた。……人間の精神は自由であるべきなのだ! ああ、私はそれを心から信じていたのだ! いかなる思考も他者に縛られ、脅かされるべきではない。理性へと向かう大いなる道はすべての人に開かれているのだ。シェーカーの女性が皆着る、細くごわついたエプロンを手でまさぐった。私は、自らの記憶を思い出し、そうして気づかされ、げんなりした。シェーカー教の中では、精神は自由ではない。また、私はブラザー・ステファンによって困惑させられた。私はこう尋ねた。「シェーカー教ではすべてが明確にされています。それなのに、なぜあなたはそのように考えられるのですか」
彼は驚いた様子で私を見た。「私はシェーカーではありませんよ!」
私は驚いて言葉に詰まってしまった。「あなたはここにいて……私たちと一緒にいて……東から、この学校で授業をするために送られてきたと聞いて……」
「それで私はシェーカー教徒だということになるのですか?」
私はどう答えることもできずに手を広げた。「わかりません。私はそう思っていました」
彼は笑った。「私は教えるためにここに来ました。ですけど、ニューヨークから来たのであって、ニューレバノンから来たのではありません。ここにいるあいだはシェーカーの教えに従わなければなりませんが、私はノヴィシエイトではないし、今後、ノヴィシエイトになることもないでしょう。私はビリーバーズの神学に魅せられてはいません」
「なぜ? 何が問題なのですか」
答える代わりに、彼は私に問いかけてきた。
「教えて下さい、レベッカ。なぜあなたはシェーカーに?」
私は幾度も繰り返した答えをまた繰り返した。「私の夫がいるからです」
「あなた自身は共感していないのですか?」
彼の率直さに私は困惑したが、正直でいようと努めた。「そうですね、いくらか疑問を感じています」
彼は前のめりになった。「レベッカ、あなたは本当に、マザー・アンが再臨のキリストであると信じていますか? 本当に、歌と踊りによる過激な感情表現を信仰していますか?
本当に、俗世からの離脱を信じていますか? 男女が分かたれた、この場所の中で?」
「あなたはどうですか」私は聞き返した。
「信じません」 彼は短く答えた。「マザー・アンは結婚に絶望した一人の女性だったのだと思います。彼女は生まれつき性に興味がなく、性行為を拒絶していた。だから彼女は否定したのでしょう。そしてマザー・アンはある種の幻想を見たり、空想に耽ったりしやすかったのだと思います。昼夜、断食とお祈りに終始すれば、誰だって幻想を見るものです。目の前のただのしみでさえ、幻想に見えてしまう。私は一瞬でも彼女が再臨のキリストであるなど思ったことはありません……」
「けれど、思うに、彼女はそう信じていました」 私は話を遮った。
「あるいは」彼は言った。
「彼女はひたすらに誠実だったのでしょう。しかし、だからと言って正しいことにはなりません。ひどく不安定な人間にとって、神が導いてくださっていると考えることほど信じやすいものはありません。そのような思想は安楽的なものなのです。また、宗教の大半は畏れと迷信に基づいています、レベッカ。地獄に落とされることへの恐怖、そして妬む神を鎮め、永遠の命への救済を受けるための儀式にまつわる迷信です」
私は躊躇しながらも尋ねた。「それならば、あなたは結局、信仰深くはないということなのでしょうか」
彼は微笑んだ。「私なりに信心深いと思っていますが、おそらくそのように思う人はほとんどいないでしょう」彼は腕を広げた。「もしあなたが、私は神を信じているのかと問いたいならば、答えはイエスです。けれど私は、神というものが完全に解明され、理解されることができるとは信じていません。どんな教会も、『これが唯一無二の真実である』と明言することはできないと思います。そういった教会のほとんどすべての儀式は、いまだ異教徒のそれと変わりないのです」
「それでも、シェーキングやダンス中に降りてくる、シスターやブラザーたちの幻想やギフトはどうなのですか?」
彼は肩をすくめた。「あらゆる感情をずっと押し殺していて、それを宗教への凄まじい熱狂へと解放したなら、どんな錯乱状態にもなりえるでしょう」
「あなたは、彼らが現実的ではないと思うのですか?」
「彼らは現実的ですよ。ただ、野蛮人でさえ、異言と幻想のギフトを得るまで、太鼓を打ち、詠唱し、踊ることができます。それはほとんど純然な感性です」
「ギフトや幻想を持てたことはありません」私は言った。
彼はおかしそうに私を見た。「欲しいですか?」
私は自身の尊厳を忘れたことはないこと、それゆえに時折他者に贈られるギフトに悩まされたことがあることを打ち明けた。
彼は強調して言った。「もうあなたはわかっているではありませんか。理性的な人間には尊厳が内在しています。どうしてそのようにあるのでしょうか? 人間の尊厳とは、神のそれを授けられたものです」
「けれど、ブラザー・ベンジャミンは理性的な人間です……リチャード・マクネマーだってそうです。彼らは共に学者です」
「彼らはおそらく、理性を持たずとも学べたのでしょう。実際、彼らのどちらも理性的な人間ではありません。彼らの信仰には盲点があります。そして彼らは共に感情的で、無知な野蛮人のようにおぞましく、迷信的です。シェーカーの信仰を見れば見るほど、私はそれらが嫌いになります。人間の心、精神と尊厳は自由のためにあるのです。レベッカ、この場所ほど自由が制限され、そうしてそれを進んで対価にし、安全を得ているところはないでしょう。
そしてそれはうまくいきません。彼らの神の国に至る偉大な行程、つまり精神による純粋な道筋は破綻するでしょう。人間の運命は生まれながらにして、甘受するものではなく、探求しなければならないものなのです。権威はまさに支配しようとする対象を殺してしまいます。それはすべての崩壊した文明が証明しています。聖霊は風のようにシェーカー教の間を吹き抜ける。彼らの信仰は少しのあいだ舞い上がりますが、風はその魂を乗せていってしまいます。
人と熱意は消え、過ぎていった風の記憶だけが残るのです」
彼の言葉はまるで心地よい鐘の音のようだった。私は神の国への道のりが脆く不完全であることに対する、自らの曖昧な不安を言葉にされたことに気づいた。「どうしてシェーカーの人々は進んであなたをここにいさせるのでしょう」
「シェーカー教にはいい教師というものはほとんどいませんから」と彼は言った。「だから彼らは外の世界に行く必要があった。私は高度な教育を受けていて、彼らが取り入れたいと思うシステムを知っています。それで推薦されて来ました」
「あなたはなぜ来たのですか?」それは差し出がましい質問だったかもしれない。しかし、彼は私に多くのことを遠慮なく信頼して話してくれたので、尋ねても差し支えないと思った。
彼は肩をすくめた。「正直、私にもわかりません。もしかすると、冒険心に駆られたのかもしれません。私はこの地方のことをよく耳にしてはいましたが、見たことはありませんでした。私は生まれながらに、じっとしていられないたちなのです。放浪癖があって」
「あなたはニューヨークで生まれたのですか?」
「私はロンドン生まれです。オックスフォードで、ジョン・ダンについて学びました」彼は微笑み、そうしてすぐに次の句を続けた。「私はその時も、冒険心に駆られてアメリカへ来ました。そこはまさしく新世界でした。私は常に後押しされ、駆り立てられていたように思います」
「だから結婚しなかったのですか」
彼は自分の手を見つめ、両手の指先を合わせて三角形を作った。「あるいは、愛する女性を見つけられていないがゆえかもしれません。ジョン・ダンの詩にあるほどのことを私に言わせてくれる愛に出合えていないのです。曰く、(4)『他の総てのものは、各々、滅亡に向かう。だた、僕等の愛だけは衰えない。これには、明日もなく、昨日もないのだ。推移しても、僕等から離れることはなく、まさに、最初の、最後の、永遠の一日を保つ』というような愛に」彼の声は詩を詠むごとにとてもゆっくりになり、また彼の視線は合わせた指に向けられていた。そうして彼は視線を持ち上げた。「けれど、私は半生でそのような愛を探し続けました。これ以下の愛では不十分なのです。どこかに逃げた愛など欲しくはないのです」
それは私もそうだった。しかし愛は、否応なしに逃げていった。
私はおもむろに立ち上がり、自分の本を取り上げた。これ以上彼から何も聞きたくなかった。彼もまた立ち上がり、そうして私を見下ろした。「このことをシスター・モリーに告げなければならないと思いますか、レベッカ?」
私は静かに首を横に振った。彼は笑った。「あなたはあまり良いシェーカー教徒ではありませんね、レベッカ」
私は震えた。「私はそうでありたいと思っています」私は答えた。
「なぜ?」彼はドアへ向かう私の前に立ち塞がった。
下階のシスター・ドルシーの部屋から聞こえていた音はずっと前に鳴り止んでいた。
「そうあらねばならないからです」私は言った。
「なぜそうあらねばならないのですか?」
「わかりません」 私はすすり泣いた。気分が悪かった。「通してください、ブラザー・ステファン」
彼はすぐさま端に避けた。「もちろんです。無作法な真似をしてすみません。もしあなたが本当に幸せなら……」
「もし私が本当に幸せなら、何ですか?」私は彼を見上げながら問いかけた。彼は私よりもとても高く見えた。
「私は何も言わなかったでしょう」
「なぜわかるのですか?」
「なぜならあなたが考えるから……そして、考えを持つ人は、ここでは誰一人幸せになどなれないからです」
「ならば私は考えることをやめます!」
彼は優しく言った。 「ああ、それでも、あなたはやめられない。それが厄介なのです……」
「やめてください」私は涙を流して逃げ出した。階段を駆け下り、外の安全な場所へと飛び出し、狭い石畳の道を通って頑丈なシェーカーの建物へと逃げた。私は震えながら深く息を吸った。私は彼のことを報告するべきだと自らに言い聞かせた。私たちからすると彼の考えは異端だったので、ここにいるべきではなかった。けれど、その異端な考えは私の考えでもあった! 私は悩んでいた。しばらくは誰ともいたくなかった。私は本を茂みの中に隠し、そして道を外れ鶏園へ向かった。私は、ヴィニーが雌鶏に餌をあげるのを手伝おうと思った。
しかし私の足は、傍らにある花の咲いた果樹園の中へ導かれた。よく晴れた五月の日だった。木々には花が満開に咲き、その花々から甘く強い香りがしていた。その香りに私は目を閉じ、深く息を吸った。芝は柔らかで、長く伸びていた。私は少しのあいだ、ここで横になろうと思った。気持ちを落ち着け、ブラザー・ステファンの異説を心から追い出そうとした。そうして心を入れ替えようと……何を入れ替えねばならないのか? 信仰心だろうか。信仰心などそもそも持っていたのだろうか? 熱情? 信条? 慰安? 純粋さ? 目的? 私はリンゴの木の下にある深い草むらに寝転んだ。伸びをして、手足を楽に投げ出し、そのまま少しのあいだ休んだ。
私はうとうとしたが長い眠りにはつかず、近づいてくる足音に気づいて体を起こした。
来たのはリチャードだった。彼は草むらの中で寝ている私に不意をつかれて驚き、慌てて立ち止まると私に話しかけてきた。「ここで何をしているんだ?」
答える代わりに、私は彼をまるで知らない人のように見つめた。実際、彼はほとんど知らない人のようになりかけていた。彼は冬のあいだに、非常にやせ細り、浅黒くなっていた。また顎ひげが顔を覆うほど伸びていた。それらもあいまって、彼は本当に他人のようだった。つばの広いシェーカーの帽子が、彼の頭に水平に乗っていた。その下から見える彼の瞳は、いつもと変わらず厳格で批判的であり、とても穏やかであるとは言えなかった。ミーティングでのみ、その瞳は喜びで輝いた。そこで彼は身を任せ、喜んでうたって踊り、聖霊に満たされるのであった。彼にとって日常の中には笑いも明るさもなかった。「リチャード、ここから逃げましょう」私は唐突にそう告げた。「私たちが共有していたすべてが失われる前に、逃げましょう。外での生活は素晴らしいものよ……そこに戻りましょうよ」
「気が触れたのか?」彼は私を見つめた。
「違うわ。自分自身を、心を見失っているのはあなたのほうじゃないの」
「黙れ」彼は言った。「僕の心は正常だ。少なくとも君よりはね。僕は絶対にここを離れない、君もそれをわかっているだろう。君と一緒にここを離れるなんて、誰か他の女性とそうするのと同じくらい考えられない。僕と君のあいだにはもう何の関係もないんだ。財産に固執するのはやめてくれ」
「土地のことでまだ怒っているの?」
「当たり前だろう。君が光明を見出すようにと祈ることもやめない」
私の心は荒んでいた。「私、あなたほど頑固じゃないわ」
「僕は君が教えることだって反対だ。学ぶことは危険なことだ。君が勉強なんてしなければよかった」彼はそう続けた。
私はスカートをはたいて立ち上がった。「けど、それはもうあなたには関係ないでしょう。
私たちのあいだには頑固さ以外には何もないのよ。だからあなたが何を考えているかは問題じゃない。私は教育を受けられて良かったと思っているし、それに教えることだって好きなの」
彼の唇は薄く一文字に引き結ばれていた。「レベッカ、君は傲慢にとらわれている。それは罪深いものだ」この瞬間、私は彼がシェーカー教徒であるにもかかわらず、夫として妻に言う通りにさせることに満足していると悟った。「あなたプリシーみたいね」と私は告げた。
彼は踵を返し、立ち去った。私は本を探し出し、イースト・ハウスのほうへと向かった。
私は彼に共にどこかへ去ることを頼まなければよかったと思った。私を突き動かしたものが何なのか、私にはわからなかった。しかしうまくいかないことは胸中で確信していたのかもしれない。私は二度と同じことをしないと自分に誓った。
私がイースト・ハウスに着いた時、そこは騒乱の最中にあった。中に入った瞬間に、私はその喧騒に気づいた。いつになくみんなが動揺して忙しくしていた。シスター・スーザンは取り乱し、スカートをたくし上げて歩き回っていた。またブラザー・サミュエルは極めて険しい表情をしてホールに立ち、待っていた。プリシーは忙しなく動き回り、粗末な皿の入ったバスケットや、状態の悪い擦り切れたキルト、脚が三本しかない机など、いくつかのものをホールの隅にまとめていた。私は寝室へ向かった。そこにはレイシーがいた。彼女はすすり泣きながら、服をまとめているところだった。「どうかしたの? 何かあったの?」私は尋ねた。
「ヘンリーが私たちを遠くにやるのよ」 エプロンの裾で目と鼻を拭いながら彼女は答えた。
「あなたたち全員? 子どもたちも?」
「私たち全員よ。一人残らず」 彼女はそう鼻をすすった。「ああ、ベッキー、私たちはこれまでに裕福な暮らしをしてはこなかったわ。それなのに、彼は行かねばならないと言うの。それで、私たちについてこいって言うのよ」
「それで、彼はすでにブラザー・サミュエルに言ったの?」
「すでに伝えたらしいわ。私の準備が出来次第すぐに出発するの。今、彼は子どもたちを迎えにいっているの」
「私がこれらをまとめておくわ。あなたは自分のことを」と私は言った。
私は彼女を慰めようとした。「レイシー、たぶんそんなに悪いことにはならないよ。
もう一度自分の居場所を見つけられる。あなたのしたいことができる。いちいち指図してくるプリシーもいないしね」私は彼女を笑わせようとした。
彼女は少し元気づいたようだった。 「プリシーがいちいち小言を浴びせてこないのは、たしかにいいわね」しかし、すぐに彼女は悲しみに沈んだ。「でも、また昔の暮らしに逆戻りだわ。食べ物も十分でなく、便利なものもなく、いつもぎりぎりでやっていくのだわ」
「そうはならないかもしれない。だってこれからはヘンリーも熱心に働くかもしれないから」
私は彼女の荷をまとめ、一緒に階段を降りた。ヘンリーが子どもたちを連れてきていた。子どもたちは何が起きているかはわからなかったけれど、ヘンリーの心配そうな顔から、何か計りしれないことが起きそうなのを悟った。「急いで」ヘンリーはレイシーに言った。
ブラザー・サミュエルはリストにチェックをつけた。「ブラザー・ヘンリー、君がここにくる時に持ってきたものを返します。それと、新しいスタートを切るために50ドルと馬を与えます」
「恩にきます」ヘンリーは言った。
「ここを去る人には誰でもそのようにしています。お礼はいりません。あなたは、たしかに出ていきたいんですね?」
「もちろんだ」 ヘンリーは歯を見せて笑った。「あれこれ指図されるのも、ずっと物を片付けたり、掃除したり、お利口にしてるのも、もう死んでもごめんだ。俺が求めるのはここから出ていって、また小屋の窓からトウモロコシのかすをぶん投げても、誰にも拾うように指図されない生活に戻ることだ」
「まずトウモロコシを手に入れられるようにならなければね、ヘンリー。まあ、よいでしょう。私たちはあなたにここを出ていくことを許可しますし、健闘をお祈りします」 ブラザー・サミュエルは冷たく言った。
「別に許可なんてなくても、勝手に出ていってやるよ。それにあんたらの祈りがなくても、俺はちゃんとやっていける」彼は子どもたちを外に出し、レイシーの背中に手を添え押しだした。
「これまで、こんなに束縛を受けたことはなかった。これからは俺の道を行くんだ」
私は、心や精神、魂は自由でなければなりません……というステファンの言葉を思い出した。心の貧しいと思っていたヘンリー・エイキンズでさえそう感じていたのだ。
プリシーは別れすら告げなかった。シスター・スーザンは、子どもたちが親についていく哀れな姿を、そしてレイシーが最後に振り返り手を振っている姿を見て大泣きしていた。「ヘンリーでは彼らを養えないわ。彼らは飢えてしまう」と彼女は言った。
ブラザー・サミュエルはドアからこちらを向いた。彼らは戻ってくる、と彼は言った。
「冬が来たら、彼らは戻ってくるでしょう。暖かい季節のうちはなんとかやっていくでしょう。しかし、寒風吹きすさぶようになれば、暖かい場所と食べ物を求めて戻ってくるでしょう。彼らはよい(5)ウィンター・シェーカー(winter Shakers)です」 彼は強く言った。
しかし彼は間違っていた。ヘンリーとレイシーは戻ってこなかった。私の知る限りでは、彼は誰に止められることもなくトウモロコシの食べかすを小屋の窓から放り投げられるような生活を満喫しているようだった。私は彼の気持ちがとてもよくわかった。
その夜、私たちはレイシーがいないことを寂しく思った。彼女は太っていて怠惰だったけれども、気立てが良くて私たちの大事な仲間の一人に違いなかった。彼女のベッドが空いているのは不思議な感じがした。
「代わりに誰か入ってくるのかしら?」パルミラは尋ねた。
「新しい人が来るまでは、ないと思うわ」とアマンダは言った。
「慣れるまで時間がかかるし、しばらく新しい人なんていらないわね。私たちがここで得た最高のものはこの部屋でお互いが慣れ親しんでいることね。もし私たちとうまく一緒にやっていけない人がきたら、ここはひどいことになるでしょうね」彼女はベッドにばったり倒れて休んだ。「ああ、疲れたわ」
「今日は何をしていたの?」私は尋ねた。
「かぼちゃとトウモロコシを植えたわ。今月はガーデニングの担当なの。文句はないわ。気分転換に外に出るのは良いことね。夏のあいだは毎月ガーデニングの担当になれたらいいのにと思う。ここはいい土地よ、ベッキー。男たちがよく耕してくれているし、ここで働けるのは嬉しい」彼女は腕を頭の後ろで組んで、目を閉じて横になった。ほどなく彼女は眠りについた。
翌朝、ファミリー・ミーティングの鐘が鳴った。センター・ハウスの頂上の鐘の響きは落ち着いていて、この音は私がこのヴィレッジで最も好きなものの一つだった。鐘の音は時計よりも美しく時間を刻んだ。
私たちは上階に上がりミーティング・ルームの席に着いた。私たちはブラザー・ベンジャミンが担当であることに驚いた。彼は新聞紙を手にしていた。お祈りと讃美歌が終わるとすぐに部屋の中央に歩み出て新聞を広げた。「俗世の出来事を考慮しなければいけないことは稀ですが、ソサエティ全体が知らなければならないことが起きました」と彼は言った。
彼は眼鏡をかけて読み始めた。「三日前、議会は結婚相手がビリーバーズの一員である時に、それを離婚の根拠とする法律を制定しました。法律では、そのような離婚を望んでいる人は誰でも申請するだけで、公正な財産権と未成年の子どもの親権が共に認められることになりました」
それを聞いて私たちは唖然とした。シェーカーは恥と嫌悪の象徴として法律的に指摘されてしまった。読み終わるにつれブラザー・ベンジャミンの声は震えた。読み終えた彼は、新聞を平手で打った。「ああ、ケンタッキー! 気高きケンタッキーよ。なんという法律を作ってしまったのだ!」
辺りは騒然としだした。私たちは動揺を隠せなかった。少しして、ブラザー・ベンジャミンは私たちに鎮まるよう言った。「これは一つの迫害に過ぎない。私たちは、迫害を受けるたびに強くなる。それゆえ、これは快く受け入れるべきだろう。今夜は、喜びと、信仰、熱意を持って労働に出向きなさい。マザー・アンの名において、迫害されていることに感謝しなさい。私たちが彼女の子であることを喜びなさい。私たちは彼女の名のもとでは何にでも耐えることができるのです」そして、彼は立ち去った。きっと、新聞のことを他のファミリーに伝えにいくのだと思った。
ブラザー・サミュエルは私たちをダンスに導こうと立ち上がった。しかし、彼が合図を出す間もなく、リチャードが立ち上がった。「我々の中に恥ずべき者がいる。私はシスター・レベッカのうぬぼれや傲慢、信仰心と情熱の欠如を非難する……」彼は一息ついた。彼はこのあと、私が彼を誘惑したことを告発するだろうと思った。しかし、彼は顔が蒼白として、まるで病気であるかのように突然脚を震わせ、硬直して座った。
私のそばでパルミラが声を振り絞って言った。 「いえ、私は非難しない!」
みんなの目が私に向けられた。シスター・プリシラの目には、たしかに勝利の輝きがあった。
ブラザー・サミュエルは私に起立するように言った。「ブラザー・リチャード、どのような理由でシスター・レベッカはうぬぼれと傲慢の罪で非難を受けるのですか」
リチャードもまた私を凝視していた。その目は冷ややかだった。「私は彼女が進んで正会員になろうとしないことや、献身的な奉仕を拒否することにおいて彼女を非難したい。そして、彼女が魂の救いよりも物質的なものを保持することにおいても」
「恐ろしや」プリシーが大声で言った。すると、他の人も口をそろえて騒ぎだした。この時の私の気持ちは、部屋の真ん中に立たされて恥と軽蔑の言葉を浴びせられる経験をしない限り、わからないものだと思う。それはぞっとするような経験だった。しかも、ほかならぬ夫がもたらしたものだったのだから、私にはさらに辛かった。自分が正会員になりたいがゆえに、こんなことをしてまで私に正会員になることを強要できるなんて、信じられなかった。
しかし、彼のこの行為がこの上なく私を頑固にした。初め、私に突き刺さっていた言葉が、だんだんと単なる音になってきて、耳に入ってきても、もはや心には響かなくなった。この時、私はこの渦中で、自分が本当にうぬぼれと傲慢で罪深いことを悟り、毅然として立っていた。私の中で傲慢さが、この屈辱を跳ねよける傲慢さが、湧き上がってきた。皆の面前で屈辱を受け、口撃に晒されながらも、私はこの屈辱のうちに、このことだけは永遠にリチャードを受け入れられないと決めた。その中に反発心があれば、もしかすると私は赦されるかもしれない。私はとても傷ついた。リチャードの行いが慎重に計画されて実行されたゆえに、本当に傷ついた。「僕は君を傷つけたくない」と彼は言ったことがある。しかし、彼は私を傷つけたいと思っていた。心の中では、リチャードの傲慢さのほうが、私より罪深いと思った。いや、そうではないかもしれない。彼は単に自分を保つために、もはやなんの考えもなく、献身への願いと必要だけで狂信的になったのかもしれない。
中央に立って、周囲の声を聞きながら、たとえそれが彼らの求める霊的な恵みであるのだとしても、狂信者たちは常に残酷で、自己中心的で自分勝手なのだと気づいた。結局、リチャードと他の人とのあいだには、ほとんど違いがないと思った。人は皆、自分自身のために大きな幸せを手に入れようと思っている。ある人は、商いや政治で豊かさを求める。また、ある人は精神的な部分で豊かさを求める。違いはなんだろう?
ブラザー・サミュエルは優しかった。彼は喚声をやめるように呼びかけ、「私たちは皆平等に罪を犯している。ひざまずき祈ろう」と言った。それから彼は私たちをダンスに導いた。リチャードは一番激しく踊った。ワーリング・ギフトを授かったり、シングル・ダンスをしたり、輪から出てスピンしたりと、聖霊に取り憑かれたかのようだった。彼のギフトは尊敬されていた。しかし、もし彼がヴィジョンを見たのだとしても、今夜はそれについては話さなかった。最後には、彼は私を非難した時と同じくらい白くなり震えていた。彼の顔には悲しみしかなかった。人に感情があり、悲しみを感じられる限り、ある目的を純粋に遂行することなど不可能だ。
階下の部屋に戻ると、私に同情して何人かが寄り集まっていた。「ベッキー、この部屋の人たちは何も言わなかったわ」とパルミラは言った。「この部屋の人は誰も『恐ろしや』とは言わなかった。残念だし、気の毒だったわ。あんたの男をひっぱたいてやりたい」彼女は憤慨して言った。
ほんとうに、残念で気の毒に違いなかった。
第16章訳註
(1)対訳出典:高木登「ジョン・ダン全詩集訳」
(2)トーマス・エガートン卿(Sir Thomas Egerton, 1540-1614)
イングランドの貴族で、法廷弁護士として司法職で出世し、庶民院議員も務めたのち、1596年から1617年にかけて大法官及び国璽尚書(こくじしょうしょ)を務めた。彼自身もオックスフォード大学の出身であり、その後リンカーン法曹院で学んでいる。
(3) ブラックリー子爵
イングランドの子爵位。第一代はトーマス・エガートンである。
(4) 対訳出典:高木登「ジョン・ダン全詩集訳」
(5) ウィンター・シェーカー(Winter Shakers)
冬の寒い期間のみシェーカー教に入信した教徒。シェーカー教は本人の意思を尊重し、入信と脱退を自由に選択できる仕組みを取ったため、ウィンター・シェーカーはにわか信者として冬の期間の食料と住居を目的として一時的に共同体に滞在した。