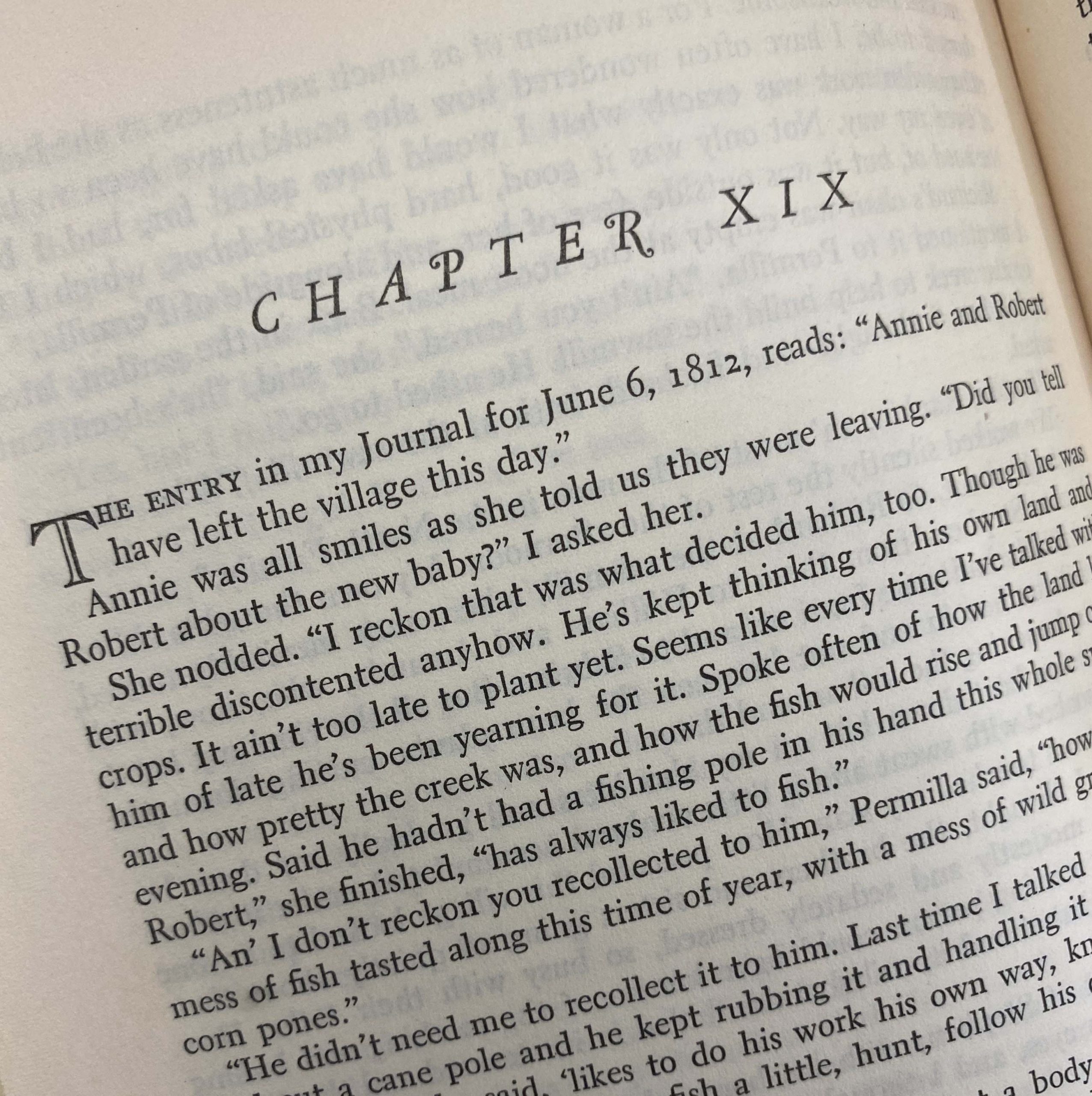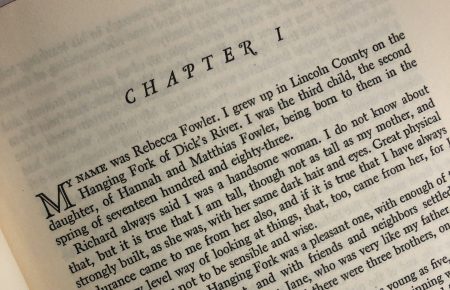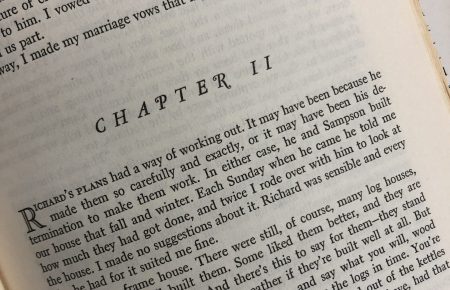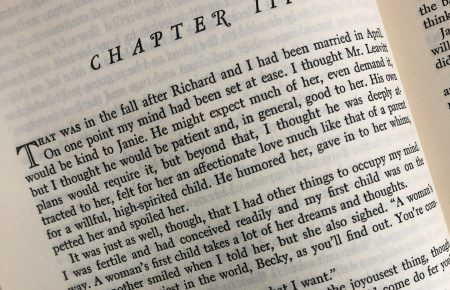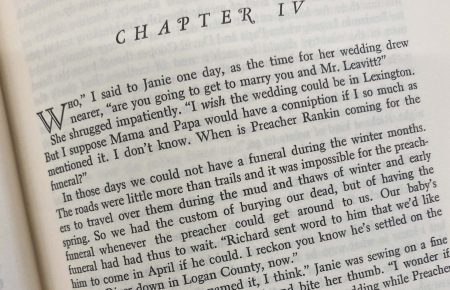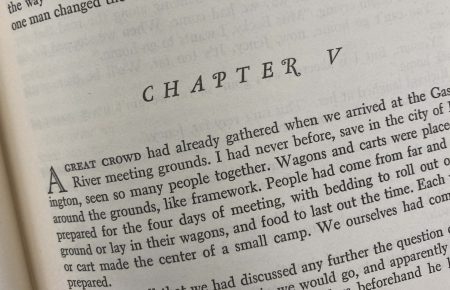一八一二年の六月の日記の書き出しは、こうだった。『今日、アニーとロバートがヴィレッジを出て行った』
アニーは私たちにここを離れるのだと話すあいだ、終始笑顔だった。「赤ちゃんのことをロバートには言ったの?」私は尋ねた。
彼女はうなずいた。「それもあって、あの人の決心がついたんだと思う。ひどく不機嫌だったけれど。自分の土地と作物のことばかり考えているの。まだ作付けには間に合う時期だって。最近あの人と話すたび、その話ばかりだった。どんな土地で、小川がいかに素敵で、晩には魚がどんなふうに浮かび跳ね回るかをしょっちゅう話すのよ。今春はずっと釣り竿を持たなかった、とも。ロバートは、ずっと釣りが好きなの」とアニーは締めくくった。
「青菜とトウモロコシパンと一緒に食べるこの時期の魚がどれだけおいしいかは、思い出させなかったんじゃないの」とパルミラは言った。
「私が思い出させる必要はなかった。最後に彼と話した時、彼、話のあいだじゅう釣り竿を作っていたの。『男ってのは、自分の仕事を自分のやり方でやるのが好きなもんだ。その仕事を自分のものにして、好きな時に休みをとったり、ちょっと釣りをしたり、狩りをしたりして、自分のやりたいようにするのが』だって」
「それであなたは何て言ったの?」
「私はずっとそう思ってた、自由に生きることが何より大切だ、って言った。それから、赤ちゃんができたことを言ったの。それを聞いてすぐに彼は決心して言った、ここを出ようって」彼女は元気にうなずいた。「ブラザー・ベンジャミンにはもう話したみたい。午前中にはここを出る」
私たちはそれぞれの仕事が忙しかったので、彼らが出ていくところを見なかった。私たちは翌朝アニーに別れを告げた。皆それぞれが彼女の出発を喜んで、幸運を願った。規約に違わず、彼らの持ち物すべてと、彼らの土地、家、家畜と設備をシェーカーに帰属させる同意書が返された。私たちはあとになって、彼らがヴィレッジで暮らしているあいだに彼らの土地で生まれた仔馬と仔牛をめぐって、アニーがブラザー・ベンジャミンと揉めたことを知ったが、どこまでが本当の話なのかはわからなかった。シェーカーは、仔馬と仔牛は自分たちのものだと考えていたのだろう。ロバートの土地で育つトウモロコシ以外には、仔馬も仔牛も彼のものとみなされなかったようだ。
アニーは他に着るものがなかったため、シェーカーのドレスを着ていった。だが、昨日の朝、足元でそのドレスの裾を振り払いながら彼女は笑っていた。「もうすぐこのさえないドレスとおさらばできる! 家に帰ったら、まず何か素敵な服を買うわ。華やかでひだつきの、リボンとレースのついたものをね。ずっと諦めてきた、素敵なものたちが欲しくてたまらない」
「一張羅を着て、会いにきてちょうだいね」とパルミラが言った。
アニーは首を振った。「またここに来ようとは思ってない。もし私のリボンとレースの服が見たかったら、あなたが会いにこなきゃ」
プリシーはその日じゅう、唇を固く引き結んで過ごしていた。「(1)地獄の炎が二人を包む時、救いの道に背いたことを後悔するでしょうね」と彼女は言った。
「もしかしたら、他にも救済の方法はあるのかもしれませんよ」と、私ははっきりと言った。
彼女は怒ったように私を見た。「マザー・アンの方法しかありません、レベッカ」
だが、私は今まで一度もそれを確信したことはないし、マザー・アンの方法にはますます満足いかなくなっていた。私は、ステファンが言っていたことについて考えた。私には、そちらのほうがはるかに理解できた。もしかしたら、子どもが起こす発作のようなもので、彼女はこれほど狂信的になっているのではないかと思った。「(2)神が望むのは、我々が謙虚に歩み、公正にふるまうことだけです」と私は言った。
「私に聖書を説かないでくださるかしら!」プリシーは言った。「聖書は最初から最後まで知り尽くしていますし、暗記しています」
もしそうだったら、そんなふうには振る舞わないだろうに、と思った。プリシーはエルドレスではなかった。彼女の熱意と手際をもってしても、彼女がエルドレスになれるかどうかはわからないだろう。エルダーとエルドレスの役職は死亡、あるいは不正行為によってしか解任されないため、シェーカーはそれらの任命を頻繁には行わなかった。ブラザー・ベンジャミンとシスター・モリーはその年に任命されたばかりだった。任命には長い時間をかけて、正当に評価をしなければならず、責任ある役職に任命される人はたいてい謙虚で、善良で、寛大なだけでなくまじめだった。マザー・ルーシーは、プリシーの行いを彼女を任命するまでずっと、長いあいだ見ていくのだと思った。彼女の手際よさ、恍惚状態やヴィジョンを受ける様子、イースト・ハウスでの絶え間ない軋轢、ちょっとした不平や、規則違反の報告と処罰の騒ぎの様子までも把握しているに違いないだろう。いや、たとえシスター・プリシラがどんなにそう望んで、そのために努めたとしても、彼女は決してエルドレスにはなれないだろうと、私は確信していた。
ジェンシーが脱走したのは、その数日後のことだった。
いつも通り、私にその報告をしにきたのはカッシーだった。彼女は新鮮な飲み水を手に庭へやってきて、私にひょうたん容器いっぱいに手渡した。「ベッキーさん、ジェンシーが逃げだしました」彼女は、私がそれを飲むのを待ちながら言った。「きっとあの混血の子と駆け落ちしたんだと思います」彼女の声音には悲しみが滲んでいたが、悲痛さはなかった。「もしかしたら、これでよかったのかもしれません」
私は残りの飲み水を地面に捨て、容器を彼女に手渡した。「彼女は自由なのよ、カッシー。彼女がそう望むなら、クレイトンと駆け落ちしたっていいの。誰も彼女を止めることはできないし、今は彼女にとってそうするのが一番だと思う。あなたには駆け落ちすることを話していたの?」
「いいえ。ジェンシーのことですから。彼女はただ出ていったんです、夜中に。」
「それじゃあ、クレイトンのところに行ったのかどうかを確かめたほうがよさそうね。それと、リチャードは彼女に書類を渡せるから。そうなるよう取り計らうわ、カッシー」
「わかりました。あなたならそうしてくれるだろうと思いました。アマンダさんは彼女によくしてくれると思いますか?」
アマンダが私とはまったく異なった人だということは、否定のしようがなかった。彼女はジェンシーの気まぐれさにほとんど耐えられないだろうし、彼女により多くの仕事を強要するかもしれないが、ただそれだけで、理解はあると思った。アマンダは人道的だった。彼女は奴隷が自分に報いないからといって、虐待するようなことはしないだろう。私はジェンシーが虐待されることはないだろうと考え、そう答えた。
カッシーはため息をつきながら去っていった。彼女は近頃、まるで生活が徐々に耐え難いほど苦しくなっているかのように、よくため息をついていた。彼女は昔はうたいながら仕事にとりかかるような陽気な女性だったので、気の毒に思った。
だが、ジェンシーのことについては私は嬉しかった。彼女はついに、おそらくはクレイトンと結婚して落ち着いて、たくさん子どもを育てて、幸せな人生を過ごすのだろう。シェーカー・ヴィレッジは彼女に合った場所ではなく、ここでは良いことはない。彼女がクレイトンのところへ行けることを嬉しく思った。
アマンダに手紙を書かなければ。そして、ジェンシーは自由の身であると伝えて、結婚を許してジェンシーとクレイトンが一緒になれるように頼もうと思った。私は、彼女は何の出費もなく人手を増やせるし、二人の子どもはそのうち彼女にとっても貴重なものになるだろうから、きっと同意してくれるだろうと思った。
だが、まずはリチャードに会わなければいけない。ジェンシーの書類を手配しなければ。彼はその週ずっと製材所にいたが、男性たちは日曜日には礼拝のために帰ってくる。そうしたら、彼に相談をしようと思った。
だから、そのことを心の内で整理して、熟考して、決断して、ジェンシーの人生が変わったことを喜んだ。
しかし、リチャードはジェンシーに書類を渡さなかった。形式上だけのものだと思っていたのに。私は彼との面会を願い出た。ブラザー・ベンジャミンは朝の礼拝から、男性が製材所に戻るまでのあいだに面会を認めた。もちろん、ブラザー・ベンジャミンの立ち会いのもとで面会した。「ジェンシーが、クレイトンと駆け落ちしたの。解放の書類を必要としている」
リチャードは、かつて私の夫だった男性とは完全に見違えていた。彼は今ややつれて、髭に覆われたこけた顔から覗く彼の目は狂信的に燃えていた。口元は、神経性の痙攣でほとんど常にピクピクしていた。彼はそれを止めることができないか、止めようとしていないようだったので、まったくそれに気づいていないのだと思った。
彼は何も言わずにずっとこちらを見ているので、私の話が聞こえていたとしたら彼は何を考えているのだろうか、と思った。「ジェンシーが」と私は再び話し始めたが、彼はそれを手で遮った。「わかった。彼女はヴィレッジを出たのか?」
「ええ。彼女はクレイトンと愛し合っていて、彼と一緒にアマンダとウィリアムのところで暮らしたがっているの」
「彼女を連れ戻さなければ」彼はぶっきらぼうに言った。
「そんな、なぜ? 彼女は自由の身よ。以前あなたは彼女に書類を渡したじゃない」
「渡したけれど彼女はそれを破った。別の書類が用意できるまでは、彼女は自由じゃない。僕は、彼女を解放して罪の中で生きさせるつもりはない。罪を抱えた人間と一緒に暮らす自由は与えない。決して、彼女に自由は与えない。彼女を連れ戻さなければ」
彼は本気でそう言っていて、彼の意思を曲げることはできないようだった。彼が強く感じた思いを曲げられた試しがなかった。私は呆然とした。これは予想外だった。何の気なしに、彼女が必要とすればいつでも書類を用意し直すという約束を、彼は守ってくれるものとばかり思っていた。私はブラザー・ベンジャミンにも掛け合った。「リチャードは、ジェンシー次第で彼女を解放すると約束していました。約束を違えるのは不誠実です」
ブラザー・ベンジャミンは組んだ手を見つめていた。「これがリチャードの決断です、レベッカ。残念ですが、私はリチャードの意見を支持したいと思います」
怒りが湧き上がったが、それはリチャードが初めて私にシェーカーに入りたいと打ち明けた時と同じ類の、拳を震わせるような冷ややかな怒りだった。私はリチャードに向き直った。「あなたがそう言ったって、ジェンシーを連れ戻すことはできない! 彼女はもうクレイトンと行ってしまったのだから。彼女は今、赤ちゃんを宿しているわ。彼女を自由にしてあげて、リチャード。彼女を行かせてあげて。彼女を連れ戻してもいいことはない。また脱走するだけよ。何度も、何度も。あなたも私と同じくらい、彼女のことがわかっているでしょう。彼女は思い通りにならないって。彼女を連れ戻しても、トラブルしか起こらないのよ」
リチャードの瞳は燃え上がり、そして曇った。「思い通りにならないのは君もじゃないか?」彼の口元が痙攣でピクピクした。「君はジェンシーと同じくらいわがままだな!」彼は前のめりになりながら私に言葉を吐きかけた。
私は彼をじっと見つめ、彼に答えた。「私は傷つかないわ、リチャード。あなたがなんと言おうと、もう私を傷つけることはできない。もし私がわがままなら、そうなのよ。その話はそれで終わり。でも、ジェンシーのことにまで癇癪を起こさないでちょうだい。あなたは彼女に本当に間違ったことをしている。私のことは忘れてもいいけれど、ジェンシーとの約束は守りなさい」
彼は肩をすくめた。「それは覚えているさ。でも、状況が変わったんだ。もし彼女がすでに罪を犯しているならなおさら、これ以上罪を犯さないように連れ戻さなければいけないじゃないか」
「四六時中、ジェンシーのことを見ていられると思うの?」私はかっとなって言った。
「いいや。でも、拘束しておけばいいじゃないか」
私は自分の耳を疑った。「あなたがそうするの?」
「それが彼女の魂のためになるなら」
「なんのためにもならないわ。」私は彼に怒鳴った。「あなたのうぬぼれと、自己満足以外には。あなたにそんな権利はない。あなたは神じゃないのだから!」
「僕は神じゃない。でもジェンシーの主人だ。彼女にとって何が最適かは僕が決める」
もし嘆願してどうにかできるのであれば、私は彼にそうしていただろう。だが、彼の考えが揺らがないだろうことは十分わかっていた。私はブラザー・ベンジャミンに対話を終える許しを乞いた。彼は了承して、「きっと大丈夫ですよ、レベッカ。神は見ておられますから」と言った。敬虔さの名の下に悪事が行われるなんて!
「では、そうしたほうがいいですね」と、私は苦々しく言った。
リチャードはウィリアムの畑に馬で向かい、泣いているジェンシーを連れ帰ってきた。日曜日でもセスと会う方法を見つけたパルミラは、私のところに来て言った。「かわいそうに、泣いてたよ」
「リチャードのいないあいだに、彼女に会いに行くわ」
「彼は本当に彼女を拘束すると思う?」
「わからない」私はげんなりしながら答えた。「彼のすることはもう予測できない。彼はそうするかもしれない。でも、逃してあげられるはず」
「私も一緒に行く」と彼女は申し出た。「手伝いが必要かもしれないし」
「大丈夫。必要であれば助けを求めにくるわ」
ヴィニーは窓の外を見ていた。「彼が出ていったよ、ベッキー」と彼女は言った。「ちょうどセンター・ハウスに向かっていったところ」
私は窓辺に覗きにいった。彼がセンター・ハウスに入ったら、ジェンシーのところに行こうと思った。リチャードから一瞬目を離した時、カッシーがこっそりとヴィレッジの端の森のそばにあるブラック・ハウスへ向かう姿が見えた。彼女は、娘の件を聞きつけて会いにいくのだとわかった。また、森の端の茂みに身をかがめている男の姿が見えた。彼は急に立ち、まわりを見回してからドアに向かって駆けていった。クレイトンも、ジェンシーのもとへ向かっているのだ。私は微笑んだ。リチャードにクレイトンとジェンシーを引き離すことはできない。
私が着いた時、建物には三人しかおらず、彼らは火のない暖炉の前に座り、うめき声を上げていた。カッシーはジェンシーを抱いて彼女の体を前後に揺らし、クレイトンは顔が膝につくまで膝を抱えて座り、体を揺らしていた。だが、ジェンシーは縛られてはいなかった。私が部屋に入ると彼女は顔をあげた。その顔は泣き腫らしていて、私を見るとまた泣きだした。彼女はカッシーの腕から抜け出て今度は私の腰元に抱き着くように膝からくずれた。「ああ、ミス・ベッキー、ミスター・リチャードは私がクレイトンと一緒に暮らすことを許してくれません! ここに居なきゃだめだと言います。私は自由ではないし、また逃げだしたら拘束すると。何とかしてください、ミス・ベッキー!
助けて!」
「みんな落ち着いて」私はジェンシーを立ち上がらせて言った。「泣いてもうめいても何も変わらない。なんとかしましょう。約束する」
「どういうことですか?」カッシーはすすり泣きをやめ、私を見て尋ねた。「どうするつもりなんですか?」
「まだわからないけれど、何か考えるわ。何か方法があるはず。きっと見つける」
「ミスター・リチャードの言う通りですよ、ミス・ベッキー」カッシーは悲しげに言った。「彼は新しい書類を作成する必要はありません。ミス・ベティアは私やサンプソンと同じようにジェンシーを彼に譲りました。彼はジェンシーを解放しなくていいんです」
ベティア! 私の頭にかすかに光が差した。たしかに、デイヴィッドとベティアは私たちにカッシーとサンプソンとジェンシーをくれた。だが、もし彼らが奴隷の移籍に関する法的な書類を作っていたとしても、私はそれを見たことがなかった。書類は一枚も書かれていないのかもしれない。リチャードは、デイヴィッドから口頭で言われただけで、三人の所有権を証明するものは何も持っていないかもしれない。おそらくこれこそが解決への道だ。「何をすべきかはわかった」私は言った。「でも最初にそれを確かめなければいけない。クレイトン、ミス・アマンダのところに戻って。二度とここには戻ってこないで、離れていなさい」「ジェンシー、あなたはここにいて、大人しくしていて。縛られたくなかったら、言われた通りにしなさい。逃げたり、クレイトンに会おうとはしないで。わかった?」
「はい……わかりました。私はここでいい子にしています。私が逃げられるまでどのくらいの時間がかかると思いますか?」
「わからないけど、二、三週間はかかるかもしれない。でも解決への道は見つけたわ。どれだけ時間がかかっても、あなたはここにいるのよ。ここにいるのがどんなに辛くても、逃げ出してはだめ。この計画をうまくいかせるには、あなたがここにいないとだめなの」
クレイトンは立ち上がった。「今すぐ行くべきですか、ミス・ベッキー」
「今すぐよ。あなたがここにいることを誰も知らないうちに」
「わかりました」
彼はジェンシーの肩に手を置いた。「ミス・ベッキーの言われた通りにやるんだよ、ジェンシー。僕たちが一緒にいられるよう、きっと彼女がどうにかしてくれるからね」
そして彼は去っていった。
他の黒人たちが部屋に戻り始めた。一人ずつ、そっとしのび入るように。リチャードはおそらく彼ら全員をこわがらせたのだと私は思った。彼らは影のようにひらひらと揺れながら消えていった。だが、彼らは信頼できるということはわかっていた。彼らは一心同体で、ジェンシーに共感し、行動するだろう。私は彼らに、ジェンシーに優しくし、協力するように頼んだ。彼らは黙ってうなずいた。「毎日連絡して」と私は言った。「毎日来ることはできないけれど、彼女の状況を把握したいの。彼女を見張って、逃がさないで」
ジェンシーは笑った。「逃げるつもりはありません、ミス・ベッキー」
しかし、ジェンシーの約束が何を意味しているのか、私はよく知っていた。彼女は考えなしに、盲目的に自分の直感に従って、森で蝶々を追いかけるように、私たちが知るより早く、アマンダのところへ行くことができるだろう。
小屋を出て牧草地をゆっくりと横切った。まるで何かが私の歩みをスクール・ハウスのそばを通る道へと運んでいるようだった。私も、ジェンシーのように考えなしに、自分の直感に従った。子どもたちや教室のことを寂しく思ったけれども、ジェンシーのことが頭にあって、気づかぬうちにスクール・ハウスに通じる道に辿り着いていた。自分が今いる場所に気づいて、私は中へ入ろうと決心した。私はただもう一度教室に入りたかった。そして、壁の向こうで教えを復唱する子どもたちの声の響きに耳を傾け、かつて私のものだった何かに少し勇気づけられたかった。
私は疲労と、苦悩と、惨めなまでの孤独を感じながら、ゆっくりと階段を上って教室へと向かった。ドアを開けようと、私は木製のノブに手をかけた。それは、シェーカーが作った他のすべてのものと同様に、丁寧に旋盤で削られ、磨かれていた。シェーカー以上の職人は世界のどこにもいない。彼らは美しさを意図していなかったが、とても注意深く、実用的に作ったものはどれも、シンプルさと細部へのこだわりによる独自の美しさを持っていた。
手の中に木の質感を感じると同時に、孤独感に圧倒され、ドアに背を向けかけた。しかし、ノブは簡単に回り、ドアが開いた。
ステファンが私の机に座っていた。彼は本を目の前に開いて、肘をその両横についていたが、私が近づく音を聞いて、ドアの方を向いた。「ベッキー!」と彼が言った。椅子を後ろに押しやって、手を伸ばしながら私に向かって歩いてきた。
彼と抱擁すると、泣きそうになるほどの強い安心感が込み上げた。彼のほっそりとした、学者のような手は温かく、私の手をしっかりと握った。私には味方がいるのだ! 「ステファン、ステファン」私は言った。「あなたにどんなに会いたかったことか。助けてほしいのです」
彼は私に椅子を用意し、私のテーブルの後ろに再び座った。事情を教えてほしいと彼は単刀直入に言った。
私はこの悲惨な事情をすべて彼に話し、これからどうするつもりかも打ち明けた。「もしデイヴィッドとベティアが奴隷たちをリチャードに譲る書類を作成していないなら、その書類を今すぐ書いてもらえるのはほぼ確実です。そうすれば、リチャードの許可なしにジェンシーを解放することもできます」
彼はうなずいて言った「誰かすぐにでも伝える人が必要です。郵便では遅すぎます。私が馬を用意して、すぐに出発しましょう」彼は立ち上がった。
「あなたが? どうやって馬を手に入れるのです?」
彼は笑った。「私がシェーカー教徒ではないことを忘れていますね。私は自分の馬を持っています。私の馬は他の馬と一緒に牧場にいますが、シェーカーのものではありません。一日でそこまで行って、もう一日で帰ってこられます」
私は彼の案について考えてみた。「でも、彼らの耳には入るでしょう」と私は言った。「彼らはあなたがやったことを知ってしまいます」
「そうですね。彼らは知るでしょう。帰ったら自分で伝えるつもりです」
「そうすれば、彼らはあなたを追放するでしょう。遠くへ」と私は言った。
彼は無意識に耳にかかった髪を触った。私の視線がその手をたどって彼の昔からの癖を見て笑っていることに気づいて、手を下ろして微笑み返した。
「あなたにとって、何か問題でしょうか?」
「あなたがここから去ることですか。もちろんです! 私たちはこの学校をどうすればいいですか? 誰が子どもたちを教えるのですか。誰が私たちを導いてくれますか」
彼の顔から微笑みが消え、彼は視線を私の後ろの窓へと移した。「他の教師もいるでしょう。そして他の指導者も、代えのきかない人など居ませんよ」
「あなたの代わりはいません」私はすぐに言った。「あなたがいなければだめだわ。私一人で行けます、ステファン! あなたが馬を貸してくれたら、あなたと同じくらい早く行ってこられます」
「そうしたら、あなたが追放されるかもしれませんよ」
私は首を振った。「それはありません。リチャードがここにいる限り、そして私がここにいたいと望む限り、彼らに私を追放することはできません。だから私がいかなければなりません、ステファン。今、今すぐにです! 馬をここに連れてきてください。イースト・ハウスに帰るつもりもありませんから」
「(3)横鞍はないですよ」とステファンは笑いながら告げた。
「私が横鞍で馬に乗る方法を学んだと思いますか。ステファン、馬を貸してください」
「落ち着きましょう、ベッキー。長い道のりで、途中に宿もないですよ」
「必要ありません。止まらずに走り続けても大丈夫です。農場もあるので食べ物を得ることもできます。大丈夫です、ステファン」
彼は長いこと考えこんでいた。私は彼の思考を妨げないように、じっと押し黙って待っていた。とうとう彼は言った。「いいえ、女性一人ではあまりに危険です。道のりもとても大変でしょう。考えてみたのですが、ベッキー、町に私の友人がいます。弁護士です。お互いに本が好きなのです。私は彼の本を借りて、彼は私の本を借りました。彼を信頼してもらえますか」
「あなたは彼のことを信頼していますか?」
「はい。彼は信頼できると思います。誰か遣いを見つけることも、あるいは彼自身が行くこともできるでしょう。あなたが望むなら、すぐに彼に会いにいきましょう。」
「ええ、お願いします。あなたがどうしても自分で行こうとするのではないかと心配でした」
「いいえ。私たちのどちらも行かないほうがよいでしょう。そうすれば、咎められないでしょうから。リチャードは警告されるかもしれませんし、そして、私はまだサウス・ユニオンを離れたくありません。ここにはやるべきことも、残る理由もあります」彼は手を振った。「でも、それは大きなことではありません。私が馬をとってくるあいだに、デイヴィッドとベティアへの伝言を書いておいてください。私がジャクソンに届けましょう。日没までには彼は出発するでしょう」
彼は出し抜けに部屋を出た。私は机の引き出しから紙を取りだし、ペンと自家製のインクを出して、べティアに宛ててすべての事情を手紙に記した。すべてがうまくいく感じがした。そして、ステファンがシェーカーとのトラブルに巻き込まれない方法を見つけたと安堵した。
第19章訳註
(1) 地獄の炎 “描写があるもの
物を焼き尽くす火は罪や汚れを浄める力をもち、神の審判を象徴する。これは永遠のひが燃える地獄の表象に引き継がれた。
(2) ミカ書6:8 人よ、何が善であり主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛しへりくだって神と共に歩むこと、これである。
(3) 横鞍はない
横鞍はないということは、馬を跨いで乗らなければならない、ということ。