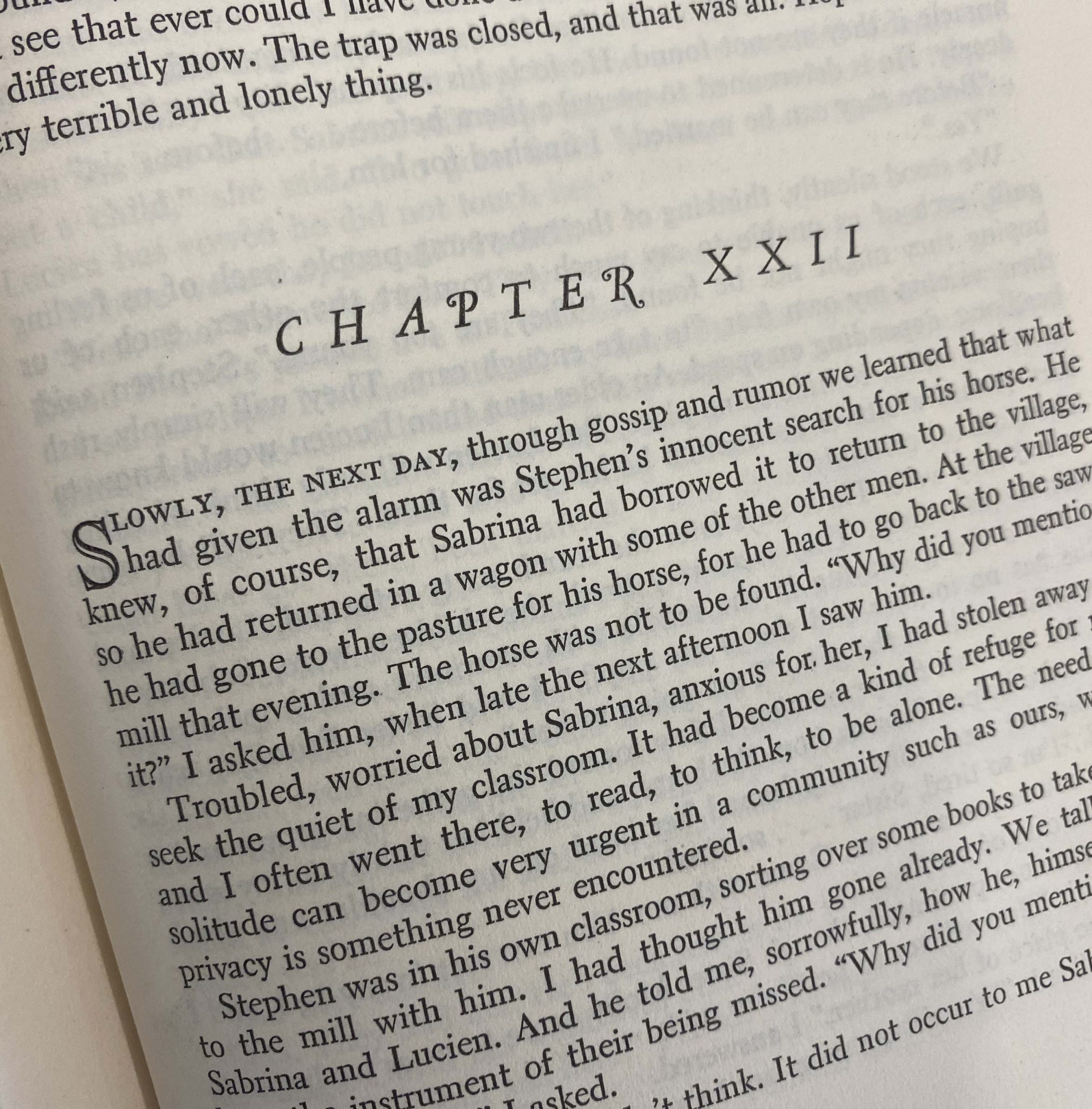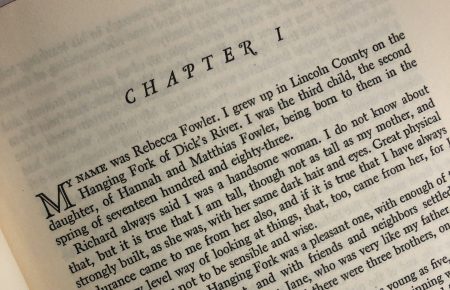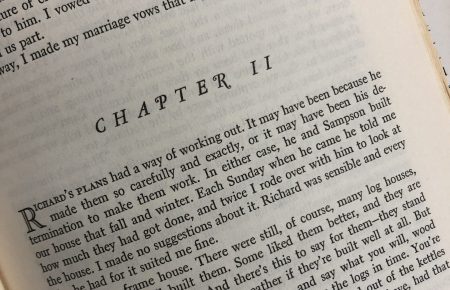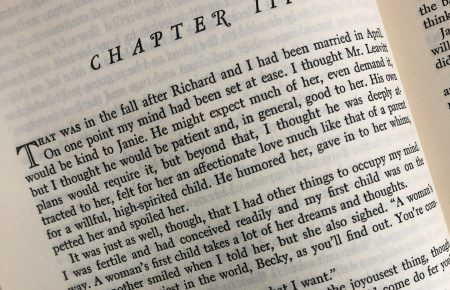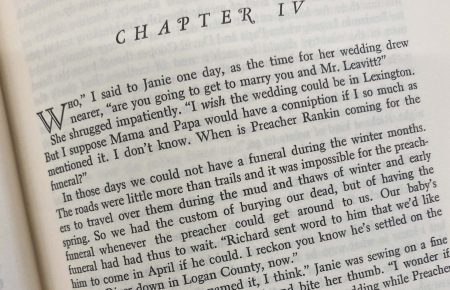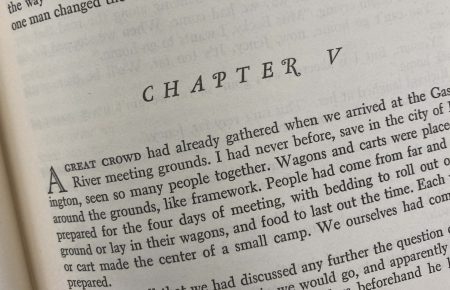翌日、 ゴシップや噂を通して、ステファンが悪気なく自分の馬を探していたことが騒ぎの始まりだと少しずつわかった。
彼はもちろん、サブリナがヴィレッジに戻るために自分の馬を借りたことを知っていたので、自身は他の男たちと一緒に荷馬車で帰ってきた。ヴィレッジに着くと、彼は馬を見にいくために牧場へ向かった。なぜなら、その日の午後のうちに彼は製材所に戻らなければならなかったからだ。馬は見つからなかった。
「どうして話してしまったのですか?」
私は翌日の午後遅く、彼に会った時にそう尋ねた。
困惑し、戸惑い、サブリナのことを心配するあまり、静かになれる場所を求めて、ひっそり教室へと向かった。
それは私にとって、一種の逃避のようなもので、私はよくそこへ赴いて読書をしたり、考えたり、一人の時間を過ごしたりした。
私たちのような、プライバシーというものをまったく得られない共同体では、一人になるためには必死にならなければならなかった。
ステファンは彼の教室にいて、製材所に持っていくために本を整理していた。
私は彼がすでに去ってしまったものだと思っていた。
私たちはサブリナとルシアンについて話した。
すると、彼は悲しげに、いかにして自分が彼らの失踪判明に関わったのか話し始めた。
「どうしてあなたの馬が去ってしまったことについて話したのですか?」私は尋ねた。
「私は何も——何も考えていなかったのです。サブリナが持ち去ったなんて思いもしなかった。彼女が馬を借りたのは知っていたけれど、牧場へ行った時にはまったく疑いなんて持っていなかった——デイヴィッド・ブラウンも仔馬の世話をするために一緒に来ました。彼と牧場へ行った時点で、彼に隠し事をするのは不可能でした。デイヴィッドのような男に何も言うな、なんてお願いしても無駄なことです」
「彼は何をしたのですか?」
「彼はすぐに他の馬を確認しに行きました——いなくなっていないかどうかを。一匹、彼の馬がいなくなってしまっていた。彼は急いでそれを報告しました。私は何が起こったかやっとわかったけれど、でも遅すぎた。デイヴィッドとみんなは、他の意地悪な農家が盗んだのだと思っていました。彼が、馬を持っていったのはルシアンなんじゃないかと疑い始めたのは、彼が夕食の席に現れなかった時です。そしてサブリナも同じようにいなくなって……そうか、そういうことかと合点がいきました」彼は肩を落とした。「私は、できることなら彼らの手助けをするつもりでした。でもそれどころか、邪魔をしてしまった」
「あなたにわかるはずなかったもの」私は言った。「誰にもわかるはずがなかったのです。ルシアンは、あなたに伝えるべきだった。サブリナは私に伝えようとしていました」私は彼に、サブリナがどうやって感謝を伝えたか、そして私がそれをどう読み違えてしまったかを話した。「私が馬鹿だったのです。これからどうなってしまうのでしょう?」
「ブラザー・ベンジャミンがこんなふうに仕切って探しているところを見ると、彼らが見つからないでいられたら奇跡でしょう。彼は深くサブリナへの責任を感じています。彼は見つけだすことを決意している。二人が……二人が……」
「二人が結婚する前に」私はそう言葉を続けた。
「はい」
私たちは静かに立ち尽くし、二人の若者について考えた。どちらも罪悪感を抱き、互いを慰めるようなことも言えず、彼らが見つからないことを祈っていた。「彼らは若すぎるのです」ステファンがそう言って、私は自分の恐れを声に出した。「自分たちだけで生きていくには。彼らはがむしゃらなまま、向こう見ずに急いでいます。ルシアンより年上の男なら、足跡を消す方法や、隠れられる場所を知っているでしょう。しかしルシアンは、自分で決めた目的地に向かって、一生懸命馬を走らせることだけを考えています。彼らはほぼ確実に追いつかれてしまうでしょう」
結局、彼らは見つかってしまった。三日後に、ルシアンとサブリナを連れて、捜索隊は戻ってきた。彼らはとても疲れていた。子どもたちも同じだった。サブリナはシーツと同じくらい青白い顔をして、鞍の上でぐったりと、絶望したように左右に揺られていた。「彼女には母親がいません。私の生徒でもあります」彼らが門に現れると、私はシスター・プリシラにそう言った。「私が預かります」
私は許可を待ったりはしなかった。集まった人だかりの中に飛んでいき、サブリナを馬から助けだしたのは私だった。私は彼女の腕を強く握った。彼女は泣いていなかった。彼女はただ私の肩に頭を預け、震えていた。「すごく疲れました、シスター……すごく疲れた」
「でしょうね、愛しい子、一緒においで。私のベッドで休みなさい、世話をしてあげる」
私たちが立ち去ろうとするとシスター・モリーが近寄ってきたが、邪魔はされなかった。「あなたが彼女を看るのですか?」彼女は言った。
「母親の代わりです」私はそう答えた。
彼女はうなずいた。「明日彼女にいろいろと質問します。今は寝かせてあげましょう」
私の中に怒りが湧き上がってきた。もし明日サブリナが質問に答えられるような気分ではなかったら、誰にも彼女を邪魔させたりしないと私は決めた。私が面倒を見る限り、彼女は平穏に過ごせるだろう。
ルシアンはセンター・ハウスに、彼の父親によって連れていかれた。
私はそっとサブリナを風呂に入れた。彼女は、手入れのされていない木が生い茂った場所を通ったかのように、体じゅうが傷だらけだった。水が傷に染みると、彼女は少しうめいた。私はできるだけ優しく、きれいになった傷に軟膏を塗ってあげた。私は彼女に何も聞かなかったし、彼女も何も話さなかった。彼女の顔は青白く、強張っていて、ぼうっと虚ろな目をしていた。私は、彼女が長いあいだ寝ていないからだろうと思った。私は最後に服を着せて、もう寝るように伝えた。「私が隣に座っているから」私は彼女にそう約束した。「誰もあなたを邪魔したりしない」
彼女が横を向いて、私から目を逸らし、ほとんど嘆くみたいに深くため息をつくと、大きな震えがその身体を駆け巡った。彼女は言った。「寒いです」
私は毛布を持ってくると、彼女にかけてやった。彼女はそれを肩まで引き上げると、頭すら覆ってしまった。それから彼女は動かなくなった。彼女は夜通し眠り、翌日になっても寝ていた。ほとんど寝返りもうたなかった。翌日シスター・モリーがやってきたが、彼女は慈悲深い女性なので、サブリナがまだ眠っているのを見ると、彼女を起こすことを差し控えた。「彼女はまだ子どもです」彼女は言った。「深刻な問題は起こりませんでした、シスター・レベッカ。ルシアンはもう彼女に触れないと誓いました」
「彼らはどこで見つかったんですか?」私はそう尋ねた。
「テネシーとの州境の近くです。彼らはルシアンの祖母の家に向かおうとしていました。デイヴィッド・ブラウンの両親がテネシーに住んでいるのです。
私は唇を結んだ。そして、彼らがそこに辿り着けたらよかったのに、と心の底から願った。もし祖父母の後ろ盾があれば、彼らは戻ってくるよう強制はされなかっただろう。私はそれに関する法律を知らないが、未成年としてデイヴィッドとナンシーはルシアンを連れ戻すことができたかもしれない。しかし私は彼らがそこへ辿り着いて、結婚することを願っていた。彼らが自由になれるような方法がどこかにあるはずだ。
私たちはサブリナ自身の口から、彼らの恐怖や、捕まって連れ戻されたことについて聞くことはなかった。目を覚ました時、彼女は一人になりたがっているかのように、ほとんど喋ろうとしなかった。彼女はセンター・ハウスに連れていかれたが、どんな質問にも答えず、事件についても何も語ろうとしなかったらしい。「彼女はただ座っているだけらしいよ」プリシーから話を聞いたパルミラが私にそう言った。「石像みたい。口を開こうともしないの。ただそこに座って、彼らを見つめているだけ。一度だけ、ルシアンはどこにいるかって聞いて、でもそれっきり」
「彼らは教えたの?」
「ええ。伝えた。彼はヴィレッジから離れるために製材所に送られて、デイヴィッドも彼に同行した」
「ああ、セスがここにいたら!」私は涙を流した。「彼女の父親はここにいなければいけないのに。彼を呼びにいくべきでしょう!」
「ええ、私も彼がここにいたらと思う」パルミラは笑ってそう言った。「私も彼にとても会いたい。でも彼らはこのために彼を呼ぶようなことはしない、私にはわかるの。彼らは彼の売り上げしか眼中にないから」
シェーカーは、常に自分たちの事業に十分な利益がもたらされることを好んだ。倹約と抜け目のなさは彼らにとって美徳であり、彼らは聖書の一節を本来の意味とはまったく違うように解釈していた。金銭は彼らにとって“唯一無二のもの”なのだ。指導者たちはかなり現実主義的であった。お金を相当に必要としていることは言うまでもなく事実だったからだ。金銭では幸福は買えないだろう。しかし、金銭がなくては幸福を求めることもできない。金銭では健康は買えないだろう。しかし、金銭は病の苦痛を大きく和らげる。金銭はあなたに知識を与えることはない。しかし、金銭によって知識をつけるための本を買うことができる。やっぱり、ブラザー・ベンジャミンはきっとセス・アーノルドをこの一回目の販売出張から呼び戻すことはしないだろう。
私はスクール・ハウスへ向かっていた。スクールは来週の月曜日から再開することになったので、シスター・ドルシーと私は部屋を掃除することになっていた。ステファンは日曜日に製材所から帰ってきて、その後、彼は製材所へ戻ることはないだろう。私たちは、先週その知らせを受けた。それまで、私たちは授業をしてはいけないと言われたきり、それ以上の連絡を受けていなかった……少なくとも、私たちは。私たちは、話し合いがあったのかどうかも、どれくらい話し合ったのかも、どんな結論に至ったのかも聞かされなかった。私たちはスクールが始まることと、私たちが再びスクールの指導の担当になるということだけを知らされた。十月には、年長の男の子たちはトウモロコシの収穫の仕事の手伝いに割り振られるようだったが、夏の仕事の大半は終わったので、スクールは九月の初めの週に始めることができた。
私はサブリナのことを悲しく思う気持ちはあったものの、その日は床を、窓を、壁を、机を、そして椅子をピカピカになるまできれいに磨いて、とても楽しく過ごした。私は働きながら歌を口ずさみ、いつになったら、子どもたちがいて、本を開き、授業の声が聞こえるこの場所で多くの時間を過ごせるのだろうと待ち遠しく思った。ここは私のいるべき場所で、私が幸せを感じられる場所だと思った。それからサブリナがスクールに戻ってきて、少しでも彼女の喜びを取り戻してくれたらいいのにと願った。
夏のあいだに、スクール・ハウスに新しい部屋が作られていたことも嬉しかった。私はその部屋に移ることになっていた。日曜日、私はわずかばかりの持ち物を持ってイースト・ハウスから出ていった。私はイースト・ハウスに二度と戻りたくないと思っていた。私は新しい部屋を見た。
それは(1)ハウスの全体分も奥行きがある二階の部屋だった。広々としていて、新しい木材のいい匂いがして、きれいで新品の硬貨みたいに輝いていた。私はベッドの数を数えた。十七台のベッドがあった。シスター・ドルシーは一番奥のベッドで寝ることになるだろうと彼女は言っていた。私が一番入り口のドアに近いベッドで眠り、十五人の少女たちが、そのあいだのベッドを埋めることになるだろう。
スクール・ハウスの女の子のために同じ大きさの部屋がさらに三つあったが、女性の教師はドルシーと私の二人しかいなかったので、他の部屋では、部屋ごとに最低二人の別のシスターか年長の女の子が私たちの役割につくことになる。ホールを挟んでハウスの反対側には、男の子の部屋があり、ステファンや何人かの未婚の男性教徒が男の子たちの面倒を見た。
私は新しいハウスでの暮らしを心待ちにした。ただ、イースト・ハウスを離れてしまうことにも一つだけ心残りがあった。もうパルミラと会う機会がまったくないということだ。リチャードはもはやイースト・ハウスにはいなかったし、二度と戻ってこないであろうことを私はわかっていた。彼はずっと製材所で働かせてもらえるように願い出ていた。彼は少しずつ責任ある立場になり、今では製材所のすべての責任を負っていた。ブラザー・ランキンは、製材所で農園の仕事についていた。私は彼から、リチャードは製材所の運営の仕事以外をする必要はないということを聞かされていた。
(2)製材所はとても儲けの多い事業だった。それは皆の期待を超えて成功していた。外部の農家たちは製材のために、製材所まで数マイルにわたって材木を運んできた。人づてに聞く限り、その功績は主にリチャードによるものらしかった。彼はあらゆる機械の扱いに手抜かりがなかった。
しかし、彼が再びイースト・ハウスで暮らしていたとしても、私はそのことに対して嬉しいとは思えなかっただろう。私たちのあいだにはあまりにも高い壁があり、彼の存在は喜びよりもむしろ悲しみを与えていた。私は食堂で彼の厳格な顔を見ることも、幸せを感じることもできないだろう。そのことはさらに私の心を傷つけるだけだった。
私は今よりもっとサブリナといられることも楽しみだった。彼女はイースト・ハウスではなくスクール・ファミリーへと戻っていた。彼女はスクール・ハウスに戻りたいと言ったらしく、夏期の仕事がほとんど終わったので、彼女の願いは聞き入れられた。私はドルシーに彼女を私たちの部屋に入れられないか相談した。「それはできません。彼女はもう年少の子たちの面倒を見られるほど十分に大きいので、彼女は(3)オールド・ルームに入ることになります」
私は残念に思った。彼女の側にいたかった。もし同じ部屋にいたら、私たちは一緒に本を読んだり話したり、彼女を慰めてやることだってできただろうと考えた。彼女がイースト・ハウスへ戻りたがらなかったことが気になった。彼女は、自分の“家””に戻りたいということ以外は何も話さなかったと、彼らは言っていた。次の日曜日の夜のミーティングで彼女を見かけた時、目の下にはくまができて、彼女の顔は悲しげで相変わらず青白かった。目は大きく見開かれていて、ひどくうろたえているように見えた。彼女は礼拝運動やダンスには加わらずに、静かに座っていることを許されていた。短く部屋じゅうを見回したあと、彼女は膝の上で組んだ両手をじっと見つめて、そのまま視線を二度と上げなかった。彼女は物憂げでうつろな様子だった。癒えないくらい傷つき、立ち直ろうとする元気もないようだった。私は彼女のそばにいたかった。うまく慰めることはできないかもしれない、それでもできる限り心を尽くして、彼女の助けになりたいと思った。
しかし、それは叶わなかった。その次の日曜日の朝に私たちがミーティングに集まった時、それはスクールが始まる前の日だったが、私はすぐに彼女がいないことに気づいた。私は、ドルシーに彼女がどこにいるか尋ねた。ドルシーは、サブリナは体調が悪いのだと言った。「彼女は頭が痛いと言っていました。ですから、私は彼女にベッドにいるように言い、ハーブティーを淹れてやりました」
私はうなずいた。あまりゆっくりと話している時間はなかったので、「ミーティングが終わったら彼女の様子を見にいきます」とだけ言った。
しかし、日曜日はシェーカーにとって特別な日なのだ。一週間の中で最高の日だ。その日は歌やダンスや祈りの中で恍惚とし、長く熱中してミーティングを行う。毎日の各ハウスでのミーティングはそのための準備として行われる。私たちは日曜日のミーティングに向けて新しいダンスを練習し、新しい歌を覚えた。安息日のミーティングは、共同体の外部からの見学も受け入れていたので、私たちは手順を完璧にこなし、正しい祈りの姿勢を見せることで、自分たちの活動を示すことに誇りをもって臨んだ。日曜日の私たちの奉仕は毎回三時間から四時間に及んだ。長い時では五、六時間になることもあった。その日曜日はうまい具合にミーティングが昼前に終わったので、私は抜けだし、スクール・ハウスへと向かうことができた。
私はサブリナの様子を見に、オールド・ルームへ行った。その部屋はもとのスクール・ハウスでは寝室として利用されていて、仕切り壁を解体して広くしたのでそのように呼ばれていた。彼女のベッドは空っぽで、きちんと整えられていた。頭痛がおさまって、散歩なり細かな仕事なりをするために部屋を出たのだと私は思った。彼女と会えないことは残念だったが、思ったよりも調子が良さそうなので嬉しく思ったのだった。
川の土手に彼女の服が重ねて置いてあるのを発見したのは、ウィリアム・スティールだった。仔馬が柵を壊して、土手のほうへ迷いでていた。その様子を見にいった彼は、彼女のドレス、エプロン、ボンネットとハンカチが丁寧に畳まれて置いてあるのを見つけた。彼女がどうしたのかは、その服からはわからなかった。小さなメモ書きが一番上に置いてあるボンネットの折り目に挟まれていた。ウィリアムが確認すると、それはルシアンに宛てたものだったので、彼はそれを持ってセンター・ハウスへ急いだ。
私は今、目の前にそのメモ書きを開いている。センター・ハウスの脇を歩いている時に、ルシアンが落としていったのを見つけたのだ。彼にそれを返そうと思ったが、そのような機会は一向になかった。そのため、それは私が持っておくことにした。私はそれを持っていることに罪悪感は感じなかった。そのメモ書きは、いくらかは私に宛てたものでもあったと感じていたからだ。彼女はメモ書きの中で、私が彼女に貸したスパルタ人の詩集の言葉を引用していたのだ。
それはとても短い文章だった。そこには『ルシアンへ——私はあなたに会えない人生を生きたくはありません。彼らは、私たちが一緒にいることを決して許さないでしょう。「若者の美しい姿は、その死に際に絶頂を極める」悲しんだりはしないでください。……でも絶対に忘れないで、私はあなたを愛しています』と書かれていた。
彼女の遺体は、スクールの始まった月曜日に発見された。サブリナの可愛らしい顔は、その朝スクールで教える私に向けられることなく、川の中をどこまでも流されながら、冷たく濡れて生気を失っていた。私がメモ書きを無意識に拾って読み、彼女の命がすでに絶たれていることを知った時、男性教徒たちはサブリナの遺体を探しているところだった。何事もなかったかのようにスクールは再開されるだろうとステファンが私に言った時、私は到底耐えられないと思った。「私には……」私はそう言いながら涙を流していた。「私にはとても教室に行くなんてできません。彼女がまだ見つかってないことを知りながらなんて。私も川へ行かないと」
彼は私の両手を取り、強く握りしめた。「他の子どもたちを、このあまりにも大きな悲しみから守ってやらなくては」彼は言った。「あなたはサブリナを愛していました。しかし、彼女たちだってあなたからの愛を必要としていて、あなたは彼女たちのそばにいてやらなくてはならない。サブリナがそこにいなくとも、あなたは授業をこなさなくてはいけませんよ」
「私にはとても……」そういって私は彼の手を振りほどいた。しかし、私にはわかっていた。私がそうできることも、そうするべきであることも。
思えばその日は一日中、暑さと寒さを交互に感じ、朦朧としながら授業をしていたので、実際に何を教えたかわからなかったし、それを気にすることもできなかった。私はどうにかして授業の時間をやり過ごしたかっただけだった。他の子どもたちの前で、悲嘆にくれず心を安定させておきたかった。彼女たちはまだ何も知らされておらず、子どもたちはサブリナがいないことを特におかしいとも思わずに受け入れていた。
長く感じられたスクールでの一日が終わり、私は真っ先に自分の部屋へ行き、川へ向かう前にボンネットを置いた。私がスクール・ハウスを出ようとすると、ステファンがあとから追いついてきた。「彼らはもうサブリナを見つけましたよ」彼が言った。
私は、ステファンが私を引き留めようと伸ばした手を振り払った。「私は彼女に会いたいのです」
「彼らは彼女をセンター・ハウスへ運んでいきましたよ」
「そのことはルシアンには知らされているのですか」
「知らされています。彼はサブリナの遺体を探すのに同行していました。彼女の遺書は彼に宛てられたものだったので、彼らは彼がそれを受け取ることも許したそうですよ」
「彼らが許したのですか!」私は思わず大声で聞き返した。「彼らがサブリナを死へと追いやったのですよ。私たち、あなたと私は、彼女の死を後押ししたのです!」
「レベッカ……」ステファンの声は静かで優しかった。
「私たちがそうしてしまった!」私は言い捨てた。たった今、私が彼に八つ当たりをしているとしても、それを気遣う余裕もないほどに私は怒り傷ついていた。「私たちは知っていました。私たちはそれを唯一知っていました。私たちは何かしてやるべきだったのです。私たちは彼らと話し、彼らを助け、彼らの信頼を得るべきだったのです。私たちは夏のあいだじゅう怠けて座っていただけで、彼らを脱走させた。どうして彼らは二人に村を出ることを許さなかったのでしょうか、ステファン。どうして彼らは二人を連れ戻したのでしょうか」私は柵に寄りかかって、それにもたれるように身体を支え、堰を切ったように泣いた。「ああ、ステファン、ステファン、なんて無慈悲で辛いことでしょう」
彼は私をなだめようとはしなかった。聖書の穏やかな決まり文句を口にしなかった。嵐の最も酷い時が過ぎ去り、私が落ち着きを取り戻すまで、私の苦痛と悲嘆の一部を、ひょっとすると全部を共にしながら、ただそこに立っていた。私は涙を拭い、姿勢を正した。「彼女に会いにいきます」と私は言った。
「そうですね」彼は答えた。「墓を作るのを手伝います」
「でも、セスが戻るまで彼女を埋葬しませんよね? 彼を呼び戻しているのでしょう?」
「わかりません。私には知らされていないのです。ですが、そうしたに違いないでしょう」それから、彼は残酷な事実を静かに思い出させた。「今の季節はとても暖かいのです、レベッカ」
そうだ……私は忘れていた。サブリナの若くて可愛らしい、愛しい体は死んでしまったのだ。外は暖かすぎた。彼女の父親が帰るまで、埋葬を待つことはできなかった。私は口元を引き結んで震えを堪え、センター・ハウスへ急いだ。
ルシアンは、彼女が横たわるカウチの側に座っていた。彼は無表情で、悲しみで蒼白になり、放心して茫然としていた。私が部屋に入った時、視線を上げることはなく、話しかけてくることもなかった。私も彼に声をかけなかった。彼に声が届くとは思わなかった。
彼女はそこに横たわり、寒そうで、孤独そうで、とても幼く見えた。髪から、そして彼女を覆う毛布の下から水が滴った。ルシアンか誰かが、彼女の顔にかかるブランケットを退けていた。彼女の目は重しで閉じられ、口を閉じるための包帯も巻かれていた。私はカウチの側にくずおれ、ひざまずいた。彼女の髪から滴る水が、私のドレスと膝を濡らした。私は水の滴る髪に、今は落ち着いて安らかな、水で冷えた若い顔に触った。私はもう泣かなかったが、心が真っ二つに割れてしまったように感じた。私は額をカウチにもたせかけ、祈りを捧げようとした。しかし、こんなにも若い命が犠牲になってしまったこと、そしてそのおぞましさしか考えられなかった。私はシェーカーも、自分自身も赦すことができず、祈りを捧げることができなかった。
シスター・モリーが私の肩に触れた。「あなたはここを去ったほうがいいでしょう」と彼女は言った。
驚いて、私は彼女を見上げた。「なぜ?」
「私たちは彼女を埋葬する準備をしなければなりません」「私がやります」私はそう言って、腰を上げた。「私にやらせてください。私は彼女を愛していました」
「私たちの誰もが彼女を愛していました」シスター・モリーは考え深げに私のほうを見た。「結構です……。もしそれがあなたの望むことならば、手伝ってください」今、私たちは部屋で二人きりだった。ルシアンはいなくなっていた。私は彼が行ってしまったことに気づかなかった。私は、ステファンが彼を探しだしてくれるか、あるいは彼のそばに彼の両親がいてくれることを願った。
シスター・モリーと私は、優しくサブリナの体を洗った。彼女の子どもっぽい体の丸みの多くは、この数カ月でなくなっていた。私は彼女の肋骨と太ももの薄さを見て、深い悲しみを新たにした。私たちは、彼女を傷つけるあらゆる方法でこの子を傷つけてしまった、と私は思った。私たちはあまりにも独善的に、自己満足的に、自分たちの正義と善良さを確信していた。私たちは善の名のもとにこの子に悪行を行った。私たちは、人間が考えられる限りの方法で彼女を絶望させた。そして、彼女は私たちと共に生きるのではなく、自死することを選んだ。
彼女は自ら命を絶ったため、(4)ビリーバーズのために設けられた埋葬地には埋められなかった。彼女は最後に自らの意思で決定的な規律を破ったのだ。彼女は救われた者に囲まれて横たわることはない。しかし、私たちの何人か、パルミラ、ステファン、デイヴィッド、ナンシーは、墓に土を盛る時に、それを木の枝で覆い、上に遅咲きの花をのせて可愛らしく飾った。
その夜、葬式のあと、ルシアンは私たちの元を離れた。そしてその後、二度と彼を見ることはなかった。彼は軍隊に入り、戦争に参加した。彼は(5)レーズン川の戦いで殺された。こうして、二人の罪のない子どもの短く甘い愛が終わった。これで、プリシーのヴィジョンが現実になった。青白い馬に乗った死神が門から入ってきて、私たちの中から一人をさらい、再び馬に乗って「この者は簡単に私のもとにやってきた」と笑いながら言っていた。
第22章訳註
(1)ハウスの全体分も奥行きがある二階の部屋
サウス・ユニオンのスクール・ハウスに関して、詳細は訳註リスト参照。
(2)製材所はとても儲けの多い事業だった
シェイカーの製材所は、シェイカー教徒の建築や大工仕事に必要な木材を加工する手段として、また製材を必要とする近隣のシェイカー教徒以外の人々から資金を得る手段として利用されていた。
(3)オールド・ルーム
スクールハウスの中で、レベッカの部屋は新たに造られたものだが、サブリナの部屋は元の寝室をいくつか合わせてつくられたため、もとからあった部屋という意味でオールド・ルームという表現が使用されている。
(4)ビリーバーズのために設けられた埋葬地
シェーカー教では教徒が亡くなった際は、遺体を洗浄し防腐処理を施し、無地の棺に入れて共同体内の埋葬地に埋葬した。彼らは、死を「魂が霊の世界に入るために肉体を捨てた段階」と捉え、遺体に対して記念碑をつくる必要はないと考えた。そのため、19世紀以降は墓標を立てずに埋葬地を簡素にするような共同体も見られた。
(5)レーズン川の戦い
1813年1月にミシガン州フレンチタウンで行われた米英戦争中の一連の戦闘。ミシガン州における最大の戦闘だったと言われ、デトロイト砦をめぐってアメリカ軍とイギリス軍が争い、アメリカ軍が全面的に敗北した。