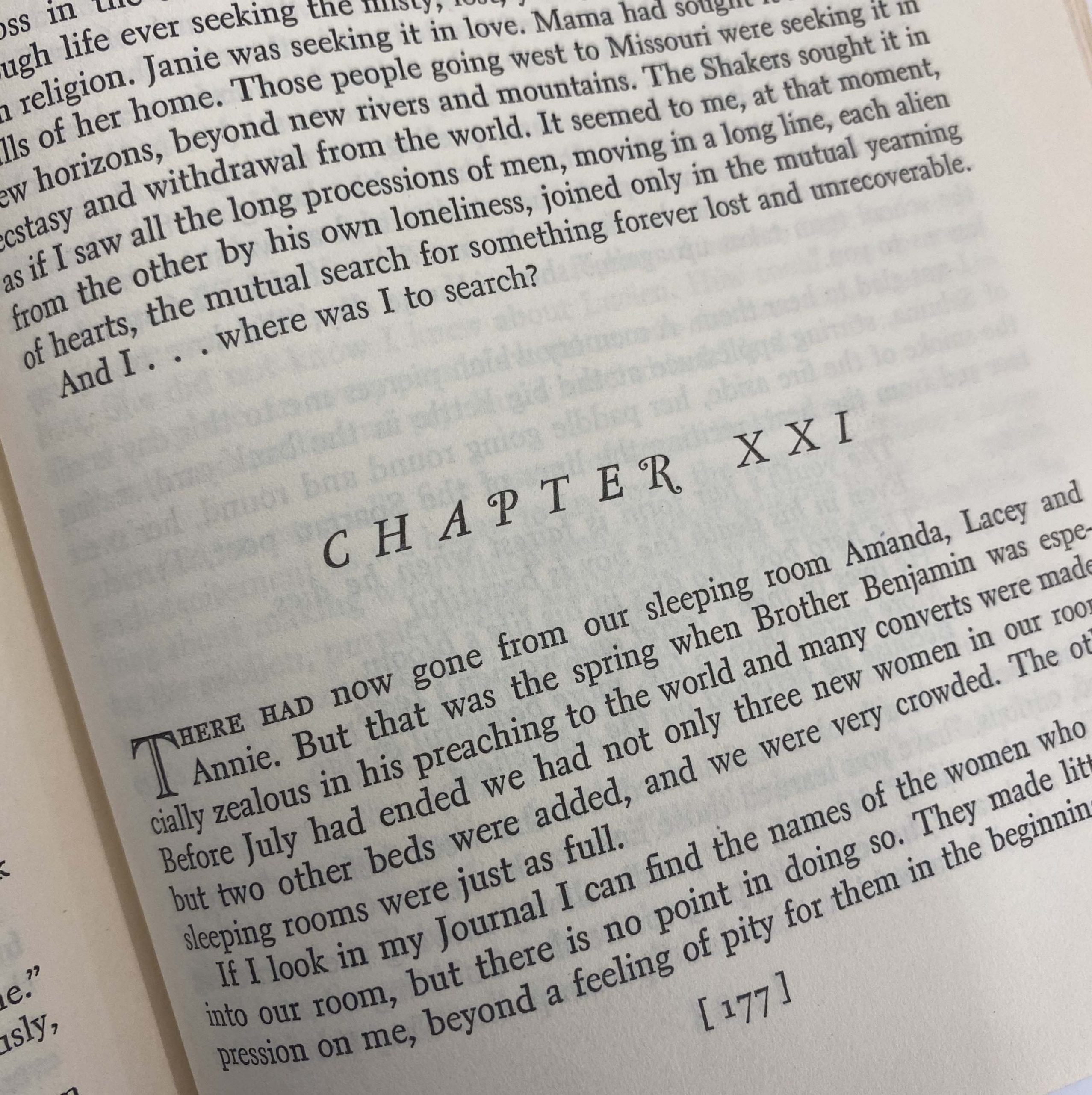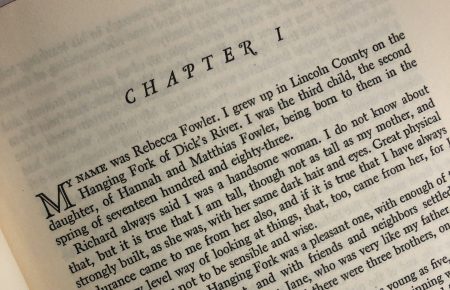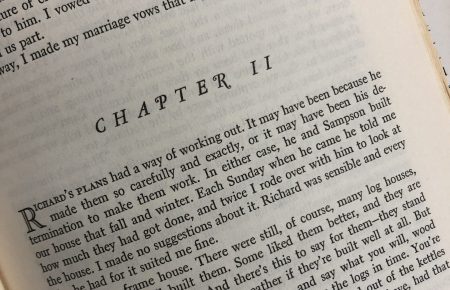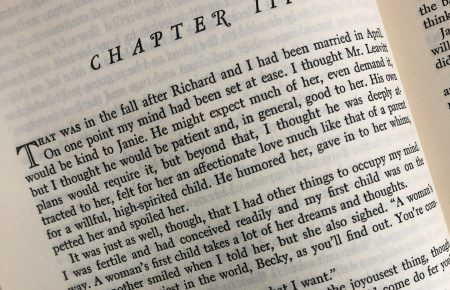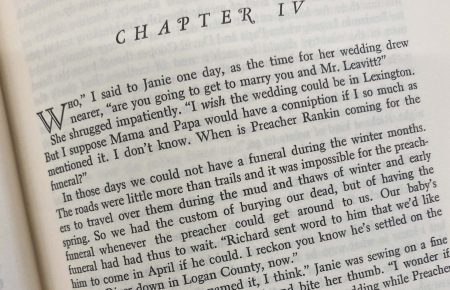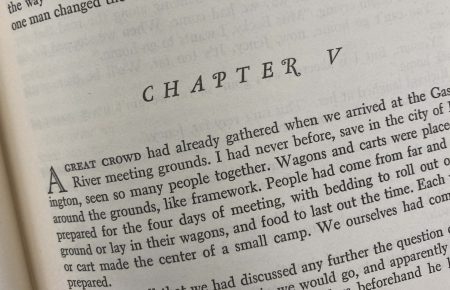いまや、アマンダ、レイシー、そしてアニーが私たちの寝室から去ってしまった。しかし、その春はブラザー・ベンジャミンが外界への宣教に特に注力し、多くの改宗者が出た。七月が終わる前に、私たちの部屋には三人の新しい仲間が加わっただけでなく、さらに二台のベッドが追加されて、部屋はとても混み合っていた。他の寝室も同様に満員だった。
日記を見れば、私たちの部屋に入ってきた女性たちの名前がわかるのだが、見返しても仕方がない。最初のうちは彼女たちを気の毒に思ったが、それ以上はほとんど印象にも残らなかった。彼女らも私たちが経験したように、当惑し不幸に感じていた。彼女たちの気持ちがわかって、私たちは彼女たちへ親切にしようとした。ハウスのしきたりを教えたり、私たちにできるあらゆる方法で手助けをした。しかし、新しく入った仲間はそう易々と私やパルミラ、ヴィニーと打ち解けることはできなかった。私たちは長い共同生活、試練を乗り越えた友情、お互いへの理解で固く結束していたからだ。私たちのあいだには、共に時間を過ごすことでしか培えないものがあったのだ。私たちは、彼女たちがまだ感じていないような不安や思惟を分かち合っていた。だから、表面上は調和をとりつつも、彼女たちへ深い好感があったわけではなかった。
その夏は暑さと仕事であっという間に過ぎた。農園は豊かに実り、イースト・ハウスの女性たちは他の仕事を終えたあと、収穫や乾燥、選別、保存にとりかかった。プリシーは常にどの作業場にも顔を出して、スカートを翻し、計画を立て、指示を出し、監督していた。彼女はイースト・ハウスが今季の最終集計で好成績を出せるよう躍起になっていた。キッチンの大きなやかんは早朝から夜までずっと温められぱなしだった。礼拝運動やダンスができる元気が残っていないほど、長時間の労働で疲れた状態でミーティングに行くこともよくあった。
スクール・ファミリーには専用の農園や果樹園はなかった。彼らはコミュニティの備蓄食料で養われていたので、スクール・ファミリーの女性や年長の女の子たち、男の子たちは分担して、他のハウスの仕事を手伝った。サブリナは、もう大人といってもいいくらいに大きくなっていたので、私たちのところへ派遣された。
彼女は器用で、彼女がキッチンで働いている様子を見るのは私の楽しみだった。ときどき、皮むきや攪拌、乾燥といった同じ仕事を引き当てると、一緒に話をすることができた。そんな時は、再び教室にいるかのようだった。彼女は勉強を続けていて、私たちがそばにいるときには、授業のことを教えてくれたのだ。「学期が再開する前に忘れてしまいそうだわ」と、ある日彼女は言った。「授業の話をあなたにしたいわ」
それを聞いて私は嬉しく思った。私の心を今日まで突き刺している記憶はあるサブリナの様子だった。彼女は裏庭にある大鍋でアップルソースをかき混ぜながら、炎から立ち上がる煙を払う。彼女の持つへらはぐるぐると回り、きれいな顔は熱で赤くなり、彼女はスパルタの詩人、テュルタイオスの詩を唱えている。
(1)『若者の美しい姿は、その死に際に絶頂を極める。
人生の花盛りのうちに死んだ英雄である青年は、死してなお美しい。
彼は男の哀悼と、女の涙の中に生きるのだ。
戦地で死んだのだから、生前よりも神聖で、はるかに美しい』
「どうして、その詩を暗記したの?」私は好奇心に駆られて尋ねた。
「だって美しいから」彼女は答えた。彼女は煮詰めたアップルソースのひと鍋をへらでゆっくりとかき混ぜながら、穏やかに煮立つそれへと視線を落としていた。
私は忠告した。「覚えておいて。それはスパルタ人の詩よ。彼らは、戦争を最も崇高な冒険だと考えていたわ。彼らは戦場で若くして死ぬのは誉あることだと考えていたの。彼らは、高貴に生きることは同じくらい名誉であることを忘れていたのよ」
「知っていますよ」と彼女は答え、私に微笑みかけた。
「それでも、この詩は変わらず美しいんです」
「そろそろ」私は彼女の手からへらを取って言った。「腕も疲れたでしょうから、少し交代するわ。それから、あなたはしばらくスパルタ人の詩を勉強するのをやめたほうがいいわ、サブリナ。代わりにラテン語の詩や、シェイクスピアを読むの。ただし、悲劇ではなく喜劇をね。あなたは悲劇的になるにはまだ早いわ」
彼女は笑った。「もう少し薪を取ってきますね」
私は、彼女が庭を横切って薪の山のほうへ行くのを見た。彼女は、以前ほどふくよかではなくなったと思った。痩せて、幼げのある丸さはなくなっていた。私は、彼女とルシアンのことを思った。もしも、今でも二人が会って、顔を合わせていたら。しかし、彼女は決してそれについては言わなかったし、ステファンは製材所にいたので、ルシアンが彼に話していたとしても、私には確かめるすべはなかった。ルシアンは終日畑にいたので、ステファンと会話をした可能性はほとんどなかった。男性たちがミーティングのために製材所からやって来る日曜日だけ、彼はステファンに会うことができた。
サブリナは、仕事を進んで元気にこなしたが、夏が過ぎるにつれ、以前よりも落ち着いた少女になったのは明らかだった。労働のあいだにはしばしば、機械的に手を動かして、彼女しか知らないどこか遠くの場所を見つめていることがあった。彼女は不幸せなのだと、私は思った。彼女はルシアンを愛していて、彼と一緒にいたいのだと。私は、彼女がそのことを打ち明けてくれるのを願った。私はいつも、自分から話を切り出してみたいと思っていた。私は勇気を出して、何気なくサブリナに聞きたかった。ルシアンに会ったかどうか、彼の様子はどうだったかを。しかし、いつも喉元まで出かかったところで、ためらいが生じて言葉を飲みこんでしまうのだった。彼女は、私がルシアンとのことを知っているとは知らなかった。どうやって切り出せばいい? 誰しも心の中には、他人に入られたり、踏みこまれたり、詮索されたり、首をつっこまれたりしたくない部分がある。それでも、そうしたかったのだ。
その夏は特に葡萄が豊作で、新しいワインの仕込みの時にはとても興奮した。ワイン造りには、私にとってどこか神聖だと言えるようなところがあった。早朝の朝露でまだ冷たく湿っていている熟れた紫の房を収穫し、絞り、濾して、赤い果汁が手のひらから濃く流れ落ち、それからそれを発酵させる。
私たちイースト・ハウスが、ヴィレッジで最高のワインを造りたいと思った。ブラザー・ベンジャミンは熱気と興奮にあてられ、最高のワインを造ったファミリーを招待して、ヴィレッジ全体で外にピクニックへ行こうと約束してくれた。「一日かけて、ヴィレッジのみんなで。それから川で食事をとりましょう」と彼は言った。「その日は休日にして、製材所で働く男性たちも一緒に行きましょう」
働いたのは、私たちなのだ! ブラザー・ランキンが何年も前に植えた一種類しかなかったので、葡萄自体は他のハウスと違いがなかった。
でも私たちは、太陽によって甘く完熟したものだけを収穫したと確信できた。それらは完璧で、果汁でいっぱいだった。皮と種が残った甘口の赤ワインだけを造った。私たちは果醪を発酵させて、注意深く観察した。気温は暑すぎないか? 発酵は急速すぎないか? 急激に冷えて、それからゆっくり温度が上がっているか?
ブラザー・サミュエル以外には誰も、大きな桶を使ってワインを造れなかった。ワインを小さな桶で発酵させると決めたのは彼だった。「一つの桶に入れる量が適切なら、もっとよく混ぜて、よく発酵させることができる」と彼は言った。
私たちは、この最初の発酵桶のまわりをうろうろしていた。まるで、雌鶏が卵の入った巣につくように! 一日に何度もワイン貯蔵庫へ行き、醸造の様子を見て試飲をし、温度を確認した。ブラザー・サミュエルはほとんど毎日貯蔵庫で寝ずに番をし、十日後に、勝ち誇った様子でキッチンへやってきて、ワインを取りだす準備ができたことを告げた。
私たちは、ワインが取りだせることを祝い、最初のワインを貰うためにコップを持って一列に並んだ。それから、おずおずと試飲をした。発酵は早すぎなかったか? 少し酸味が強くないか? しかし、それはまるで葡萄そのもののように甘かった。私たちは、他のハウスはこの出来を超えられないと確信した。ブラザー・サミュエルが最後に自分のコップにワインをとった。私たちは彼がそれを口元へ近づけるのを見守った。彼が定期的に試飲をしていて、完成したと判断したことは皆わかっていたが、今コップ一杯を飲み干したら、彼は何と言うだろうか? 私たちは彼が最初の一口を含み、口内の熱で、舌の上でよく味わい、それからうなずいたのを見た。「もしこれよりおいしいワインがあったなら、それが優勝するでしょう。しかし、これ以上に良いワインがあるとは思えません」
私たちはまるで小さな子どものようにひどく喜んで、叫び、うたい、踊った。ブラザー・サミュエルは、私たちの誇りが傲慢になるのを恐れ、誇りは堕落へとつながると諭し、私たちを優しく叱責した。私たちは恐縮して身を慎んだが、シェーカー教徒たちは、このように仕事への誇りが湧き、ちょっとした喜びが報酬となるようなコンテストを決して非難しなかった。男性たちは藁を編んで売り物の帽子を作るコンテストを行っていた。各ハウスではどこが初めに農園を育てられるか、そこで果実を実らせることができるか、一番肥えた仔牛を育てられるかをお互いに競いあった。コンテストは仕事に小さな楽しみを与え、勝った時の栄誉としての報酬が私たちを高まらせた。それらを楽しむことは、とても人間らしかった。
ノース・ファミリーは私たちから四日遅れてワインを完成させたが、センター・ハウスはそれからさらに丸三週間かかった。私たちは、他のハウスのワインの発酵期間が長くなることでワインがより甘くまろやかになるかもしれないと感じ、待っているあいだは不安だった。
ブラザー・ベンジャミンがすべてのワインを試飲する日が来た時、私たちは研いだばかりのナイフのように神経質になり、落ち着かず興奮に震えた。彼はその夜、センター・ハウスの集会室で行うミーティングにおいて試飲を行うことになっていた。
集まった時、私たちは三種類のワインが入ったガラス容器から目を離すことができなかった。部屋の中央には机が置かれ、各ワイン用の容器とコップがそれぞれ用意されていたので、一つのワインの不純物が他に混入するようなことはなかった。
私たちは、いつものお祈りと歌唱を行った。するとブラザー・ベンジャミンは一歩前へ進み出て、新しい歌の歌詞を読み上げた。それは特別な機会に彼が書いたものだった。果実と、果樹、そしてワインを造るのに労使した手に捧げる歌だった。歌詞を読み終えると、彼はその歌をうたい、私たちは音をすぐに覚えて全員一緒にうたった。それは美しい歌だった。私たちはうたい、ブラザー・ベンジャミンの導きに沿って、ワインの容器が置かれた机を囲んでマーチと(2)カウンター・マーチを行った。お祝いや儀式をできるだけ簡素にするということはシェーカーの美徳の一つだった。
私たちが再び座った時には、先のマーチング運動と勝利への期待によって心臓が飛びでるかのようだ。ラベルは私たちからは見えないようになっていたので、私たちはどのフラスコに自分たちのワインが入っているのかわからなかった。私たちはブラザー・ベンジャミンが一つ目、二つ目、そして三つ目のフラスコからワインを注ぎだし、味わう様子を注視した。それから、彼はその順番でコップを水ですすいでからワインを再び注ぎ、味わった。彼は机に並べられた三つ目のフラスコの上に手を乗せた。「すべてとても良いワインです」彼は言った。「どの作り手も恥じることはありません。しかしこのワインは最も濃厚で香り高く甘い味わいを持ち合わせています」彼はフラスコを回しラベルを見て、そして微笑んだ。「このワインはイースト・ファミリーによるものです」
私たちは喜びから思わず大声で叫んだ。それからブラザー・サミュエルがフロアをぐるぐる回って、私たちに自由に踊る許可を出したので、彼のように喜んでそれぞれが回ってうたった。他のファミリーにねたみや嫉妬のような感情はなく、彼らもダンスに混ざって、みな満面の笑みを浮かべ、うたいながらだんだんと声が大きくなっていった。
プリシーが異言とトランス状態になるギフトを受けた時、私たちは冷静になった。そして私はブラザー・ベンジャミンが平常を装う前に眉をひそめたの見て、彼でさえわずかな焦りを覚えたのだと思った。私はギフトが本当のものなのだろうかといぶかしく思った。私にはプリシ―があまりに頻繁にギフトを授かっているように思えた。もちろん私たちはこのギフトを尊重するために着席しなければならなかった。彼女は早口で、時折声を振り絞って、一度か二度泣きながら、大声で震えながら話した。それからトランス状態が解けて、彼女の顔は蒼白になり、かすれてしわがれた声になった。「見えました……」彼女は喉が痛いかのように手を当てていた。
「はい、シスター・プリシラ」ブラザー・ベンジャミンは言った。
プリシーは震えていた。「私は死神を見たのです。黒いローブを纏って青白い馬にまたがり、ヴィレッジの門を通って私たちのうち一人を馬に乗せて連れ去りました。」
「私たちは死への心構えはできています、シスター・プリシラ」ブラザー・ベンジャミンは言った。「死は私たちにとって恐れるべきものではありませんから」
「けれど彼は笑っていました……見えたものは曖昧で連れ去られたのが男性か女性かわからなかったけれど……とにかく死神が笑っていたのです。しかし彼は『こいつは簡単にこちらへやってきた』といったのです。そして彼はその人を自分の前に乗せ、再び笑って馬に乗って去りました」
それは非常に奇妙なヴィジョンだったので、私たちはみな頭を悩ませた。そして、もはや誰もプリシーがそのヴィジョンを見たことを疑っていなかった。彼女は真っ青でとても震えていたし、彼女の声は恐怖でかすれていた。彼女は私たちの前で目に見えて縮こまり、死神に選ばれた者を見つけようとしているかのように辺りを見回した。彼女の目がこちらに向いているようで私は恐怖に震えたが、彼女はくまなくそれぞれの顔を見回し続け、自分の喉をおさえながら私たち全員を見た……そして立っていられないくらい疲れきってしまったかのように床に崩れ落ちたので、ブラザー・ベンジャミンが優しくシスター・モリーとシスター・スーザンに彼女をホームに連れていくように言った。
彼は簡潔に死について説き、私たちの不安な気持ちを落ち着かせようとした。「私たち信者は……」彼は言った「死を求めはしませんが、その時が来れば受け入れます。私たちは、死を恐れることもなければ嫌うこともありません。私たちがこれまでに知ることのなかった世界、純粋な精神と新しい生命の世界への扉のようにそれを迎え入れるのです」
しかし、宗教が死について何を説こうと、人間というものはそれを恐れ、嫌い、その必然性に深く悲しむのだ。そしてブラザー・ベンジャミンの説教によって少し慰められたが、私たちは恐れとギフトから完全に解放されたわけではなかった。
誰が、いつ? と私たちは思った。しかし、ブラザー・ベンジャミンが説教を終え、金曜日にピクニックを行うことを発表した時、私たちは暗い気持ちを完全に取り払うことはできなかったものの、外出への喜びで少し希望を持てた。
ミーティング後、私たちの部屋で皆が沈黙する中、パルミラが笑って「でも、神経をすり減らしても仕方ないと思うの。村には二百人以上の人がいて、プリシーのヴィジョンでは、(連れ去られたのは)一人だけだったじゃない。その時が来るまで頭を悩ませることはないわ。本当、プリシーったらいまいましい!」と言った。
私は、皆も同じように、午後を台無しにしたプリシーを忌々しく感じているだろうと思った。ヴィニーも「人生最後だと思って、ピクニックを楽しむことを目標にするわ。」と笑って言った。
ブラザー・ベンジャミンの説教よりも、笑いがプリシーの予言への恐れを取り払ってくれた。私たちは冗談交じりに、私たちのうちの誰かの葬式でやりたいこと、うたいたい曲 、説教してほしい人の話をした。そして、ヴィニーは震えたいつもの声で (3)“Cover Me with Lilocks”をうたった。私たちは、こんなちょっと陰惨な方法で恐れを払いのけた。
金曜日は美しく晴れ渡った日で、雨の心配もなく、暑さも川の水から直接吹くようなそよ風によって和らげられた。男性たちは前の晩に製材所から帰ってきた。
私たちはやらなければいけない雑用を急いで済ませ、忙しく食事をバスケットに詰めた。それから男性たちは厚く藁が敷かれた三台のワゴンを裏口へ持ってきて、私たちはそこへ荷物を積みこんだ。女性たちは、楽しそうにピクニックについて話していた。男性たちは、馬に乗るか徒歩で来た。
リチャードは来なかった。私は川に着いた時、男性たちの中から彼を探したが、彼の姿はなかった。私は彼が病気になったのではないかと恐れ、夫を気遣う癖というものは妻の中からはなかなか消え去らないもので、ブラザー・ランキンを探して彼に関して尋ねた。「リチャードは病気なのですか?」
「いいえ」ブラザー・ランキンはそう言って首を横に振った。「彼は病気ではありません。自ら製材所に残る許可を求めてきました」
「なぜですか?」
「やらなければいけない仕事があるといっていました。リチャードは熱心なのです、レベッカ」
「熱心すぎます」と私はとげとげしく言った。
「彼は今日の計画に賛同していなかったのですね?」
「そうは言っていませんでした」
「そう言う必要がなかっただけで、現に来ていないことがそれを示しています。彼はすっかり変わってしまいました、ブラザー・ランキン」
「彼はとても献身的になったのです」
「そのために彼は相当な対価を払いました」
ブラザー・ランキンは悲しそうに私を見た。「同じ対価を払えば良いのでは」彼は言った。「あなたはリチャードの心に重い負担をかけています」
「彼も」私は強い口調で言った「同じく私の心に重い負担をかけています」私は彼から離れた。
リチャードがやせこけてしまったのは、私の頑固さによるものなのか、それとも彼自身の狂信によるものだったのか? リチャードがピクニックを欠席したことで、私の一日が台無しにならないように、考えるのをやめた。たしかに、彼は病気で来なかったわけじゃないけど、彼がいないことが私をがっかりさせそうだった。リチャードの困った顔から彼との確執を思い出しかけて、とても幸せな気分ではいられなくなってしまった。その日は私自身努めて楽しもうと思ったし、そうしようと振る舞った。皆もそうした。
私たちはあまり遊ぶことに慣れていなかったので、最初はどうすればいいのかよくわからなかった。
私たちは川岸を行ったりきたり歩き回り、花を摘み取り、貝殻やきれいな石を探した。シスター・モリーは編み物を持ってきて、ずっと針を動かしていたが、私たちは手を膝に置いて、一緒に座って話した。
プリシーは、病んでふさぎこんでいるようだった。きっと彼女は死神のヴィジョンを見たことで、死の宣告を受けたのは自分自身かもしれないという恐怖に襲われていたのだと思う。私たちは彼女を話に引き込もうとしたが、あまり上手くいかなかった。
食事後、男性たちは徒競走や馬のレース、両方を行った。そして私たちは列を作って観戦して、彼らを応援し、普段のまじめなシェーカーである自分たちとはまったく違う行動をした。
ステファンが馬のレースで勝利した。彼は金髪を風になびかせて走った。他のどの馬も彼の美しい栗毛の馬には到底追いつかなかった。彼は仕事で日焼けをして黒くなり、そして彼の顔は少しふっくらしているように思った。冬のあいだ、彼はやせすぎて青ざめていたので、私はこの変化が嬉しかった。
ルシアン・ブラウンは徒競走に勝った。彼のかかとは太陽の下で光っていたし、彼の足は信じられないほど速く動いていた。彼も夏の仕事で小麦色の肌になったので、改めて彼は格好いい人だと思った。私たちのリーダーたちは、ここ数カ月のあいだに、若い独身男性についてますます悩んでいた。ついに、この国とイギリスのあいだで戦争が起こり、若者たちが軍務に就く可能性があったためだ。(4) シェーカーは暴力での解決を信じていないので、ブラザー・ベンジャミンはワシントンに多くの手紙を送り大統領に伝えていた。これまでに引き抜きをされたことはなかったものの、一人か二人は入隊するために立ち去っていったと思う。彼らは自分の意志で出ていって、その後はもちろんソサエティの管轄外だった。
ルシアンがコースを速く駆け抜けるのを見て、彼が戦う義務を感じて入隊しようとするのではないかと思った。いいや……サブリナが側にいるのだから、入隊はしないだろう。
私は彼がサブリナを見つめる様子を見た。そして、サブリナを見ると、彼女は、他の皆を挟んで離れてはいたが、ルシアンがここにいることで、今日という日を喜んでいるようだった。彼女はなんとか彼の食事を給仕し、おそらく短い言葉を交わすことはできただろう。それは愛の? 望みの? それとも約束の言葉? 彼らが報われない関係であることを考えると私は悲しくなったが、彼ら自身は今日はそんな悲しみから遠く離れているようだった。
レースのあと、男性たちは川を離れてブラブラし、私たちは思うままに奔放に遊んだ。私たちは靴とストッキングを脱ぎ、澄んだ浅い水の中を歩いた。もう何年ものあいだ、小川の中を歩いたり泳いだりしたことはなかったが、足に触れる水の涼しさは、驚くほど幸せな気分にしてくれた。濡れすぎないように、優しく水をかけ合いさえした。私たちは笑いながらお互いの名前を呼び合って、小川に向かって石を投げた。このヴィレッジが作られ配属されて以来、かつてないほどに解放されて自由な時間だった。それは陽気でとても無邪気な戯れだった。
そうしていたら、足を置いた苔むした岩が動いたせいで、サブリナは足を滑らせた。そして、全身を濡らしてしまった。私たちは彼女のひどい有様に笑った。服はすべてびしょ濡れで、髪の毛さえも顔に張りついていた。しかし、私たちが彼女を笑った時、シスター・スーザンは、「サブリナ、ヴィレッジに戻って服を着替えなさい。寒いでしょう。それに男の人の前ではその格好はよくないわ」と言った。
シスター・モリーが声をあげた。「彼女に馬を一頭使わせてあげましょう。乗れるわね、サブリナ?」
「はい、乗れます」サブリナは自分がずぶ濡れになったことでまだクスクス笑っていた。彼女は屈んで足首を怪我していないことを確かめた。私も彼女の足首を指で押して確認した。「どこか痛む、サブリナ?」
「大丈夫です。滑っただけ」
「きっと転んだ時、怪我する前に足を退けたのね」
「そうだと思います」
「どの馬がいい?」私は彼女に聞いた。
馬のほうに一緒に歩いていって、彼女に馬を選ばせた。「ブラザー・ステファンの馬に乗ったら、気にするかしら?」
「大丈夫よ」私は断言した。私は彼女の気持ちをわかっていた。ステファンの馬は純血種で、とても速く走った。私だってその馬に乗ることを楽しんだだろうと思った。「喜んで貸してくれるわ」
私たちはステファンの馬に頭絡と鞍をつけた。そのあいだ、ステファンの馬は落ち着いてじっとしていた。それから、彼女が乗れるように、切り株の側に動かした。行儀よく、跨らずに横乗りになって馬に乗って、彼女は手綱を持った。「気をつけるのよ、サブリナ」シスター・モリーが呼びかけた。「戻ってこなくて大丈夫よ。私たちももうそろそろハウスに帰るから」
「わかりました」サブリナは言った。それから、彼女は濡れたスカートをできるだけ整えて、もう一度笑って、もごもごと私に「その、ありがとう、シスター・レベッカ」と言った。
私は笑いながら彼女を見上げた。「あら、いいのよ。あなたが馬を貸してもらえるように手伝っただけよ」
彼女は微笑んで、踵で馬に合図すると、馬は後脚で少し跳びはねた後、野原を横切って道路に出た。私は彼女があまり速く馬を走らせるのを見て、向こう見ずさに眉をひそめた。しかし、それから微笑んだ。彼女は若いのだ。馬の速さと強さを感じたいのだ。彼女の年頃なら、私だって同じようにしたいと思ったはずだ。
ハウスに戻る道すがら、私たちはあまりに疲れて黙っていた。外出した休日のあとに、いつもなるみたいに。精も根も尽き果てていた。馬車から荷を下ろしたあと、私たちはすぐにそれぞれの仕事に取り掛かった。私は鶏園で仕事があった。もう日中の暑さは和らいでいた。それでも、日没直後のこの時間帯の空気はいつもすごく穏やかで、夜の冷たさを嫌うように、日中の名残で暖かかった。私の服は流した汗で湿っていた。首のまわりのスカーフを緩めて、喉を風に当てた。鶏に餌をやり、卵を集めた。夕食の鐘の音を聞いて、機嫌が良くなった。
サブリナは夕食の場にいなかった。彼女は夏の仕事のためにイースト・ハウスに配属されていたので、私とは別の部屋だったけれど、寝るのも食事をとるのもイースト・ハウスだった。夕食の彼女の席が空いているのはすごく目立っていて、何が起きたのかすぐにわかった。彼女はいなくなってしまった。昼間、彼女はこれまでの私の行為すべてに感謝を示そうとしていたのだ。ルシアンもいなくなったと、私は確信していた。
ヴィレッジを抜け出した人が思い出されて、さみしくなるのは、いつも、食事の時間だった。二百人規模のコミュニティでは、みんなそれぞれの仕事に追われていて、時間があっという間に過ぎるし、抜け出した人に気がつかないくらいだった。それでも、食事の際に空席があれば誰もが気づいた。
しかし、見たところ、この時、起きたことをうすうす感じていたのは私一人だけのようだった。二人の若者の秘密は、あまりにも慎重に守られていた。サブリナはたしかに夕食の席に不在だったが、誰もそのことを心配していないようだった。もちろん、私たちは食事の際は話すことができなかったが、みんな、誰かしらはサブリナの居場所を知っていると思っているのだろう。彼女は小川に落ちたのだ。
思っていたより足首を痛めていたかもしれない。寒くなって部屋にいたかもしれない。一晩だけスクール・ファミリーに戻ったかもしれない。みんなが何を考えているかは推測しかできないが、彼女がいなくても誰も気に留めていなさそうなのは、はっきりとわかった。そのことに気がついて、安心した。
頭の中で考えごとが止まらなかった。まだルシアンがいないことに気がついていないのかしら。ステファンは何をしているのかしら。もうこのことを知っているのかしら。手助けしたのかしら。サブリナは本当に足首を痛めたのかしら。全部計画していたことだったのかしら。でもそんなことはどうでもいい。重要なのは、サブリナとルシアンがついに自分たちで物事を運んだことだ。私は彼らがシェーカーの手の届かないところまで完全に逃げられるように祈った。彼らは未成年だから、連れ戻される可能性があった。
それから、サブリナの父であるセスが、販売出張のためにテネシー州に出かけていて、数週間は帰ってこないということを思い出した。そして、サブリナへの監督責任は、ブラザー・ベンジャミンや他の指導者たちにあることを思い出してぞっとした。セスにはサブリナを不憫に思う気持ちや、娘の幸せを願う気持ちもあったかもしれない。彼らを逃すために言い争ったかもしれない。ブラザー・ベンジャミンは、セスに対しサブリナに関する責任があるので、彼女を探しだすことになるだろう。私は祈った。どうか、どうか彼らが遠くまで逃げられますように。見つかりませんように。
長い食事の時間はやっと終わり、私たちは部屋に戻った。私は自分のベッドで休みながら、サブリナのことを考え、朝まで彼女がいないことに気がつかれないことを祈った。
しかし、それは儚い望みだった。パルミラはミーティングの鐘の音に目を覚ました。
私たちは二階のミーティング・ルームで集まった。シスター・モリーが慌ただしく入室し、シスター・スーザンに囁いて、二人が女性の列を見下ろすように振り返った時、私たちは席についているだけだった。「サブリナはどこですか?」シスター・モリーが聞いた。
「部屋にいるんじゃないんですか?」パルミラが無邪気に聞いた。
シスター・モリーがサブリナと同じ部屋の女性たちに問いかけるように目配せした。みんな首を横に振ったが、一人が声をあげた。「スクール・ファミリーにいるんじゃないんですか? サブリナは夜をそこで過ごしたのかと思っていました。小川に落ちたあと、寒くなって、温まるために帰ったのかと思っていました」
「サブリナはスクール・ハウスにはいません」シスター・モリーが言った。そしてそれ以上何も言わずにミーティング・ルームから出ていった。
パルミラは私を軽く肘でつついた。「サブリナは脱走したの?」
「しーっ。静かに」私は言った。
彼女は、私がまるで彼女に対して傲慢に振る舞ったかのように、にらみつけた。しかし、私はあまりにもサブリナが心配で、気にならなかった。その夜、ミーティングは行われなかった。私たちはそこで解散となったが、ブラザー・サミュエルとシスター・スーザンはセンター・ハウスに急いで向かった。私たちは何も話さなかったが、今やみんなが推測していた。サブリナとルシアンがいなくなったことではなく、サブリナが何かしらの理由でいなくなったことを。というのも、彼らのつながりはステファンと私しか知らなかったからだ。
部屋に戻ってから、サブリナがいなくなった話が出ていたが、私は会話に入らなかった。直接考えを聞かれた時には、ただ「知らないわ」とか「わからない」と答えた。ついに、打ち明けないまま、話は途絶えた。みんなベッドに入ると、パルミラすらも、すぐ眠りについた。けれども、私はその夜長いあいだ目を覚ましたまま横になっていた。サブリナとルシアンに思いを馳せて、彼らがどこに行ったのかと考え、いいスタートを切ったことを願っていた。深く愛し合う若い二人のことを考えていて、リチャードのことを思い出した。記憶の中で、子ども時代にも遡って、その時の幸せを思い出して、それがなくなってしまったことを少し悲しんだ。結婚や、一年目の至福の時間や、ベティアの家の裏に埋葬された赤ちゃんのことも思い出した。リチャードに感じた一番初めの不安も、惨めな気持ちも不満も思い出した。自分自身の恐れや根拠のない無茶な希望を思い出し、これまで二人で歩んできた長い道のりをなぞった。違うように生きられたとも、今違うようにできるとも思えなかった。罠に掛かって、それでおしまいだった。絶望とは非常に孤独でひどく嫌なものだ。
第21章訳註
(1) 『若者の美しい姿は、その死に際に絶頂を極める。
人生の花盛りのうちに死んだ英雄である青年は、死してなお美しい。
彼は男の哀悼と、女の涙の中に生きるのだ。
戦地で死んだのだから、生前よりも神聖で、はるかに美しい』
テオグニス他西村賀子訳『エレゲイア詩集』(京都大学学術出版会、2015)の「テュルタイオス」の項を参照したが記述はなかった。現状見つかるテュルタイオスの詩の邦訳がこの書籍のみのため、ゼミ内で検討し、訳案を作成した。
(2) カウンター・マーチ
シェーカー教では、高齢の教徒が礼拝運動に参加できるように1820年代に行進(march)の動きがつくられた。 一方向に行進を続けるマーチに対して、反対の方向に進む動きをカウンター・マーチという。
(3)Cover Me with Lilocks
「Cover Me with Lilacks」というタイトルの曲は、『The Gift To Be Simple Songs Dances And Rituals Of The American Shakers』に記載されているシェーカー教の記録した曲の中では参照できなかった。
(4)シェーカーは暴力での解決を信じていないので、ブラザー・ベンジャミンはワシントンに多くの手紙を送り大統領に伝えていた。
シェーカー教は、教義の中で平和主義を掲げ、戦争に参加することに抵抗した。『Historical Dictionary of the Shakers』によれば、南北戦争中シェーカー教の男性が徴兵の対象になった際に、これを受けて、シェーカー教の指導者はリンカーン大統領と面会し、シェーカー教の非戦主義を主張し、シェーカー教徒は戦争への強制的な徴兵の免除を勝ち取ったと記述されている。