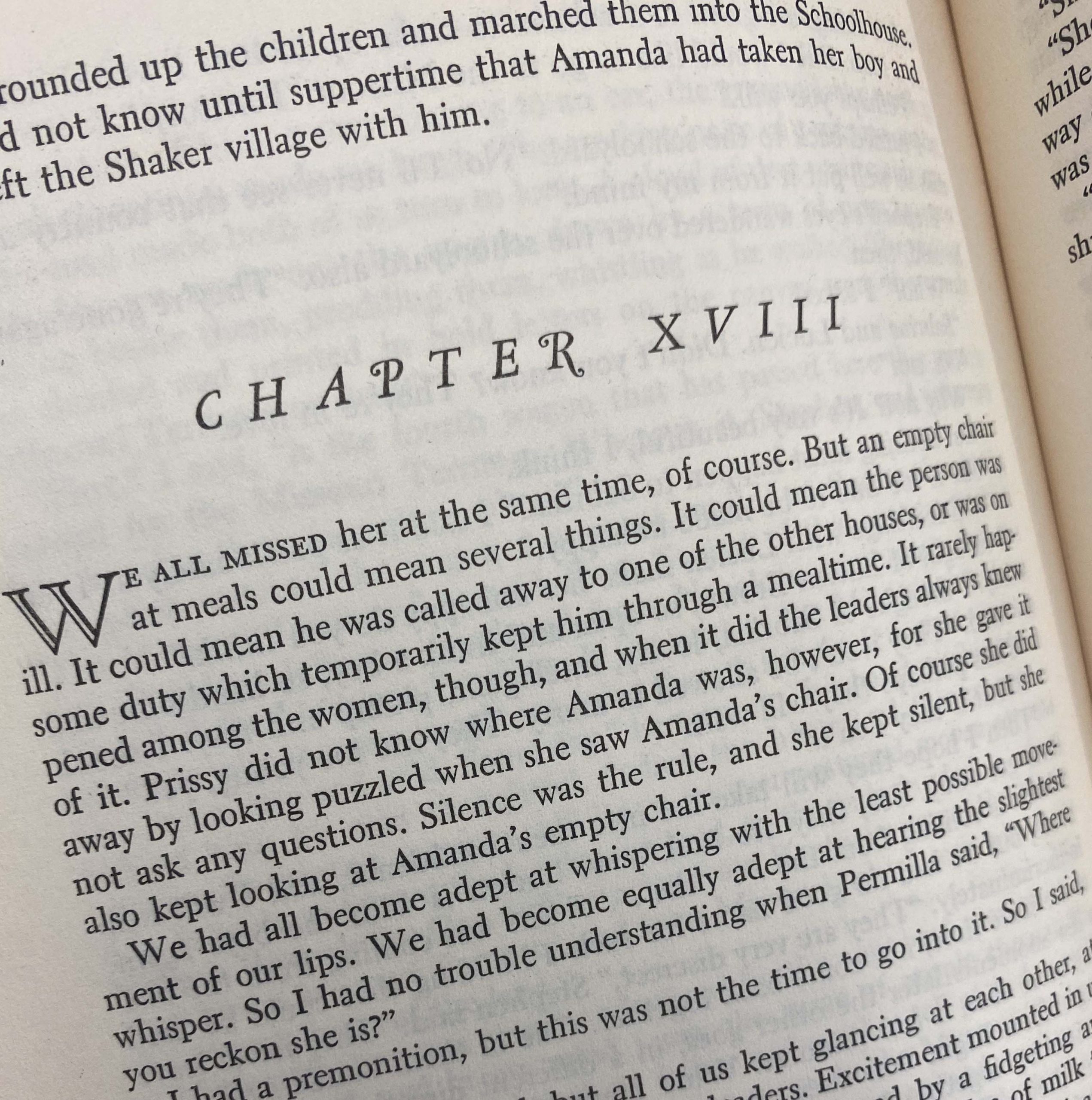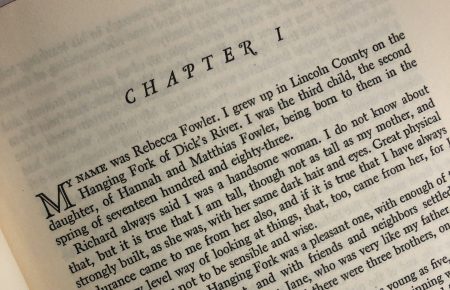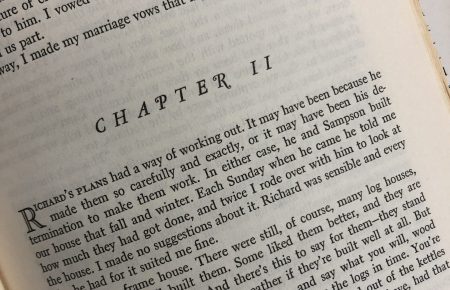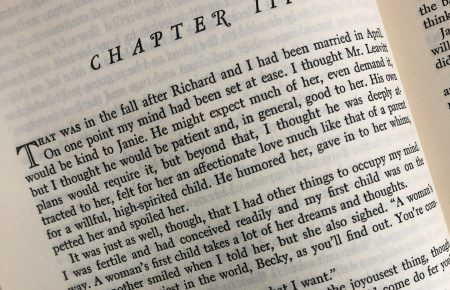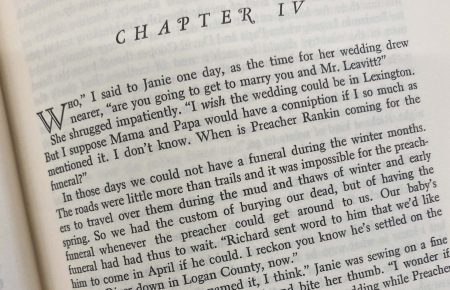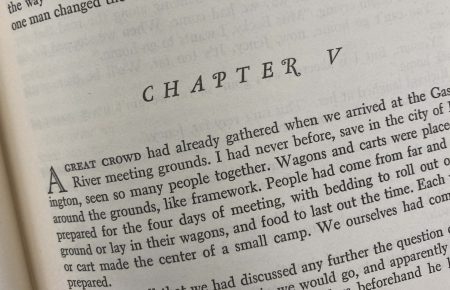もちろん、誰も彼女の行方がわからなかった。しかし、食事の際の空席はよくあることだった。その人が病気かもしれないし、他のハウスに呼び出されているとか、食事の時間に手が離せない仕事に一時的に就いているのかもしれなかった。けれども、女性教徒ではめったにないことだった。そして、女性教徒の中で食事中に不在にする人がいた時には、指導者たちはいつもそのことを把握しているのだった。しかし、プリシーはアマンダの行方を知らなかった。というのは、彼女がアマンダの空席を見た時に困惑しているように見えたことからうかがえた。もちろん、彼女はなにも問わなかった。沈黙がルールなので、黙ってアマンダの空席を眺めていた。
私たちは皆、唇の動きを最小限にして囁くことに長けていた。同時にちょっとした囁きすらも聞き逃さないことにも長けていた。それゆえパルミラが「彼女はどこだと思う?」と言った時、私は聞き取るのにまったく困らなかった。
私は予感していたが、それを検討する時機ではなかった。だから私は「わからない」と言った。
私たちはいつものように静かに食事をしたが、みなお互いのことや、アマンダの椅子、プリシーや他の指導者らをちらちら見続けていた。私たちのあいだには、動揺が広がっていた。食事の場での忙しさよりそれは明らかだった。私たちはフォークやパンをいじり、牛乳を一息に飲み干していた。私は、夕食に青菜を食べたこと、いつもならそれらがとてもおいしかっただろうことと、しかしテーブルの向かい側のアマンダの席が空席の状態では、何を食べているのかわかるのがやっとだったことを覚えている。
彼女は学校が終わる前に息子を返さなかったが、私は彼女が必ず夕食までにはスクール・ハウスに彼を連れてくるだろうと思っていた。私はそこで何が起きているのだろうと思った。ステファンが対処するのだと、私は思った。彼は何をすべきかわかっているのだろう。
私たちが食事を終えてすぐに、私たちは皆、プリシーがシスター・スーザンのそばに駆けつけ、囁き声で会議を始めるのを見た。それから二人はブラザー・サミュエルに近づいた。私たちはその時食堂を出ていくところだったので、それが私たちの見たすべてだった。私たちは、部屋に戻ると皆で顔を見合わせた。「彼女はどんな当番だった?」とうとう私は尋ねた。
アニーは答えた。「彼女は養鶏場と庭にいた」
私はパルミラを見た。「そこから彼女が出ていくのを見た?」
パルミラはうなずいた。「ええ。あたしは彼女を見たよ」
私はそれから打ち明けた。「彼女はスクール・ハウスに来て、息子を連れだしたの」
「彼女は、たびたび彼を見るためだけに、そこに下りていってた」とパルミラは言った。
「彼女は息子を連れ去った。彼女は少しのあいだ息子と話せるかと尋ねて、ブラザー・ステファンと私は彼を行かせたの。最初、彼女は小道を少し下って彼と話していたけれど、気がついた時には、彼女は姿を消していた。学校が終わっても、彼女は息子を返さなかったわ」
「彼女はその時に脱けたんだ」とパルミラはきっぱり言った。「彼女は彼と逃げるように出ていった」
「でも彼女はどこに行ったの?」 私は不思議に思って尋ねた。
ヴィニーは話しだした。「彼女はいつも無口なほうではあったけど、ここ二日間は、特に何かを考えこんでいるようだった。おそらく彼女はそのことで計画を練っていたんでしょう」
アニーは私を見た。「息子に会わせるなんて、あなたもトラブルに巻きこまれるのはわかっていたでしょう?」
私はうなずいた。ステファンと私が疑われることはたしかだったが、私はまったく気にしていなかった。私はアマンダが今どこにいるのか、何をするつもりなのかを考え、彼女のために祈った。何をしようとしているにしても、すべてうまくいくように私は願っていた。
私たちは毎晩何かしらミーティングを開いたが、プリシーはその時刻の前に、その夜ミーティングがないということと、センター・ハウスで私を呼んでいたということを伝えにきた。彼女はしたり顔で、満ち足りているように見えた。彼女はその他の情報を進んで話さず、私がシスター・モリーに報告することになっているとだけ言った。彼女の言い方から、穏便に済まないことはわかった。私が行く準備をしていた時、「今は彼らに悩まされないように」とパルミラが同情的に言った。
私は首を横に振った。「私ができることは真実を伝えることだけ」
センター・ハウスには、私たちのファミリーやノース・ファミリー、スクール・ファミリーからはステファンとシスター・ドルシー、それから当然センター・ハウスから、指導者全員が集まっていた。ウィリアム・スティールは固く決心した様子で、彼らに囲まれ座っていた。私は座っているよう言われた。ステファンは部屋の向こうから私に微笑んだ。私は自分がまったく怖がったり混乱したりしないことに驚いた。私はただ真実を伝えさえすればよい。私は皆が知る以上のことは何も知らなかった。そして私はアマンダが彼女の計画について話したがらなかったことを幸運に思った。私はどんなに尋ねられても、アマンダがスクール・ハウスに来て、サイラスと話したいと頼んできたこと、ステファンと私がそれを許したことしか知らなかった。それがすべてだった。
だがしばらくのあいだ、誰も私に質問しなかった。ブラザー・ベンジャミンはウィリアムと話していた。「彼女は息子を連れだして、こんなふうに逃げ出す必要はなかったでしょう、ウィリアム」
ウィリアムは「彼女は恐れていたのだと思います。あなたが彼女を止めるのを恐れていたのです」と言った。
「彼女がどこへ行ったか知っていますか? 一緒に計画したのですか?」
ウィリアムは首を横に振った。「いいえ。彼女は私に一言も言いませんでした。彼女が行くことのできるのは一箇所で……農場に戻るでしょう」彼は頭を上げた。「そして、私もそこに行くつもりです、ブラザー・ベンジャミン。 私は信仰を曲げません。私は自身の魂を救うことを考え、光の中で生きようとしてきましました。息子から離れて暮らすことは、私にもアマンダにとっても死ぬような思いでした。けれども、あなたたちにはそうする権利があるのだと信じて我慢してきました。しかし、子どもたちと離れて暮らすのは、辛い生き方です」
「マザー・アンのやり方でした。彼らの両親と同様、子どもたちの救済のためです」
ウィリアムは立ち上がった。「それがマザー・アンのやり方なのかもしれませんが、私はもうたくさんです。五人いた子どもの中で、サイラスが私たちに残された最後の子なのです。彼が熱を出して寝込んでいた時、私たちは彼と会うことも許されませんでした。私たちは、他の方々のところに彼を預けなければならなかったのです。普通のやり方ではありません。ブラザー・ベンジャミン、人々の持つ感性は揺らがないでしょう。アマンダは彼女が思いつくことのできた唯一の逃げ道を選択したのでしょう。彼女は私に何も話さなかったけれど、私は彼女を責めたりしません。彼女も私が反対してしまうのを恐れていたのかもしれません。でも私は違います。私はここから脱けて、自分たちで私たちの息子を育てるつもりです。
一人しか残されていないのだから、何よりも大切なのです」
「不朽の魂でさえも、ウィリアム?」
ウィリアムは頭を下げた。「不朽の魂でさえも、ブラザー・ベンジャミン。あなたに歯向かうつもりはありませんが、私には子どもを親から離して育てることは間違った指導だと思います」
ブラザー・ベンジャミンはため息をついた。「正しさへの道を追求するのは難しいことです、ウィリアム。だが、あなたが決心しているならそうしましょう。朝にはあなたに財産を寄与しましょう」
ウィリアムは大股歩きで部屋を出た。
ステファンは再び私を見て微笑んだ、そして私は、彼が左耳のあたりの髪の毛を触っているのを見て微笑んだ。彼はいつものように髪を引っ張っていた。それを除いては、彼は十分に静かに見えた。ブラザー・ベンジャミンはそれから私のほうを向いた。言うまでもなく、彼はすでにスクール・ハウスで何が起こっていたのか知っていた。ステファンが彼に言ったようだ。「ブラザー・ステファンはアマンダがサイラスと話すのを許したと私たちに伝えました。
シスター・ドルシーはそれに関して何も知りませんでした。あなたは?」
「はい、ブラザー・ステファンだけでなく、私もアマンダが息子に会うことを許しました」と私は言った。ステファンはすべての責任を取ろうとしたのだろう。
ブラザー・ベンジャミンは、咎めるように私を見た。「あなたは彼女が子どもと話すことを許してはいけないとわかっていますね?」
「あなたたちがそう思っているのは知っています」
彼は下唇をかみ、床を見て、それからまっすぐ私を見た。「なぜあなたはそのようにしたのですか」
「だって彼は彼女の子どもなのだし、彼は病気だったんですよ。だから、私は彼女は自分の息子と会って話をして、彼は大丈夫なんだって安心してしかるべきだと思ったのです」
「親と子がどのような関係であるべきかは私たちが決めますし、そこにはとても素晴らしい道理があります」彼は私に確かめるように言った。
「その通りです。けれども、あなたのその考えは間違っていると思うのです」
「あなた個人の意見など何の意味もありません」と彼は厳しく言い、それから続けた。
「村での暮らしを選んだ者は皆、規則を知っていますし、我々は例外なくその規則に従って当然なのです」
「そんなこと、あなたはそうして当然と思っているかもしれませんが、それに従うことはまた別の問題です」と勇敢にも私は反論した。
「レベッカ、我々が異を唱えることは許されていないのです。今、あなたの反抗的な行為が問題を引き起こしました。これはあなたの決定するようなものではないのです。あなたもブラザー・ステファンもそんな権利は持ち合わせていません。もちろん彼は重い責任に耐えていますが、それは彼がスクール・グループの指導者だからです。しかしあなたはあなた自身の反抗心に従っているだけなのです」彼は今度はステファンのほうを振り返って言った。「学校は今期は閉鎖されます。あなた方がまた教鞭を執るかどうかは、我々がじっくりと信仰心に従って、検討しなければならない問題となるでしょう」
シスター・スーザンとブラザー・サミュエルは、悲しそうに私のほうを見た。彼らが私の反抗心に本当に心を痛めていたことは明白だった。自身の義務を果たせなかったためかもしれない。彼らはとても良い人間で、信心深く、彼らの仕事に対して献身的だった。しかし、彼らは改宗者としてこの村にやってきた私たちの問題を理解することはできなかった。二人とも、生まれながらにシェーカー教徒だったのだ。彼らは怒りや、不和や、反抗心を感じることも、それらを他人の中に感じとることもできなかった。彼らは外の世界がどうなっているか、まったくもって知らないのだ。彼らは、結婚したことも子どもを持ったこともなかった。生まれてこの方、彼らはシェーカー共同体という隔絶された世界で生きてきた。他の生活に関する知識など知らずに育ったのだ。そんな彼らがどうして理解できるというのだろうか。
ブラザー・ベンジャミンはステファンと私を退室させた。私は先に部屋を出たが、部屋の外でしばらく帰らずにいた。外は月もなく暗かった。夜空いっぱいに星が輝いていた。空気は果樹園からの甘ったるい香りで満たされ、小川のほうからはたくさんのカエルの鳴き声がしていた。私は父がかつて、カエルたちは小川の水を見ながら「どれくらい深いの? どれくらい深いの?」と問いかけているのだと教えてくれたことを思い出した。それから彼らは自らその問いかけに答えて、「ひざくらい深いかいやもうちょっと深いか、ひざくらい深いかいやもうちょっと深いか」と言うのだ。それから一番大きなカエルが低い声で鳴きながら、「回れ。回れ。回れ」というのだった。私は思い出して顔がほころんだ。これまでの私の人生で、春先にカエルたちの鳴き声を聞くと、彼らの声は質問を投げかけ、答えを与え、助言を与えてきた。彼らは私にとっては単なるカエルではなかった。彼らは感情豊かで考えを持っていて愚痴っぽくてお互いにおしゃべりをするようなカエルたちだった。そして私はいつも心の中で、ひざくらいの深さの水面や、心配するカエルたちの声や、回れというカエルの会話を思い描いた。私はいつでも鮮明に思い描ける。
私はステファンと話そうと心に決めて、穏やかな夜の闇の中、彼を待った。彼は何かもっと言いたいことがあって居残っている様子だった。彼は私を非難から擁護するために、骨を折っているようだった。私はいばらのそばに立っていた。黄色いバラの花の甘い香り、星の輝き、カエルたちの鳴き声、それにそよ風の感触が入り混じっていた。ああ、世界はこんなにも美しいのだ。こんなにも魅力的で、こんなにも愛と生で満ちているのだ、と私は思った。ステファンを待ちながら、私の心の中に、生きることを、満たされ満足することを望む新しい気持ちがあることを感じた。同時にそこには、干ばつの季節の泉を思わせるように、それらはいつか必ずなくなってしまうのだという深い悲しみも覚えた。
しばらくして、ステファンが部屋から出てきた。ステファンはまだ外の暗闇に目が慣れていなかったようで、私が服の袖を引っ張らなければ、彼は私に気づかず通り過ぎてしまっただろう。「ステファン?」
「ベッキーですか?」
「ええ、あなたはこれからどうするんですか?」
「いえ、何もありません」
「彼らはあなたをどこかへやるのですか?」
「そうはしないと思います。彼らは小川の上流に新しくできる(1)製材所で私に手伝うように言っていますから」
「彼らは私たちにもう一度子どもたちを教えさせると思いますか?」
「そう思いますよ。他に代わりもいないのですから」
「東部から誰かを連れてくるかもしれませんよ」
「そうですね。けれども彼らはそうしないのではないかと思います。今回のことも、そのうちほとぼりが冷めると思うんです」
ステファンが動き出すまで、私たちは黙って立ち尽くしていたが、私にはそれがひどく長く感じられた。
「おやすみなさい、レベッカ」彼は言った。
「待ってください」私は彼の袖をつかんだ。
「いつ製材所に行ってしまうのですか?」
「明日です」
「ステファン、私はとても悪いことをしてしまいましたね。ごめんなさい、私のせいであなたを巻きこんでしまって」私が遠慮がちに言うと、彼は笑って「気にしないでください。私はもう立派な大人ですし、ちゃんと自分で考えた上で行動していますよ。それに何を具合の悪いことがあるのですか、アマンダとウィリアムが彼らの息子と一緒になれた。そうでしょう?」と言った。
「ええ、その通りですね」私はサイラスと元の農場に帰ったアマンダのことを思った。ウィリアムは忠実に彼女に寄り添うだろう。私はなんだか猛烈に彼女のことが嬉しくなった。
「製材所で怪我をしないように気をつけてくださいね、ステファン」
「ありがとう。君も元気で、レベッカ」
「ええ」
それから彼は去ったが、途端に夜空は暗さを増したようだった。星はぼやけて輝きを失い、さっきまで陽気に鳴いていたカエルたちの鳴き声はやけに攻撃的に感じられた。私は小道をイースト・ハウスへ急いだ。茂みの影がなんだかひどく恐ろしくて、動悸が激しくなった。私は怖かった。何もかもが私にとって怪しげでなじみのないごちゃごちゃしたものに思われた。足の裏に感じる慣れ親しんだ石の感触にも、イースト・ハウスの窓から見える柔らかなろうそくの明かりにも、今は安らぎを感じなかった。地面でさえも、あの恐ろしい地震が再びやってきたように、揺れているように思えた。私はなぜだがわからなかったが、無性に泣きたい気持ちに駆られた。泣くようなことは何ひとつとしてなかった……。私はもどかしくなって、涙を拭い去った。涙を流す理由なんてないし、何も怖いことなんてないのだと、私は自分に言い聞かせた。あと三週間で夏休みだったので、そうなれば、どのみちスクールは閉鎖していたのだ。私はイースト・ファミリーでまた自分の仕事をしていただろう。何がこうも涙を誘うのだろう。しかし、どうにも涙はあふれてくるのだ。涙はしかるべき時に流すものなのだ。だから私はハウスに入るまでに、一度立ち止まり涙を流しきってしまった。私は、独り込み上げるように笑った。女というものはどれくらい意味もなく涙を流すのだろう。どのように、いつも変わらず涙は彼女の不安と悲しみを取り除き、幾分の安らぎを与えるのだろう。私が涙を拭うことができるようになった頃には、感情の波は過ぎ去ってしまって当分やってこないことがわかっていたし、気分は良くなっていた。
次の日、プリシーが私に庭の仕事を命じたことにいくらか勝ち誇ったような気持ちになった。五月にしては季節外れの暑さだったし、作業も長ったらしくて退屈なものだった。自らを抜け目のない女性だと信じているプリシーが、どうしてそんなに盲目的でいられるのだろうと私はしばしば不思議に思っていた。希望が通るなら、自ら進んでいくくらい、庭の仕事はちょうどやりたい仕事だった。私が求めていたように体力的にきつい仕事であるだけでなく、外仕事であるためプリシーから逃れられたし、パルミラと一緒だったのだ。
その日の昼食の時間、リチャードの姿は見えなかった。あとで庭に戻った時、私はそのことについてパルミラに言ってみた。するとパルミラは、「あら、あなた聞いていないの。彼、上流の製材所の建設現場へ送られたのよ。自分から行きたいって言ってね」と言った。
ステファン、それからリチャードが二人とも製材所にいるのだ。「他には誰が?」私は尋ねた。
「ブラザー・ランキンとか、ノース・ファミリーのほとんどの男の人みたい」
午後の残りの時間、私たちは黙ったまま仕事をした。私は次から次へと忙しくいろいろなことを考えていた。もちろん製材所にいるリチャードのこと、それからステファンのこと、今は奴隷と共に私たちのところから去ってしまったウィリアムやアマンダのこと、それにサブリナのこと。様々なことを考えながらも、私は絶えず豆の苗のあいだに鍬を入れ、雑草を刈り、まわりの土を耕していた。
太陽は私の肩に容赦なく照りつけ、次第に私のドレスは汗でびっしょりになってしまった。汗で濡れた衣服が肌に触れると、ほんの少し涼しさを感じられた。外から見ると、この村はどれだけ平和に見えることだろう。ブラザーたちもシスターたちも静かに彼らの仕事をしているし、穏当なうえに物静かだけど、しかし彼らはいつも忙しそうに何かしているのだ。外から見ただけでは、彼らのぐらぐらと沸き立つような怒りや、恐ろしく感情的な一面なんて知る由もないのだ。
私はステファンのことを思った。彼の骨ばった学者の顔を、瞳の中の古典への夢を。彼の自由への確固たる意志を妨げることなどできようか。
私はアニーのかしこまった態度を、彼女の可愛らしいうつむいたまつ毛、男の視線を気にしながらおめかしをしていたあのまつ毛を思った。それから、サブリナのふくよかな可愛らしさと潔白さを思った。私は、自分が切望するものに思いを巡らせた。私たちは皆、本当にお互いを知っていたのだろうか。私たちは誰しも、仮面に隠された本当の自分を明かすこともできずに、それぞれの夢に悩まされながら孤独に生きていたのではないだろうか?
第18章訳註
(1) 製材所
研究調査ページ参照