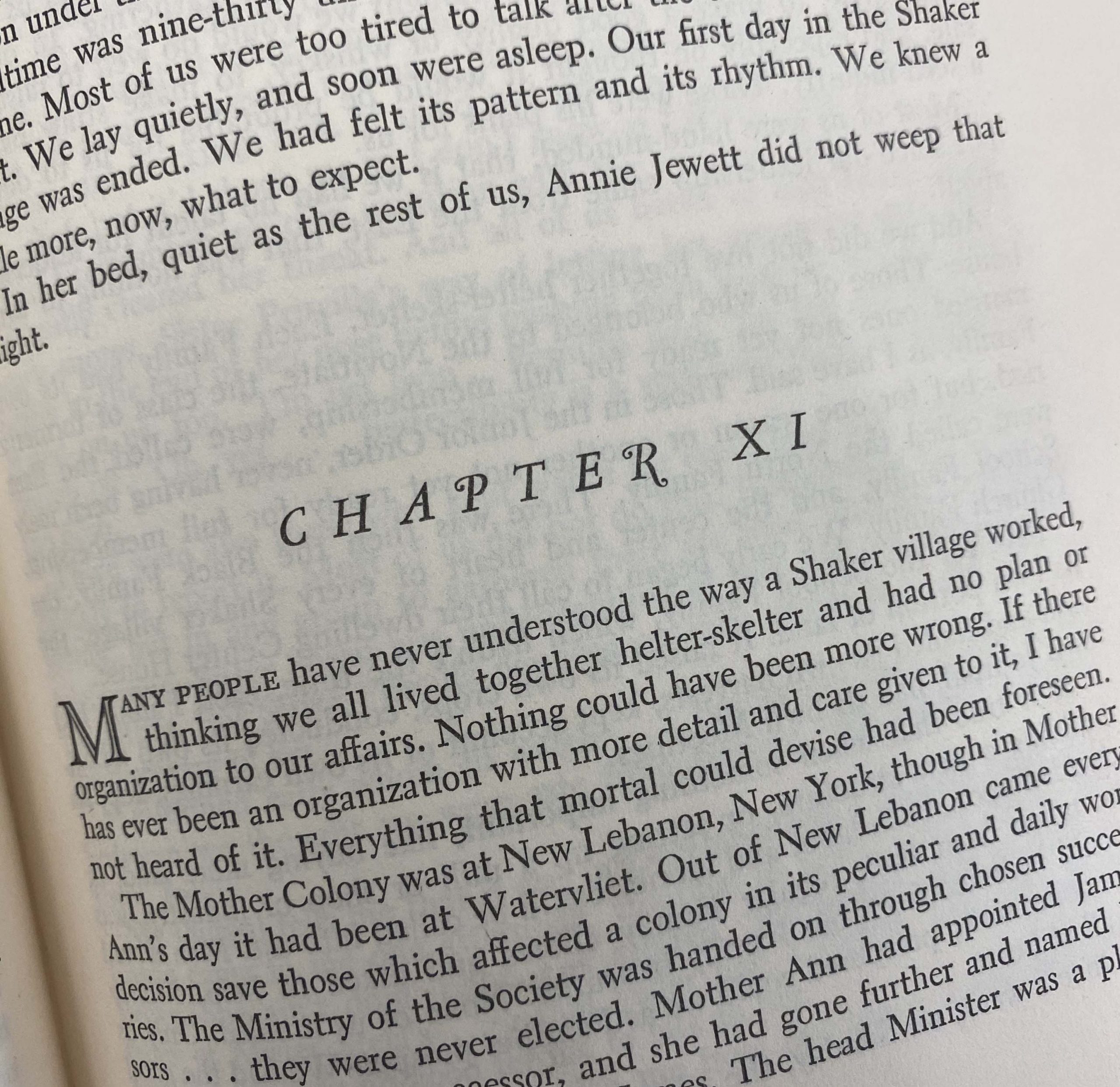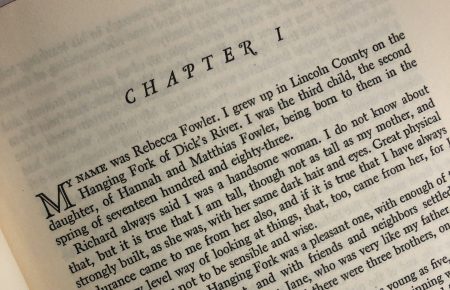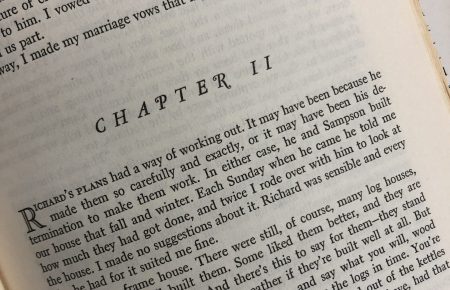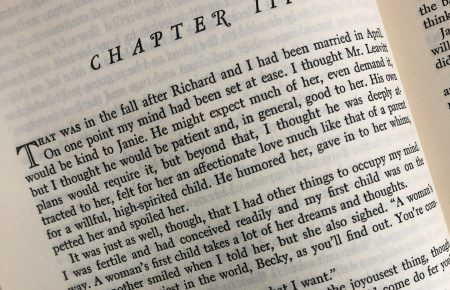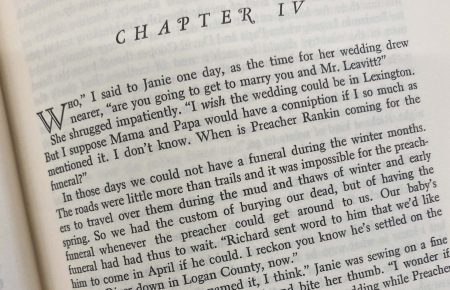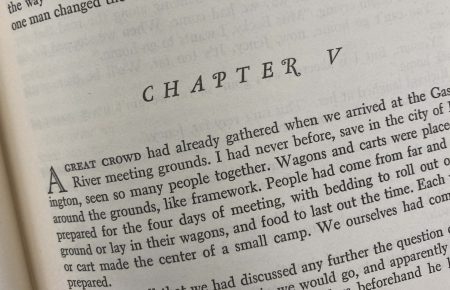たくさんの人々が、シェーカーの共同体がどう運営されているかをまったく知らず、計画も組織もなしに、行き当たりばったりに生活していると思っていた。これはまったくのでたらめで、シェーカーの共同体ほど綿密に計画された組織を聞いたことがない。シェーカーの共同体は、人間が考えうることすべてを見越して計画されていた。
母体組織(Mother Colony)はニューヨークのニューレバノンにあったが、マザー・アンがいた頃はウォーターブリートにあった。一つの共同体に限ったことや些細なこと以外は、すべてニューレバノンが決断を下した。共同体の(1)ミニストリーは選挙によってではなく、前任者の指名によって決められた。マザー・アンは自分の後継者としてジェームス・ウィタカーを、ファーザー・ジェームスの後継者としてジョセフ・ミーチャムを指名した。最高指導者(the head Minister)は終身制であった。それはまるでローマ法王のような立場だったと思う。
各コミュニティのエルダーとエルドレスは、現在の最高指導者である(2)マザー・ルーシーによって任命された。私たちがサウス・ユニオンにいた頃、西部の共同体はまだ新しく、お手本となるものが必要だと思われていたため、エルダーたちは東の共同体から派遣されていた。また、エルダーたちも終身制で、節度のない振る舞いをした場合にのみ解任された。私たちの指導者、(3)ブラザー・ベンジャミン、ブラザー・ジョセフ・アレン、シスター・モリー・グッドリッチ、そしてシスター・マーシー・ピケットは、まだ任命されていなかった。彼らはのちにエルダーやエルドレスの役職についたが、いきなりではなかった。
日記はすべての共同体でつけられ、ニューレバノンへの徹底的な報告が義務づけられていた。そしてほぼ毎年、指導や助言をするために、東部から指導者が送られてきた。
東部の共同体では作業場が整えられ、種々の産業がすでに機能していた。それぞれの共同体には(4)トラスティーと呼ばれる集団があり、俗世との取引を行っていた。私たちはまだトラスティーを必要とはしていなかったが、ブラザー・ベンジャミンの大計画によると、集結の半年から一年後には私たちもトラスティーを持つことになっていた。ブラザー・ベンジャミンの考えでは、私たちの地域では純血種の家畜の飼育、良質なウイスキーと麦わら帽子を生産し販売するのに適していて、特に(5)種子産業は利益に繋がるだろうとのことだった。彼の私たちへの計画はそのようなものだった。
私たちのほとんどが手仕事に勤しんだ。力には欠けていたけれど、指導者たちも東からやってきたので、何も心配することはなかった。
私たちは無計画に共同生活を送っていたわけではなかったのだ。それぞれのファミリーは自分たちの住居を持っていた。結婚の経験があり、まだ完全には一員になる準備ができていない階級の(6)ノヴィシエイトに所属している私たちは、前にも言ったように、イースト・ファミリーと呼ばれていた。(7)ジュニア・オーダーと呼ばれる人たちは、結婚経験はないけれど、なんらかの理由でまだ完全には一員になる準備ができていない人たちで、ノース・ファミリーと呼ばれていた。それから、ブラック・ファミリー、スクール・ファミリー、そしてシェーカーの共同体の核であるチャーチ・ファミリーもあった。私たちは早くから、チャーチ・ファミリーの住居をセンター・ハウスと呼ぶようになった。
時間のなかったスクール・ファミリーを除いて、それぞれのファミリーは自分たちの土地を持っていた。農作物の栽培、事務的な仕事、収穫物の売買とその収支記録、日記をつけること、そして集会。これらはすべて、ファミリーごとに行われた。
新しい土地を購入したり建物を建設したり、水車や作業場や産業を立ち上げるといった重要なことが決められた時には、労働力とお金の両方が投入された。その時は、男性たちは通常のファミリーの仕事から離れ、手を貸すことが求められた。資金はファミリーの共有財産から供出された。そのことを気にする人はいなかった。共同体の繁栄は、私たちファミリーの繁栄でもあったのだ。私たちは、心からみんなの利益を考えていた。
雨でない限り、毎週日曜日に全ファミリーが礼拝を行うためにミーティングハウスに集まった。私たちは倹約の必要性や財産の価値について非常に自覚的だったため、少しでも地面がぬかるんでいれば、その日は集会場のカーペットを汚す危険を冒してまで礼拝を行うことはなかった。そういう場合、ファミリーごとに集会を行った。
まれに、臨時の礼拝が行われることになると、平日の夜に集まった。しかし、そうでない日には、それぞれの仕事があって、他のファミリーもそれぞれの仕事に励んだ。そして、ファミリーごとに礼拝を行った。
外での仕事を割り当てられた人たちは、他のファミリーの人たちと接触する機会が多かった。例えば、ウォッシュ・ハウスにいた私の場合、他のファミリーから来る女性たちと一緒にいることがあった。同じように、搾乳場にいるパルミラも、他のファミリーの人たちと仕事に取り組んだ。一方で、室内の仕事を担当することになれば、働いているあいだは自分のファミリー以外の誰とも会わなかった。そのようなことから、しょっちゅう同じ顔ばかりを見ているので、私たちはあまり見ない人たちと一緒になることのできる屋外での仕事を好んでいた。私たちは、集まれば決まって、噂話に花を咲かせた。ファミリーで起きたことは他のファミリーの者に伝わり、どんどん話は広まっていった。基本的に、そうやって私たちは共同体全体で起きていることを知っていた。
噂話の中には、ただの過敏な粗探しもあった。それは、同じ部屋で暮らし、同じテーブルで食事をとることで、当人のあらゆる癖を知ってしまうことからくるものに違いなかった。 パルミラはアマンダについてこう言っていた。「彼女、毎朝同じように着替えるのよ! 靴とストッキングを履くことから始めるの。もし彼女が一回でも先に服から着ていたら、安心したでしょうね。でもね、そうしたら逆に驚いてしまいそう」
かわいそうなヴィニー・パークスは、しょっちゅう喉をうるさく鳴らし、痰を切った。この行為に私はいらいらした。みんな、レイシー・エイキンズのひどいいびきを嫌っていた。シスター・プリシラが、眼鏡を鼻から落ちる限界まで押し戻さないことも気に障った。「あたし、あれが地面に落ちる日を心待ちにしてる」パルミラが言った。完璧であることは、実際にやろうとするとすごく大変なことなのだ。
規則を少しでも破る者がいないか見張り、待っていましたとばかりに報告しにいく者もいた。私たちの中にはそのような人はほとんどおらず、知らず知らずのうちに団結していた。一方で、良かれと思って告げ口に勤しんでいる人たちもいた。シスター・スーザンはこれをよくわかっていて、告げ口屋を諭すこともあった。一方、シスター・プリシラは、まるで楽しむかのように、規則を破った人を責め立てた。
私たちは早い段階で告げ口屋を見極め、寝室を共にするグループには告げ口屋はいないようだと思っていた。しかし、それは間違いだった。
日記を見ると、それは十二月のことだった。ちょうど私が酪農の担当になっていた時だった。ある日の午後、悩みを抱えたカッシーが私のところへやってきた。「ミス・ベッキー、ジェンシーのことなんですけど……よい行いをしていないのではないかと心配なんです。ミスター・スティールの男の子に色目を使っていて……クレイトンという名の、黄色い肌をした男の子です。会って話すべきです。私が話してもどうにもならないんです」
私と同じファミリーに属するアニー・ジュエットは、私と一緒に仕事に勤しんでいた。私は彼女に、ナースリーに急いで行き、ジェンシーに一目会うつもりだと伝えた。アニーはうなずいた。そして私の担当分のチーズ容器から目を離さないと言った。「長くはかからないわ」 私は彼女に言った。
もちろん私はその事態をシスター・プリシラかシスター・スーザンのところに持っていかなければならなかったけれど、私はジェンシーを問題に巻き込むのは嫌だった。それに、シスターたちがジェンシーと話し合ってうまくいくとは思わなかったし、まだ彼女に対する責任を感じていた。
ジェンシーは、癪に触るくすくす笑いをしながら私を出迎えた。「ベッキーさん! こっちに来てからなかなか見かけなかったから、会えて嬉しいです」 「ゆっくりはできないわ」私は彼女に言った。「元気だった、ジェンシー?」 ジェンシーは「はい、元気でした!」と言って目をくりっとさせて、くすくす笑った。「とっても元気でしたよ」 「ナースリーはどう?」 「ええ、知ってるでしょ。私小さい子が好きなんです。本当に小さい子が好きなんですよ」
本当にそうだった。ジェンシーはどんな子どもも大好きだった。そして、彼女の長所の一つは、決して子どもたちの世話を疎かにしないことだった。彼女に世話される子どもはみな、愛と思いやりを感じることはたしかだった。たぶん、彼女の気まぐれな性格を埋め合わせるための特別な才能なのだろう。本当に子どもの扱いが上手で、いつも子どもたちは彼女によく懐いていた。
私は単刀直入に要点を言った。「あなたがクレイトンに色目を使っていたことをカッシーが伝えてくれたけど。どういうこと?」 「そんなことしてません」 「カッシーが言っているの」 ジェンシーは鼻であしらった。「ママはみんなを警戒しているから。夜、家の外でうろうろするなって言うんです」 「集会がある時以外は、夜の外出は控えるべきよ。子どもたちと一緒にいなきゃ」 「そうしてます。集会に行く時以外、この子たちを放ったらかしにしたことなんてないです」 「集会には行くの?」ブラック・ファミリーも、他のファミリーと同じように彼らの集会を開いていた。 「ええ、毎回必ず。私、集会が好きなんです。踊ったりうたったり……そういった全部がすっごく楽しいんですよ」 「楽しむためのものじゃないのよ。歌やダンスは、礼拝の儀式なのよ」 「そう。だから神とマザー・アンを讃えて大声で叫びます。誰よりも大きな声で。本当ですよ、ミス・ベッキー。それにしても、おもしろいと思いませんか?」
私がそれに気づいたのは年月が経ったあとのことだったが、シェーカーのミーティングは、実のところ素晴らしい喜びを伴ったものだった。婚姻から得られる恍惚ととても近いところにあって、その代わりになったのだ。ともかく、ジェンシーにしかめっ面をして厳しく言い聞かせた。「いいえ、楽しむものじゃないわ。踊るのは、悪を振り払って神の恵みを得るため。儀式なのよ」 「悪を振り落としています! 私はよいシェーカーですよ、ミス・ベッキー」 私はそれを疑っていなかった。なぜなら彼女の足取りの軽さや踊り方を知っていたから。きっと礼拝中の運動(the exercise)の時には、喜びと活力あふれる動きをするだろうと思った。「クレイトンはあなたに色目を使っているの?」 と私は聞いた。 彼女はくすくす笑った。「そう思います」 私は非常に毅然として言った。「ジェンシー、もしクレイトンと結婚したいと思うならできるでしょう……あなたは解放されているし、彼もそうだから。でももし結婚したら、コミュニティを出なくてはいけなくなる」 「まあ、私たち結婚するつもりなんてないです」 「それならあなたは彼から離れたほうがいいわ。とにかく、いつ彼に会ってるの?」 彼女は意味ありげに私を見た。「ぶらぶらしている時以外は、彼には会いません」
それ以上、真実を知ることはできない。黒人とどんなに個人的に仲良くなったとしても、彼らを本当に理解することはできない。ただ一つだけ、たしかなことがある。彼らが心を閉じて、こわばった表情をしてしまったら、諦めるしかない。それは、白人のあなたはこれ以上近づけません、という彼らのサインなのだ。私には、命令を出す昔のやり方しか頼りにできなかった。「ジェンシー、もういい子になって。これ以上あなたのくだらない話を聞きたくないの。クレイトンのことは放っておきなさい」 「いつも、いい子にしてます」ジェンシーは反発してきた。 「じゃあ、いい子にしているか見てるわ。もしクレイトンと関われば、やっかいなことになる」 彼女は目を見開いた。「どんな問題ですか?」
あの時私はなんと言えばよかったのだろう。私は彼女に男女間にあること、妊娠すること、非嫡出子を持つことについて話したことがなかった。カッシーがすでに伝えていてほしかった。おそらく、その時その場でちゃんと話をするべきだったのだろう。でもそのようなことを、ましてや黒人の女の子に一対一で話すのは私には難しかった。だから私は曖昧にして、「あなたが困るのよ」と言った。
ちょうどその時、隣の部屋にいた赤ん坊の一人が泣き出し、ジェンシーは様子を見にいった。彼女はアニーの赤ん坊をおぶって戻ってきた。「この子、可愛いでしょう?」彼女は言って、彼の髪の毛をおでこから撫でつけて、顔を寄せた。「この子寝ていたんだけど、起きちゃって。お腹が空いてるみたいなんです。アニーさんは今すぐ来てこの子の世話をするべきですよ」
私はその子を少しのあいだ抱っこして、柔らかくふっくらした体に触れた。ずっとこうしたかった気持ちは、その時も変わらずにあったようだ。かつての我が子に対する思いがこみ上げてきてしまって、彼をジェンシーのもとへ戻した。「もう行かなくちゃ。いい、覚えておいてね、ジェンシー。愚かなことはしちゃだめよ」 「わかりました。アニーさんに会ったらロバート坊やが起きたことを伝えてください」 私は作業場に戻るとジェンシーの伝言をアニーに伝え、彼女はすぐに彼のもとへ行った。
その夕食後のことだった。私たちが集会の前に部屋でくつろいでいた時、シスター・プリシラが扉のところにやってきた。戸口に立つだけで、入ってはこなかった。「シスター・レベッカ、一緒に来てください」 何か厄介事がある時、シスター・プリシラはいつもこうして人を呼び出した。私はパルミラに言った。「わかった。私が今日の午後、仕事を抜け出してナースリーに行ったのを見たんだわ」 パルミラは笑った。「頭の後ろにも目があるからね、プリシーは。どうやってあんなに見つけるのかしら」
ホールの端のクローゼットのようなもので、小さな部屋が作られていた。そこではシスター・スーザンやシスター・プリシラが個人的に私たちを見ることができた。シスター・プリシラは、事務机としても使われるテーブルの前にすでに座っていた。部屋に入るなり、彼女は厳しい目つきで私を見た。「帽子が曲がっていますよ」
横になっていたので、帽子のことなんて、気にも留めなかった。私はシスター・プリシラに監視されながら、帽子の向きを直した。「あなた、うぬぼれていますよ。首にかかった巻き毛を自慢しているのですか?」
シスター・プリシラの発言はカッとなるほど理不尽だったが、彼女に文句を言っても仕方がなかった。断固として、彼女は自分の考えに沿うものしか受け入れず、彼女以外の判断を含む意見には耳を貸さなかった。私の髪は、母譲りの太くて黒いくせっ毛だ。着用しなければならなかった小さい白い網目の帽子の中に髪の毛を全部しまう努力をしても、日々の仕事のあいだに、後ろの短いくせっ毛がはみ出してしまう。気をつけようと努力はしたが、常に覚えておかない限りは間違いなくボサボサに見えてしまう時があるのだった。私は、帽子の中にくせっ毛を押し込んだ。
シスター・スーザンは彼女のいるところで人を座らせるけれど、プリシーは立たせっぱなしにする。ある性質を持っている人に権限を与えると、くだらない横暴さを発揮することがある。「今日の午後、あなたが酪農の仕事を放っておいたことが報告されていますよ」と彼女は始めた。 他の人のためだったら、私は嘘をついただろう。でも、これは私自身のことだった。「ええ、本当です。カッシーがジェンシーのことで悩んでいたので、ナースリーに行って少し話しました」 「あなたはきっかり三十分いなくなりました。ジェンシーと何をそんなに話し込んでいたのですか?」 シスター・プリシラに本当のことを伝えるつもりはなかったので、最初に思いついたことを言った。「まあ、ジェンシーはカッシーに対して生意気だったので彼女を叱っただけです」 「あなたは、私かシスター・スーザンのところに来るべきでした」私が言い終わると彼女は言った。 私は丁寧な口調を心がけて、「私のほうが、シスターたちよりも彼女をもっとどうにかできると思ったんです」と言った。 「大きなうぬぼれです! そういったことはすべて、ファミリーの指導者の仕事です!」シスター・プリシラは突然激しく怒りだした。「いつになったら、その黒人たちに干渉しなくなるんですか! 彼らはもう、あなたのものではないのですよ! あなたの思い通りにはできないのです!」 私は黙っていた。 プリシーが薄い手をこすり合わせると、乾いた紙みたいにカサカサ音がした。「小さい納屋に行ったのですか、シスター・レベッカ?」 「小さい納屋ですか? 行っていません。私に納屋へ行く理由がありますか?」私は訝しんで言った。 「私が質問しているのですよ」彼女は私にぴしゃりと言った。それから彼女は素っ気なく付け足した。「ブラザー・リチャードの今月の仕事は、納屋にいる仔牛の世話です」
言いたいことは明白だった。仔牛のいる小さい納屋は、ナースリーからとても近かった。しかし、私はリチャードの仕事を知らなかったし、もし彼がそこにいると知っていても探そうと思わなかった。私の信念が強かったからではなく、彼のがそうだったからで、探すことには何のメリットもなかっただろう。私は正直に言った。「それは知りませんでした。納屋に行ったと報告されているのですか?」 「何が報告されているかなんてどうでもいいのです。納屋に行ったかどうか聞いているんです」 「さっき行っていないとお伝えしました。たしかに証明できるものは何もないし、あなたの考える通りに、どう判断していただいても構いません。でも、本当に納屋には行っていません!」
シスター・プリシラの目が激怒した。「シスター・レベッカ、恥を知りなさい! 傲慢で横柄なあなたの魂は、皆の前で改められなければなりません」 「私は傲慢なのかもしれません。でも納屋に行っていないのは事実です。シスター・プリシラ、もう一つ言わせていただきます。ジェンシーをカッシーの近くで働かせなければ、あなたは後悔することになります」 「誰がどこで働くかは私が決めます」彼女はいらいらしたように言った。「私は自分の判断に対して後悔することはありません。あなたの意見が欲しい時には、こちらから聞きます。もう行っていいです」
私は喜んでその場を去った。シスター・プリシラの勝手な決めつけに、私のはらわたは煮えくりかえった。また、彼女が私を信じていないことはたしかだった。もし本当に辱めを受けることになったら、受けよう。その辱めとはファミリーミーティングの前に、おそらくさらにはフルミーティングで、横柄さや尊大さについて責任を問われることである。そしてすべてのメンバーが「恐ろしや」と叫んで、彼らの前で恥をかかされるということを意味している。あまりこういった考え方をしたくはないけれど、その時は、座って静かにプリシーの陰険な嫌味を聞くよりも、少しのあいだ耐えて、辱めを受けたほうがましだった。
その夜、みんなが寝ついてから、例の出来事をパルミラに伝えた。 私はまだ怒って動揺していた。「告げ口した奴がいるのよ」パルミラが言った。「プリシーは抜け目ないわね、でも全部を知れっこないわ」 「私がいないあいだ、彼女は酪農場に行っていたのかもしれない」 「違うと思うわ。だって、私が糸紡ぎの仕事場にいた時、そこで彼女を見たもの。やっぱり誰かが告げ口したのよ。あなた、誰と一緒にいたの?」 私はその場にいた女性たちの名前を挙げていった。 「私たちと同じファミリーなのはアニーだけよね?」 「ええ」 私たちは口を閉ざして、同じ考えに至った。「アニーなわけないよね、パルミラ? だって、私たちみんな、ずいぶん彼女の味方をしてきたもの」 「しーっ…… 考えているところよ」
しばらくして、パルミラが再び話し始めた。「私がトーマスと落ち合って、少し話した時のこと覚えてる? アーロンがカタルで倒れて、会ってほしいとお願いするためにトーマスと会った時よ。プリシーは許可しないとわかっていたけれど、リチャードはしばらくのあいだトーマスを自由にしてくれると思っていたわ。ところがね、プリシーはそれを前の晩に知っていたの」パルミラは笑った。「彼女は私たちが屋根裏の干し草置き場に上がっていって、そこでじゃれ合っていたかのように振る舞っていたわ」それから彼女は冷静になった。「その時、アニーは私と一緒にウォッシュ・ハウスで仕事をしていたわ」
私たちの誰かが告げ口された他の時のことを考えても、つじつまが合ってきた。アマンダがスクール・ハウスにいる彼女の子どもを見るために抜け出した時……、レイシーができたてのワインを飲みすぎたせいで居眠りして、午後のあいだずっと彼女の仕事を他の人たちがしていた時。アニーはいつもいた。「彼女ね、間違いないわ」パルミラは言った。「他の誰でもないわ。すべてうまく話が繋がったわ」 「でもどうして? どうして彼女は告げ口をするのかしら? 彼女は何を得すると考えているのかしら?」 パルミラはしばらく静かにして考えていた。それから彼女は言った。「彼女がプリシーの機嫌をとっているように思えるわ。自分がうまくやり過ごせるように」
私たちはみんな、彼女が踊りや礼拝運動(the exercises)の時にロバートの近くで顔を赤くしていたのを見ていた。私たちはみんな、彼女に哀れみを感じて、それを胸に秘めておいた。しかし他に何が彼女の考えにあったのだろうか? 突然、私は彼女が一日に何回かナースリーに行かなければならなかったのを思い出した。その納屋はとても近くで、ナースリーまでの道沿いにあった。私はベッドの上で背筋を伸ばして座った。「パルミラ、ロバートがリチャードと一緒にその納屋で仕事をしていたに違いないわ。彼女は彼に会いに抜け出したのよ」 「その通りね! 理にかなっているわ。どうしてこれまでそれを思いつかなかったのかしら?」
しかしさらに疑問があった。アニーが納屋の中でロバートと会った時、リチャードはどこにいたのだろう? 「まあ、ベッキー……牛たちと一緒に牧草地にいたんじゃないかしら。塩をあげたり、あちこち移動させたり。簡単にアニーにリチャードがそこにいるかどうかを知らせる合図を作ることができたのね」 「私たちは何をすべきなのかしら」 「彼女から目を離さないことよ。あなたは彼女と酪農の仕事をしているわ。彼女がナースリーに行く時に、ドアの近くで作業をする言い訳を作るのよ。納屋の扉か窓に何か掛けられてないか見るの。たぶん、それはロバートのジャケットやハンカチみたいなものだわ。とにかく彼女から目を離さないで」
私はそうした。でも数日間アニーはまっすぐナースリーに行った。それからある午後、私がドアの外でリチャードが牛の一団を集めて外の丘の牧草地に行くのを見た時、牛小屋の藁を積み上げる熊手が納屋のドアに立てかけてあった。ロバートは熊手を手にして納屋から出て、リチャードを少しのあいだ見た。それから、ごくごく自然に熊手を下ろして、開いたドアに立てかけた。私は忙しくしていたが、アニーを見ていた。彼女は酪農の部屋の端で働いていて、壺とたらいを洗っていた。洗い物が全部終わって、近くにかかっていた麻布で手を拭くと、彼女は大きなため息をついた。「ふう! 外の空気を吸わなくちゃ」と彼女は言った。
その時、私は彼女が頻繁に、毎日息抜きのためにドアのところに立ちに行っていることに気づいた……それは十二月のことだった。彼女はドアのほうにゆっくりぶらぶら歩いていって、途中で立ち寄って樽の中をじっと見た。まるでそれらを管理しているかのように。彼女はドアを開けて、そこに少しのあいだ立っていた。それから笑って、彼女は自分の胸を押さえた。「私の赤ちゃんにミルクをあげる時間よ。もう出てきて、ドレスにしみてしまった。長くはかからないわ、もしプリシーが入ってきたらそう言って」私たちみんなと同じように、彼女はシスター・プリシラをプリシーと呼んだ。
私は、外の様子を見ることができるように、窓の側にある棚からしわのないきれいな洋服を取るふりをした。しかしアニーはまっすぐ納屋に行くという間違いを起こさなかった。 彼女はナースリーへの道を歩いていった。片側にハシバミの茂みがあって、彼女が納屋を通り過ぎたあと、私は彼女がその茂みから納屋の裏口に抜け出すことがとても簡単にできると気づいた。私が見ていたどの日も、彼女はそうしていたかもしれない。私は熊手を合図だとは考えていなかった。それも私の見ていたどの日にもそこにあったかもしれない。ほとんど完璧な計画だった。
私は自分の分担の仕事を続けた。戻ってきた時のアニーは、愛を受けた女性らしく頰を紅潮させていて、幸せそうに見えた。陽気に彼女は言った。「私の赤ちゃんはたしかに育っているわ」彼女は笑った。「男みたいに吸いついてくる」
結婚していたことがなかったので、他のシスターたちはショックを受けていたようだった。私は、センター・ハウスの小柄で未婚のシスター・サラが、髪の生え際まで紅潮させていたのを覚えている。彼女は、突然凝固乳を注ぐのに集中し始めた。そして注ぐ時、彼女の手は震えていたので、床に牛乳がこぼれた。アニーは彼女をじっと見て、それから意地悪く言った。「どうしたの、シスター・サラ? あなたのに吸いついてきた男はいないわけ?」 シスター・サラはわっと泣き出した。「どうしてそんなことが言えるの? 品が悪いじゃない!」 アニーは肩をすくめた。「あなたみたいな人たちのほうが、おかしなことをしてるじゃない」 彼女がスカートを振った時に、後ろの裾に干し草が付いているのが見えた。私はそっとかがんでそれをとった。「アニー、私があなたならシスター・サラをからかうのはやめるわ」私は干し草のはしきれを彼女に見えるように持って言った。「あのハシバミの茂みはすごく乾燥していたみたいね。こうやってあなたのスカートにくっつくくらいには」 彼女は顔面蒼白になり目を見開いた。彼女は手で口を覆った……それから彼女は堂々と白を切った。「そうね。もし少しの火種があれば燃えていたでしょう」
パルミラと私はその夜再び話した。アニーがぐっすり寝入っていないことがわかっていたので、私たちは小声で話した。ついに彼女はベッドの上に座った。「私について小声で話しているなら、言いたいことをはっきり言ったらいいじゃない」 「わかったわ」私は言った。「私のベッドまで来て。ちゃんと言うわ」 彼女はこちらへ来た。 パルミラは彼女に「あなたが何をしているかみんな知っているわ。プリシーに知らせてほしくないなら、私たちの些細な行いについて黙っていることね。それ以外は何も気にしてないわ。少なくとも、私たちの誰もあなたがやっているようなことはしていないわ」と伝えた。 「私は何も言っていないわ」アニーはふてくされて言った。 「あら、違うわ、あなたは言ったのよ。私たちの誰かが告げ口された時はいつも、あなたが近くにいたんだから。プリシーの目がいくら鋭くても、すべてもれなく見ることはできないわ。彼女に告げ口してる人がいて、それはあなたなんでしょ。あなたは姑息で卑劣な蛇よ、アニー・ジュエット。この部屋のみんなが、その目で見て、報告することもできたけどしなかったことだってたくさんあったのよ。私たちはあなたの味方だったのよ。あなたがやっていることはユダの裏切りに匹敵するわ。何があなたにそうさせたの?」 アニーは泣き出した。「今までロバートに会わないことに耐えられなかったの。 私は彼に会わなくてはいけなかったわ。他の人のことで告げ口しておけば、プリシーは私のことを疑わないと考えたの。私は善良すぎてそんなことできないと考えるだろうと思って」 パルミラは鼻であしらった。「あなたは臆病なねずみより度胸がないものね。あなたの味方を密告するなんて」 アニーはむせび泣いた。「私はただこういう離ればなれの状態に我慢できないの。それに、私はこういう女の人たちと一緒に暮らすのが大嫌いよ。あなたも、ベッキーも、アマンダも、みんな嫌いよ! あなたたちがどれだけトラブルに巻き込まれても、私には関係ないわ!」 「立場をわきまえなさい……私たちだって、あなたを差し出せるのよ。今すぐに気をつけるべきよ!」 アニーは涙を拭いて、部屋の中を見回した。「あれを見てよ! あの質素さと惨めさを見て! ここには素敵なものなんて一つもないじゃない。ペグにかかっているあのドレスを見て! なんて醜いの! これより醜い服なんて思いもつかないわ。こういうのが全部嫌いなの!」
その時には新しい洋服ができていた。可愛くて派手なものを愛する人にとって、その服はとても質素で見栄えが悪いのだろう。チャーチ・ファミリーのシスターたちは時間がなかったので、作る色は少しだけと決めていた。彼女たちは、他の染料を作るにはあまりに時間がかかりすぎるだろうと言っていた。私たちには、青、茶、赤色の服しか提供されなかった。赤の服はあまりにも色が濃くてほとんど黒だった。私は青と茶を選んだ。パルミラは同じようにして、他のシスターたちもそうだった。しかしアニーはどちらの服も赤を選んだ。
シェーカーの女の人の服は簡素で質素なものだ。胴着とウエストバンドのところでプリーツの入ったゆったりしたスカートがあった。もちろんスカートは地面につく長さだった。そしてシェーカーは、たとえ女性の胸の形がわかるのでさえも不適切だと考えていたため、私たちはみんな白いスカーフを首の周りにかけて、前に持ってきて胸の前で交差させた。白いスカーフは往々にして体型をより丸くふくよかに見せるだけだったので、シェーカーは、女性のありのままのふくよかな身体を隠す方法として下手なやり方を選んだものだと何度も思った。例えば、パルミラはスカーフでは隠せなかったし、私も問題を感じていた。
涙がまたアニーの目からあふれた。「まあ」私は言った。「嫌ってもただの労力の無駄遣いよ。あなたはここにいるんだし、ロバートがいる限りここに留まるんでしょう。慣れたほうがいいと思うわ」 「もし私が好きなようにできるなら」彼女は怒って言った。「私たち二人とも、あなたが思う以上に早くここを立ち去るわ」 「あら」パルミラは言った。「それがあなたの狙いってことね。ロバートに脱退するように説得しようとしているのね。彼が不満を抱いて脱退しようとするのに期待して、彼の欲望を掻き立てるために干し草に押し倒させようとしているのね。あなたならわざとファミリーの邪魔をしかねないわね、彼があなたを連れて出ていかざるをえなくなるように」 「できることならそうしたかったわ!私の調子が戻るよう、ロバートをここから引き離せられればいいのに!」 「まあ、私はあなたを咎めることは少しも言ってないわ」パルミラは笑って言った。「もしロバートが私のものだったら、私もきっと同じことをするわ。でもあなたは罪を犯していないのだから、センター・ハウスのプリシーやシスター・スーザン、シスター・モリーを説得するのに苦労するでしょうね」 「そんなことしようとしてないわ」 「そうでしょうね」 「告げ口しないわよね?」アニーは心配そうに聞いた。 「あなたが私たちのことを告げ口していたのを考えると、言わざるをえないわね」 「もうやめるわ。これ以上はしないわ」 「誓える?」 アニーは右手を挙げた。「誓います。もう何も告げ口しません」 「プリシーは変に思うでしょうね……あなた今まで彼女のところにすぐ駆けつけるくらいいい子にしてきたものね」 「彼女の好きに思わせておくわ。もしあなたが告げ口しなければ、証明できるわ。」 「ベッキーはどう思う?」
告げ口をしようと思ったことは一度もなかったが、パルミラはもう十分にアニーを脅したと思った。私としては、アニーとロバートが何をしたかはどうでもよかった。私は、彼女がロバートをここから引き離すことができるかもしれないことが羨ましかっただけだ。「また告げ口されない限り、私たちも言わないわ」私は言った。 「それはないわ」アニーは言った。「私からは。私は誓ったもの」 私は彼女の誓いに大した価値があるとは思わなかったが、ロバートとの関係が知られて、彼が砂糖製造や製材の仕事に異動させられることへの恐れが彼女を止めるだろうと考えていた。 パルミラは横になって掛け布団を引っ張り上げた。「まあ、もう寝ましょう。プリシーがすぐに覗きにくるでしょうし、他の人が目を覚ますかもしれないわ。私たちが今話したことをよく考えておきなさい」 「そうするわ」
少ししょんぼりしてアニーは自分のベッドへ戻った。彼女はずっと告げ口をしていて、それは咎められるべきことだと思った。でも私は彼女をかわいそうに思った。もし私が彼女のように、それほど強い信念を持たない夫と一緒だったら、彼女と同じことをしたかもしれない。告げ口ではない……私はそんなことは絶対しないだろう。でもリチャードが納屋から私に合図していたなら、私はすぐにでも飛んでいっただろう。
再び部屋が静かになった時に涙がこぼれたが、それは私へ合図が送られることは絶対にないからだった。あるかもしれなかったと信じ込むことは決してできなかった。夫についていくと、ひどく孤独な場所に辿り着くこともある。そのさびしさが私の日記のページの上のしみの原因なのだ。
第11章訳注
(1)ミニストリー(Ministry)
シェーカーの宗教的な指導について最終的な責任をもつ男性または女性のことを指して「Ministry」という。複数の共同体ごとに男女二人ずつで担当していた。それぞれのファミリーの長である長老に比べて、宗教的および俗世的な管理について高度な役割があった。本ゼミでは「ミニストリー」と訳した。
(2)マザー・ルーシー
ルーシー・ライト(Lucy Wright, 1760-1821)は実在した女性教徒で、指導者の立場についていたという記述が残されている。同じ指導者の立場にあったジョセフ・ミーチャムと二人で10年にわたって教会を率い、1796年にジョセフ・ミーチャムが他界した後は、マザー・ルーシーが25年間トップの立場で教会を率いた。ジョセフ・ミーチャムとルーシー・ライトは米国で生まれた最初のシェーカー教指導者であった。
(3)ブラザー・ベンジャミン
ベンジャミン・セス・ヤングス(Benjamin Seth Youngs,1774-1855)は、19世紀初頭にオハイオやケンタッキーで布教活動を行った、最初期のシェーカー教宣教師。1805年から約20年間オハイオ州の共同体で生活し、長老の役目以外に、時計工や機械工としてはたらいた。シェーカー教の神学を文書で記した “The Testimonies of Christ’s Second Appearing”(1810)の著者の一人。
(4)トラスティー(Trustee)
シェーカー教の共同体において、外部との取引や財政管理を担った役職。財産運用係という側面から、コミュニティの持続性にも大きな影響力を持っていた。
(5)種子産業
18世紀の終わりから、様々な種類の野菜の種が複数のシェーカー・コミュニティで独立して作って売られるようになった。その売り上げがシェーカー・コミュニティの収入の大部分を占めていた。田舎の市場を相手にしていたので、19世紀中頃に輸送手段が発達したことで競争力がなくなり衰退した。
(6)ノヴィシエイト(Novitiate)
シェーカー・コミュニティに入ったばかりで、シェーカーの生活を試している成人のことを指す。18歳以上の者は俗世から離れる契約書に署名することで、コミュニティの恩恵を受けることができた。また、ノヴィシエイトのメンバーでもミーティングに参加すること、日々の労働を行うことは必須であった。
(7)ジュニア・オーダー(Junior Order)
チャーチ・オーダーに加入する契約をしていないシェーカー教徒たちが属するギャザリング・オーダー(Gathering Order)のうちの一段階を指す。ジュニア・オーダーには、試しにシェーカー教の生活を体験しようとする段階の人々が所属し、俗世との関係を断ち切る義務はなかった。しかし、この語の正式で明確な定義は残されておらず、シェーカー教のなかでどれだけこの語が一般的なものであったかは不明である。