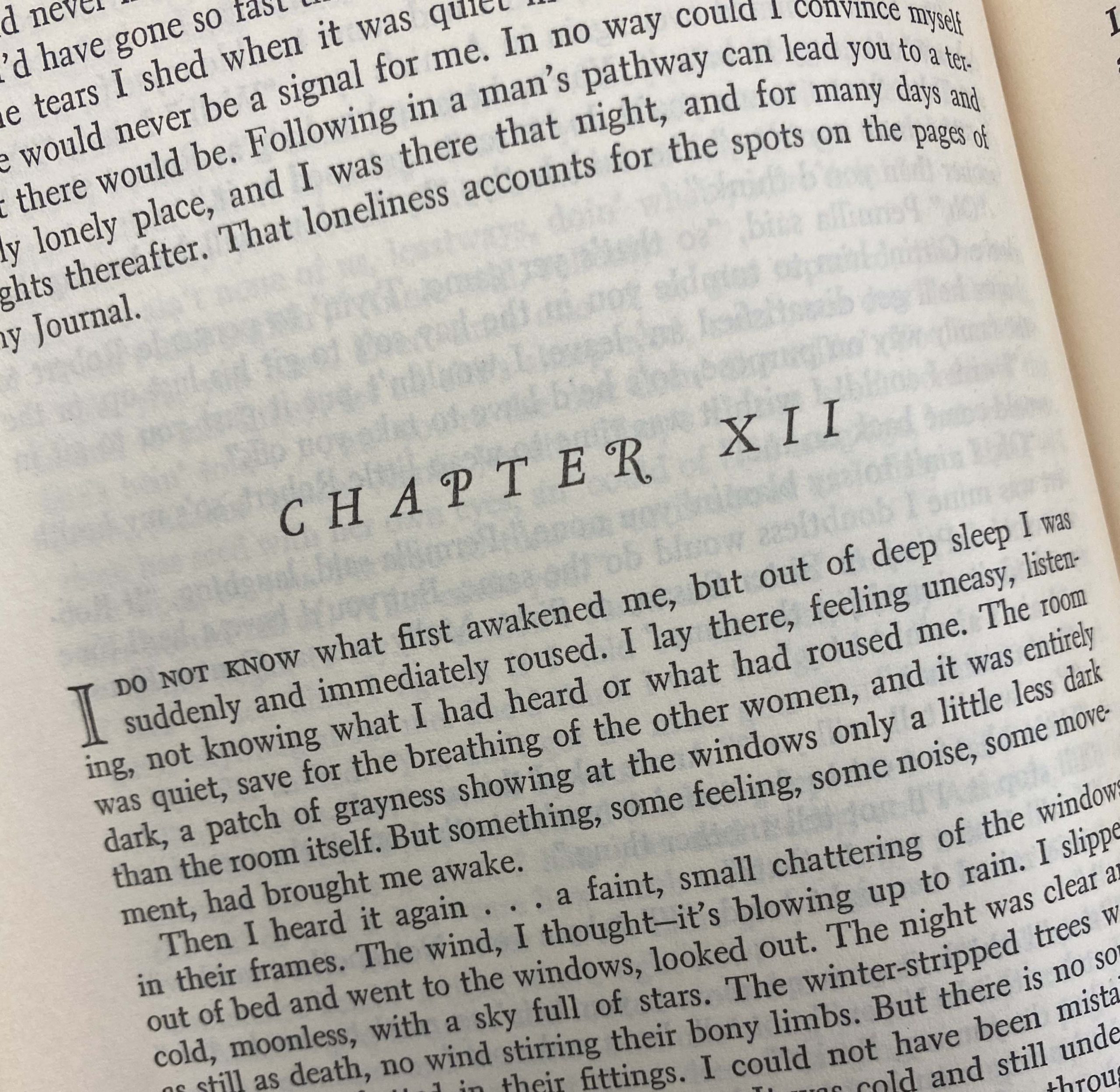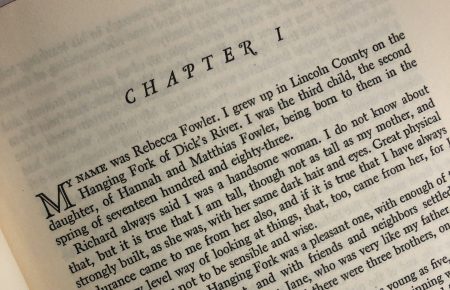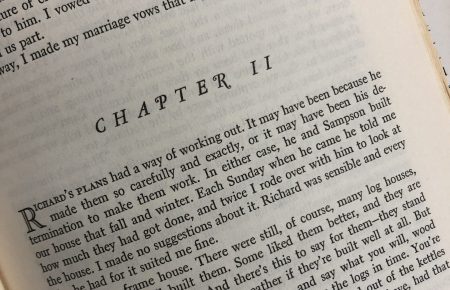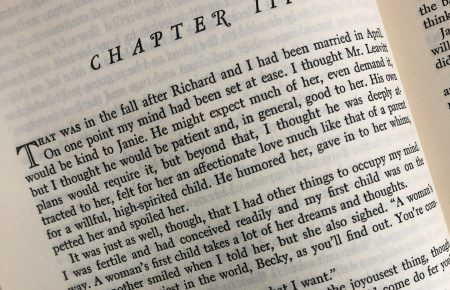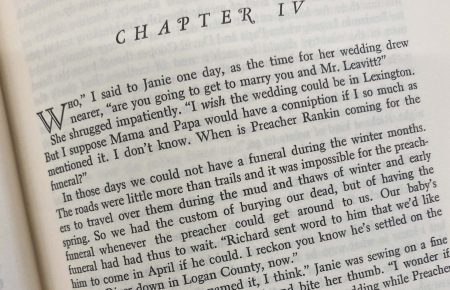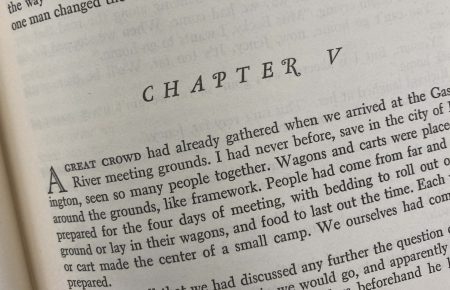何が最初に私を目覚めさせたのかはわからないが、私は深い眠りから、突然呼び起こされた。何が聞こえたのか、何が私を目覚めさせたのかもわからず、落ち着かないまま耳をすませて横になっていた。部屋は他の女性の呼吸を除いて静かで、完全に暗かった。灰色の四角い窓は、部屋よりも少し明るく光っていた。何らかの予感か物音か気配が、私を目覚めさせた。
再びそれが聞こえた。フレームにはめられた窓のかすかな、ガタガタという音だった。風が雨を吹きつけているのだった。私はベッドから滑り降りて、窓の外を見た。夜は澄んでいて寒く、月は見えないが、星がところ狭しと空を覆っていた。冬が来て裸になった木々は、死んだようにじっと動かず、やせた枝を揺らす風はなかった。窓から音が鳴っていたような形跡もなかった。しかし私の聞き間違いだったはずはなかった。
私はガラスに手を当てた。静かに手のひらに冷たさが伝わった。しかし、そこに手を当てていると急に振動し、ガラスが揺れ、窓枠が震え、ねずみが壁を引っ掻くような音がした。
そして、私の素足の下で床が震えた。家が――と私は半狂乱になりそうになりながら思った。家全体が揺れている。ぎょっとして、私は辺りをうろついた。ベッドに向かって走っているあいだ、床全体が傾き、まるで下り坂を走っているようだった。(1)ローラーがついたベッドは部屋の端に向かって滑り始め、誰かが床にどすんと落ちた音が聞こえた。泣き叫んだ声を聞いて、すぐにヴィニー・パークスだとわかった。「ああ、ベッドから落ちたわ! 誰か私を助けて。床に落ちたの!」それから顔を布団で覆ったかのように彼女の声がくぐもった。
私は人生で、ここまでうろたえ混乱したことはなかった。足元の床が震え傾き、ベッドが転がり回り、風がないのに窓がガタガタと音を立て、まるで大地を震わせながら、何かが巨大な足で歩いているかのようだった。それは奇怪で薄気味悪く、この世のものとは思えない恐ろしさだった。リチャード、私は思った……リチャードのところにすぐに行かなければならない。本能的だった。危険な状況の時、リチャードはいつも私のそばにいた。 私はドアに向かった。
今や誰もが目を覚ましていて、がやがやとたくさんの声が聞こえていた。私はホールを走る足音を聞いた。「何が起こっているのですか?」誰かが言った。「何がベッドを転がしてるの?」その時、ヴィニーの哀れな、くぐもった声が聞こえた。「何かが私の上に落ちた! もううんざり! このベッドを私からどけて……助けて、誰か助けて!」 ドアノブに手をかけた時、私に理性が少し戻ってきた。明かり、と私は思った……明かりを灯して、ヴィニーを助けなければ。
揺れが止まり、家が静かさを取り戻した。「みんなその場にいて。ろうそくを見つけて明るくするわ」と声をかけた。
私はろうそくを探し回った。火を灯すのに手っ取り早い方法は一階にある暖炉の炭からだと思い、ろうそくを持ってホールへ走った。しかし、すでに服をしっかりと着て、明るいろうそくを手に持ったリチャードがホールにいた。私がひどく怖がっているのと比べて、彼は驚くほど冷静で落ち着いて見えた。恐怖の中で私は彼に駆け寄り、そして彼は私をしっかりと抱きしめた。「大丈夫か?」彼はろうそくを持ちつつ私を抱きしめるのに苦労しながら言った。「ベッキー、大丈夫か?」
ああ、彼の腕の中はなんと心地いいのだろう。私は安堵して熱におかされたように震えながら泣き、彼の胸に寄りかかり、耳元にある彼の心臓の鼓動を聞いていた。私はすすり泣きながらも、なんとか「大丈夫」と言った。彼の強さと、再び私に温かさをもたらした、たしかながっしりとした肉体から二度と離されたくないと思った。しかし、すぐにリチャードは何かを思い出したかのように、私を突き放した。
もう一度彼に抱きしめられたくて彼のほうによろめいたが、彼は私に目を向け、だめだという顔をした。「部屋着じゃないか、ベッキー」 「わかっているわ。私は明かりを灯しにきたのだから」 男性の部屋からも女性の他の寝室からも、騒音と混乱が聞こえてきた。「ほら」彼は、炎を差し出して言った。「急いで自分の部屋に戻るんだ」 私の手は震えていて、芯をほとんど炎に当てることができなかった。「何なの?」私は囁いた。「何が起きているの?」 「わからない。誰もわからない」 「それでも、何ができるかしら?」 リチャードはもどかしげに言った。「誰にもわからないと言っただろう。今はろうそくを持って急いで部屋に戻るんだ。服を着て、他の女性たちにも服を着させて。何があっても、私たちはきちんとしていなければならない。誰かが来て、何をすべきか教えてくれるはずだ」
しかし、彼はたしかに私のことを考えていた。彼は私の安否を第一に気にかけていた。私は部屋に走って戻りながら、それを自分自身に言い聞かせ、喜びに浸った。彼はまだ私への気持ちがあったのだ。そして、私の部屋着姿に向けられた彼の目は難色を示していたが、同時に過去を思い出しているようだった。記憶が完全に消されることはないのだ。何年ものあいだ、彼はこの部屋着の下の隠れた身体を知っているのだ。彼はしまい込んでいるが、それを知っている。贖われた聖者でさえ、ときには自分の記憶を引き出し、ひそかに心を満たす必要があるのだ。
寝室は乱雑としていた。すべてのベッドは転がり、ひとかたまりになっていた。 部屋を簡単に清掃するために、ベッドには子どもが片手で押してもスムーズに動かせるくらいのローラーがついていた。今やそれらは傾いた床を転がり、壁に沿って積み重なっていた。ほとんどはきれいに積み重なっていたが、いくつか歪んでいるものもあった。ヴィニーのベッドは、私が恐れていたように、ひっくり返っていた。
パルミラは部屋の真ん中に立っていた。アニーは彼女にしがみつき、白い顔をしてすすり泣いていた。アマンダ・スティールは窓際に立ち尽くしていた。レイシーのベッドの上にはあたかも布団をかき集めたようないびつな塊があり、その下からはレイシーのうめき声と祈りが交互に聞こえていた。私はろうそくをホルダーに置いた。「アマンダ」私は叫んだ。「レイシーが怪我をしていないか確認して! パルミラ、ヴィニーを見つけるのを手伝って」
アマンダは窓から素早く振り向いた。「私はレイシーが怪我をしているかなんて関係ないわ。息子のところに行くわ」彼女はそう言うと、私たちの前をさっと通り過ぎてドアから出ていった。
私はアニーの肩をつかんで、揺すった。「静かに! 服を着て、今すぐ着て!」 「これは裁きよ」彼女は私の手から後ずさりしながら、唸った。 「これはロバートと私が罪を犯したことによる裁きなの。世界の終わりだわ」 「神はあなたとロバートが罪を犯したくらいで、世界を終わらせたりしないわ」私は彼女にきつく言った。「パルミラ、ベッドの下にヴィニーがいるか探して」
私はレイシーに被さった布団を次から次へと引きはがした。彼女は膝をついて、丸々とうずくまり、頭をうずめていた。「私たちは死んだの?」彼女は言いながら、明かりに目を瞬かせた。「ここは天国なの?」 「まだよ」と私は言った。私も怖かったが、笑いをこらえられなかった。「もしもう少し長く布団の下に埋まっていたら、天国に行っていたところだったわよ。さあ、服を着て」
パルミラはすぐには起きられない性質だったため、動きが遅く、まだ眠気でぼーっとして怖がっていなかったようだ。私はヴィニーのベッドで悪戦苦闘しているパルミラの元に走った。
私が彼女に向かって走っていった時、アニーが泣き叫んだ。「ああ、(2)壁にかかった服を見て!」 私は彼女が指差すほうを見た。ドレスはまるで風に吹き上げられたかのように揺れ、そして今度は別の方向に床が傾き始めた。ベッドが再び転がり始めた。パルミラと私は、それらとヴィニーのひっくり返ったベッドに挟まれ、それらを押し返すように身構えた。パルミラはヴィニーのベッドに寄りかかったが、ゆっくりとまっすぐ立ち上がった。布団と枕に守られ、床に横になったヴィニーがいた。パルミラと私は彼女をじっと見たが、どう助けていいかわからなかった。パルミラは私に振り返りながら「誰かここで何が起きているのか私に教えてほしい。家が揺れて、ベッドはあちこちに転がっていて。シェーカーは家からも邪悪なものを振り落とそうとしているの?」
(3)地震だ! なぜ気づかなかったのだろう? 他の地域で地震が起こることは知っていたが、ケンタッキー州で地震なんて聞いたことがなかった。だが、家をきしませ傾かせ揺らすこれは、地震に違いなかった。そして、私の恐怖はピークに達した。家が崩れ落ちて、下敷きになってしまうかもしれない。地面が割れて開き、私たちを飲みこむかもしれない。「これは地震よ、パルミラ!」と私は叫んだ。 「地震!? 地震って一体なんなの?」 「地面自体が揺れて震えることよ」 彼女の目が見開かれた。「そんなの聞いたことがない」 「私たちはちょうどその最中にいるの。ヴィニーを助け起こすまでベッドをしっかり支えておいて」
人々がホールを走ったり、話したりする声が聞こえ、私は残りの部屋も私たちの部屋と同じくらいひどい状態なのだとわかった。「リチャードは私たちに、服を着ろと言っていたわ。それに、誰かが来て何をすべきか伝えてくれるだろうって」 パルミラは笑った。「それはのんきなものね。誰かが来るまでこの家がもつと思う?」
まさに恐れていたことだったけれど、ただ頭を振った。揺れはゆっくりとおさまり、私たちはベッドを押し戻した。ヴィニーは死んだように横たわり、ベッドのかどでひどく怪我をしたのかもしれないと私は思った。パルミラと私は彼女を覗き込んだ。「ヴィニー」私は彼女に呼びかけた。「怪我をしたの?」 彼女の目が開いた。「脳みそが飛び出たんじゃないかしら」 私は素早く彼女の頭を撫でて確認した。ベッドに囲まれ、暗くてはっきりと見ることができなかったが、明かりで手を照らして見ると血はついていなかった。「出血はないわ」と彼女に言った。「さあ、立ち上がって」
彼女は小さく軽かったので、私たちは問題なく彼女を持ち上げ、ベッドに寝かせた。彼女は唸り、突然まっすぐに起き上がると私たちを指差し、「あんたたちのせいね! ベッドを私ごとひっくり返して! 冗談なんてものじゃないわ!」と激怒した。 パルミラは頭をのけぞらせて笑った。「じゃあ私たちのどっちがやったと思う、ヴィニー?」 「もう、パルミラ」私は言った。「冗談を言っている暇はないわ。ヴィニー、大丈夫なら起きて。地震なのだから。リチャードは私たちに服を着ろと言ったわ」 パルミラと同様、ヴィニーは目を見開き、仔羊のように素早くベッドから転げ落ちると、壁にかかっている彼女の服を取りに走った。
パルミラと私も急いで服を着た。ドアが開くとそこには、とても小さく虚弱に見えるが、帽子までもしっかりと服を着たシスター・スーザンが立っ
ていた。「シスターたち」少し震えた声で彼女は言った。「ブラザー・ベンジャミンから全員下の階に降りてくるようにと伝言です。地震が起きたので、下の階にいたほうが安全でしょうから」 「この家から早く出たほうが安全だと思うけど」とパルミラは言った。 シスター・スーザンは頭を振った。「ブラザー・ベンジャミンはそのようなことはないと仰っています。地面に亀裂が開くかもしれないのです」 「亀裂が開いてこの家全体を飲みこまないと言えるのかしら?」パルミラは知りたがっていた。 「祈りましょう。服を着たら明かりを消してすぐに紡績室に行きなさい」 「ふん、祈るよりもっとするべきことがあるわ」とパルミラは言った。
シスター・スーザンが去ると、私たちは各々服を着終えて、一人ずつ階段を下っていった。「ろうそくを消してくる」パルミラと私が残った時、彼女に言った。「頼むわ」
彼女はドアを出ていった。一人になりたいという気持ちが、私を長くそこに留まらせた。 意識的に祈りはしなかったが、静かになった部屋に佇み、私は落下してくる木材や地割れでみんな死んでしまうのかと考えていた。二度目の揺れ以降、不思議と恐怖心は和らいでいた。これは古いが頑丈なログハウスで、下の地面が割れない限り、おそらく倒れはしないだろう。
それから私は、ろうそくを消して、真っ暗な部屋を横切り真っ暗なホールへと出て、真っ暗な階段を下りた。私は、なぜ下の階には、暖炉からでさえ明かりがないのか疑問に思った。 そこは私たちの寝室やホールと同じくらい暗かった。大紡績室に行く途中、誰かが呼吸を荒くし急いで私を追い越していった。
紡績室の扉から、窓を背に人が集まり、ブラザー・サミュエルが祈りを捧げているのが見えた。皆、椅子の横でひざまずいているようだったので、私も空いている椅子を見つけて膝をついたが、ブラザー・サミュエルが言っていることは私の耳には入らなかった。私は家が再び揺れ始めるのを待っていた……頑丈な丸太の壁が歪み捻れ、もしかすると私たちに崩れ落ちてくるかもしれないと考え続けていた。
ブラザー・サミュエルが祈りを終えると、誰かが、そしてまた誰かが彼に続いた。最後に、シスター・スーザンのかすれた小さな声が、震えながら祈りを続けた。私は、このまま夜が明けるまで祈りを続けるのかと疑問に思った。もしも私たちが死ぬのなら、彼の手を握って死にたいと思った。
私は目を閉じていたが、突然光が見えた。シスター・スーザンの声は止まり、彼女ははっと息をのんだ。私は目を開けた。扉のところにろうそくを掲げたシスター・プリシラが立っていた。彼女の髪は乱れ、彼女は帽子を被っていなかった。「帽子が見当たらないの。二つともなくなったわ!」彼女はろうそくを持っていない手で、乱れた髪の毛をいじり、取り乱して言った。
私は彼女が帽子を被っていないところを見たことがなかったが、その時初めて、彼女の髪は細く、前方はほとんど禿げていることを知った。彼女は必死に後ろの髪を引っ張り、高く盛り上がった額を隠そうとしていた。「私の帽子がないの」彼女はしくしくと泣くように言った。「帽子が見つからないの!」
みんなが彼女を見て、驚いた顔をした。彼女は男性たちもそこに集まっている事を完全に忘れていたのだろう。彼女は戸口に立ち、手に持っているろうそくにはっきりと照らされ、取り乱し当惑していた。いつも帽子の下から見えている前髪がなくなり、変にむき出しになっていた。私は、頭の前方が禿げているのだから、彼女はいつも後ろの髪を前に持ってきて帽子を被せているに違いないと思ったのを思い出した。彼女は、明かりに照らされた禿げた額を気にかけるように撫でていた。彼女は、私が今まで見たことがないほどになりふり構わず取り乱していた。
誰かがくすくす笑った……もちろんパルミラだ。そしてシスター・スーザンが立ち上がり、ハンカチを首から取り、プリシーのところへ行くと彼女の頭にハンカチを結びつけた。そして優しく調整すると、何か囁き、彼女を椅子へ連れていった。そしてシスター・スーザンは彼女からろうそくを取りあげ、火を消して言った。「家に燃え移ってしまうかもしれないから、ブラザー・ベンジャミンがどんな火でもつけないようにと……」
暗闇の中でみんな立ち上がり、椅子に座る音がした。そしてシスター・スーザンは優しく、年老いた震え声でうたい始めた……ファーザー・ジェームスの歌だ。「(4)In yonder valley there grows sweet union……」みんなも続いてうたい、声を上げたので少しのあいだだけ平穏な気持ちになった。私たちは次から次へとうたった。
私たちはその日の夜中うたい祈り続けた。日記には、最初の地震は夜中の一時を過ぎてから起こったと記されている。ブラザー・ベンジャミンも証言している。彼はマサチューセッツ州の時計屋の家元で、センター・ハウスのホールにある美しい時計からも彼の時計に対する愛がうかがえる。夜明けまでに幾度か余震が起きたが、最初の二つの地震ほどではなかった。毎回、警告するような揺れが起き、窓が鳴った。歪み、みしみしという家や傾く床を想像し、私のお腹は緊張して締めつけられるようだったが、家が壊滅することはなかった。揺れはわずかで短かった。
チャーチ・ファミリーの誰かが、いつものように朝の鐘を鳴らした。冬の季節には五時に鐘を鳴らすのだ。私たちが部屋に戻ろうとした時、暗闇の中から誰かが話し始めた。「私はステファン・バークです」と声は言った。「スクール・ファミリーにいる子どもたちは皆無事だということを伝えにきました……彼らは取り乱すこともなく静かに恐れず夜を過ごしました」
彼の姿は見えなかったが、戸口に立つ彼はすらっとしていて背が高く細身で、静かで声が低く、優しいということはわかった。彼は学校長で、三十歳に満たない若い男性で、独身で、頭が良く、子どもを愛し、じっと見守る人だった。彼もまた、子どもの教育のために東部から送られてきたのだ。
微かな風が煙突から通り抜けるように、父母が安堵のため息をつく音が部屋中からひそひそと聞こえた。私はアマンダを思い出し、どこにいるのだろうかと思った。ブラザー・サミュエルが喜びに声をあげ、夜中気を配り面倒を見てくれたことに感謝を述べた。彼が言い終えると、ステファン・バークの足音がホールに響き、彼が出ていきドアが閉まるのが聞こえた。
地震の夜は、長い時間火がなくても寒さを感じなかったことをずっと覚えている人たちがいた。彼らは歌と祈りによって高揚していて寒さを感じず、むしろずっと火が燃え続けているかのように暖かく感じていたと言っていた。私たちの部屋はそうではなかった。私自身、朝になるほどひどく寒さを感じた。パルミラは骨の髄まで凍っているかのように感じていたと言っていた。アニーは彼女の手と足が麻痺したと訴え、かわいそうなヴィニー・パークスは音をたてるほど歯を震わせていた。
シスター・プリシラは、私たちの部屋の人選は偏っていてやっかいだと言っていたが、たしかにそうかもしれない。私たちはたしかに別々の部屋に分けられるべきだった。もっと敬虔な人たちと一緒だったら、私たちに起こったことで避けられたこともあったかもしれないが、今となってはわからない。私たちのあいだに起こったことは、しかるべくして起こったのだろう。何よりもまず、私たちは妻であり、母である人もいた。私たちは、心まではシェーカーになりきれなかった。
その日の予定はわずかにしか乱されなかった。私たちはやっと火を灯すことが許されたので、ろうそくを手に部屋へ戻ると、ベッドを正しい位置に戻し、布団を掛け、整頓した。そこにはアマンダもいた。彼女がいつ戻ったのかは知らなかったが、私たちは子どもたちがひどく怯えていなかったか尋ねた。「いいえ。ブラザー・ステファンはメインルームで子どもたちを集めて地震について話していたわ。地球の何かがどうやってごろごろと鳴り震えたのかとか。何も悪いことはなかった。彼はとてもうまく話すものだから、子どもたちは一生懸命聞いていたわ。私が見る限りでは、一人も怯えている子はいなかったわ」 「私の子たちはお利口にしていた?」とパルミラは尋ねた。 アマンダはうなずいた。「ブラザー・ステファンはあなたの子を膝に乗っけていたわ。最後に見た時は、親指をしゃぶって、まるで彼が自分の母親かのように満足げだったわ」 パルミラは笑った。「あの子は大人になるまで親指をしゃぶっているかもしれないわ。私でもやめさせられなかったわ。それにしてもブラザー・ステファンはいい人ね」 「そうに違いないわ。」と私は言った。
私たちは部屋を整えることに専念した。洋服は壁掛けから落ち、ボンネットや帽子も落ち、椅子は倒れ、正しい位置に戻すのは大変だった。椅子を起こすと、パルミラはけらけらと笑い始めた。それから頭を投げ出して震えるまで笑った。「何がおかしいの?」アニー・ジュエットが聞くと、「プリシーよ」とパルミラは言った。「ろうそくの光に照らされた禿げ頭よりも、おもしろいものを見たことがある?」 その言葉は、私が「彼女の帽子はどうなったのかしら」ということを思い出して言うまで全員を笑わせた。 パルミラは笑いすぎて涙で目元が光っていた。「もし彼女たちの部屋が私たちの部屋のようにめちゃくちゃになっていたなら、おそらく布団と一緒くたになっていたのかも」
私はその時初めて、あの夜に何が起こったのか感づいた。パルミラはあまりにも瞬時に答えたし、帽子が床に落ちることはあったかもしれないが、ベッドの上にある布団に紛れこむことはないだろう。それに、予備の帽子が少なくとも一つは彼女の引き出しにあったはずだった。私はパルミラを見た。彼女は故意に私にウインクをしたので、彼女が盗んだのだとわかった。私は彼女の大胆さに少し驚いた。暗闇の中で急いで私を通り過ぎていったのは彼女だったのだ。彼女がどのようにしてやったのかは、私にはわからないが、シスター・プリシラにとって最悪の屈辱となった。思い出すだけでも笑いが込み上げてきた。私たちにいつもちくちくと意地悪をしてきたプリシーは、生殺しの蛇に噛まれたのだ。もちろん、それは間違っていた。ひどく間違っていたが、よくできたいたずらで、とてもおもしろく、私は笑うことしかできなかった。
私たちが階下に行く時、私はパルミラに囁いた。「どうして彼女が禿げていることを知っていたの?」 「一度彼女の帽子が斜めになっているのを見たことがあるの。彼女は後ろの髪を前に押し上げていたわ。おもしろいでしょ?」彼女は手で口を隠して静かにくすくす笑い、肩を震わせた。 「しーっ」と私は彼女に注意した。「どこに隠したの?」 「私のコルセットの中に隠したわ。今日どこかに埋めるつもりよ。彼女がこの帽子を見つけることはないわ」
シスター・プリシラの帽子の謎は数日間、噂の的になった。みんなが帽子を探した。誰も帽子がどこにいったのか見当もつかなかった。彼女は最終的にはもちろん、いつまでも帽子が見つからなかったので、誰かが奪ったのだとわかったが、誰がそれをしたのかを知る余地はなかった。家は暗く混乱しすぎていた。彼女は、数日間は私たち全員を疑い深く見て、新しい帽子を作るまではスカーフで頭を隠すのが精一杯だった。
彼女の屈辱には少し哀れなものがあった。再び帽子を被るまでは、彼女の頭が堂々と前を向くことはなかったし、まっすぐ歩くこともなかった。代わりに、彼女はせかせかとして、部屋にこもりがちで声は小さく、悩み苦しんでいるように見えた。
私の良心が少し痛んだが、それほどではなかったし、何よりすぐさま他の問題が浮上したのだ。黒人たちは、最初の揺れが始まってからひどく怯えており、ブラザー・ベンジャミンが彼らを落ち着かせるためにやや遅れて駆けつけた頃には、ばらばらになって逃げ出していた。朝になっても行方がわからない者の中には、ジェンシーもいた。
カッシーは作業場まで私を訪ねてきて、手を固く握って泣いていた。「ベッキーさん、ジェンシーがいなくなったわ。誰もあの子を見つけられないわ」 私は彼女を慰めるために全力を尽くした。「リチャードがきっと彼女を見つけてくれるわ」私は彼女に約束した。「彼はすぐにでも彼女を探しにいくわ。そう遠くには行っていないでしょうから、すぐ見つかるはずよ。泣かないで、カッシー。リチャードがジェンシーを探し出すわ」 カッシーは丸い顔を悲しみで歪ませ、背中を丸めて震えながらすすり泣いた。涙が彼女の黒い頬を光らせた。「ベッキーさん、ジェンシーは気まぐれだから、誰もあの子がどこに行ったのかも、どこへ向かっているのかもわからないわ。もしリチャードさんが探してくれるなら、すぐにでも取り掛からないと」 「そうね」私は言った。「私が今すぐ彼に頼みにいくわ。ジェンシーはどうやってあなたの元から離れたの?」 「ベッキーさん、どうやって稲妻を握るの? どうやって羽ばたく鳥を捕まえたり、震える仔馬を落ち着かせたりするの? さっきまで他のみんなと一緒にシェーキングをして祈っていたと思ったら、次の瞬間にはもういないのですよ。他のみんなも、世界がばらばらになるのじゃないかって恐れて、(5)ガブリエルのラッパを恐れていて……彼女がどこに行ったかなんて、わかりゃしないわ……彼女を探しても、名前を呼んでも、思いつくところは隅々まで探しても、見つからないの。彼女はいなくなりました、ベッキーさん。彼女は家に帰るまで止まらないでしょうね」 「家ってどこなの?」 カッシーは口を押さえた。「あの子の家なんて神様しかわからないわ。ああ、ベッキーさん、なんて災難が私たちに降りかかったのかしら」 私は彼女を抱きしめ、撫でて彼女を落ち着かせようとした。「もうウォッシュ・ハウスに戻るのよ、カッシー。しっかり休みなさい。私たちはあの子を見つけるまで諦めないわ。泣かないで……自分の仕事に戻りなさい」
カッシーはキッチンからウォッシュ・ハウスに異動させられたばかりで、プリシーの元から離れられて嬉しいようだった。彼女は頭を振りながらエプロンで涙を拭い、腰をかがめながら戻っていった。
私はすぐにでもリチャードのもとへ行きたかったが、踏まなければならない順序を思い出そうとした。プリシーはその日、自分の部屋に引きこもっていて、シスター・スーザンが担当だったので、彼女のもとに行った。私はセンター・ハウスに行って、ジェンシーのことをブラザー・ベンジャミンに報告する許可を求めた。担当がシスター・スーザンだったことが何よりもありがたかった。「私もあなたと一緒に行きましょう」彼女はすぐに言った。
センター・ハウスではまず、この問題をシスター・モリー・グッドリッチに報告しなければならなかった。彼女はシスター・スーザンのように思慮深く、ブラザー・ベンジャミンを呼ぶように手配してくれた。すぐに彼は私たちと合流した。私はリチャードの仕事を免除するように頼んだ。リチャードだけがジェンシーを見つけることができると説明し、すぐに見つけなければ、冬の寒気と雨で危険に晒されることを訴えた。
彼はリチャードが彼女を探すべきだと即座に同意し、彼の仕事を免除することを約束した。私の心配事のほとんどが解消されたので、私はシスター・スーザンと共に自分たちの住居に戻った。私ができることはすべてやったので、もう私がやるべきことはなくなった。私は、リチャードがすぐにジェンシーを探し始めるだろうとカッシーに伝える許可を求めた。シスター・スーザンも大いに同意し、それを許可した。
噂は回って、その日の午後には私たち全員が、まだ黒人たちが何人か見つかっていないことを知った。リチャードとウィリアム・スティール、そしてもう一人が夕食中にいなかったので、彼らが捜索しているのだとわかった。
午後には、ブラザー・ベンジャミンが先頭に立って彼らと一緒に捜索を進めているということが私の耳に入ってきた。ウィリアム・スティールの、黒人と白人のミックスであるクレイトンも、まだ見つかっていないことも耳にした。捜索が進んでいるという安堵は、その時、言い表せない恐怖に変わった。私は作業場で、チーズの樽をかき混ぜ、バターを型に入れながらも、いろいろな方向に意識が飛んで、ジェンシーがどこに行ったのか考えようとした……もしクレイトンも彼女と一緒だったら……彼らはどこに隠れるだろうか。
突然、まるで写真が私の目の前にあるかのように、私たちの昔の家の裏にある丘のスギ林の中の小さな小屋が頭に浮かんできた。そして私がもちろん自分の名前を知っているように、ジェンシーが、大好きなその小屋へ行っていることがわかった。よくパルミラの子どもたちと一緒に遊んでいた場所だ。「小さな洞窟みたいです」と彼女は言っていた。「この中で隠れることができるんですよ」
私は今、彼女を見つけるためには私が行かなければならないとわかっていた。もしクレイトンが彼女と一緒にそこにいたら……私が二人が一緒にいるところを見つけたのであれば、どうにかしてコミュニティの非難や怒り、さらには罰や戒めから守ることができるかもしれない。
私はエプロンを外して何も言わず、ドアからするりと出た。これはシェーカーのやり方では解決できないことだった。私のやり方でしか解決できないだろうし、その責任は私が負わなければならないだろう。
私はコミュニティの中を通っている道を避けて、ナースリーを通り過ぎて森に入った。あの道はとても開けていて、誰かに見つかってその場で止められていただろう。どちらにしろ、森を通るほうが早かった。森を抜ければ、昔の家の裏にあるスギ林に出られる。
森に入って人目につかなくなると、私はでこぼこした地面に躓きながら走った。くぼみや小さな丘を横切ってまっすぐ進み、谷の底に流れ込んだ小さな川を渡った。私は、自分より先にリチャードたちが小屋に辿り着いてしまうのではないかと心配した。ブラザー・ベンジャミンのところへ行き、リチャードを送るように頼んだことを後悔した。リチャードは、ジェンシーを批判し容赦しないだろう。私の一番の願いは、彼より先にジェンシーのところへ辿り着くことだった。もし一行ではなく、リチャードだけがジェンシーとクレイトンを見つけたとしても、彼は彼女たちを必ず報告するだろう。
私が行った道は三マイルもないほどだったが、小さな丘を登る頃には私は息を切らし、棘でぼろぼろで、濡れて、へとへとになっていた。私は静かにいかなければならないと思った。彼女を警戒させてさらに遠くへ逃げさせるわけにはいかない。
しかし、そんなことを気にする必要はなかった。彼らは抱き合って眠っていた。ジェンシーの針金のような三つ編みは、クレイトンの肩にのっていた。彼らは、二人ともとても若くあどけなく見えた。しかし、彼らがそうではなかったことは明らかだった。私自身がショックを受けてドアに立っているあいだも、クレイトンは揺れ動き、彼のシャツの裾からのぞいたジェンシーの滑らかな黒い太ももをさすっていた。
私はドアから後ずさり、何をすべきか考えた。彼らから見える場所から呼びかけるよう、自分に言い聞かせた。長く深いため息が、一息聞こえた。彼らが目覚めるのも時間の問題だろう。私はすぐにドアの前に立ち、彼らに背を向けて叫んだ。「ジェンシー!」 小屋の中で慌ただしい動きがあり、ジェンシーが甲高い声を上げた。そして、おそらく習慣から、彼女は私に答えた。「なんでしょう?」 「急いで服を着て。リチャードとウィリアムがあなたとクレイトンを探してる。急いで。今すぐにでも来るかもしれない」 彼らが急いで慌てている音が聞こえた。「急いで」私は言った。 私が思っていたよりも素早く、ジェンシーは私のそばにきた。彼女の目は恐怖で見開かれていた。「ベッキーさん、彼らは私たちをどうするの?」 私は彼女がどこかへ行かないように彼女の腕をつかんだ。「クレイトン」私は言った。「森に戻りなさい。急いで。できるだけ早く戻るの。空洞のある木を見つけて、その中に隠れて、見つかるまでか、明日までそこにいなさい。あなたは森に走って逃げ、この空洞のある木を見つけ、そこに隠れて、ずっと過ごしていた……眠っていたと言うの。覚えられる?」 彼は頭を伏した。「はい。森に入って、空洞のある木を見つけた。僕は眠っていた」 「絶対にジェンシーの名前は言ってはだめよ!」 「はい」 「あなたはジェンシーがどこに行ったのかわからない。彼女が逃げ出したことも知らなかったし、彼女や他の誰も見なかった。ずっと一人でいたの」 「はい。僕は一人だった」 「たとえ誰が質問したとしても……たとえなんと聞かれたとしても、あなたは一人でいたのよ。森の中で、空洞のある木で」 「はい」彼はにっこりと笑った。「本当に一人だった気がします、ベッキーさん」
私は彼らを見つけたこと、これからつかなければならない嘘が残念で仕方がなかった。 その場で二人とも鞭で打つこともできた。私は険しい顔をして言った。「忘れないようにしなさい」私はジェンシーのほうを向いた。「そしてジェンシー、あなたは小屋に来た……あなたは怯えていて、この小屋のことを思い出した。ここなら安全だと思った」 彼女の目は、白目しか見ることができないくらい回った。「はい……それはたしかに本当です。どうにかなっちゃうくらい怖かった!」 「でも、あなたはクレイトンを一度も見なかった」 「はい。私はクレイトンを見ていない」
彼らがあとで必ず言わなければいけない嘘を教えるのにはうんざりした。自分の悪知恵に毒されているようだった。なんて簡単にこんな嘘を思いつけたことか。私は自分自身の器用さに驚いた。私の心はどこか少し汚れているのだろう。私は胃の中の食べ物を吐きそうだった。しかし、私は他の方法が思いつかなかった。「行って、クレイトン」私は彼に言った。「あなたが森に入るまで、私たちはここで待っているわ」
ジェンシーを見ることなく、彼は小屋の角を曲がって姿を消した。その時、彼らの心は白人のそれと似てすらいないのではないかと思った。まるで獣のように速く、激しく交尾するのだろう。不適切な考えだが、私はあまりにも腹が立ち、嫌気がさしていた。
私はジェンシーを見た。彼女と話そうとしても無駄だった。私が彼女に伝えるのをずっとためらっていたことを、彼女は今、理解したのだ。ためらわずに、はっきりと伝えるべきだった。しかし、もう手遅れだった。あとは彼らの種が根づかないことを願うしかなかった。私はそれがとても心配だったが、それが彼らの運命なのだと思った。そして、ジェンシーが自分に何が起こるか知っているのか疑問に思った。彼女は知っているのだろうか? 彼女は、はるか心の薄暗い奥底で、最初の症状くらいは知っているのだろうか? 私は彼女に警告しなければならなかった。「もし次に体調が悪くなったら私に言いなさい」と私は言った。
彼女は素早く私のことを一瞥した。彼女は理解していた。なぜか私は安心した。 彼女は私が恐れていたほど無知でも純粋でもなかった。「聞いて、ジェンシー。そのことで嘘をつこうとしないで、あなたの時間を無駄にするだけよ。何もいいことはないからね」 彼女は三つ編みが乱れるほど激しく首を振った。「嘘をつくつもりはありません。言います……でもママには言いません。殺されるわ」 「もしそうなったらカッシーの耳にも入るわ……すぐにみんなの耳に入る。これだけは隠せないの。でもまず私に言ってくれれば、どうにかできるかもしれない」 彼女はくすくす笑った。「はい。でもまだそうなってないわ」 「ああ、きっとそうなるわ、お馬鹿ね!」私は彼女の肩をつかみ、自分の怒りや苛立ちに任せて、彼女の歯がガチガチ音を立てるまで揺すった。「それにしてもどうしちゃったの? こんなことしたらどうなるかわかっているはずよ。そこまで馬鹿じゃないでしょう!」 私が肩を離すと、彼女は何事もなかったかのように、満面の笑みを浮かべた。「はい」彼女は囁いた。「でも、いつもやっている歌と踊りとシェーキングを同時にやっているみたいじゃない……自分から解放されるような。どうして悪いことなの?」
私はその場で死んでしまいたい思いだった。自分の切望や嫉妬、そして無様な断念に突然嫌気がさした。それを思い出させたジェンシーもその場で殺したいくらいだった。私は彼女の腕をつかんだ。「来なさい。戻りましょう。あなたはこの一日で十分なほど問題を起こしたわ」
二週間のあいだ、ときには夜に、ときには日中にも地震が起こった。地球のどこか内部が震えたようで、わずかな揺れにしかならないものもあれば、窓や食器をカタカタ揺らすほどのものもあった。しかし、あの夜に起こったほど激しい揺れはなかった。
数カ月後、ここより西のほうで、地殻の広大な領域が深く沈み、オハイオの水がぶくぶくと沈んだ土地に流れ込んで、木々も飲み込んでしまうほどの(6)大きな湖を形成したことがわかった。私たちにはそこまで凄まじい被害はなかったけれど、まだ用心して歩き、常に少し不安を感じながら、次の地震を恐れていた。とても平和な日々とは言えなかった。
私は、ブラザー・ベンジャミンが十二月の最後の夜、チャーチ・ファミリーの日記に「旧年が振り払われた」と書いたことを覚えている。そして、彼は真剣に「私たちの小さな塊はあまりにも簡単に散らされるようだ」と言った。 本当にそうだった。
第12章訳註
(1)ローラーがついたベッド
ベッド台の脚部にローラーが取り付けられたもので、これによって容易にベッドを動かすことができた。ローラー付きのベッドはシェーカー教による発明品といわれている。
(2)壁にかかった服
シェーカーの建物にはあらゆる部屋や廊下の壁にペグやペグボードがついている。そこには椅子、壁掛け時計、鏡、壁掛け式のラックや棚、洋服ハンガー、台所用具、掃除用具、教室や教育の用具、作業用具や道具類など様々なものが掛けられた。
(3)地震
1811年12月16日に発生したマグニチュード8クラスのニューマドリッド地震のことであると推定される。本小説内で、日記には最初の地震は夜中の1時を過ぎてから起こったと記されているが、午前2時15分ごろに発生したようである。
(4)In yonder valley…
7章にて出てきたFather Jame’s SongはNo.1からNo.5まであるが、この曲はNo.1で、広く知れ渡った初期の曲である。
(5)ガブリエルのラッパ
最後の審判が下されるまでに、七人の天使がラッパを吹いていく描写があるため、天使がラッパを吹くことに終末のイメージを持っていると考えられる。
(6)大きな湖を形成
ニューマドリッド地震の原因となった活断層はニューマドリッド断層といい、ミズーリ州ニューマドリッドから南西に伸びる、南部および中部アメリカの主要な地震帯である。 イリノイ州、ミズーリ州、アーカンソー州、ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州の6つの州にまたがり、 1812年以来この地域には頻繁に小さな地震が記録されている。 また、本文に登場する湖は、ニューマドリードの地震による地盤沈下によって形成されたテネシー州北西部のレイク群とオビオン群にまたがったReelfoot湖という浅い自然湖のことであると推定される。