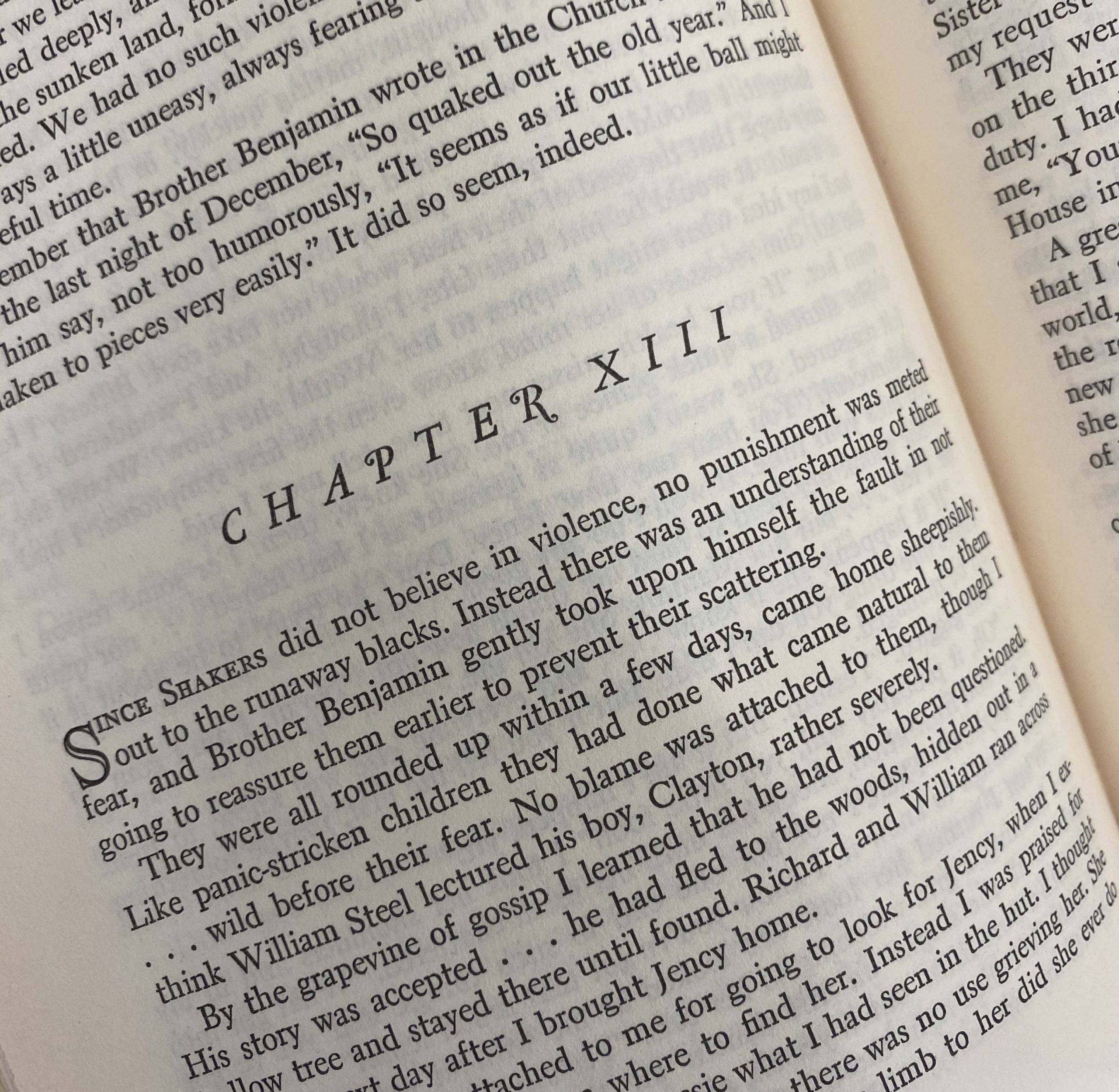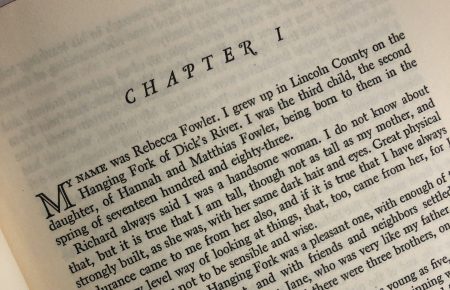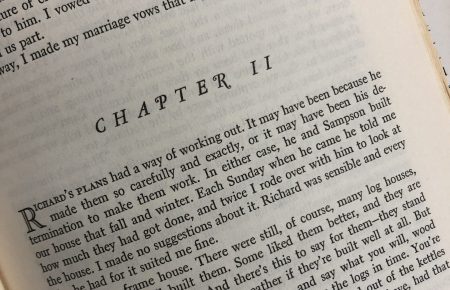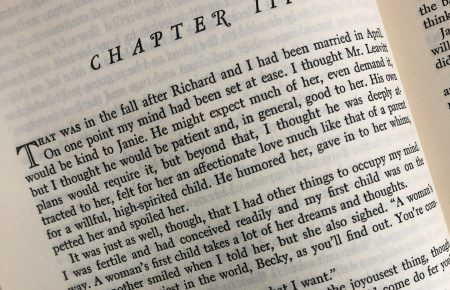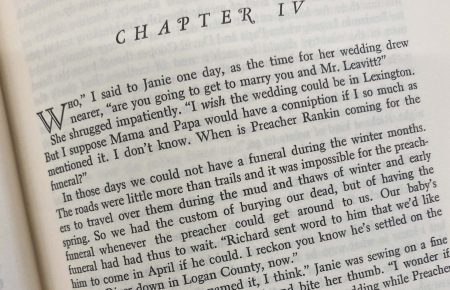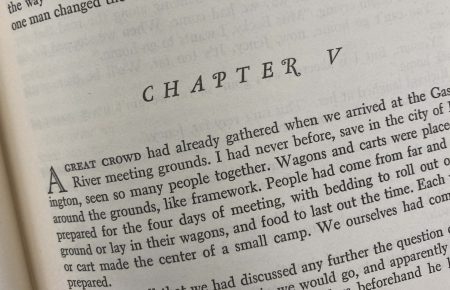シェーカー教では暴力は良しとされていなかったため、逃げだした黒人たちに懲罰が加えられることはなかった。むしろ、ブラザー・ベンジャミンは彼らの味わった恐怖を理解し、今回の騒動を未然に防ぐことができなかったことへの責任を感じていた。
彼ら、逃げだした黒人たちは皆、数日のうちに怯えながら戻ってきた。子どもがパニックに陥ってしまうように、彼らの行動はいたって自然なことだった……恐怖の前で自我を失ってしまったのだ。彼らが責められることはなかったが、ウィリアム・スティールは奴隷のクレイトンにかなり厳しく説教したようだった。
森の中へ逃げて木の洞に隠れていたというクレイトンに与えた作り話が、疑問を持たれることなく受け入れられたということを、私は人づてに聞いた噂で知った……。リチャードとウィリアムは、私がジェンシーを連れて帰った翌日に彼を見つけたそうだ。
また、私が責められることもなかった。むしろ、私はどうやってジェンシーの居場所を突き止めたかを説明すると、その迅速な行動を褒められた。カッシーには、私が小屋で目撃したことを伝えなかった。必要がない限りは、彼女を無駄に悲しませたくはなかったのだ。カッシーが、次にこんなことをしたら痛い目に合わせるとジェンシーを脅すと、彼女はくすくすと笑いながら、もう二度と逃げだしたりしない、とうわべだけの約束をした。
私のシスター・プリシラへの驕りに対する罰は、地震による騒ぎで忘れられたようだった。彼女は二度とそのことを口に出さなかった。しばらくのあいだ、彼女は地震の夜にかいた恥で頭がいっぱいだった。彼女は恥をかいたことをずっと気にしていた。シスター・プリシラの慈悲深い態度はそう長くは続かなかったけれども、ほんのひととき、彼女は柄にもなくおとなしくしていて、いつものように堅苦しい態度ではなかった。
ちょうどその頃、メッセージが届いた。父の体の具合が悪いので家に帰ってこられないか、との打診だった。その知らせが私を救ってくれた。母は父の死期が近いことを感じていた。私たちはコミュニティの外へ一人だけで出かけることを禁じられていたため、許しが出るかはわからなかったが帰宅を願い出た。私はリチャードにも一緒に来てほしかったが、それは言わないでおいた。リチャードは私たちが二人きりになりたがっていると思われるのを恐れて、同行してくれないかもしれないと思った。しかし、私は誰か男性と一緒に出かけなければならなかったし、男女が第三者なしで二人きりになるのは禁じられていたので、誰かもう一人女性が同行しなければならなかった。私からは同行者について何も意見せず、ただ外出の許可だけを申し出た。シスター・プリシラはいつもより優しく、私の申し出をセンター・ハウスの役員に伝えるのを快諾してくれた。
申請の詳細をつめる役員たちの手間は省かれたようで、申し出から三日後に、私は日課の最中に呼び出された。その月は厨房担当で、プリシーがわざわざ私のところへ現れ、「お姉さんがいらしていて、あなたに会いたがっています。すぐにセンター・ハウスへ行ってください」と伝えた。
ジェイニーが来たのだ。彼女に会えると思うと、とてもわくわくした。世間から離れたシェーカー・ヴィレッジでは、誰しも村の外に家族がいるということすら簡単に忘れられてしまうのだった。新しい環境に置かれ、自分のことに没頭する日常の中では、ジェイニーについて考えることはあまりなかったと認めざるを得ない。だが今、ここに彼女がいて会って話そうとしていることを知って、彼女との思い出があふれてきて、期待に震える心地がした。
私は髪が整っていて、帽子がまっすぐで、スカーフが正しく結ばれていることを確かめて、青いドレスを着ているため茶色のドレスよりも鮮やかに見えることをひそかに喜んだ。ジェイニーは私の服装を変わっていると思うかもしれないが、少なくとも清潔で、しみがなくきちんとしていてぐしゃぐしゃでなく、前みたいに石鹸水の桶に屈みこんで水浸しになったりはしていなかった。
私が来客面会用の大部屋に入った時、彼女は窓際に立っていたが、私の声を聞くやいなや振り返った。私たちはお互いの腕の中に飛び込んで、きつく抱きしめあって軽くたたきあい、泣きながら笑い合っているのがおかしくなって歓声をあげた。私は彼女を離し、そうしてやっと「顔をよく見せて」と言った。
彼女はやせて老けて見えたが、いまだに美しく、服装はとても豪華だった。彼女の顔つきにはまだ表情が豊かに現れていた。けれども笑っていない時に見える彼女の口元のしわは、彼女の日頃の苦労と尊大さを表していた。「私はあなたを家に連れて帰るためにここへ来たの。レヴィットさんも一緒に、大きな馬車で来ているの。パパの具合がとても悪いのは知ってる?」
「ええ」私は、村の静寂を飛びだしてもう一度外に出ることを考えると、びくびくして少しうろたえた。
「あなたの……なんていうのかな、長老? この村を運営している男性には話したから。とにかく、彼はあなたが私たちと一緒に行くことを許可しようと思っているみたいよ」
「私からも話さなきゃ」と私は言った。
「それなら急いでね。もう出発しなきゃ」
私はシスター・モリーとブラザー・ベンジャミンに許可を求めに行った。彼らは私たちのもとへ来て厳粛に、同情と思いやりをもって話した。彼らは私がジェイニーと一緒に行くことを快諾した。「戻って来る時に」彼らは私に言った。「もし方法がなかったら、私たちに言伝してくれれば、迎えに行きましょう」
もちろん、村のメンバーが外の世界へ出ることは異例のことだったし、もしも私がチャーチ・ファミリーの一員だったら、決して許されなかっただろう。正会員は永久に教団に身を捧げ、世俗的な繋がりは一切断たれている。彼らは父母や兄弟とは離れ、教団と結びつけられた。しかし、ノヴィシエイトである私には適用される免責があった。
「リチャードに会って伝えてもよいですか?」と私は尋ねた。
「彼を呼びに遣っておきましたよ」とブラザー・ベンジャミンは言った。
私たちはリチャードが来るまで黙って座っていた。ジェイニーは考えこんでいるようだった。ブラザー・ベンジャミンとシスター・モリーは、これ以上話すことがなかったので黙っていた。静寂は私たちの生活の一部だった。ブラザーとシスターたちのミーティングでは、会話はほとんどなかった。
シスター・モリーは背が低く、ふくよかで色黒の女性で、快活さとユーモアのある人だ。彼女は編み物で暇を潰しているようだった。彼女の手は毛糸を器用に動かして、棒針がリズミカルにカチャカチャと音を立てた。シスター・モリーよりも素早く、スムーズに編むことができる者は誰もいなかった。彼女の冬季の仕事は毎日の放牧で、彼女はこれを普段の仕事に加えてやってのけた。私はミーティング以外で彼女の手が暇になっているところを見たのを思い出せない。彼女はマザー・アンの言葉、「手は労働に」という通りに働くことに少しも苦労しなかった。センターハウスで最も見慣れた光景は、シスター・モリーの膝の上に仕事が積み重なっているところと、彼女の常に忙しそうな様子だった。
リチャードが到着すると、ジェイニーと私の向かい側に座った。彼はレヴィット氏について失礼のないよう尋ね、ジェイニーの用件について説明されると厳かに頷いた。「シスター・レベッカが行くべきだと考えていただけたことを嬉しく思います。彼女はお母さんを落ち着かせ、助けることができるでしょう」
リチャードが私のことを「シスター・レベッカ」と呼んだ時、ジェイニーの口元が歪んだが、彼女は何も言わなかった。「もしあなたのご両親に伝えたいことがあれば、取り計らいましょう」ブラザー・ベンジャミンは言った。
「両親に伝えてください、私は元気で幸せにしています、と」リチャードは私を見て言った。
彼はもうビリーバーズ以外にとって……私にも、彼らにも、死んでしまったも同然だと私は苦々しく思った。「伝えておきます」と私は言った。もし私の声が冷酷に突き放すようだったとしたら、それは私の感情を表したにすぎない。
リチャードは、それ以上何も言わずに立ち去った。「ああ、そういえば……」ドアの所で彼は振り返って言った。「お父上の身体については気の毒に思います。無事であることを祈っています」
それはまるでテーブルから振り払われたパンくずのような物言いだった。ジェイニーは毅然と顔をあげた。「父は病気くらい自分でなんとかするわ」
彼は少しお辞儀をして、部屋を出ていった。
ブラザー・ベンジャミンは、私に旅のための資金をくれるブラザー・サミュエルに会いにいくように言った。「彼女にお金は必要ないです」ジェイニーがすかさず言った。
「だとしても、彼女に支給をするのは我々の義務なので」ブラザー・ベンジャミンは穏やかに言った。
私はほとんど物を持っていなかったので、出発する支度はすぐにできた。馬車で待っていたレヴィット氏は、私に優しく声をかけ、私の小さな荷物を持って積み込んでくれ、私たちは出発した。馬車はとても立派で、ゆったりとして快適だった。黒人の御者が美しい鹿毛の馬たちを走らせ、道を走る速度は心地よく感じた。私は一度振り返り、あまりにも慣れた場所を離れることへの心配からくる心許なさを再び感じた。でも、ジェイニーのそばにいることや、父と母に再会しにいくのだと思うと、それもまた心地よかった。
ジェイニーが沈黙を破った。「ああ、もう」彼女はボンネットを脱ぎ、傍らのシートへ放りながら言った。「あなたはどうして耐えられるの、あんな息苦しくて、ぞっとするくらい醜くて、苦笑いしてしまうくらいの純真さに!」それから彼女はリチャードの、私の名前の敬虔な呼び方をふざけて真似た。私は顔を赤らめずにはいられなかった。「どうしてあんな所に引きこもっていられるの、ベッキー?」
「あなたも暮らしてみれば慣れるわよ」と私は言った。
レヴィット氏は議会上院での任期を終えて、もう選挙には出馬しなかった。彼とジェイニーは、かつて彼が弁護士業務に就いていたレキシントンに帰っていた。今は彼は裁判官で、州の中で評判の著名な市民だった。しかし、彼は今やでっぷりと太って、生気のないパン生地のような顔色をしていた。馬車の動きは、彼を随分疲れさせているようで、彼は具合が悪いのではないかと思った。私は食事のために馬車を止めた際に、ジェイニーに彼の体調について尋ねた。「よくないわね。彼は息切れを患っていて、足腰が弱くなっているの。階段を上るような、それほど激しくない運動でもふらついているわ。でも彼はそれを軽く見ているのよ」彼女は言った。
「もっと用心させないと、ジェイニー」と私は言った。
「レヴィットに何かさせることはできないの、ベッキー」彼女は言った。「でも心配だわ」
彼女が彼をとても好いていることが私にはわかった。
しかし、それは夫と妻のあいだにあるべき深い愛というよりも、子どもを甘やかす父親に対する愛情のようだった。
私たちは三日かかって、ハンギング・フォークへとやってきた。ハンギング・フォークはまったく変わっていなかったが、かつてこの小川で水に浸かって釣りをしたり泳いだりしたことを思うと不思議に感じられるほどに、私は変わってしまったのだった。それはまるで、夢の中でほとんど忘れかけた日々へ戻ったようだった。馬はゆっくりと家へと続く長い坂に差し掛かった。家の古い部分はまだ丸太が残っており、風化で銀色になっていて、新しい部分がその隣で白く輝いているのが見えた。
母はドアのそばに立っていて、彼女を見ると深い痛みが走るようだった。とても久しぶりだった。母は、私がかつて何千回も見てきたのとまったく同じように、胸の前で腕を組んで、静かに、家と同じくらいしっかりと立っていた。違和感はすべて拭われ、私は子どもに戻って、家に帰ってきて、母のたくましい腕に抱きしめられるのを切望した。すべての痛みと傷を抱きしめてほしかった。
私は馬車を転げ降りて、母に駆け寄った。彼女は私を嬉しそうに抱き止め、涙が顔をつたったが、彼女の腕はかつてのようにきつく強く抱きしめた。「来てくれたのね」と母は言った。それからジェイニーに向かって、同じように親愛を込めて歓迎した。
「パパはどうなの?」家の中に入って、私は尋ねた。
「よくないわね」
「よくなってないの?」ジェイニーが素早く尋ねた。
母はうなずいた。「彼はもうよくならないわ。寿命が来たのよ。会いたいだろうけれど、まずは落ち着いてちょうだい」
ジェイニーは外套とボンネットを脱いだ。私はケープと、私たちシェーカーが帽子の上に被るボンネットを脱いだ。ママは私の白いネットキャップを見て、私に微笑んだ。「会えてよかったわ、ベッキー。元気そうね」彼女はジェイニーに向き直った。「ジェイニー、あなたは随分やせたわね。元気がないのかしら」
待ちきれなくなって、ジェイニーはスカートを巻きつけた。「私は大丈夫。パパに会いたいわ」
母は私たちを寝室へ連れていった。父は知らない人のようだった。もちろん、十年も経っていたから……彼は今や七十代だった。しかし、歳に加えて、病気によって彼はやせていた。ほとんど骨のようにやつれて、掛け布団がわずかしか盛り上がらないほどだった。彼の頭は枕の上で骸骨のように見えて、髪はほとんどなくなっていた。彼の頬は落ちくぼんで、皮膚は血色がなく、しまりなくたるんでいた。彼の目は閉じていた。私は恐る恐る、父の胸元の布団を見た。それはほんのわずかに、ひどくゆっくりと動いていた。ナイフが素肌を切り裂くような痛みが、私の胸中に深く刺さった。ああ、父を置いていかなければよかった……家に残って、嫁がずに、リチャードが私に強要したおかしな方向へ行かなければよかったのに。その瞬間、何年も前に戻って元気な父に会い、もう一度笑い合い、馬のように私を肩に乗せ、私が彼の髪を掴んで横腹を小突き、笑いながら家じゅうをまわることができたらいいのに、と思った。「パパは眠っているの?」とジェイニーは尋ねた。彼女はとても声を詰まらせて、私はそっと彼女のほうを見やった。涙が彼女の睫毛を濡らしていた。
母は首を振った。「もう二日間ずっとこうよ……どうなっているのかわからないわ。もうそれほど長くはないでしょう」
「でも、どうして?」私は尋ねた。「どうして病気に?」
「何かがあるんだと思う……それから歳も。数年間、胸を患っていたの。決して大げさに痛みを訴えなかったけれど、完全に痛みがなくなることはなかった」
ジェイニーは手に顔をうずめて、咽び泣いた。「耐えられない!」
母は彼女の髪をなでつけた。「仕方ないわ、ジェイニー。命とはそういうものなのよ」母の声は低く、悲しげで、でも落ち着いていた。私は、彼女が「なるようにしかならない」と言うのを何度聞いたことか、と思った。私も自分にそう言い聞かせて、気持ちを落ち着かせてきた。それはまるで、母が運命を受け入れているようだった……彼女の言うように、なるべきものはなるとしても、私は決してそれに屈しないと思った。
「何か私たちにできることはある?」と私は尋ねた。
「いいえ。もう手は尽くしたわ。今はもう、最後まで見届けることしかできない」
近所の人たちは親切にしてくれた、と母は私たちに言った。村は発展していて、そこらじゅうに良い友達がいた。彼らはうちへやってきて、看病をしたり、様子を見たり、仕事を手伝ったりしてくれた。男兄弟のうち二人は家を出て、一人はペンシルバニア、もう一人はオハイオへ行った。母は、とてもどこに便りを出せばいいかわからなかったので、彼らには連絡をしなかった。一番上の兄、サミュエルは、まだ家にいた。彼は疲れて、憔悴していた。「彼はパパが倒れてからずっと、ほとんど休んでないの」母は言った。「仕事をして、看病をして、生きるのに最小限の時間しか寝てないのよ」
「やっと寝られるね」ジェイニーが言った。「ベッキーと私とで交代で看病するわ」
レヴィット氏は少しのあいだ滞在して、レキシントンへと向かった。彼にできることはなく、家の中には居場所がなかった。ジェイニーに知らせるとすぐに、彼は家を発った。彼女は綺麗なガウンを脱ぐと、部屋中を探し回って何年も前に置いていったドレスを見つけて着ると髪をうしろで縛り上げ、袖をたくし上げた。「今夜は私が乳搾りをする」
母は彼女のほうを見た。「まあ、ジェイニー。あなた、出ていった時よりもあなたらしくなったわね」母は肩を震わせて笑うと、古いドレスの織物をこすった。「あなたたちが置いていったものはとっておいたのよ」
「そうだと思った。ママはものを捨てないもの」ジェイニーは手を頭の上にあげて伸びをしながら言った。「昔の私に戻ったみたい!」
私は突然、シェーカーの服を脱ぎたくなった。私ははやる思いで母のほうを向いた。「私のドレスもあるの?」
「ジェイニーのと同じ棚の中にあるわよ」
ジェイニーは私について部屋に入ってきて、ベッドに腰掛けた。私は服を脱ぎ、ネットキャップを脱ぎ、髪をおろし、肩が楽になるのがわかった。「やっと自然に戻ったね」と彼女は言った。
私たちはお互いに笑いあった。もう一度昔の姿に戻るのは心地よかった。
毎日、今日が父の最期になるのではないかと思ったが、父は一週間持ちこたえた。いろいろな人が行き来し、食べ物を持ってきたり、夜どおし見守ったりした。ジェイニーと母と私は、仕事を始めるとすぐに昔の習慣どおりに戻った。サウス・ユニオンでの生活は徐々に薄れた。リチャードやシスター、ブラザーの思い出も薄れ、唯一現実味があるのは、朝の乳搾り、家の片付け、パパの看病、料理、近所の人との会話といった昔の日課だった。過去の楽しかった日々に時が巻き戻り、昔の暮らしに戻ったようだった。私はもう一度、この家での生活しか知らないレベッカ・ファウラーに戻ったように感じた。
ジョニー・クーパーがやって来たのは、私とジェイニーが帰った日から三日目だったと思う。彼は、ベティアが作ったプディングを持ってきた。それから、ベティアとデイヴィッドが明日の朝か、必要であればそれより早くに来ることを伝えた。母が連絡さえしてくれたら、と彼は言った。彼は体重が増えたが、いまだにたくましく、相当な筋肉質で、かつてのとおりスリムだった。母は彼を歓迎し座らせた。彼は私に明るく話しかけた。「君が来ているとは知らなかったよ」
「私とジェイニーは数日前に帰ってきたのよ」
「ジェイニーが?」彼の眉が釣り上がった。
私はうなずいた。「彼女とレヴィットさんが私を連れてきてくれたの。彼女は納屋にいると思う。ママの雌鳥が冬のあいだに卵を産んで、ひよこたちを孵化させたの。ジェイニーはその世話をしているわ」
彼はリチャードについて尋ねた。私はできるだけうまく説明した。彼の質問に、シェーカーたちとコミュニティと、私がそこに置いてきたすべてを思い起こした。「あいつは馬鹿なのさ」とジョニーがぶっきらぼうに言った。「いつも頑固で、強情な馬鹿だよ。君は彼と別れたほうがいい。彼は彼の選んだところへ置いていきなよ。君の人生を無駄にする必要はないよ」
私は生まれて初めて、リチャードを熱心に擁護しようと思わなかった。私はただ首を振って、返事をしなかった。
私は川岸の、昔なじみの場所について尋ねた。彼はワージントン家についてと、彼らがその場所で何をしたか、どうやって家を建て、一財を築いたかを話した。私は嬉しかった。「見にくるかい?」と彼は尋ねた。
「いいえ」私は行かなかった。見てもしかたがなかった。そこは、もう長らく故郷ではなかったから。
彼は立ち上がり、それから部屋の中をうろうろと動き回った。母は父と一緒にいた。「それじゃあ、戻るよ」と彼は言った。
彼がなぜ実家にいるかを話していなかったことに気づいたので、私は尋ねた。「まだ貨物輸送の仕事を続けているの?」
「まあね」彼は言った。「今はニューオーリンズまで川を下る貨物輸送をしてるよ」
「うまくいってるの?」
彼は笑った。「思っていたよりね。ルイヴィルに店舗があって……レキシントンにも一つ、あと河川交易用のボートが三艘と馬車がたくさんあるんだ。僕は貿易が好きなんだ。親父はそう思えないようだけどね。僕が農場に残ったほうがよかったんじゃないかって、いまだに思ってるみたいだよ」
「いいえ」私は言った。「農場はあなたには落ち着きすぎているでしょ」
「僕もそう言っているんだ。でも、できるだけ家には帰ってこようと思ってる。両親が歳をとってきたからね。心配に思うようになったんだ」
私は彼の仕事がうまくいっていると聞いて喜んだ。それから、貿易がどれだけ彼にとって魅力的なものなのかがわかった。彼は昔から切れ者だった。うまく商売をするのが楽しいのだろう。私は暖炉のそばに立っている、日焼けした黒髪の落ち着きのない彼を見て、彼の父であるデイヴィッド・クーパーも、ケンタッキーの荒野で開拓や狩猟をしていた若い頃にはこんなだったろう、と思った。彼はジョニーの落ち着きのなさをこれ以上ないほど理解しているのではないか。きっと、彼は同じ気持ちを知っているはずだ。「あなたがうまくやっていてよかった、ジョニー」と私は言った。「結婚はしてるんでしょ?」
「いいや」彼はこれ以上説明しようとしなかった……ただ否定だけして、それ以上話を続けなかった。
「ジェイニーが寂しがるよ。納屋へ行って少し話してきたらどう?」
「そうするよ」と彼は言った。「必要なら言ってくれよ」
私が約束すると、彼は行った。
彼はそれから何回か帰ってきた。彼とジェイニーは、今までよりも感じよく、うまくやっているように見えた。相変わらずジェイニーをちょっとからかったり、ときどき彼女を怒らせたりした……彼女が行っていたパーティーやダンスパーティーをいじった時のように。「レキシントンには何もないよ」彼は私に言った。「レヴィット夫人の名前を新聞で見かけることもない」
「なぜかしらね?」彼女は頭をふいに上げて言った。
「別段理由はないさ。レヴィットさんがどれだけ有名な市民かってことを考えればね」
ジェイニーはジョニーがそう言った時、彼をさっと見た。だが、彼は火をおこしていて、彼女の目を見なかった。彼女は自分の古い服を見下ろした。「私、今すぐにでもダンスパーティーに行きそうに見えないかな?」と言って彼女は笑った。
「僕にはとっても素敵に見えるよ」と彼は言った。それから彼は腰を上げ、トングをガチャガチャと暖炉の上に置くと、それ以上何も言わずにドアから出ていった。
「それにしても……」ジェイニーは言って、笑った。「ジョニーは昔と変わらないわね。何を言い出すかわからない」
彼は本当に昔のジョニーのままだった。それで私は、彼がジェイニーの結婚式で酒を飲みすぎていた理由が今になってわかった。彼はあの時ジェイニーを愛していて、今も愛しているのだ。それから、それが彼が決して結婚しない理由だと思った。
父は、ジェイニーと私が帰ってきたことを知ることなく、日曜日に亡くなった。もしかしたら一度、父は起きたかもしれない。彼の目が開いて、多分私のことを認識したように思われた。視点を合わせたように見えて、それから涙をためて、何かを言うように唇を動かしたが、再び瞼をぐったりと閉じて、呼吸が苦しそうになった。それから、彼のいつも冷たい足にあてるための温めたレンガを持って母が入ってきた。彼女は温めたレンガをいつもの位置に置き、もう一度温度を確かめた。「彼はもう長くはないわね」
ジェイニーは前の晩に徹夜で看病していて、午前中はずっと寝ていた。それから、ジョニーが午後に来て、馬を用意して乗馬に行かないかと彼女を説得した。「きっと気分転換になるよ」と彼はジェイニーに言った。
母も彼女を行かせようとした。「あなたは少し外に出たほうがいいわ」と母は言った。「家にこもりすぎよ。病気になってしまうんじゃないか心配だわ」
だから、ジェイニーは父の最期に立ち会えなかった。サミュエルと、母と、私が立ち会った。ベティアとデイヴィッドもいた。それはちょうど日没の頃で、ベティアは私たちの食事を作っていた。デイヴィッドは餌やりに出ていた。母とサミュエルと私はそこで、喋らず、一週間ずっとそうしていたようにただ座っていた。父はため息をつくと、深く息を吸った。そして吐き出すと、二度と息をすることはなかった。私たちは、彼の呼吸がとてもゆっくりになって、ときには呼吸のあいだが数分にもなることがあったので、待っていた。でも、もう息をすることはなかった。母はベッドの側へ寄り、彼の顔に触ると、彼の頬に手をあてた……それからかがみこんでキスをした。「さようなら、タイス」彼女はそう言って、優しく彼の顔に布団をかけると、立ち上がって部屋を出て、家を出ていき、丘を登ってしまいにはその頂上、山の尾根の草地へと歩いて行った。サミュエルと私は彼女が行ってしまうのを見ていた。「後を追ったほうがいいと思う?」とサミュエルは言った。
「いいえ」と私は返した。「ママは、二人がいつも愛していた場所へ行ったのよ。結婚したあと、そこから家を建てる場所を選んだって言っていたのを覚えてるでしょ。そっとしておいてあげましょう」
ジェイニーが帰って来た時、彼女の顔色はまるで幽霊を見たかのように蒼白で、泣いていた。よろめきながら居間を抜けて寝室へ走っていくあいだもずっと泣いていて、涙で視界がほとんど見えなくなっていた。私は彼女がどうやってか聞きつけたに違いないと思いながら、あとをついていった。「そんなに悲しまないで、ジェイニー」私は、そう言って、彼女に腕を回した。「ママが言ったように誰しも最期の時は来るの。パパはもう苦しまなくてよくなったのよ」
彼女は咽び泣きに震えて、それでも急に振り向いて私のほうを乱暴に見た。「パパは死んでしまったの?」
私が答える前に彼女は私の横をすり抜け、父の部屋へと入っていった。彼女が大声で泣くのが聞こえて、私が部屋に入った時にはベッドの脇の床に突っ伏していて、父の布団は引っ張られて彼女の手にしっかりと握られていた。彼女は卒倒してしまっていた。
葬儀の時はいつも、どこか非現実的で夢のようだ。人々が代わる代わるやってきて、食事が用意されて、それを食べて、必要なことをして、寝て起きるのだ。デイヴィッドとベティアと他の近所の人たちが仕事の負担を引き受けて、何とか埋葬の手はずを整えてくれて、墓が掘られ、棺が作られた。夢うつつの状態でいるあいだに、これらの必要なことが執り行われていた。父は、三人の子どもたちが亡くなった時に埋められたのと同じ尾根の平原に埋葬されることになった。そして、すべての用意が整うと、デイヴィッド、ウィリアム・ワージントン、ウィリアム・ケーシーと、その他彼の友人たちが彼の棺を担いで、皆で急な丘を登った。
レヴィット氏もそこにいて、ジェイニーは丘を登るあいだ、彼に支えられていた。私は母とサミュエルと一緒に歩いていたが、丘を登りきる頃に喋れるほど息が切れずにいられたのは母だけだった。彼女には、支えは要らなかった。サミュエルにも、私にも支えられることはなかった。「彼はここで安らかに眠るでしょう」と母は私たちに言った。「彼の愛した場所を見下ろしながらね」
その夜、私たちは暖炉を囲んで話をした。デイヴィッドは、また一人友人を失って悲しんでいた。「みんな先に逝ってしまったよ」彼は言った。「危険を冒して土地を開拓して、後に続く者たちのために安全な場所にした仲間たちが。じきに誰もいなくなってしまう。(1)ベン・ローガンに、ジム・ハロッドが死んで……ダニエル・ブーンは遠くへ移った……古い開拓者たちは皆死ぬか、立ち去ってしまったな。俺もそろそろだな」
「そんなこと言わないで」とべティアが彼に手を差し伸べながら言った。
彼はそんな考えを振り払うかのように肩を震わせると、彼女に微笑みかけた。「ああ、母さん。俺はとっても元気さ。まだまだ長生きするよ」
「そう願うわ!」
レヴィットさんは、ジェイニーを残してレキシントンへ帰っていった。彼はまた来週、彼女を迎えにくることになっていた。ジェイニーは母とともに街へ帰り、そこで一緒に暮らしたがっていた。だが、母にそんなつもりはなかった。「サミュエルが、春にメアリー・ワージントンと結婚する予定なの」と母は言った。「彼はここに彼女を連れてきて、私たちの世話をしてくれようとしているわ。ここが私の住まいだし、離れるつもりはない」
ジェイニーもそれが一番いいと思ったようだった。彼女は私に向き直った。「あなたは、あのシェーカー・タウンとかなんとかという所へ戻ったりしないわよね。ベッキー? あなたはもう自由なんだから、私と一緒に街へ帰りましょう」
私はジェイニーについていくつもりはなかった。都会での彼女の暮らしぶりは、私には絶対に合わないだろうと思った。でも、正直にいうと、母と一緒にいるつもりはないとは言えなかった。昔の幸せな暮らしが私を揺らがせていた。ここに残りたいと言えば、喜ばしく、優しく歓迎されることはわかっていた。草原を渡って小川へ至る道、尾根を登った空き地への道、家とすべての建物の行き帰りの道といった慣れ親しんだ小径のことや、暖炉からテーブル、ベッドにいたるまで家のことを考えていた。
ここに残るのは幸せなことだろう。そうとわかっていて、平穏を望んでいても、私はここに残らないだろうし、平穏な暮らしもずっとは続かないことを知っていた。慣れ親しんだ道のことを考えているあいださえも、ヴィレッジに続く舗石や、二つの階段や、ベッドの並んだ長い部屋、パルミラ、アニー、レイシー、ヴィニーやシスター・プリシラのことを思い出してしまうのだった。それからリチャードのことも。私はもう引き返せない旅に出てしまったのだ。子ども時代に戻ることはできないし、昔住んだ家をもう一度取り戻すことも決してできない。私はリチャードについてサウス・ユニオンへ行ったのだし、今はそこが私の家だった。私は首を横に振った。「私はシェーカーから離れられない、ジェイニー。帰らなくちゃ」
ジェイニーは私に腹を立てたが、母は私の言い分を理解して微笑んだ。母も父のあとについていっただろうし、彼がいる限り、彼のもとを離れなかっただろう。彼女は私がすべきことをわかっていた。
第13章訳註
(1) ベン・ローガンに、ジム・ハロッドが死んで……ダニエル・ブーンは遠くへ移った
ベンジャミン・ローガン(Benjamin Logan,1742-1802)、ジェイムズ・ハロード(James Harrod,1746-1792)、ダニエル・ブーン(Daniel Boone,1734-1820)の3名は、本作の舞台であるケンタッキー郡の民兵隊(1776年に編成)で隊長を勤めた4名のうちの3名である。もう1名はジョン・トッズ(John Todd, 1750-1782).
本文ではそれぞれベン・ローガン(Ben Logan)、ジム・ハロード(Jim Harrod)、ダニエル・ブーン(Daniel Boone)と表記されている。