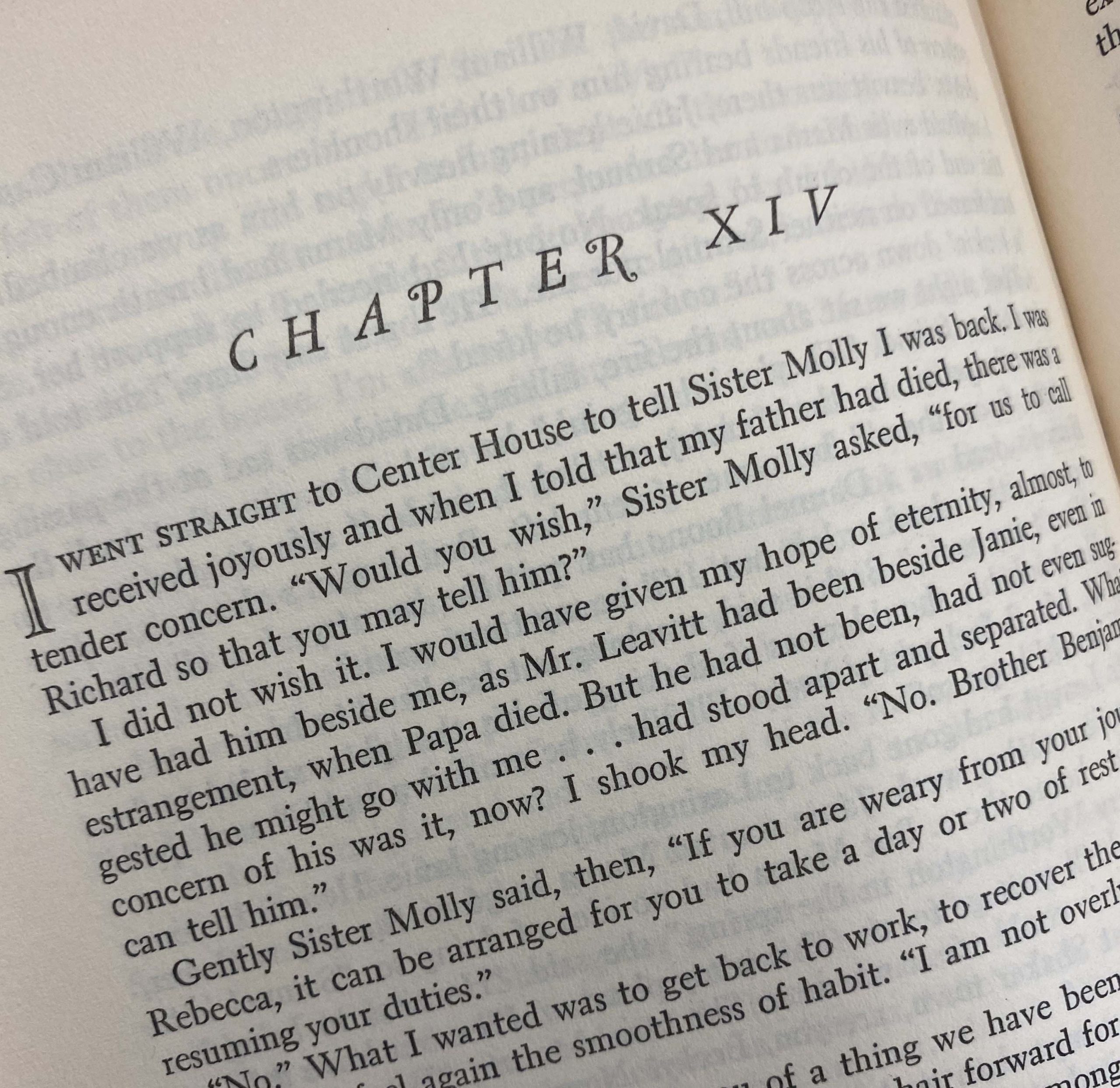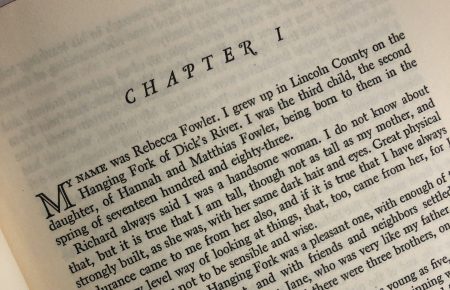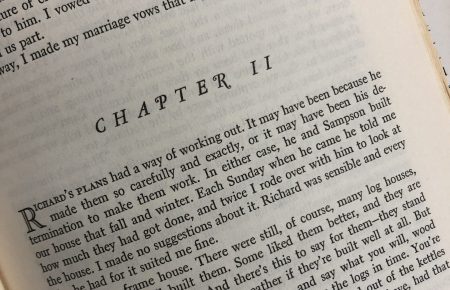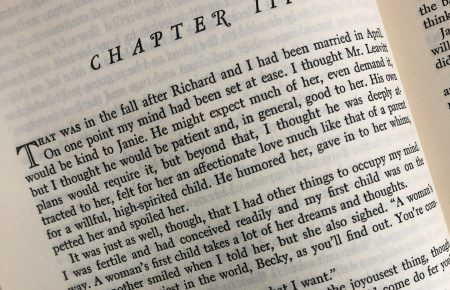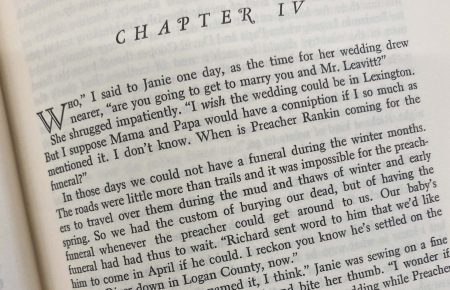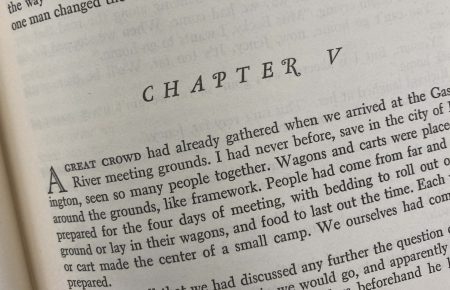私はセンター・ハウスに直行し、シスター・モリーに帰ってきたことを伝えた。彼女は喜んで私を迎え入れてくれ、父が亡くなったことを伝えると、気遣ってくれた。「リチャードに伝えるために彼を呼んできましょうか?」と彼女は尋ねた。
私はそう望んではいなかった。ジェイニーの側にレヴィットさんがいたように、たとえ疎遠であっても、父親が死んだ時にリチャードが私の側にいてくれたら、と希望を持ってしまうところだった。しかしリチャードは私の側にいなかった。私と一緒に帰る気配すら見せず、私から離れていってしまった。彼は今どんなことを考えているのだろうか。私は首を横に振った。「いいえ、ブラザー・ベンジャミンから伝えてください」
すると、親切にも 「もしあなたが旅路で疲れているならば、仕事を再開する前に一日か二日間の休息をとる手はずを整えられますよ」とシスター・モリーは言った。
しかし私はそれを望んでいなかった。私が望んでいたのは、仕事に復帰して、日々の仕事をこなす感覚を取り戻し、習慣が与えてくれる落ち着きを取り戻すことだった。「そこまで疲れてはいません」と私は言った。
「それでは、私たちが話し合っていることについてお伝えしましょう。レベッカ、座って聞いてください」と彼女は言って、私の前に椅子を引いた。彼女は熱心に話した。「あなたは他の女性たちの中でも特によく学んでいます、レベッカ。ブラザー・ベンジャミンと私はずっと話していたのですが、あなたはイースト・ファミリーでの仕事ではなく、教える立場に回るべきではないかと思っています。スクール・グループが急増しており、新しい指導者が必要なのです。やってくれますか?」
やってくれますかですって?私たちは普段そういった質問をされることは滅多にないし、初めて提案されたことだったのですぐには飲み込めなかった。最初に感じたのは、イースト・ファミリーを離れてスクール・ハウスの指導者へ回ることへの不安だった。私はあまり気が進まなかった。「イースト・ファミリーから離れるべきかどうか私にはわかりません。ここでの生活に慣れてしまったものですから」と私は言った。
「あら、すぐにというわけではないわ。スクール・ファミリーには今のところあなたが生活するための部屋がありませんから、引き続きイースト・ファミリーと寝食を共にしてもらいます。あなたはファミリーの仕事を免除されます。シスター・プリシラの指導から離れ、一時的にブラザー・ステファンと(1)シスター・ドルシーの下に移るのです」
それはありがたいことだった。しかし私は教えることに自信がなかった。どうして私にできると思ったのだろう。もし失敗したら? 彼らが私を買いかぶっているとしたら?「私が勉強したのはしばらく前のことです、シスター・モリー」私は恐る恐る言った。「指導できるかどうかわかりません」
彼女は微笑みながら言った。「私たちはできると思っています。あなたは素晴らしい教師になれると思っています。ヴィレッジの女性の中で、あなたがもっとも能力のある適任者なのでは、と私たちは考えていますよ」
誰だって、人間なのだから、一人選び出されたことに誇りを感じずにはいられないだろう。それは私たちシェーカー教徒が感じる唯一の誇りである……お金を稼ぐことや、個人の財産や権力といったものへの関心や羨望がないかわりに、毎日の仕事を変わりなく続けていくという能力への誇りである。我々にはただ、与えられた仕事をよくこなし、自分の能力を認めてもらうことへの誇りが存在するのである。これは私たちみんなの誇りだった。「何を教えればよいのですか?」と私は尋ねた。
「ブラザー・ステファンから伝えられるでしょう。彼が教育上のすべての責任を任されています。年長の女の子たちを担当することになると思いますが」
私はスクールに関してほとんど何も知らなかったので、どんな科目が教えられているのかまったく知らなかった。たとえば、私はラテン語の指導に不安を感じ、そのことを伝えた。「あら、私たちは語学の指導は行っていないわ。語学が実用的で必要なものだとは考えていませんから。私たちは子どもたちに、修辞学、読書、算数のしっかりとした基礎を与え、それから地理と歴史についてある程度の理解を与えたいのです。私たちは歴史が果たして必要かどうか疑問に思ったけれど、ブラザー・ステファンは絶対に必要だと考えていて、だから少なくともさしあたりは続けることにしているのです」とシスター・モリーは言った。
シェーカーの人々は私たちにあまり深く考えさせることを好まないのだという考えが、再び私の頭をよぎった。おそらく彼らは正しい。考えることはしばしば疑念と不幸に結びつく。考えすぎる教徒たちはシェーカー教の全体構造をひそかに蝕むのかもしれない。「いつから教え始めればよいですか?」と私は尋ねた。
「もし休む必要がないのであれば、明日からがよいでしょう」
教科書を一読し、スクールを訪ねてやり方を観察し、準備をするのには少し時間がかかるように私には思えたのだが、シスター・モリーには、明らかにそのような考えはないようだった。私は思い切って飛びこんでみることに決めた。 「わかりました」
「レベッカ、それではシスター・プリシラにそのことを伝えるので、私に直ちに会いにくるようにと伝えてくれますか。今夜の集会で、あなたの異動を発表します。ブラザー・マクネマーが来ているのですが、日曜日まで滞在することができないので、今夜(2)ユニオン・ミーティングを行います」彼女の丸くて、しっかりした頬は、にっこりと笑っていた。「私たちはこの一週間、ブラザー・マクネマーから素晴らしき教訓を授かっています。あなたが間に合って帰ってこられて、また彼の教えを聞くことができてとても嬉しいです、レベッカ。私たちは彼のもとで聖霊の偉大なる訪れを体験しました」
私はブラザー・マクネマーに再び会ったり彼の話を聞いたりすることに、大した喜びを感じなかった。私は、彼の宣教師としての熱意が私たちをシェーカー教一派に引き込んだことを忘れたことはなかったし、彼らと関わらなくてもうまくいったと思っていた。シスター・モリーが私の腕に触れた。「お帰りなさい、レベッカ。ヴィレッジからしばらく離れていたことは辛かったでしょうね」
私は驚嘆して彼女を見た。これまで彼女は人生の中で一度だってシェーカー・ヴィレッジの外で生活したことがないのだ。彼女の全世界を構成しているすべてのものから引き離されることは、確かに辛いことなのだ。
夕食の鐘が間もなく鳴る時間だったので、シスター・プリシラを探し出してシスター・モリーからの伝言を渡すために、私は真っ直ぐキッチンへと向かった。私が彼女を見た時、彼女がだいぶ落ち着きを取り戻していることがわかった。帽子が盗まれたことへの屈辱をあえて心の奥底へと押しやり、それが二度と彼女の心をかき乱すことのないようにしていたのだろう。彼女は眼鏡を上げると、私を見つめて、歓迎の言葉のひとつもなしに「あら、こんな時間に何の用事でしょう? 夕食を用意している最中だとわかっているでしょうに」と言った。
私は彼女の言葉を無視し、ただシスター・モリーがすぐに来るようにと言っていたことを伝えた。彼女は落ち着かない様子で辺りを見回した。
「わかりました。あなたはキッチンを手伝いなさい。もはや酪農の仕事をする必要はありません。夕食まであと三十分もないですから」
彼女が行ってしまうと、みんなが他の部屋から慌てて走ってきて、私のところに駆け寄ってきた。パルミラは紡績室から慌ててやってきた。「あなたがセンター・ハウスから歩いてやってくるのが見えたの。あなたに会うのが待ちきれなかった」彼女は私を強く抱きしめて、キスをした。「まあ、私も会いたかった。元気でやっていたの?」
ああ、パルミラに再び会えるなんて! 「元気よ」私は言った。そこには古くからの友人であるレイシーとヴィニーや、アマンダもいた。酪農場にいるアニーだけはいなかった。アマンダはキッチンで業務についていて、私が、今は話してはいけないと言うと、不満そうに話した。「すべて準備は整っているわ。プリシーは彼女なしでも事が回っていくということが許せないみたい。時間になったらすべてテーブルの上に用意されるわ。あなたのお父さんは回復した?」
再び私は彼の死について伝えると、みんな同情してくれた。レイシーは普段からすぐ泣くが、しくしく泣きながら悲しげに人生の儚さについて口にした。ヴィニーも同情し、それは残念なことだけど、すべての人間にやってくることだと考えを話した。「私の目の前に死神が見えるわ」と彼女は言った。
「まあ、あなたは(3)メトシェラと同じくらい長生きするわよ」とパルミラは彼女に言った。それから彼女は思慮深く私を見た。「あなたの気持ちはいったいどんなものか、私にははっきりとはわからない。今まで自分の父の面倒を十二分にみたことがないから、あなたの気持ちがわかるなんて言いたくはないけれど、あなたはずっと辛かったと思うし気の毒に思っているわ」パルミラはいつだって正直な人だった。
私がいないあいだに起こった出来事について聞きたいと思ったが、特に変わったことはないようだった。プリシーは元に戻った。仕事の当番が明日から変わるようで、みんな何に割り振られるのかを知りたがっていた。「次は私がキッチンを担当する番だと思うわ」パルミラはため息をつきながら言った。「プリシーが四六時中邪魔に感じられることでしょうね」
その時、私は教育係を始めることを言いかけたが、やめておいた。もしかしたら直前で変更があるかもしれない。私からは何も言わないでおいて、彼女たちは今夜の集会での発表で初めてそのことを聞けばいいと思った。そしてそれは公式のものとなるのだ。代わりに私は「ブラザー・マクネマーが来ていると聞いたわ」と伝えた。
「ええ、毎晩ユニオン・ミーティングをやっているわ」とヴィニーは応えた。「骨が軋むまでダンスして、耳が疲れるまで歌を聞いたわ。これが彼の最後の夜でないと、私、耐えられるかわからないわ」
「聖霊からのギフトがたくさんあったとシスター・モリーから聞いてるわ」
パルミラは真面目にうなずいた。 「ある夜、プリシーは(4)ワーリング・ギフトを授かったわ。彼女がブラザー・マクネマーの前に躍り出て、彼女のスカートがめくれ上がって脚が見えるまでぐるぐる回っていたのを思い出すわ」
「プリシーがそんなことを!」
「プリシー……本当よ」みんながそう証言した。 ヴィニーはくすくす笑い出した。 「あなたも見るべきだったわ!」
私も見ることができたらと思った。「ブラザー・ベンジャミンはダンスを中断したの?」
「ええ、そうよ。すぐにやめさせたわ……彼女のギフトに十分な場所をつくるためで、彼女もそれが必要だったに違いないわ」
「どのくらい続いたの?」
「一時間ぐらいだったかしらね」とヴィニーは続けた。「すごい光景だったわ。彼女は爪先立ちのような格好で、ものすごい勢いでぐるぐる回って、あてもなくさまよって、それから本当に鮮やかな動作で部屋中を滑るように回って、もし邪魔になっている人がいても、気にしないみたいだった。誰かが止められるような感じでもなかった。トランス状態から突然気を失った彼女を床に寝かせるまで、彼女は火かき棒みたいに硬直していたと彼らは言っていたわ。意識が戻った時、彼女は天国の光景を見たと断言し、そこは純白かつ金色に光輝いていて、それから彼女は天国に居を定めるのが待ちきれないのだと言っていたの」
「私も待ちきれない」パルミラは皮肉交じりに言った。「天国が本当にあるといいんだけど、もしプリシーがそこに行くつもりなら、私は行きたくないわ」
アマンダは、キッチン棚の上にある時計を見た。「盛りつけの時間だわ。関係ない人たちは外に出て、準備をさせてちょうだい」
私たちは鐘が鳴ると同時に机に料理を運び、十分ほどでブラザーやシスターたちが列になって入場してきた。「あなたは食べにいって」 アマンダは私に言った。「まだあなたはキッチン当番ではないわ」
私たちがお祈りのために膝をついていたちょうどその時、プリシーが慌てた様子で入ってきて、私が立ち上がって席に着くのをあからさまに見ていた。勝利の喜びが私の中に湧き上がってきた。あなたは自分の管轄下にあるのだと、彼女は以前私に言った。もう私は彼女から自由になったのだ!
彼女は私が異動することを嫌がっていたと思う。というのも、私はこれまで彼女の意地悪な言動の恰好の餌食だったからだ。彼女は、私を完膚なきまでに卑しめることを日課と定めていたに違いない。その日課は今や彼女から取り上げられて、まるで私に裏切られて一杯食わされたとでもいうかのように、私を不満げに見ていた。しかし私は堂々としていられた。私は何もしていない。この幸運はひとりでにやってきたわけだから、私はその幸運に浸った。
部屋の向こう側からリチャードが私のほうをちらっと見たが、彼の顔に笑顔はなかった。彼は代わりに真面目な顔つきで、こちらを一瞥して会釈すると、すぐさま食事に取り掛かかった。私が思うに、ブラザー・マクネマーは、リチャードにまた影響を及ぼし、彼をより厳格でより従順にしたように見えた。リチャードは私の存在に口元を緩めることもしなければ、彼の目が同情や歓迎の意図を送ってくることもなかった。
苦痛の代わりに、私は信念が固まるのを感じた。上等よ、私は思った。かた苦しくなって、冷淡になって……勝手にすればいい。初めて私は自分自身の価値の存在を意識した。私はリチャードよりも学んだのだ。リチャードにはできない仕事のために、ヴィレッジの長老たちによって選び出されたのだから。私はその名誉を深く感じ、嬉しく思った。これからは、リチャードの影に生きることなく、彼を思いやったり彼に恋い焦がれたりすることなく生きると固く誓った。私は妻としては捨てられたのだ。だから……私は独立した個人に変わるのだ。私は自分のために思考し、自分のために行動し、リチャードの信念に満ちた顔に怯えることもなければ、それに従順になることもない。私は指導をし、指導をすることから学び、そして私はレベッカ・ファウラーとしてではなく、新しくよりたくましいレベッカ・クーパーとして生まれ変わるのだ。私は誓いを立て、その日の晩、日記に記した。これは私にとって、節目、それも重要な節目であると。
人生で初めて、自分にもできることがあると思えた。私はそれを上手くできるだろうし、そしてきっと私にしかできないことなんだ、と。私は、子どもの頃はずっと母の強さを感じ、その強さに守られていた。さらにリチャードの強い決意の中で、彼の保護の下にいた。今初めて、私は選ばれたのだ……レベッカとして。私、レベッカはこの機会を最大限に活かすつもりだ。
夕食のあとの休憩時間に、シスター・スーザンが私のもとに来た。「センター・ハウスへ行きなさい」と彼女は言った。
私の新しい仕事と関係していると思って、急いで行った。しかし私はシスター・ミリーに迎えられ、応接室に導かれた。リチャードはブラザー・マクネマーとブラザー・ベンジャミンと一緒にそこにいた。彼らは私の父について尋ねた。そして彼らは礼儀正しく彼の死の知らせに同情の念を抱いた。「あなたのお母さんとお父さんは健康よ」と私はリチャードに言った。「よろしくって頼まれたの」
私には彼がよりやせ細ったように見えた。毎日誰かに会っていると、小さな変化には気づきづらいが、しばらく会っていないと、その変化に気づくことができる。リチャードはほとんどやせ衰えたように見え、彼の頬骨は高く、顎のラインはより鋭くひきつっていた。「両親が健康で嬉しいです」と彼は言った。
私は言った。「ジョニーは今は商人で、レキシントンとルイヴィルに店を持ち、河川貿易にも携わっていたわ」
「俗世の商売か」と彼は言ってジョニーを退けた。
その後、ブラザー・マクネマーが会話を継いだ。「シスター、私たちがあなたを呼んだのは、正会員になる準備ができているか話をしたかったからだ。 リチャードは専念することを大いに望んでいる。 もちろんそれはあなたの理解と意志次第だ」
私は、足元のカーペットを見つめているリチャードを見た。「私たちの土地を教団に託すことも意味するのですか?」
「いかにも。正会員は誰であろうとあらゆる財産の所有は認められません。あなたはもう神のギフトを受け取りましたか? 意志はありますか?」
一カ月前であれば、私はリチャードを幸せにさせる望みと私自身の望みとのあいだで迷っただろう。一日前でさえ、そうだっただろう。しかし自分でも驚くほどの堅実さを持って、私は話しだした。「私にはそのような意志はありません。私はまだ自分たちの土地を手放すことも、正会員になることも望んでいません。リチャードがこれをよく思わなかったとしても、残念ですが、私は私自身の気持ちに従うしかありません」
リチャードは私を見た。そのとき、もしまわりに人がいなかったら、彼は私を叱りつけただろうと確信した。彼は顔を赤らめ、目を細めた。しかしながら、彼は長老を前に何も言わなかった。ブラザー・マクネマーは悲しそうだった。「あなたがそう仰るのを聞いて残念だ。あなたがここを離れていた数カ月間で、俗世の過ちに気づき、チャーチ・ファミリーに入るだろうと思っていたのだが……何が不満なのでしょう、シスター?」
私は彼の質問について考えた。「わかりません」 彼に正直に話した。「私は適応するよう努力しました。心からそう思いたいです」 私は正直に付け加えた。 「しかし、自分たちの残りの財産を手放すことは気が進みません。私は……」
ブラザー・マクネマーは私に微笑んで、首を振った。「レベッカ、あなたが物理的に財産を持っている以上、それを手放すのは気が進まないでしょう。すべてを自分の意思で捧げることが、神の国に入る唯一の方法なのです」
彼が正しいことはわかっていた。確かに私はヴィレッジでそれほど不幸ではなかった。短い期間なりに、私はここでの生活に慣れてきた。しかし、自分の居場所があるという事実が私には必要であることは確かだった。いつか私がそこに戻るかもしれないということは考えても望んでもいないけれど、そこに私とリチャードの名前が残っているという事実が、いつも私を安心させていた。私はそこから離れることができなかった。
また、私は神の国に入りたいかどうかわからなかった。そこまでの道のりは脆く、不完全であることに内心不安があった。それはどういうわけか、生命の水をせきとめるダムのように思えた……ダムはいつか決壊するだろう。そして水は海を求め、ダムを越えてあふれて、最後には手に負えなくなるのだろう。私は頭を振って、繰り返した。「同意できません」
リチャードは怒りの表情で私を見た。私はリチャードの足を引っ張っていたのだ。今やっと、彼がやせ細った理由がわかった。彼の心は正会員になることを決めていたのだ。彼は、他の人より神聖で、崇高で、信頼されたチャーチ・ファミリーの一員になることを強く望んでいた。彼はそうでないことに耐えられなかった。「お前は頑固だ、レベッカ」 彼は言った。
「どんぐりの背比べよ!」と私は叫んでやりたかった。しかし何も言わなかった。私はリチャードが自分自身を頑固だと自覚したことがあるのか疑った。彼は常に自分の信念が正しいと思うあまり、自分の頑固さを自覚できないのだろう。私は初めて彼を否定した。そして彼は動揺し、私に腹を立てていた。私にはどうしようもなかった。心を決めたのだから。
「祈りを捧げましょう」とブラザー・マクネマーは言った。そして私たちはひざまずいた。彼とブラザー・ベンジャミンは、私が目を覚ますようにと熱心に祈った。私が聖霊を受け入れ、聖霊に受け入れられ、完全な教徒になることを。私は彼らの声がほとんど聞こえなかった。私は自分の中に新たな勇気を発見したばかりなのに、すでにリチャードに対して反抗している自分に気づいて深く身震いした。それは今までの私の生き方に完全に反することだったが、このえも言われぬ不安が私のもとから取り去られるまでは、彼に逆らい続けると決めた。
ミーティングの鐘が鳴ると、私たちは腰を上げた。私はシスター・モリーとシスター・マーシーに加わり、ミーティング・ハウスへの道を辿った。
私たちは歌い、ブラザー・ベンジャミンは証言を読んだあと、私のスクール・グループへの異動を発表した。私は彼らが心を変えるかもしれないと思っていので、私はそれを聞いてほっとした。しかし、直ちにブラザー・マクネマーが歌い出した。「Whoever wants to be high, highest, Must first come down to low, lowest, And then ascend to high, highest, By keeping down to low, lowest.」それは以前に聞いたことのない歌だったが、それは私の驕りを戒めるものだと思った。
ブラザー・マクネマーが、その夜さらに祝福のダンスを私たちに教えることを選んだのも、偶然ではないと私は思った。部屋の片側に男性、もう片側に女性が方形に並び、お互いに向かい合った。そして聖霊の祝福を受けるように手のひらを上に向けながらシャッフル・ステップでゆっくり交錯した。私も行った。しかしダンスが終わっても、ダンスを始めた時と同じように、手のひらには何も感じなかった。私に祝福は与えられなかったのだった。
第14章訳註
(1)シスター・ドルシー
実在したシェーカー教徒であるシスター・ドルシー(Dorothy Durgin, 1825-1898)のことであると思われる。シスター・ドルシーは、1857年から1912年までカンタベリーの共同体で指導者をつとめ、理想のシェーカー教徒とされた。
(2)ユニオン・ミーティング
ユニオン・ミーティングは、6名程度の少人数のブラザーとシスター達が一所に集まり、対面して着席した状態で社交的な交流や賛美歌の歌唱を行うミーティングである。定期的に開催されるユニオン・ミーティングは、仕事や礼拝の時間を除いて日常的な生活の時間を共有することがなかったシェーカー教の男女が、お互いを知ることができる希少な機会だった。
(3)メトシェラ
ノアの洪水以前のユダヤの族長で、969歳まで生きたと言われる長命者。『旧約聖書』第1巻「創世記」5章21節から27節に登場する。
(4)ワーリング・ギフト(whirling gift)
ワーリング・ギフトとは、礼拝中に教徒が授かるギフトのうち、コマのようにその場でぐるぐる回る行為。