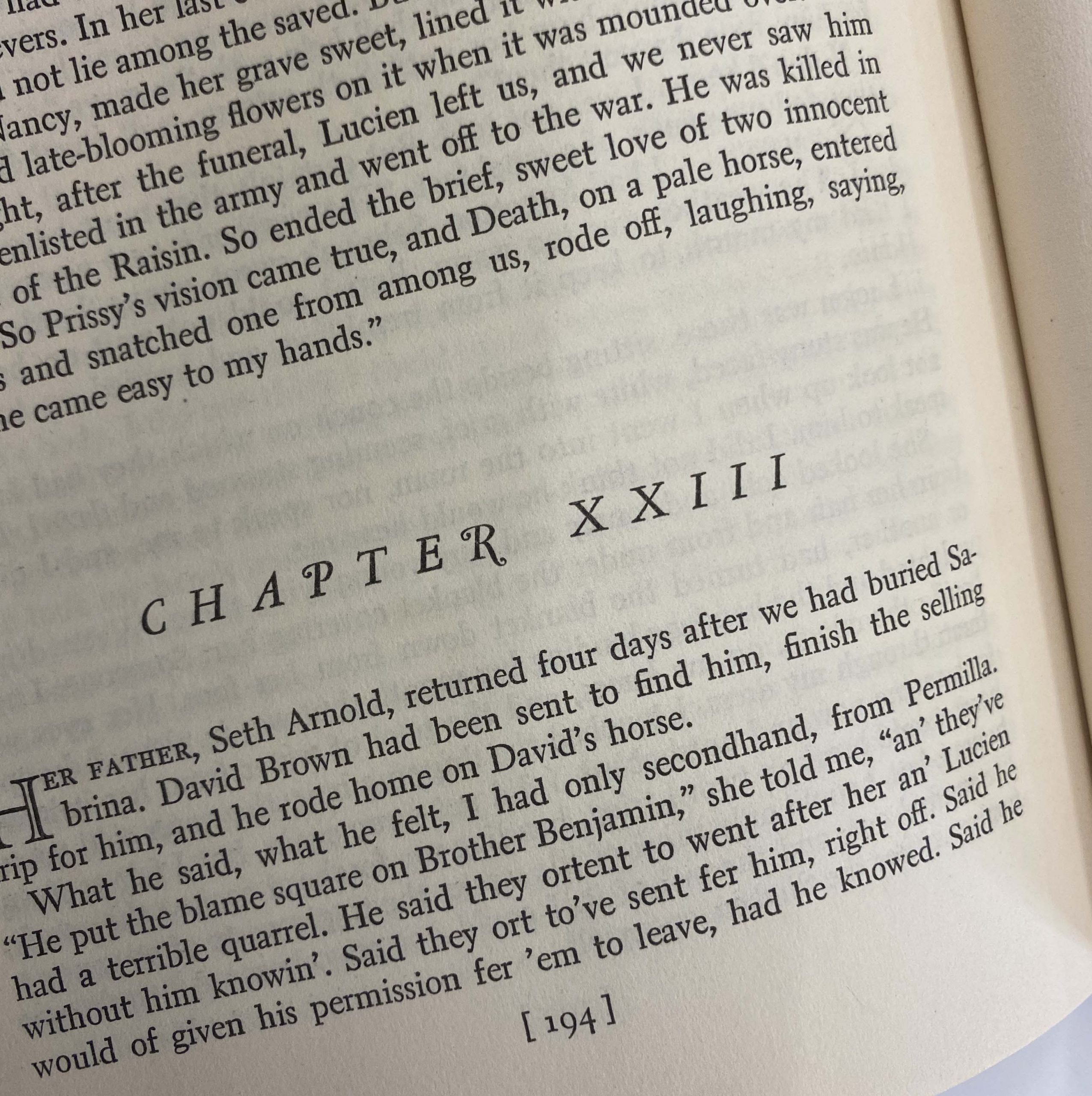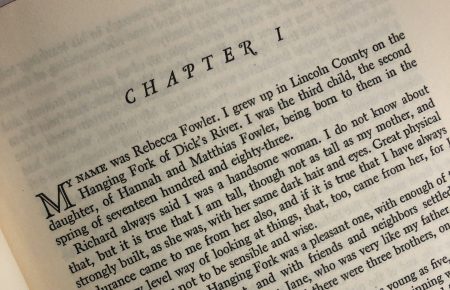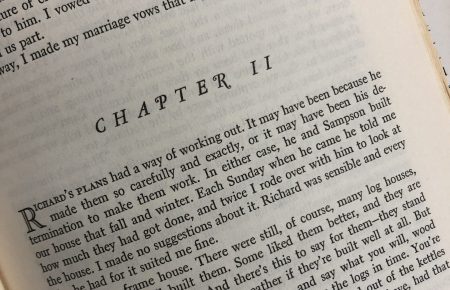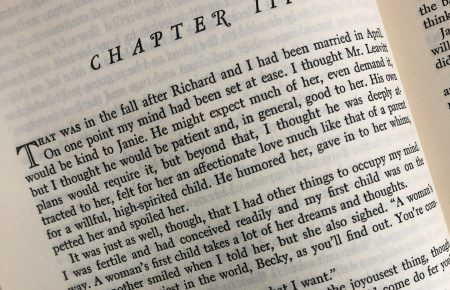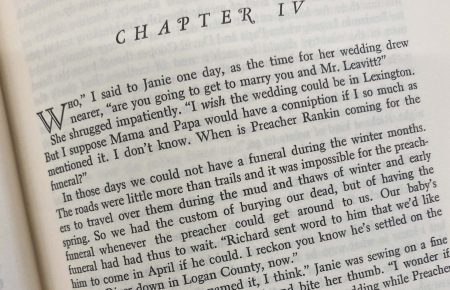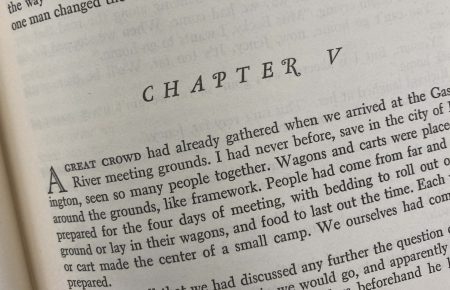サブリナの父親であるセス・アーノルドは、彼女を埋葬してから四日後にコミュニティに戻ってきた。デイヴィッド・ブラウンが彼を探しに遣わされて、アーノルドの販売出張を終わらせた。そして彼はデイヴィッドの馬に乗って帰ってきた。
私は、彼の言ったことや彼の感じたことを、パルミラ伝いでしか聞かなかった。彼女は「彼はブラザー・ベンジャミンを真っ向から非難していた」と私に言った。「それで、彼らは酷く口喧嘩をしていたよ。彼は、自分に知らせずに彼女とルシアンの後を追いかけるべきではなかった、って言っていた。自分をすぐに呼び戻すべきだった、もし自分がサブリナとルシアンが逃げだしたことを知っていたら、彼らにここを離れる許可を与えていたのに、って。それから彼は、彼女がここに満足していなかったことに気づいていたし、そのことがかなり長いあいだ気がかりだったんだって。彼はここに彼女を連れてきたことについて、自分自身のことも責めて、自分がここにきたことが間違っていたんだ、と言ってたよ」
「私は彼を責めないよ」と私は言った。
「私もそう」と彼女はすぐに賛同した。「彼の立場なら私だってそうしたと思うよ」
私は揺るぎない、私たち教徒のためのシェーカーの建物を見つめながら、その建物がシェーカーたちのどれだけの心傷や悲しみを見下ろし、縛りつけ、閉じ込めてきただろうかと思った。私は「このヴィレッジはこうなるはずではなかった」と言った。
パルミラは笑った。「うーん、そうかなぁ。ここを気に入ってる連中にとっては悪い場所じゃないよ。ここでは身体が疲れてうんざりするほどのことはほとんどないし、癒しがたくさんある。私たちには食べるものがたくさんあって、頭上には頑丈な屋根があって、やるべき仕事もあるし。私はこれ以上快適な環境を知らないよ。ここでなければ、子どもたちがちゃんとご飯を食べられるかどうかを心配して、学校に通うのを見届けることはできなかったと思うね。私にとって、ここ以外の場所は考えられないな」
私には彼女の意味することを理解できた。その一方でパルミラは無知であったし、のんきで、抑圧された生活から解き放たれると,すぐに満足するような人だった。私にとってシェーカー教徒としての生活は監獄のようになっていた。彼女にとってそれは、彼女の人生の中で最良だった。
その違いは私たちの内にあったのだ。私は、パルミラがシェーカーの理念を今まで一度も遵守したことがなかったことを知っていた。しかし、彼女にとってそれらすべては何ら問題とならなかった。彼女は美しく、健やかで,はつらつとしていた。そして彼女の人生にとって必要最低限のことは十分に揃っていた。彼女はトーマスとは縁が切れ、ご飯も暖かい場所も安全な場所もあって、何も心配なことはなかった。それはパルミラにとって十分だった。
ステファンと私は、数日後にそれについて話し合っていた。私は「パルミラは彼女と年齢の近い男の人と結婚することができなかったことがかわいそうだ」と言った。
彼は「彼女は十分幸せそうに見えますよ」と言った。
「そう。でも彼女はもっと幸せになるべきだった」
「あなたはどうでしたか?」
彼の質問は私を立ち止まらせた。もちろんリチャードの年齢、彼の活力、私たちの人生は私の最大の傷につながっていたからだ。「結婚について」ステファンはとつとつと続けた。「私は所帯を持つことに強い望みを持っていませんでした。私はいろいろな場所を転々とし、山の上にある新しいものに何でも引きつけられた。しかし最近、私は結婚にいくらかの価値を見出したのです」
「そして……」私は言った。「結婚しなかったことを悔やんでいるのでしょう?」
彼の口が苦々しくゆがんだ。「いいえ。いや、それは違います。ただ……その、気にしないでください」
私は彼の話についてよく考えた。私は言った。「私は、相応しい年齢があるのだと思います。そしておそらく、あなたはその年齢になりつつある。人との付き合いがとても魅力的に見える年に。若いうちは、いろいろな場所を転々とするのはとてもよいことです。人生のすべてが目の前に広がっています。でも中年になれば、炉辺を妻やよき仲間と囲んでいるのが相応しく見えます。そして歳をとって骨がきしみ始めると、何をするにも簡単にはいかなくなります」と、私は最後にからかうようにちょっと付け加えた。
ステファンは笑いながらのけぞった。「ベッキー、ベッキー! 私の骨はきしまないし中年であることも認めない。私はまだ若い」
「もちろんまだ若いです」私は認めた。「結婚して家庭を持つのには十分すぎるくらい。どうでしょう、ステファン?」
「もしも私が去ってしまったら、学校はめちゃくちゃになってしまう、そうあなたは考えていたと私は思っていました」
「引き留めたのは私のわがままでした。私たちはなんとかやっていけます。もしかしたら、そろそろ結婚する時が来たのかもしれません。あなたがその気持ちを強く持っているうちに」
彼は肩をすぼめた。「もしかしたら……でも、しばらくは違うのではないでしょうか」
「あなたは後々、結婚に対する考えに固執しすぎてしまうようになるかもしれません。もしあなたが望むなら、あなた自身のための家、妻、そして家族を今にでも持つべきです」
彼はつま先で意味もなく地面に何かを描きながら、地面を見つめていた。「この気持ちを失う恐れはありません。家庭があったらいいなと願いました。あるほうがいいかもしれないですね」そして彼は地面に描いていた落書きをこすり消し、本を移動させて笑った。「でも、そこに気持ちでは不十分です、ベッキー。ふさわしい女性がいなければなりません」
「シェーカー・ヴィレッジでその女性を見つけることは決してできないですよ」私は彼を笑いながら言った。「ステファン、もしかしたらいずれにせよ長い冒険をする運命なのかもしれませんよ。あなたには行きたかった、ミズーリ準州があるじゃないですか」
「ミズーリ準州か」彼は同意した。
秋の数週間が過ぎた。 十月の下旬に最初の霜が降り、木々は緋色、金色、深紅色、黄色になり、葉は風にからからと吹かれて、緩まり漂い落ちた。柿は熟し、木の実は落ち、牧草地の草は茶色く色づいた。火を起こすための木材が切りだされ積み上げられた。カボチャが倉庫に山積みにされ、カブやサツマイモが掘り出された。私たちは羊毛の服に衣替えをした。そして、私は過ぎていった悲しい日々の憂鬱を吹き飛ばしたいと思い、新しいドレスを真っ赤に染めた。「あなたによく似合う色ですね」と、ステファンはそれを着た私を初めて見て言った。「あなたの暗い髪と目の色に、赤が映えています」
「アニーを思い出します」私は笑いながら言った。「彼女は可愛いものを愛していた」
「女性は皆そうですね」彼は言った。トウモロコシが集められて、皮むきの会が行われた。
昔は、(1)赤いトウモロコシを見つけた男性は、好きな女性からキスをお願いすることができた。ビリーバーズの中では、赤いトウモロコシはファミリー全体の得点に五点が上乗せされることを意味した。それでもトウモロコシの皮むき会は楽しかった。私たちはワインを少し飲み、歌いながら作業した。男性がどんどん速く剥くあいだ、さまざまなファミリーの歓声が上がっていた。そして、最終的にノース・ファミリーの若い男の人が勝った時は、皆で彼らを愉快に祝福した。
十一月に初めて、一晩中降った雨の水たまりの表面に氷が張った。そして、数週間後のクリスマスの直前に大雪が降った。本格的な冬の訪れだ。毎日、私は太陽がかろうじて顔を出し始める時間に、スクール・ハウスから自分の教室まで乾いた草の小さな区画を歩いた。そして、毎晩歩いて戻る頃には、太陽はすでに沈んでいるほど、日は短くなっていた。今、私の勉強と授業の準備の他にいつもしていることは、小さな女の子たちのためにストッキングを編むことだった。ブラザー・ベンジャミンが秋に説教に出かけ、多くの改宗者を得たので、ヴィレッジは成長し続けた。スクール・ファミリーの人数は限界に近づきつつあって、イースト・ハウスではもはや、男性も女性も信者は受け入れられないと言われていた。「ウィンター・シェーカーは」シスター・ドルシーは軽蔑を込めて言った。「冬になると、カラスのようにトウモロコシ畑にやってきます。彼らが欲しいのは、暖かく寝られる場所と、十分な食べ物だけです」
もちろん……常にそうした人々はいた。そして、次の春になれば、彼らは来たのと同じくらいの速さでここを離れていった。それは指導者にとっては、最も深刻な問題の一つになりつつあった。
翌年に新しい家がスクール・ファミリーのために作られることが決まった。イースト・ファミリーについてもそうなった。どちらも煉瓦で建てられる予定だったため、働ける男性はみんな煉瓦工場と窯で働き始めた。
クリスマスがあっという間に過ぎた。シェーカーは、聖餐礼拝を開いて信仰告白を聞くことを除いて、クリスマスをあまり重視しない。何十人もの子どもたちが冬の疫病にかかった時は、私はミーティングに出席できなかった。そして、他の人たちと一緒に看病しなければならなかった。それはかえってよかった。私はもはや罪の告白の美徳や必要性に心惹かれていなかった。本当のことを言えば、ミーティングにはもはや思い入れはなかった。
私はミーティングでリチャードの手が寒さで赤く荒れているのを見て、彼のためにミトンを編んだ。彼やブラザー・ランキンはどんなことがあっても、村から十二マイル離れた工場から日曜日のミーティングのためにやってきた。彼らは雨が降っていても、みぞれが降っていても、風が強くても、雪が降っていてもやってきた。彼らは到着してから一時間震え続ける時もあり、礼拝運動とダンスのあいだだけは、悪寒がおさまった。彼らは、ブラザー・ベンジャミンや他の指導者たちから高く評価され、実直さと美徳の模範として示された。
私はそれには賛同しなかった。私は彼らを馬鹿げていると思った。ブラザー・ランキンが肺熱で倒れて、ほとんど死にそうになっていた時でも、私は驚かなかった。いつでも、私はそれを予期していたし、リチャードが病気であると聞くこともまた予期していた。ところが、彼はやせ細っているにもかかわらず、彼の持つ強さはとても立派だったに違いない。ますます肉がそぎ落ちて筋肉と神経が丸見えだが、彼にとっては肉づきがよい身体よりもそれは優れた状態だった。その冬、私たちの中で彼だけが病気にならなかった。
私は、青色のミトンをリチャードのために編んだ。青はシェーカーが最も好んだ色だった。
ステファンのためには、赤色のミトンを編んだ。ステファンはそれに満足し、常にそれを身に着けていた。リチャードは集会所のベンチに自分のミトンを残していった。私はそれを誰が捨てたのか、あるいはそれを誰かが使ったのかどうかは知らない。雨が多く、底冷えする寒い冬だった。疫病が家から家へとヴィレッジを駆け巡り、ある時期には私たち全員がかかった。鼻水、喉の痛み、咳、悪寒、発熱に苦しみながらも、私たちはお互い世話をしあって、治るまでできる限り長くいつもの暮らしを続けようとした。手は尽くしたにもかかわらず、五人の子どもたちが亡くなった。その五人は、私の直接の世話を受けていなかった。彼らの悪寒は肺熱になり、息をつまらせ呼吸が困難になり亡くなった。あまりに幼く無防備な彼らを埋葬することは悲しかったが、深く悲しむ時間はほとんどなかった。病気にかかり、私たちの世話を必要とする患者がいた。
二月になって疫病が少し弱まってきたものの、プリシーは依然として寝込んでいた。センター・ハウスから知らせがあった。「シスター・プリシラのために祈るのです。彼女は死の淵にいます」
私たちにできることは祈ることだけだった。二十人もの子どもたちがまだ伝染病で衰弱していて、その子たちが治るまでにまだ多くの時間を必要としたが、おおむね伝染病が過ぎ去って、学校はその前の週に再開されたのだった。プリシーの容体の知らせは毎日数回届いた。「彼女の喉は腫れています」
「熱は非常に高く、触れると痛がります」
「錯乱していて、うわごとを言っている状態です」
彼女はせん妄で自分の帽子を探していると……帽子が盗まれたと泣いているというのだ。さらに、彼女が両手で自分の髪を引っ張り続け、ぐしゃぐしゃにしているということ。彼女が子どものように泣いて帽子を欲しがっていること。帽子を見つけて自分の元に返して欲しいと訴えていることを聞いた。悲しいことに、パルミラのいいかげんな冗談が、彼女の心を随分と深く突き刺し傷つけたのだろうと思った。私たちは、それはすぐに終わるだろうと思っていた。数カ月もの長いあいだ、恥が彼女をさいなめ続けたとは、決して夢にも思わなかった。しかし、彼女の朦朧とした意識は、それが彼女にとってどれほど辛いことだったか、彼女にとってどれほど恐ろしいことがあったかを明らかにしたのだ。私はプリシーに哀れみを感じるとは思いもしなかった。しかし、彼女が帽子を見つけてほしいと懇願していると聞いた時、私は哀れみ以上のものを感じたのだった……私は、自分たちの残酷さや無遠慮に悲しみを感じ、そして私たちが他人に対してしていることにどれほど無神経かということ、どれだけ不注意に他人の心を傷つけその一生を損なってしまうかということを考えた。
私はどうにかしてプリシーをなだめようと考え、彼女に会えるように頼んだ。一見彼女だとわからなかった。それほど病気は彼女をすっかり変えてしまっていたのだ。彼女はしなびて乾ききり、こめかみに青く浮き出た静脈は膨張していた。両手で髪をむしり続け、うめき、落ち着きなく辺りを見回していた。彼女の白いネットキャップは、もちろんあるべきところにあった。彼女は、何度も、何度も、帽子をなくしてなどいないと諭されていた。ちゃんと帽子を被っているのだということも伝えられていたが、何を言われても彼女の病んだ心に届かなかった。私は彼女の他の帽子を持ってくるように頼み、シスター・スーザンが急いで持ってきてくれた。それから私は彼女の帽子を脱がせ、彼女の額と顔のまわりの細い髪の毛をとかした。髪が整えられていないかのように、そして帽子を被っていないかのように彼女に感じてほしかった。彼女は私を押し退けうめいた。「私の帽子……私の帽子……ない……誰か見つけて……私の帽子を見つけてください……」
私は櫛を置いて、彼女に話しかけた。「あなたの帽子を見つけましたよ、シスター・プリシラ。ほら、両方あります。手にとってみてください」
私は彼女の手に帽子をしっかりと乗せた。彼女はそれらを抱きしめ、感じとり、指でなぞった。それから穏やかな表情を浮かべ、彼女は微笑んだ。私は彼女の髪を束ね、それから自分の髪の毛から帽子を外し、それをピンで留めた。「帽子を彼女に持たせておいてあげてください、シスター・スーザン」と私は言った。「帽子がここにあると実感できていれば、彼女は満足するだろうと私は思います」
それは、彼女をとても傷つけてしまった冗談に対して、彼女を笑ってしまったことに対して、そして彼女を嫌ってしまったことに対して、私がすることができる唯一の償いだった。そして彼女は死んだ。帽子を握り締めたまま。意識を回復することはなかったが、帽子を見つけて心のどこかで平穏を感じていたはずだ。
プリシー、彼女には欠点があったのだ……そして彼女のやり方は、私のやり方とは異なっていた。しかし私たち全員がそうであるように、彼女も肉と血で作られ、いずれ死すべき者であったのだ。長い(2)葬儀のあいだ、そしてすべての追悼の言葉と賛美のスピーチのあいだ、ある考えが浮かんできた。プリシーを動かしたものが何であっても、それは彼女に働く情熱を与え、決して屈しない権威を与え、真の誇りを与え、彼女を奮い立たせ、そして彼女を優れたリーダーにしたのだ。しかし私たちが指導されていた時には、それを理解することができなかったのだった。ささいなことで彼女は私たちをうんざりさせたが、イースト・ハウスは順調に運営され、その日常業務は油を差した機械のようにスムーズであり、組織はきちんと整っていた。
こんな考えも浮かんできた。シェイカー・コミュニティのどんなリーダーにも、多くの欲求不満や我慢しなければならないうんざりすることがあるだろう。距離が近すぎて起こる人間の魂の摩擦、人々のちょっとした騒動やゴシップ、喧嘩、よくある気難しさなどだ。プリシーもよく私たちと同じくらいいらいらしたり、二度と私たちに会いたくないと思ったり、あるいは私たちの悩みや不満をもう聞きたくないと思ったりしたに違いない。例えるなら、しばしば手に負えないほどのひなを持つ母鶏のように取り乱していたに違いないのだ。しかし、彼女は鉄の意志でイースト・ハウスを整然と守っていた。そしてその唯一の報いは、彼女の務めが滞りなく遂行されたことを知ることだった。ここで彼女は今、死んで横たわっている。彼女はもう彼女への追悼と賛美の言葉を聞くことはできないのだ。最後の対面をし、棺を閉じる際に、最後に彼女の顔を見て、私は彼女を心から許した。そして天国で与えられる報いが、地上で与えられたものよりもどうか大きいものあってほしいと思った。
冬は終わらないだろうと思っていたけど、常にいつか終わるものだ。これまでも常にそうだったし、これからもそうだろう。二月でも男たちは深い溝を耕した。そして、まぐわでならし、作物を植える時期まで休耕にした。四月になり、小川のそばのヤナギは緑のベールとなり、ハナミズキは十字の印がついた白い花を咲かせた。(3)アメリカハナズオウの木はピンク色になり、私たちはそれを腕いっぱいに集めてスクール・ルームに持ちこんだ。長く寒い冬の病気を乗り越え、私たちは成長すること、生き物、輝きや元気を渇望していた。
四月になり、カエルが水辺で鳴き始め、今年最初の仔牛が生まれた。庭は区分けされ、ジャガイモやエンドウ豆の苗が植えられた。私たちはカラシナやレタス、クレソンや(4)ギシギシといった野生の植物を集めてきて、それらを思う存分食べた。新鮮な野菜を欲していたのだ。私たちは(5)サッサフラスの根も掘り、ポットでお茶を作り、それをごくごくと飲んだ。冬のあいだは、血が濃くなったような気がした。サッサフラス茶と野生の野菜はそれを薄めて、私たちの体に春をもたらしてくれた。
製材所が焼けたのも、同じく四月のことだった。
第23章訳註
(1) 赤いトウモロコシ
アメリカの一部の地域では、植物の糖の不均等によって生まれる穂が赤いトウモロコシは、珍しいのものであり、幸運の証とされていたため、それを見つけた人間は報酬としてキスを受け取ることができた、という伝承が伝え残されている。
(2) 葬儀
シェーカーの葬式は、その日の証言(the testimonies)が故人についてであることを除けば当時の通常の礼拝と非常によく似ていた。葬儀に際して特別な詩や歌が作られることもあった。1900年頃まで、遺体は洗われ覆いに包まれたのち、蓋を開けたままのごく普通の棺の中に置かれた。葬儀はその後、ドウェリング・ハウスのそのファミリーのミーティング・ルームで行われた。
(3) アメリカハナズオウの木
アメリカの東部に広く分布する落葉樹。3月から4月にかけて淡い紅色の花を咲かせる。
(4) ギシギシ
タデ科の多年草。ヌルヌルした若い芽を食用として利用する。
(5) サッサフラス
クスノキ科の落葉高木。根や樹皮は薬に使われていた。サッサフラスの根を蒸留して得るサッサフラス油は黄または赤黄色でサフロール原料、せっけんの香料などに用いられた。サッサフラス茶には有毒なサフロールが多く含まれ、1976年に米国食品医薬品局(FDA)は販売することを中止すると決定した。